犬のワクチン接種は
愛犬の健康を守る上で
非常に重要なテーマ
でありながら、その
・必要性
・安全性
については様々な意見があり、戸惑われているかもしれません。
・狂犬病ワクチンの義務付け
・複数ある混合ワクチンの種類
・ワクチンによる免疫異常の可能性
まで、考慮すべき点は多岐にわたります。
この記事では犬のワクチン接種について
・多角的な視点から掘り下げ
飼い主さんがご自身の愛犬にとって
・最適な選択をする
ための一助となることを目指します。
犬のワクチン接種とは?:オーダーメイドの選択へ
ワクチンは
病原体の一部
※弱毒化・不活化されたウイルスや細菌
あるいはその成分
を体内に投与することで
・病気に感染することなく
・免疫システムを活性化
させることで
病原体に対する抗体を作り出す
ことを目的としています。
これにより
▶将来的にその病原体に接触した場合
▶速やかに免疫応答が起こり
・発症を防ぐ
・症状を軽減する
などができます。
犬のワクチン接種は
感染症から命を守る
重要な手段です。
しかし近年
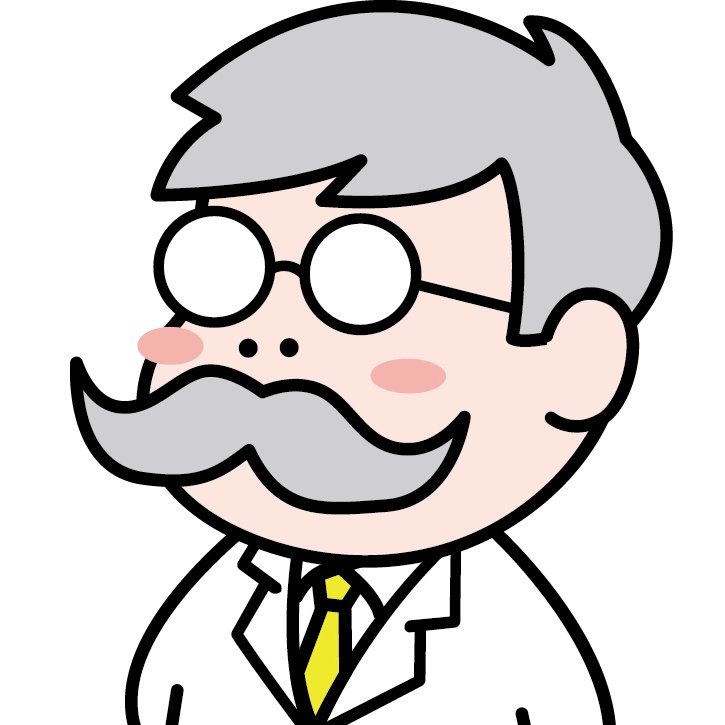
ワクチン接種は、その子の個性に合わせてオーダーメイドで考えるべき
という考え方が広まっています。
安易な
毎年接種
にはリスクが伴う場合もあり
・免疫学の進歩
・ワクチンの安全性に対する懸念の高まり
が背景にあります。
国際的な獣医学会(WSAVAなど)のガイドラインも、この個別最適化の考え方を支持しています。
2.狂犬病ワクチンと混合ワクチン
犬に接種されるワクチンは
大きく分けて
・狂犬病ワクチン(法的義務)
・混合ワクチン(任意)
の2種類があります。
狂犬病ワクチン(法的義務)
日本において、狂犬病ワクチンは
狂犬病予防法
において
年1回の接種
が義務付けられています。
狂犬病は人間にも感染し
発症すればほぼ100%死亡する
という非常に恐ろしい
人獣共通感染症
であるため、公衆衛生を守る上で不可欠な措置です。
●免除される場合
特定の健康上の理由(病気や高齢)により
獣医師が接種困難と判断
した場合
▶猶予証明書を発行してもらうことで
▶接種を免除されることがあります。
混合ワクチン(任意接種)
混合ワクチンは
狂犬病ワクチンと異なり
法律上の接種義務はありません。
しかし犬が感染すると
重篤な症状を引き起こす可能性のある
複数の感染症
を予防するために推奨されています。
予防できる病気の数によって
3種・5種・7種・8種・10種
など様々な種類があり、一般的に予防できる病気の数が多いほど価格は高いです。
3.混合ワクチンの種類と予防できる病気・必要な犬
愛犬の
・ライフスタイル
・健康状態
に応じて
最適な混合ワクチン
を選ぶことが重要です。
※混合ワクチンの例

※ 実際のワクチンの種類や構成は、製薬会社や動物病院によって異なる場合があります。
※ 特にレプトスピラ症は地域によって流行している血清型が異なるため、獣医師にご相談ください。
※ 最新の情報や詳細については、必ずかかりつけの獣医師にご確認ください。
全ての犬に推奨される「コアワクチン」
ほとんどの混合ワクチンに含まれる
犬にとって
・特に重要で感染力が強く
・重篤な症状を引き起こす
可能性のある、以下のような病気を予防します。
◇犬ジステンパーウイルス感染症
・発熱
・下痢、嘔吐
・呼吸器症状
・神経症状
などを引き起こし
致死率が非常に高い
病気です。
回復しても神経症状が残ることも。
◇犬パルボウイルス感染症
・激しい嘔吐
・下痢(血便を伴うことも)
・脱水
などを引き起こし
特に子犬では重篤化しやすい
病気です。
◇犬アデノウイルス感染症
※犬伝染性肝炎および犬アデノウイルス2型
・発熱
・嘔吐、下痢
・腹痛
・肝臓の腫れ
・目の濁り(ブルーアイ)
などを引き起こします。
重症化すると
肝不全で死亡
することもあります。
●<3種混合ワクチン>
上記の3つの病気
・ジステンパー
・パルボウイルス
・アデノウイルス
を予防します。
他の犬との接触が少ない
室内飼いの犬でも
・散歩
・動物病院での接触
など
感染リスクはゼロではない。
そのため
全ての犬に最低限接種
しておくことが望ましいとされています。
ライフスタイルによって検討する「ノンコアワクチン」
コアワクチンに加えて
・愛犬の生活環境
・他の犬との接触機会が多い
場合に検討すべきワクチンです。
●<5種・6種混合ワクチン>
3種混合ワクチンに加えて、以下の病気を予防します。
◇犬パラインフルエンザウイルス感染症
ケンネルコフと呼ばれる
・乾いた咳
・鼻水
・軽い発熱など
の呼吸器症状を引き起こします。
他の病原体と混合感染
すると重症化することもあります。
◇犬コロナウイルス感染症
・下痢
・嘔吐
などの消化器症状を引き起こします。
パルボウイルスと混合感染
すると重症化しやすい傾向があります。
【どんな犬に必要か?】
・ドッグラン
・ペットホテル
・トリミングサロン
・しつけ教室など
他の犬と接触する機会が多い犬
に推奨されます。
●<7種・8種・10種混合ワクチン>
5種混合ワクチンに加えて、主に
レプトスピラ症
を予防します。
レプトスピラ症には
複数の血清型
があり、予防できる血清型の数によって種類が異なります。
また、種類によっては
犬ボルデテラ症
も予防します。
◇レプトスピラ症
人間にも感染する
人獣共通感染症
です。
・発熱
・黄疸
・腎不全
・出血傾向
などを引き起こし
重症化すると死に至る
こともあります。
感染した野生動物
・ネズミ
・アライグマなど
の尿によって汚染された
・水
・土壌
を介して感染します。
【どんな犬に必要か?】
川、湖、沼、田んぼ、湿った草むらなどに
・散歩、レジャーでよく行く犬
・農村部や自然豊かな地域で暮らす犬
・狩猟犬やアウトドア活動が多い犬
に推奨されます。
都市部であっても
・公園の池
・水たまりなど
ネズミが生息する場所
でも感染リスクがあります。
◇犬ボルデテラ症
※ケンネルコフの原因菌の一つ
ケンネルコフの原因となる細菌で
・乾いた咳
・鼻水
・軽い発熱
などの呼吸器症状を引き起こします。
パラインフルエンザウイルスなどと
混合感染
すると
・症状が長引く
・重症化する
ことがあります。
4.ワクチン接種のメリット・デメリット
ワクチンを
・「打つ」こと
・「打たない」こと
にはそれぞれ
・メリット
・デメリット
があります。
ワクチンを「打つ」メリット
●感染症の予防
愛犬を
・致死的な
あるいは
・重篤な
感染症から守ります。
特に免疫力が未熟な子犬には重要です。
●重症化の回避
仮に感染したとしても
▶ワクチンを接種していれば
▶症状が軽度で済む
可能性が高まります。
●集団免疫
多くの犬がワクチンを接種することで
▶地域全体での感染症の蔓延を防ぎ
▶ワクチンを接種できない犬(高齢犬、病気の犬、子犬など)も守る「集団免疫」の効果が期待できます。
●行動の自由
多くの
・ドッグラン
・ペットホテ
・トリミングサロン
などでは、他の犬への感染を防ぐため、ワクチン接種証明書の提示を求められます。
ワクチンを「打つ」デメリット
●副反応(副作用)のリスク
ワクチンは体内で
▶免疫反応を引き起こすため
▶少なからず副反応のリスク
があります。
◇軽度な副反応
一時的な
・発熱
・食欲不振
・元気消失
・接種部位の腫れや痛み
など。
これらは通常、数日以内に自然に治るもの
◇重度な副反応
稀ではありますが
アナフィラキシーショック
・呼吸困難
・意識消失
・痙攣など
命にかかわる重篤なアレルギー反応
が起こる可能性があります。
またごく稀にワクチン接種が原因で
免疫介在性疾患
・免疫介在性溶血性貧血
・免疫介在性血小板減少症など
が引き起こされる可能性も指摘されます。
接種部位に
肉腫(腫瘍)
が発生する可能性もゼロではありません。
●過剰な免疫負荷
頻繁なワクチン接種は
犬の免疫システムに
過剰な負荷をかける
可能性があります。
特に
・すでに十分な抗体を持っている犬に
・毎年追加接種することが本当に必要?
かどうかなどが議論されています。
●費用
ワクチン接種には費用がかかります。
・ワクチンの種類によっては高値
・抗体価検査にも費用がかかる
そして
ペット保険がこれらの費用をカバーしない
ことが一般的である点も考慮が必要です。
ワクチンを「打たない」メリット
●副反応リスクの回避
ワクチンによる副反応、特に
・重篤なアレルギー反応
・免疫介在性疾患のリスク
を完全に回避できます。
●免疫システムへの負担軽減
ワクチンによる
▶免疫システムへの刺激がないため
・体質的に免疫力が弱い犬
・持病がある犬にとって負担が少ない
という考え方もあります。
●費用がかからない
ワクチン接種にかかる費用が発生しない
ワクチンを「打たない」デメリット
●感染症へのリスク増大
・致死的な
あるいは
・重篤な
感染症に感染するリスク
が飛躍的に高まります。
特に
・子犬
・高齢犬
・基礎疾患を持つ犬
は一度感染すると命に関わる可能性。
●重症化のリスク
感染した場合
▶症状が重篤化しやすく
治療に多大な
・時間
・費用
・労力
がかかる可能性があります。
●他者への感染源となる可能性
感染症にかかった場合
狂犬病やレプトスピラ症のように
・他の犬
・人間
に感染を広げてしまう危険性があります。
●行動制限
ワクチン接種が必須とされる
・ドッグラン
・ペットホテル
・トリミングサロン
などの施設を利用できなくなります。
●精神的な負担
もし愛犬が
ワクチンで防げたはずの病気
にかかってしまった場合
飼い主さんの精神的な負担
は計り知れません。
5. 闇雲な毎年接種の危険性と「抗体価検査」
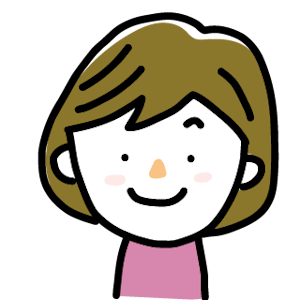
ワクチンは毎年打つもの
という従来の考え方に対し
近年では
闇雲な毎年接種にはリスクが伴う
という意見が広まっています。
闇雲な毎年接種の危険性
1.免疫システムへの過剰な負担
ワクチンは、犬の免疫システムに働きかけることで効果を発揮します。
しかし
・すでに十分な免疫(抗体)
を持つ犬に
・毎年追加でワクチンを接種すること
は免疫システムに
不必要な負担をかける可能性
があります。
犬のコアワクチンの免疫は
一度接種すれば
・数年間
あるいは
・生涯にわたって持続する
とする研究結果も多く報告されています。
それにもかかわらず
▶毎年同じワクチンを接種することは
▶過剰な免疫刺激となり
▶犬の体にストレスを与える
可能性があるのです。
2.副反応リスクの蓄積
ワクチン接種には
・軽度なものから
・重篤なものまで
様々な副反応のリスク
が伴います。
毎年接種することは、単純にこの副反応リスクにさらされる回数を増やすことに。
◇アレルギー反応
稀ではありますが
アナフィラキシーショック
などの重篤なアレルギー反応は、いつ起こるかわかりません。
◇免疫介在性疾患の誘発
・免疫介在性溶血性貧血
・免疫介在性血小板減少症
などの自己免疫疾患は
ワクチンの免疫刺激
が引き金の一つになるとの指摘あり。
体質的な問題もあるため、すべての犬に起こるわけではありませんが、リスクを無視することはできません。
◇慢性的な不調
目立った副反応がなくても
・軽度の体調不良
・食欲不振
・元気消失など
が接種後に繰り返し見られる場合
それが
免疫システムへの負担のサイン
である可能性も考えられます。
3.個体差を無視した一律の接種計画
・同じワクチンを
・同じ頻度で接種する
ことが最適
という考え方は
犬の個体差を無視
しています。
・遺伝的背景
・年齢
・健康状態
・生活環境
・過去のワクチン歴など
犬は一犬一犬異なります。
例えば
・過去に副反応歴がある犬
・すでに自己免疫疾患を持つ犬
・高齢で免疫力が低下している犬
に安易にワクチンを接種することは
・病気を悪化させたり
・新たな健康問題を誘発したり
する危険性があります。
解決策としての「抗体価検査」と「個別接種計画」
闇雲な毎年接種
を避けるための解決策として
多くの専門家が提唱しているのが
「抗体価検査」
に基づいた
「個別の接種計画」
です。
●抗体価検査とは?
血液を採取して、その犬が
特定の感染症に対する抗体
をどれだけ持っているかを調べる検査。
この検査によって
その年にワクチン接種が必要かどうか?
を科学的に判断できます。
◇抗体価が十分にある場合
その年のワクチン接種は不要と判断し
▶次回の検査を1~3年後など
▶適切な期間に設定します。
これにより
・不要な副反応リスクを回避し
・費用も抑える
ことができます。
◇抗体価が不十分な場合
免疫が低下している可能性があるため
▶獣医師と相談の上
▶その年にワクチンを接種します。
●個別の接種計画の立て方
抗体価検査を
・毎年行うか?
・数年ごとに行うか?
あるいは
・コアワクチン
・ノンコアワクチン(レプトスピラなど)
で接種頻度を変えるか?
など、愛犬の状況に合わせた
最適な計画
を立てます。
◇コアワクチン
一度十分な免疫がつけば
▶数年間の持続が期待できる
そのため
▶抗体価検査を数年ごとに行い
▶必要に応じて接種を検討します。
◇ノンコアワクチン(レプトスピラなど)
・地域
・ライフスタイル
によって感染リスクが変動します。
一般的に持続期間が短く
毎年接種が推奨される
傾向にあります。
特に
感染リスクが高い環境
にいる犬は毎年接種を検討することが推奨されます。
6.ワクチン接種時の注意点と飼い主さんに求められること
ワクチン接種前後の体調管理
●接種前の健康チェック
ワクチン接種は
犬が健康な状態である
ことが大前提です。
接種前に
・元気や食欲があるか
・下痢や嘔吐がないか
などを確認し、少しでも異変があれば必ず獣医師に伝えてください。
体調が優れない場合は、接種を延期することもあります。
●接種当日は安静に
接種当日は
・激しい運動を避け
・できるだけ安静に過ごさせます
●接種後の観察
接種後、特に数時間は愛犬の様子を注意深く観察してください。
賢いワクチン接種計画の立て方
●子犬の初回接種プログラムの目安
子犬は
母親からの移行抗体
によって一時的に守られています。
しかしその抗体は徐々に消失します。
そのため
・適切な時期に
・複数回のワクチン接種
が必要です。
◇一般的な目安
・生後6~8週齢で1回目
・その3~4週後に2回目
・さらに3~4週後に3回目
計2~3回の接種が推奨されます。
最終接種は生後16週齢以降に行われることが多いです。
●海外渡航予定
渡航先の国や地域によっては
・ワクチンの種類
・接種時期
・抗体価の確認など
厳密な条件が定められている場合も。
事前に獣医師と
▶入国要件を確認し
▶計画的に進める必要があります。
副反応が発生した場合の対応
●軽度な副反応
・一時的な発熱
・元気消失
・食欲不振
・接種部位の軽い腫れや痛み
などは、通常数日以内に治まります。
●重度な副反応
・顔の腫れ
・呼吸困難
・激しい嘔吐・下痢
・痙攣
などの異変が見られた場合は
▶すぐに獣医師に連絡し、指示を仰いでください。
・夜間
・休日
の場合でも
緊急対応可能な動物病院
に連絡することが重要です。
●過去の副反応
過去にワクチン接種で何らかの副反応があった場合
▶その内容を必ず獣医師に伝え
▶今後の接種方針について相談すること
ワクチン接種証明書の重要性
●狂犬病ワクチン接種済証と鑑札
狂犬病ワクチン接種後は、狂犬病予防法に基づき発行される
「狂犬病予防接種済証」
「犬鑑札」
の携帯・装着が義務付けられています。
●混合ワクチン接種証明書
・ドッグラン
・ペットホテル
・トリミングサロン
・しつけ教室など
多くの施設で
混合ワクチン接種証明書
の提示を求められます。
紛失しないよう、大切に保管しておきましょう。
信頼できる獣医師とのコミュニケーション
最も重要なのは
愛犬の
・健康状態
・生活環境
をよく理解し
信頼できる獣医師
と密にコミュニケーションをとること。
疑問や不安に思うことは遠慮なく質問し、納得いくまで説明を求めましょう。
獣医師は専門家として
・科学的根拠に基づいた
・適切なアドバイス
をしてくれるはずです。
獣医療の進歩と未来
近年、特定の疾患に対する新しいワクチンの開発が進められるなど
獣医療は常に進化
しています。
将来的には、遺伝子検査などにより
個体ごとの
・アレルギーリスク
・免疫応答の特性
をさらに詳細に把握し
よりパーソナライズされた
ワクチン接種ができる可能性も。
・常に新しい情報に目を向け
・獣医師と協力しながら
愛犬にとって最善の医療を選択
していくことが求められます。
まとめ
犬のワクチン接種は
・メリットとデメリット
そして
・個体差
を考慮すべき複雑な問題です。
狂犬病ワクチンは法律上の義務
ですが、混合ワクチンについては
・愛犬のライフスタイル
・年齢
・健康状態
・飼い主さんの考え方
によって、最適な選択が異なります。
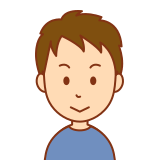
ワクチンなんか打たん方がいい
という意見も耳にします。
しかしそれは
・個々の状況
・リスク評価
に基づくものであり
一概に正しいとは限りません。
感染症の脅威は常に存在し、特に
・他の犬と接触する機会の多い犬
・子犬・高齢犬
にとってはワクチン接種が
命を守る重要な手段
となり得ます。
最終的な判断は飼い主さんが下すもの。
ですが、そのためには
・正確な情報を多角的に収集し
・獣医師と十分に話し合い
愛犬にとって
何が最も幸せな選択なのか?
を深く考えることが何よりも大切です。

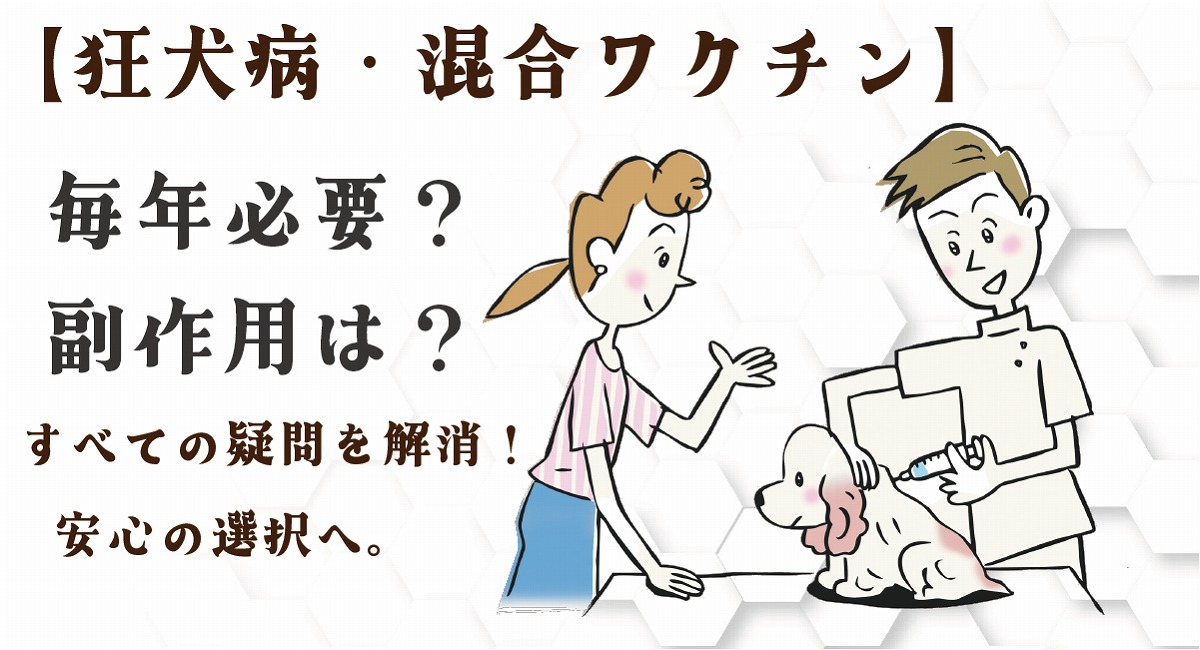
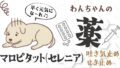

コメント