保護犬を家族に迎えること
それは
・かけがえのない喜びと
・感動
をもたらします。
しかし、それは同時に
大きな責任
を追うことを意味します。
そして知識を持っていなければ
「こんなはずじゃなかった」
と感じるような困難に直面することも。
この感情は、あなただけでなく
保護犬にとっても望ましくない
ものです。
この記事では保護犬との暮らしを
本当に幸せなもの
にするために
・美しい理想
だけでなく
・向き合うべき現実
そしてそれに対する
・具体的な対策
までを徹底的に解説します。
あなたが保護犬との生活を想像する上で
知っておくべき「真実」
を余すことなくお伝えし、
一歩踏み出すための確かな準備と心構えをサポートします。
- 1. 保護犬とは?その背景と多様性:「第二の犬生」を待つ命たち
- 2. 保護団体の現実:なぜ彼らは厳しい条件を提示するのか?そして、その「見えない努力」
- 3.知っておきたい!病気になりやすい保護犬とは?その「隠れたリスク」
- 4. 保護犬を迎えるのに向く人・向かない人:あなたの「覚悟」を測る基準
- 5.保護団体が提示するであろう条件:その裏にある「保護犬ファースト」の視点
- 6.保護犬の理想と現実:そしてその先にある「希望」
- 7.保護犬を迎えるにあたって注意すべき点:医療・しつけ・心構えの徹底
- 8.相性の見極め方:「直感」と「客観」のバランス
- 9.保護犬の探し方:信頼できる団体を見極める「チェックリスト」
- 10.受け入れ準備:「ようこそ、我が家へ」その日からの始まり
- 11.受け入れてからの注意点:信頼を築き、共に歩む日々
- 結び:保護犬との未来は、あなたと犬の幸せな共生という名の「物語」
1. 保護犬とは?その背景と多様性:「第二の犬生」を待つ命たち

「保護犬」と聞くと、どんなワンコを想像しますか?
・捨てられてさまよっていた犬
・虐待を受けていた犬
といった悲しい過去を持つ犬だけではありません。
保護犬とはさまざまな事情で
・飼い主との生活が困難になり
・新たな家族を待っている犬たち
の総称です。
彼らが保護される背景:社会が抱える様々な問題
●多頭飼育崩壊
繁殖がコントロールできず
▶飼い主の手に負えない数の犬が
▶劣悪な環境で暮らしているケース。
●高齢者の飼育放棄・他界
飼い主の
・高齢化
・病気
・逝去
により犬の世話ができなくなるケース
●経済的困窮
飼い主の経済状況の悪化により
▶飼育が困難になるケース。
●引退犬・繁殖犬
・ブリーダーによる繁殖引退
・何らかの事情で「商品」として扱われなくなった犬たち。
●迷子犬の収容
迷子として行政に収容され
▶期限内に飼い主が現れなかった犬。
●災害時の置き去り
災害時に避難を強いられ
▶置き去りにされてしまうケース。
このように
保護犬の背景は多岐にわたります。
そして彼らは
・純血種からミックス犬
・子犬から老犬
まで、実に様々な個性を持ちます。
その一犬一犬が
・異なる過去を背負い
それでもなお
新たな家族との出会い
を心待ちにしているのです。
2. 保護団体の現実:なぜ彼らは厳しい条件を提示するのか?そして、その「見えない努力」
多くの保護団体は
非常に限られたリソース、つまり
・人材
・資金
・設備
・時間
の中で、来る日も来る日も
命と向き合っています。
●財政的な課題
・保護犬の医療費
・フード代
・施設の維持費など
その活動には膨大な費用がかかります。
多くの団体は
・寄付
・ボランティア
に支えられています。
とは言え、常に綱渡りの状況です。
●人手不足
・保護犬の世話
・医療処置の補助
・譲渡会
・情報発信など
多岐にわたる業務を
・少数のスタッフ
・ボランティア
で回しています。
●精神的負担
劣悪な環境から保護された犬たちの
心身のケア
は想像を絶するほどの
・時間と
・労力
を要します。
彼らは、犬たちの
・傷ついた心と身体
・その回復
を見守り、そして
・再び送り出す
という重い役割を担っています。
彼らが最も望むのは
一度不幸な経験をした犬たちが
二度と同じ苦しみを味わわない
ことです。
だからこそ譲渡の際には
厳しい条件
を提示せざるを得ない現実があります。
すなわち
保護団体の厳しい譲渡条件は
単なる「ハードルの高さ」
ではありません。
それは
・犬たちの未来を真剣に考え抜いた
・愛情と覚悟の表れ
なのです。
私たち飼い主になる側が
▶その背景を理解し
▶誠実に向き合うことで
▶保護団体との信頼関係が築かれ
▶より良いマッチングに繋がります。
保護団体の日々の「見えない努力」
多くの保護団体は
新しい飼い主さんのもとで犬たちがスムーズに生活できるよう
日々「見えない努力」
を重ねてくれています。
●基本的な医療ケア
保護した犬たちには、まず
・獣医師による健康チェック
・ワクチン接種
・不妊去勢手術
・マイクロチップ装着
といった
・基本的な医療ケア
を徹底して行います。
病気やケガがある場合は、その治療にも尽力し、健康な状態での譲渡を目指します。
●心身の回復と社会化
特に過去に辛い経験をした犬たちは
・人間への不信感
・環境への慣れにくさ
を抱えています。
保護団体では
▶時間をかけて犬たちの心に寄り添い
▶人間との信頼関係を築き直す
ための努力を惜しみません。
個々の犬の
・性格
・過去の経験
に合わせて、少しずつ社会化を進め
・他の犬や人
・様々な環境
に慣れさせる訓練を行うこともあります
●基本的なしつけの導入
新しい家族のもとで問題なく暮らせるよう
・トイレトレーニング
・散歩の練習
・基本的なコマンド
(おすわり、待てなど)
といったしつけを、できる範囲で進めている団体も少なくありません。
これにより
▶譲渡後の飼い主さんの負担を軽減し
▶犬が新しい生活にスムーズに順応できるよう配慮しています。
●個性を引き出す観察と記録
犬たちの
・性格
・行動パターン
・好み
・苦手なこと
などを詳細に観察・記録します。
それらの情報を基に
▶最適な飼い主さんとのマッチング
を行っています。
これは
・犬
・飼い主さん
双方にとっての
「こんなはずじゃなかった」
を防ぐ、非常に重要な取り組みです。
このように保護団体は
単に犬を保護する
だけでないのです。
かけがえのない命が新しい家族のもとで
幸せに暮らせるよう
・多岐にわたる専門的なケア
・惜しみない愛情
を注いでいます。
私たちは保護犬を迎えるにあたって
こうした団体の方々の
・熱意
・愛情
・努力
を理解し
感謝の気持ちを持って接すること
が、保護犬の未来をさらに明るくする一歩となるでしょう。
保護犬は
「かわいそうだから引き取ってあげる」
という気持ちではなく
・犬の幸せを第一に考え
・保護団体の意見を聞き
家族として「迎える」
という意識を持つことが大切です
3.知っておきたい!病気になりやすい保護犬とは?その「隠れたリスク」

保護犬って病気がちとちゃう?
というイメージを持つ人もいるでしょう。
確かに
一般的なペットショップの犬と比べ
特定の病気のリスクが高い
保護犬もいます。
中でも注意すべきは
繁殖引退犬
が抱える
「隠れたリスク」
過酷な繁殖環境がもたらす心身の不調
●精神的ストレス
・狭いケージでの飼育
・出産と交配の繰り返し
・人間との触れ合い不足
により
極度のストレス
を抱えている場合があります。
これが
・不安症
・分離不安
・攻撃性など
行動問題の根底にあることがあります。
●身体的問題
・適切な栄養
・医療ケア
を受けられなかったために
・歯周病
・皮膚疾患
・関節疾患
・目の病気など
を抱えているケースが多く見られます。
また
・子宮
・乳腺
の病気のリスクも高まります。
●社会化不足
幼少期に適切な社会化の機会がなかった▶
・他の犬や人間
・初めての環境
に対して
・極端に臆病になったり
・逆に興奮しやすかったり
する場合があります。
その他の病気のリスク
●野犬出身の犬
・寄生虫(フィラリア、回虫など)
・感染症
(パルボウイルス、ジステンパーなど)
のリスクが高い傾向にあります。
●多頭飼育崩壊の犬
不衛生な環境で生活していたため
・皮膚病
・呼吸器疾患
・感染症など
を抱えていることがあります。
●虐待を受けていた犬
肉体的な傷だけでなく
精神的なトラウマ
からくる心因性の症状
(食欲不振、下痢、過剰なグルーミングなど)
が見られることもあります。
これらのリスクをお伝えするのは
決して不安を煽るためではありません。
「こんなはずじゃなかった」
と後悔しないために
・現実を直視し
・長期的な医療費の覚悟
・精神面でのケアの重要性
を理解しておくことが
保護犬を幸せにする上で不可欠
だからです。
保護団体から提示される情報だけでなく
可能であれば譲渡前に
獣医による健康チェック
を受けるなど
・積極的な情報収集
・その確認
が大切です。
4. 保護犬を迎えるのに向く人・向かない人:あなたの「覚悟」を測る基準
保護犬を迎えることは、誰にでもできることではありません。
あなたの
・ライフスタイル
・心構え
が保護犬との幸せな共生を左右します。
保護犬を迎えるのに向く人
●覚悟
犬の
生涯にわたる責任
を全うする覚悟がある人
最期まで
家族の一員
として大切にする覚悟。
●経済的・時間的に余裕がある人
・医療費
・フード代
・しつけの時間など
犬にかかる
・費用と
・時間
を惜しまない。
●犬の愛される権利を尊重できる
完璧を求めず
その子のありのまま
を受け入れる心。
犬の
・個性
・過去
を受け入れ、根気強く向き合える人
●家族の理解と協力
家族全員が
▶保護犬を迎えることに賛成し
▶協力体制を築ける人
●犬のペースを尊重できる
犬が心を開くまでには時間がかかる場合があることを理解する。
その上で
・焦らず
・犬のペースに合わせて
信頼関係を築ける人
●しつけや健康管理
困ったとき
・自分で調べたり
・専門家に頼ったり
する姿勢。
積極的に情報収集し、取り組める人
保護犬を迎えるのに向かない人(安易な気持ちでは難しい!)
●衝動的
見た目の可愛さだけで判断
安易に犬を飼いたいと考えている人
●しつけや健康管理
犬の
・しつけ
・健康管理
に時間や手間をかけたくない人
=問題が起きたときに責任を放棄してしまう可能性。
●完璧な犬を求める人
期待値が高い人も。
人間都合で理想を押し付けてしまう。
●問題行動への対処
犬に根気強く向き合えない人。
問題行動を起こした時にすぐに諦めてしまう人
●単身者で留守がち
留守番時間が非常に長い人
これは犬の性格にもよります。
特に分離不安などがある犬にとっては大きなストレス。
●集合住宅での規約確認
・引っ越し
・吠えの問題
で手放すことになりかねません。
集合住宅では規約を十分確認しておきましょう
5.保護団体が提示するであろう条件:その裏にある「保護犬ファースト」の視点
保護団体が提示する
譲渡条件
は時に厳しく感じられるかもしれません。
しかし、これらはすべて
保護犬が二度と不幸な目に遭わない
ための
徹底した「保護犬ファースト」
の視点に基づいています。
●終生飼育の誓約
保護犬の一生涯の責任を背負うこと
当たり前のこと
ですが、最も重要な条件です。
●完全室内飼育
特に
・小型犬
・中型犬
・繊細な性格の犬
にとっては、安心できる環境が必要です。
外飼いでは
・逃走や感染症
・熱中症
・凍傷
などのリスクが高まります。
●譲渡後の定期的な報告
犬が新しい環境で
幸せに暮らしているか
を確認するためです。
信頼関係の証でもあります。
●脱走対策の徹底
一度辛い経験をした犬ほど
▶環境の変化に敏感で
▶脱走のリスクがあります。
●不妊去勢手術の実施
※未実施の場合
・望まない命を増やさないため
・病気のリスクを減らすため
に必要です。
●先住動物との相性確認
既存の家族構成に新しい命が加わることは、先住動物にもストレスがかかります。
●経済的安定
犬の
・医療費
・生活費
を安定的に賄えるかを確認します。
●譲渡費用、交通費の負担
保護犬の
・医療費の一部
・団体運営費
に充てられます。
●同棲中のカップルへの譲渡制限
・環境の変化が起こりやすい
・責任の所在が曖昧になりがち
などの観点から
慎重な判断が求められます。
未成年者も同様です。
●高齢者単身世帯への制限
万が一の事態に備え
・引き取り手
・保証人の確保
が求められることがあります。
これらの条件は
「あなたを試している」
わけではありません。
あなたが
・犬と真剣に向き合い
・責任を持って最後まで飼育できるか
団体が一緒に確認してくれている
と捉えるべきです。
条件をクリアするために
・誠実に対応
・疑問があれば遠慮なく質問
などすることで、団体側もあなたの真剣な気持ちを理解してくれるでしょう。
6.保護犬の理想と現実:そしてその先にある「希望」
保護犬との暮らしには
理想と現実のギャップ
が存在するかもしれません。
しかし
▶そのギャップを理解し
▶乗り越えた先にこそ
他では得られない
・深い喜び
・絆
が待っています。
理想の先にある現実の喜び
●命を救う喜びと達成感
あなたの選択が
一犬の犬生を大きく変える
ことに繋がります。
●個性豊かな愛しい存在
一犬として同じ犬はいません。
その子の個性を受け入れることで、唯一無二のパートナーとなります。
●困難を乗り越えて築く深い絆
問題を一緒に乗り越えた分だけ、犬との信頼関係は強固なものになります。
●自己成長の機会
犬と向き合う中で
・忍耐力
・愛情
・問題解決能力
が培われます。
●社会貢献への意識
保護犬を迎えることは
▶動物保護活動への関心を深め
▶自己啓発に繋がることもあります。
直視すべき現実
●心の問題
◇過去のトラウマから
・人間や他の犬に対して警戒心が強い
・留守番中に問題行動を起こす
などの可能性があります。
・人間不信
・分離不安
・臆病
・攻撃性など
◇犬が抱えるストレス
または
・不安
・過去の経験
から
「吠え」
「噛みつき」
「トイレの失敗」
などの問題行動があることも
●身体の問題
・潜在的な病気
・持病
が後から見つかり、医療費がかさむ可能性があります。
●しつけの問題
・過去にしつけを受けていない
・誤ったしつけをされてきた
などのために
・基本的なコマンドが入らない
・散歩ができない
などの問題がある場合があります。
●社会化不足
・新しい環境
・人
・他の犬
に慣れるまでに時間がかかり
ストレスを感じやすい
ことがあります。
●環境の変化への適応
新しい家に慣れるまで
・食事を摂らない
・隠れて出てこない
などの行動が見られることもあります。
しかし、これらの一見
「デメリット」
に見える部分も、その犬の
「個性」
であり
「これまでの犬生の証」
と捉えることができます。
そして、これらの問題の多くは
・適切な理解
・根気強いアプローチ
そして必要であれば
・専門家のサポート
を受けることで
必ず改善の兆しが見えてきます。
7.保護犬を迎えるにあたって注意すべき点:医療・しつけ・心構えの徹底

こんなはずじゃなかった…
そんな悲しい結末を避けるために
・具体的な準備
・心構え
を徹底しましょう。
医療:過去と未来を見据えた健康管理
●情報確認の徹底
保護団体から提供される
・健康情報
・過去の病歴
・治療履歴
を詳しく確認しましょう。
必要であれば
検査データを見せてもらう
など、積極的に情報収集を。
●譲渡後の健康診断
譲渡後は速やかに
▶かかりつけの動物病院を見つけ
▶全身の健康チェックを受けましょう。
特に
・歯の状態
・関節
・内臓の状態
などを重点的に診てもらうことをおすすめします。
●長期的な視点
・持病が発覚した場合
・高齢犬を迎える場合
などでは
長期的な医療費の計画
を立てる必要があります。
ペット保険の加入も検討しましょう。
●予防医療の徹底
・ワクチン接種
・フィラリア予防
・ノミダニ予防
は欠かせません。
かかりつけ医に相談しましょう。
しつけ:犬のペースに合わせた「学び直し」
●過去のしつけ状況を把握
・しつけが全くされていない
場合もあれば
・間違ったしつけをされてきた
場合もあります。
その子の現状を理解することが第一歩。
●ポジティブトレーニング
・叱る
のではなく
・望ましい行動を褒めて伸ばす
ポジティブトレーニング
を基本にしましょう。
犬にとって
・安心できる環境で
・自ら考えて行動する喜び
を教えてあげることが大切です。
●焦らない
保護犬が
・新しい環境に慣れ
・信頼関係を築く
までには時間がかかります。
特に
過去に辛い経験をした犬
は、時間をかけて
「人間は怖くない」
と理解する必要があります。
●プロの活用
・問題行動がなかなか改善しない
・しつけに自信がない
そんなときは
・動物病院の行動治療科
・信頼できるドッグトレーナー
などに相談しましょう。
一人で抱え込まないことが大切です。
心構え:揺るがない「覚悟」と「愛情」
●長い目で見る
数日で結果が出なくても落ち込まない。
・半年
・一年
・それ以上
かかることも珍しくありません。
●完璧を求めない
▶「理想の犬」像を押し付けず
▶その子の個性を受け入れてください。
・できないこと
よりも
・できるようになったこと
を喜び、褒めてあげましょう。
●家族全員で協力
飼育は一人でするものではありません。
▶家族全員で役割分担をし
▶犬に対する接し方を統一する
ことで、犬も安心して暮らせます。
●困った時の相談先
・保護団体
・かかりつけの獣医
・ドッグトレーナー
・信頼できる友人
に相談できる関係を築いておきましょう。
8.相性の見極め方:「直感」と「客観」のバランス
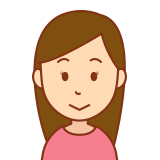
あ!きっとこの子だ!
という直感も大切ですが
・冷静に客観的な視点から
・相性を見極めること
が後悔しないための鍵です。
●譲渡会や面会時の徹底観察
◇人への態度
・警戒心が強い?
・友好的?
・近づくとどう反応する?
など
◇他の犬への態度
他の犬とどのように接しているか
・友好的?
・無関心?
・攻撃的?
など
◇触れられることへの反応
・抱っこ
・頭を撫でられる
などへの反応。
◇音への反応
・大きな音
・初めての音
にどう反応するか。
◇遊び方、落ち着き方
・遊びに積極的?
・落ち着いていられる?
◇アイコンタクト
・目を合わせてくれる?
・逃げずに見つめ返せる?
●保護団体スタッフへの徹底質問
◇犬の性格
・行動パターン
・過去の経緯
・得意なこと
・苦手なこと
◇普段の生活での様子
・散歩の様子
・食事の好み
・睡眠時間
・留守番の仕方
など
◇特に
「困った行動」
「苦手なこと」
について
▶具体的なエピソードを聞き
▶あなたが対応できるか?
想像してみてください。
●トライアル期間の活用
可能であれば
一定期間自宅で一緒に過ごす
「トライアル期間」
を設ける団体を選びましょう。
実際に生活を共にすることで
想像だけでは見えなかった
・相性
・問題点
が見えてきます。
この期間は、犬にとっても新しい環境に慣れるための重要なステップです。
9.保護犬の探し方:信頼できる団体を見極める「チェックリスト」
保護犬を探す方法は様々です
しかし最も重要なのは
「信頼できる団体」
を見つけることです。
主な探し方
●インターネット検索
「保護犬 譲渡 +住んでる地域名」
で検索。
●保護犬譲渡サイト
・OMUSUBI
・ペットのおうち
・ハグーなど
全国の保護犬情報が集約されています
●SNS
・Twitter
・Instagram
などで保護犬の情報を発信している
・団体
・ボランティア
のアカウントをフォローする。
●動物病院、地域の広報
・地域の動物病院
・役場の広報
などでも
・譲渡会
・保護活動
の情報が掲載されることがあります。
信頼できる団体のチェックリスト
□情報公開の透明性
・活動報告
・会計報告
などがきちんと公開されているか。
□譲渡条件の明確さ
条件が明確で
▶その理由が説明されているか。
□譲渡前の丁寧な審査と面談
一方的な判断ではなく、時間をかけてあなたの状況を理解しようと努めてくれるか。
□譲渡後のアフターフォロー
・困ったときに相談できる体制があるか
・定期的な連絡を求めているか
□動物取扱業の登録
法律に基づき、正式な登録をしているか。
□シェルターや一時預かりの環境
犬たちが
・清潔な環境で暮らしているか
・適切なケアを受けているか
可能であれば、見学させてもらいましょう。
□医療ケアの徹底
保護犬が適切な医療
・ワクチン
・不妊去勢手術
・マイクロチップ装着
・健康診断
を受けているか。
10.受け入れ準備:「ようこそ、我が家へ」その日からの始まり
保護犬を迎える日を
心待ちにしながら
それでいて
着実に
準備を進めましょう。
物理的準備:安心できる「基地」を作る
●犬の「基地」の準備
・ケージ
・サークル
・ベッド
・毛布など
犬が
安心して過ごせるプライベートな空間
を確保しましょう。
最初のうちはこの基地が
一番落ち着ける場所
になります。
●食事と水
・食器
・給水器
・給水ボトル
・皿型など
犬の好みや慣れに合わせる
フードは、保護団体が与えていたものと同じものを最初は用意し、徐々に切り替えるのがストレスを減らすポイントです。
●散歩用品
・首輪
・ハーネス
・リード
特にハーネスは
脱走しにくいタイプ
を選びましょう。
●トイレ用品
・トイレシート
・トレー
●おもちゃ、お手入れ用品
・噛むおもちゃ
・ブラッシング用品
・爪切りなど
●緊急時の連絡先
・かかりつけの動物病院
・夜間救急病院の連絡先
をすぐにわかる場所に控えておく。
●脱走対策の徹底
・ドア
・窓
・ベランダの鍵
・玄関からの飛び出し防止ゲート
・網戸の補強など
万全の脱走対策を講じましょう。
特に保護されたばかりの犬は
▶環境の変化に戸惑い
▶脱走を試みることがあります。
心の準備:焦らず、ゆっくりと
●家族会議で共通認識を持つ
犬を迎えることの
・責任
・役割分担
・犬への接し方
について
・家族全員で話し合い
・共通の認識を持つ
ことが大切です。
●最初の数日間はそっとしておく覚悟
新しい環境は犬にとって
非常に大きなストレス
です。
最初のうちは
▶無理に構いすぎず
▶犬のペースに合わせて
そっとしておいてあげましょう。
●「完璧な犬」を求めない
期待値を上げすぎず、犬が
「普通」に暮らしてくれる
「それだけで幸せ!」
という気持ちで迎え入れましょう。
●長期的な視点
信頼関係を築くには時間がかかります。
・焦らず
・根気強く
向き合う覚悟が必要です。
11.受け入れてからの注意点:信頼を築き、共に歩む日々
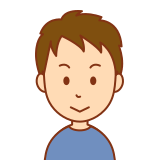
いよいよ今日から新しい家族が増えるんです!
ここからが、真のスタートです。
最初の数日間:静かに見守る「お出迎え」
●焦らない
犬は
・新しい環境
・新しい人間
に戸惑っています。
無理に
・抱っこしたり
・撫でたり
しないで
犬のペース
に合わせましょう。
●お出迎えモードになりすぎない
大勢でワーッと歓迎すると
▶犬は圧倒されてしまいます。
・静かに見守る
・犬が自ら近づいてくる
のを待ちましょう。
●ルーティンの確立
・ごはん
・トイレ
・お散歩など
基本的な生活リズム
をなるべく早く確立し、犬に安心感を与えましょう。
●安心できる場所の提供
・ケージ
・サークル
は犬にとっての「安全基地」です。
いつでもそこに逃げ込めるようにしてあげましょう。
おびえるときの接し方:その子の「声」に耳を傾ける
●無理強いしない
怖がっている犬に
・無理に近づいたり
・触ろうとしたり
すると
さらに人間不信
になる可能性があります。
●低い姿勢で優しく声をかける
▶目線を低く合わせ
▶穏やかな声で「大丈夫だよ」
と安心させてあげましょう。
●そっとしておく時間も大切
落ち着くまで、そっとしておいてあげることも必要です。
●ポジティブな体験を増やす
怖がらない距離から
・おやつをあげる
・おもちゃを転がす
など
あなたとの良い体験
を積み重ねていきましょう。
●「叱る」ではなく「教える」
問題行動の多くは、犬が
・不安
・ストレス
を抱えているサインです。
原因を探り、その行動を
「やめさせる」
のではなく
「どうすれば良いか」
を教えてあげましょう。
問題行動への対応:諦めずに「寄り添う」姿勢
●原因を探る
・無駄吠え
・破壊行動
・トイレの失敗
・攻撃性など
問題行動には必ず原因があります。
・分離不安
・運動不足
・ストレス
・痛みなど
可能性を一つずつ探りましょう。
●ポジティブトレーニング
▶望ましい行動を促し
▶褒めて強化する
トレーニングを続けましょう。
●専門家の力を借りる
どうしても解決できない場合は
・動物病院の行動治療科
・経験豊富なドッグトレーナー
に相談することを躊躇しないでください。
・プロの視点
・適切なアドバイス
は、あなたの大きな支えになります。
●決して諦めない
問題行動の改善には時間がかかります。
途中で心が折れそうになることも…
しかし
その子の未来のために
粘り強く向き合いましょう。
健康管理と定期検診:生涯にわたる「責任」
●定期健診
・定期的な健康チェック
・ワクチン接種
・フィラリア予防
・ノミダニ予防
は欠かせません。
●少しでも体調の変化を感じたら
すぐに獣医に相談しましょう。
・早期発見
・早期治療
それこそが
・犬の負担を減らす
だけでなく
・医療費の軽減
にも繋がります。
●食事や体重管理も重要
適切なフードを選び、肥満にならないよう注意しましょう。
結び:保護犬との未来は、あなたと犬の幸せな共生という名の「物語」
保護犬を迎えることは、確かに困難な道のりであるかもしれません。
しかし
▶その困難を乗り越え
▶共に成長していく中で
あなたと犬の間には、何ものにも代えがたい深い絆が生まれます。
一見デメリットに見える部分も
・その子が歩んできた「歴史」
であり
・その子の「個性」
それを
・丸ごと受け止め
・愛情を持って接する
ことできっと
▶あなたに心を開き
▶最高のパートナーとなってくれるでしょう。
このブログ記事が、一人でも多くの人が
「保護犬を迎えてみようかな」
と前向きに考え、そして何よりも
「こんなはずじゃなかった」
ではなく
「保護犬を迎えて本当によかった」
と心から思える、幸せな共生への第一歩となることを心から願っています。
あなたの手で、保護犬の
「第二の犬生」
を温かい光で満たしてあげませんか?

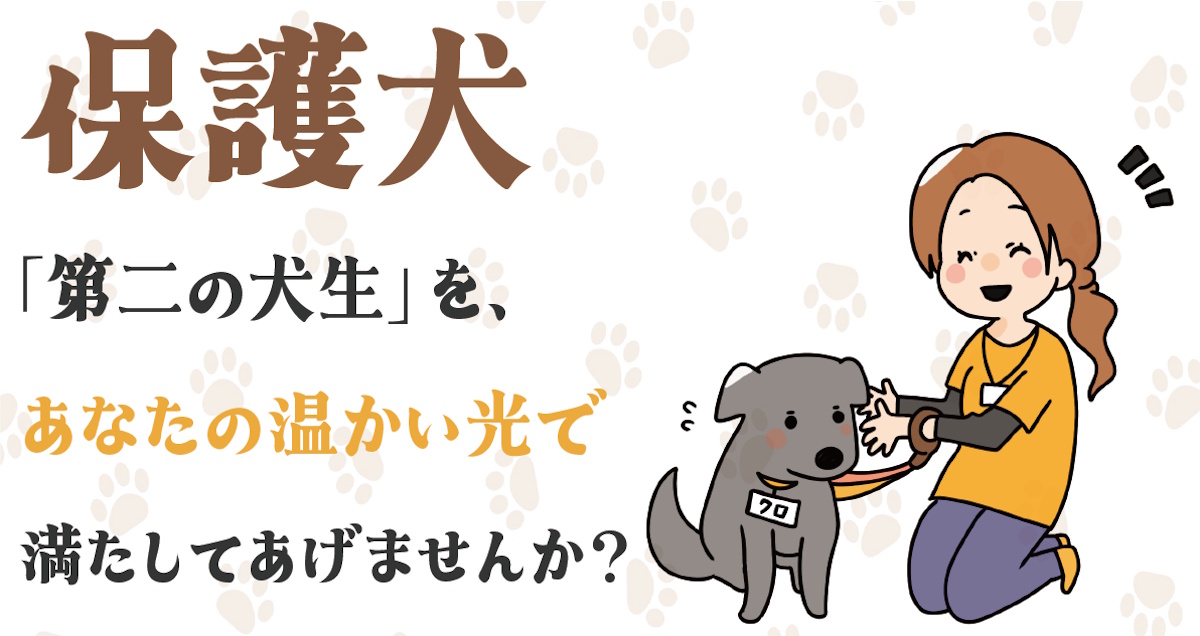

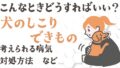
コメント