もしかして…
この記事を読んでくれるあなたは
愛する家族を失ったばかりで、計り知れない悲しみの中にいるのかもしれません。
もしそうであれば、心よりお悔やみ申し上げます。
・深く心を痛めている方
あるいは
・ご自身のペットロスとの向き合い方
を探している方もいらっしゃるでしょう。
また、ご自身の悲しみと向き合いながら、
大切なご家族の心のケアについて
・真剣に学び
・寄り添おうとされている
方もいるかもしれません。
どのような状況であっても、このページにたどり着いたあなたの心には、きっと
愛犬への深い想い
があることと思います。
この記事では
・ご自身の悲しみを乗り越える
そして特に
・他のご家族のペットロスを癒す
ための方法を紹介していきます。
あなたのご家族へのサポートは
専門家でも決して真似のできない
・深く
・温かい
愛情と絆
に根差したかけがえのないものです。
長年愛犬とともに過ごした
最も身近な存在だからこそ
・言葉以上の支えとなり
・心を癒す
力があるのです。
1.ペットロスとは何か:家族を失う深い悲しみ
ペットロス(Pet Loss)とは?
愛するペットとの
・死別
・何らかの理由による別離
・行方不明
・盗難
・災害など
によって生じる
・心身の様々な苦痛
・症状
を指します。
近年、ペットは単なる動物ではなく
かけがえのない家族の一員
として認識されるようになりました。
そのため、ペットを失う悲しみは
・人間との死別に匹敵する
あるいは
・それ以上の喪失感
として経験されることが多くあります。
かつてペットは
「たかが動物」
と軽視されがちでした。
しかし現在では、その深刻さが広く認識されつつあります。
ペットロスは
・年齢
・性別
・社会的な立場
に関わらず、誰にでも起こりうる普遍的な心の反応です。
1‐2.ペットロスで現れる心身の症状
ペットロスによる悲しみは、人によって様々な形で現れます。
主な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
●精神的な症状
◇悲しみ・絶望感
・深い悲しみ
・虚無感
生きる意味を見失ったような感覚。
◇罪悪感
「もっとできたはず」
「あの時ああしていれば」
といった自責の念。
◇怒り
・獣医師
・家族
・自分自身
あるいは
・亡くなった愛犬
への怒り。
◇抑うつ
・無気力
・集中力の低下
・睡眠障害
・食欲不振
◇不安・恐怖
・一人になることへの不安
・新たな喪失への恐怖
◇麻痺・現実感の欠如
・何も感じない
・現実ではないように感じる
◇幻覚・幻聴
亡くなった愛犬の
・鳴き声が聞こえる
・姿が見える気がする
●身体的な症状
◇頭痛、めまい
◇吐き気、胃痛、胸の痛み
◇疲労感、だるさ、倦怠感
◇呼吸困難、動悸、過呼吸
◇免疫力の低下、体調不良が続く
これらの症状は
ごく自然な心の反応
であり異常なことではありません。
しかし
・症状が重く
・日常生活に支障をきたす場合
は専門家のサポートを検討することが重要です。
2.ペットロスを乗り越えるための具体的な心のケアとサポート
ご自身が中心となって
ご家族をサポート
するために
・まずご自身のケアも大切にする
・具体的なアプローチを知っておく
ことが役立ちます。
2-1.悲しみを「許す」こと:自分と家族への受容
感情を否定しない
●「泣いていい」
悲しい時は
▶我慢せずに泣く
ことが大切です。
涙には
・感情の排泄作用
があり
・心のデトックス
になります。
泣いてばかりではいけない
と思いがちですが
▶無理に感情を抑え込むと
▶かえって長引くことがあります。
●「怒っていい」
・亡くなった愛犬
・獣医師
・病気
あるいは
・自分自身
に怒りを感じることも自然なことです。
怒りの感情も
▶吐き出すことで
▶心が少し軽くなることがあります。
●「罪悪感を抱いてもいい」
「もっとこうしていれば」
という
・後悔
・罪悪感は
深く愛していた
からこそ生まれる感情です。
自分を責めすぎず
「精一杯愛した」
という事実に目を向けるよう努めましょう。
喪失を悼むための儀式
●葬儀・火葬
適切な方法で愛犬を見送ることは
▶現実を受け止め
▶心の整理をする
上で非常に重要です。
家族で相談し
▶納得のいく形で執り行いましょう。
●供養
・遺骨を自宅に置く
・お墓を作る
・合同供養に参加する
など、それぞれの家族に合った形で供養を行うことで、心の区切りをつけることができます。
●追悼の場を作る
・写真を飾る
・好きだったおもちゃを置いておく
・日記をつけるなど
いつでも愛犬を偲べる
・場所
・方法
を作ることも心の安定につながります。
2-2.家族間のコミュニケーションと共感
ご家族でペットロスを乗り越えるためには
▶それぞれの悲しみを認め合い
▶共有すること
が非常に重要です。
互いの悲しみを尊重する
家族であっても
・悲しみの表れ方
・悲しみの深さ
は異なります。
「なぜあの子はこんなに悲しむの?」
と疑問に思うのではなく
「それぞれに悲しんでいるんだな」
と受け止めましょう。
「もう元気出して」
「いつまでも悲しんでちゃダメ」
といった励ましは
▶相手を追い詰めることがあります。
無理に前向きにさせようとせず
「悲しんでいてもいいよ」
「つらいね」
とただ寄り添い
▶共感する姿勢が大切です。
思い出を語り合う
・愛犬との楽しかった思い出
・一緒に経験した出来事
などを家族で語り合いましょう。
笑いながら話せるようになれば…
それは悲しみを乗り越え始めている証拠でもあります。
「ありがとう」
「ごめんね」
「大好きだよ」
など
伝えきれなかった気持ち
を言葉にすることも、心の整理につながります。
身体的接触の重要性
・手をつなぐ
・肩を抱く
・そっと背中をさする
などの身体的接触は
言葉以上に
相手に
・安心感
・温かさ
を伝えることができます。
特に言葉にならない悲しみの中にいる人には有効です。
【①深く悲しんでいる相手へ】
▶ただ寄り添う
悲しみが深い時期は
▶感情を吐き出せる安全な場所を提供
▶共感と傾聴に徹しましょう。
【会話例】
※隣に座り、手を握る・肩にそっと触れるなど

・・・つらいな~

うん・・・涙

ムギがおらんようになって、ホンマに寂しいな…胸が締め付けられるみたい

うん…もう会われへんて思うと…

まだ信じられへんね。無理に元気を出そうせんでええから。悲しい時は、思っきり泣いてええねんで。

ありがとう・・・
【②罪悪感を抱いている相手へ】
▶気持ちを和らげる
「もっとできたはず」
「あの時こうしていれば」
といった罪悪感に苛まれている場合
▶その気持ちを理解し
▶否定しない姿勢が重要です。
愛からくる感情
であることを伝えましょう。
【会話例】

あの時、もっと早く病院に連れて行ってたら、ムギは助かっとったかもしれん…

そんなことないよ。ムギのためにホンマにできる限りのことをしてあげてたやん。どんなけムギを大切にしてたか・・・うちはずっと見てたよ。

でもな…もっと他に何かできたんちゃうかって、ずっと考えてまうねん。

ムギへの愛情が深いから、そう思うんやで。その気持ちは、めっちゃ分かる。でもムギのために一生懸命、できることは全部やったって思うよ。ムギもその愛情を、全部知っとったと思うし…自分を責めたらあかんよ。
【③怒りや不満を感じている相手へ】
怒りの感情は悲しみの裏返し
であることが多いため
▶その感情を受け止め
▶吐き出せるように促しましょう。
【会話例】
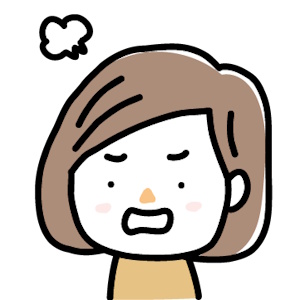
なんでこんなことになったん(怒)あの獣医さん、もっと早く気づいてくれたらよかったのに!
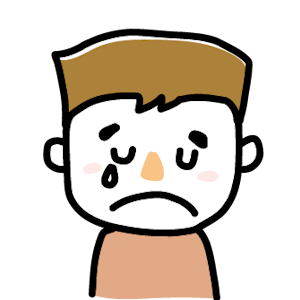
なあ、悔しいよな。そう思うのもしゃあないよ。俺も…なんでこんなに早くムギが…って、腹立ってくる。
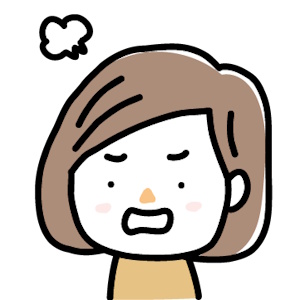
ホンマに納得いけへんねん…
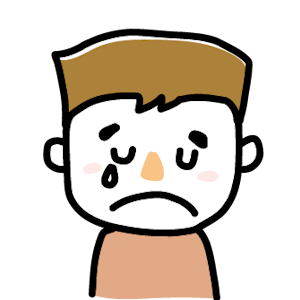
そうやな。その気持ち、言いたいこと、全部俺に話してくれていいから。話してくれるだけで、嬉しいで。
2-3.日常生活の維持と小さな変化
悲しみの中でも
▶できる範囲で日常生活を維持し
▶少しずつ変化を取り入れること
が回復を助けます。
●生活リズムを整える
規則正しい
・食事
・睡眠
は心身の健康を保つ上で不可欠です。
食欲がなくても、食べやすいものから少量ずつ摂取するなど、できる範囲で栄養を摂りましょう。
睡眠不足が続く場合は、専門家に相談することも視野に入れましょう。
●適度な運動
・散歩
・軽いストレッチなど
体を動かすことは気分転換になり
▶心の健康にも良い影響を与えます。
愛犬との散歩コースを、歩いてみるのも一つの方法です。
●気分転換とリフレッシュ
無理のない範囲で
・好きな音楽を聴く
・映画を観る
・自然に触れるなど
気分転換になる活動を取り入れましょう。
ただし
・無理に明るく振る舞う
楽しいことをしようとして
・かえって疲れてしまう
などのないよう、ご自身のペースを大切にしてください。
●愛犬の遺品との向き合い方
愛犬が使っていた
・ベッド
・食器
・おもちゃなど
すぐに片付ける必要はありません。
無理に処分せず
▶心が落ち着いてからゆっくりと整理しましょう。
・写真
・動画
を見返すことは
▶良い思い出を振り返り
▶感謝の気持ちを育む
ことにつながります。
【④少しずつ回復に向かっている、あるいは日常を取り戻そうとしている相手へ】
悲しみが少しずつ和らぎ
▶前向きな気持ちが見え始めた時
その小さな変化を
・肯定し
・支える
言葉をかけましょう。
【会話例】
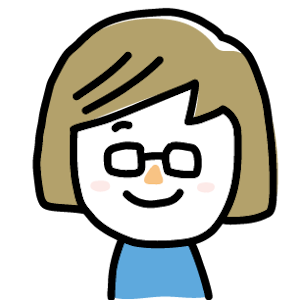
この写真のムギ、ホンマにおもろかったね(笑顔)

ホンマに!顔が最高(笑)!あんな表情なかなか見んで。ムギとの思い出は全然数え切れへんな。
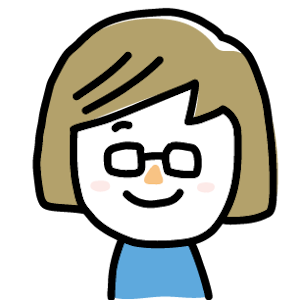
やな~。時々まだ悲しくなるけど、最近は楽しかったことの方を思い出せるようになってきたわ。

ええやん。無理に忘れんでいいし、悲しい時はまた悲しもや。楽しい思い出を笑顔で話せるようになったのは、ホンマにすごい!ムギも、絶対喜んでると思うで。
2-4.周囲の理解とサポートを求める
・自分
・家族
だけで抱え込まず、外部のサポートも積極的に利用しましょう。
●理解ある友人に話す
・ペットロスを経験した友人
・動物を飼っている友人
はあなたの気持ちを理解してくれる可能性が高いです。
安心して気持ちを打ち明けられる人を見つけましょう。
ペットを飼ったことがない人
の中には
・ペットロスを理解できない人
もいるかもしれません。
そのような場合は
▶無理に理解を求めず
▶距離を置くこと
も大切です。
●ペットロスサポートグループ
同じ経験をした人たちが集まるグループに参加することで
・共感
・連帯感
が得られます。
自身の体験を語り
▶他者の話を聞くことで
・孤独感が和らぎ
・回復への道筋が見えてくる
ことがあります。
オンラインのコミュニティもあります。
●専門家への相談
・悲しみが長期化している
・日常生活に著しい支障が出る
などの場合は
・心療内科医
・精神科医
・公認心理師
・カウンセラー
あるいは
・ペットロス専門のカウンセラー
などの専門家に相談することをためらわないでください。
獣医師の中には
・ペットロスケアに理解があり
・飼い主の精神的ケアも提供
している方もいます。
まずはかかりつけの獣医師に相談してみるのも良いでしょう。
・日本アニマルウェルネス協会
・日本動物病院協会(JAHA)
などの団体が、ペットロスに関する
・情報提供
・相談窓口を紹介
している場合があります。
3.新しい家族(子犬)を迎えることとペットロスケア:その効果と向き合い方
新しい家族を迎えること
はペットロスケアにおいて非常に大きな効果をもたらす可能性があります。
しかし、同時に
デリケートな問題
であり、その
・タイミング
・心の持ちよう
によっては
・かえって悲しみを深める
・新しい子にとって負担になる
などの可能性もあります。
3-1.新しい家族がもたらすポジティブな効果
●生きる活力・生きがいの回復
子犬の世話を通じて、日常生活に
・新しい目的
・活力
が生まれます。
●「責任感」と「行動意欲」の再燃
新しい命を預かる責任感が
▶閉塞していた心を動かし
▶行動を促します。
●新たな愛情の対象と心の癒し
行き場をなくした愛情を再び注ぎ
新しい子の
・無邪気さ
・温もり
が大きな癒しとなります。
●後悔の克服と「愛の継承」
先代犬にしてあげられなかったことを
▶新しい子に活かすことで
▶後悔を学びへと昇華し
▶愛を次の命へとつなぐ感覚を得られる
●笑顔が戻り家族の絆を再構築
家庭に
・明るさ
・笑い
が戻り、家族の絆を再構築するきっかけとなります。
3-2.新しい家族を迎える際の重要な注意点
●タイミングの見極め
最も重要なのは
心の準備が整っているか
です。
・悲しみがまだ深い時期
・衝動的に
「寂しさを埋めるため」
「亡くなった子の代わり」
といった理由で迎えるのは避けるべき。
●「代わりではない」という認識の徹底
新しい子は
亡くなった愛犬の「代わり」
ではありません。
それぞれが
・独立した個性を持つ
・新しい命である
ことを深く認識し
比較しないこと
が大切です。
●新しいペットへの負担
飼い主の心が不安定だと
新しい子に
・十分なケアができない
・比較してしまう
など双方にストレスがかかる可能性があります。
●予期せぬ困難への準備
子犬を迎えることは
・喜び
だけでなく
・しつけ
・病気
・医療費など
新たな苦労も伴います。
これらに対処できる
心身の余裕があるか?
確認しましょう。
3-3.実際の飼い主の声から見るリアリティ
ペットロスを経験した飼い主さんたちの声を見ると
新しい愛犬を迎えること
に対する多様な
・感情
・経験
が垣間見えます。
【新しい子を迎えて良かったと感じる声】
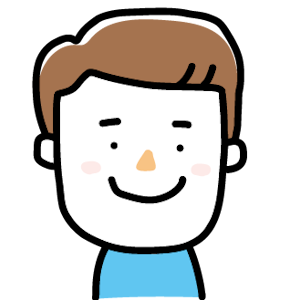
あの子が亡くなった直後は引きこもりがちやったけど、新しい子のお世話で強制的に外に出るようになって、気分が晴れた
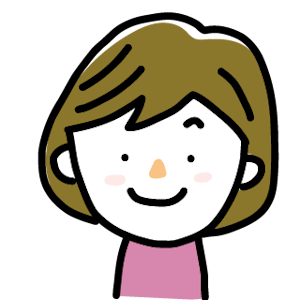
最初は罪悪感があったけど、新しい子の無邪気な姿を見てたら、自然と笑顔に。亡くなった子も喜んでくれていると思う

先代の子にしてあげられなかったことを、この子にはしてあげたいという気持ちが、前向きな原動力になった

家の中が明るくなって、家族間の会話も増えた。またみんなで動物との生活を楽しめるようになって、ホンマに幸せ
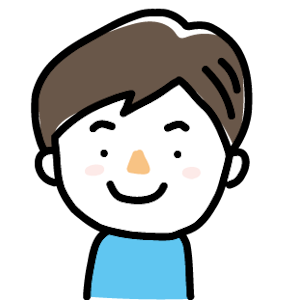
新しい子もめっちゃ可愛くて、亡くなった子とはまた違う愛おしさ。どっちも大切で、心の中に生きてる
【新しい子に葛藤や難しさを感じた声】

新しい子を可愛がれば可愛がるほど、亡くなった子に申し訳ない気持ちになってしまう

どうしても亡くなった子と比べてしまい、新しい子の個性を受け入れにくい時期があった

寂しさを埋めようと焦って迎えた結果、新しい子とうまく関係を築けず、かえってストレスになった

新しい子が亡くなった子の生まれ変わりやと期待しすぎて、現実とのギャップに苦しんだ
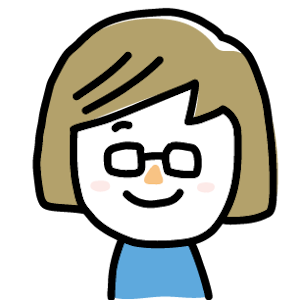
最初は愛せないと感じたけど、時間が経つにつれて徐々に愛着が湧いてきた
これらの声からも分かるように
新しい家族を迎えること
は必ずしも即座に
すべての悲しみを消し去る魔法
ではありません。
しかし
・適切なタイミング
・心の準備
があれば、失われた
「生きがい」
「愛情の対象」
を取り戻し
再び笑顔で生活する
ための大きなきっかけになる可能性を秘めていると言えるでしょう。
4.あなたが家族を支えるために:実践的なアプローチ
ご自身もつらい状況の中
ご家族のケア
を考えているあなたのために。
具体的な行動指針を紹介します。
4-1.まずは「自身の心のコップ」を満たすこと
まず最も重要なのは
あなた自身が枯渇しないこと
です。
自分を犠牲にして
▶家族を支えようとすると
▶共倒れになるリスク
があります。
●ご自身の悲しみを認める
家族を支えたいという思いから
自分の悲しみに蓋
をしてしまっていませんか?
まずは
「自分も悲しい」
という事実を認め
・泣きたい時は泣き
・休みたい時は休む
勇気を持つことが大切です。
●休息と気分転換
意識的に
・睡眠をとる
・栄養を摂る
ことを心がけましょう。
短い時間でも、愛犬とは関係ない
・趣味
・活動
に没頭する時間を作ることも必要です。
●「私」のサポート体制
あなたを支えてくれる人
・友人
・別の家族
・専門家
にあなたの正直な気持ちを話せる場を持ちましょう。
あなたが相談することで
家族をより良く支えるためのヒント
が得られることもあります。
4-2.家族の悲しみに寄り添うための具体策
家族の状況は千差万別。
それぞれのメンバーの悲しみに合わせた対応を心がけましょう。
●サイレント・グリーバーへの配慮
家族の中には
▶感情を外に出さず
▶一人で抱え込む
サイレント・グリーバー
(静かな悲嘆者)
がいるかもしれません。
特に
・男性
・感情表現が苦手な人
に多い傾向があります。
彼らも悲しんでいないわけではない。
無理に話させようとせず
・そっと見守り
・話せる時に話せる環境を整える
ことが大切です。
共通の趣味を通じて、何気ない会話の中で気持ちを聞き出すのも有効です。
●子供へのケア
子供は
死を理解する能力が未熟
なため、ペットの死を
・突然の別れ
・自分のせいだ
と感じている場合があります。
◇正直に伝える
「眠っているだけ」
「どこかへ行った」
といった曖昧な表現ではなく
「死んでしまった」
と分かりやすい言葉で伝えましょう。
◇感情の表現を促す
・泣くこと
・絵を描くこと
・お話を作る
あるいは
・愛犬への手紙を書く
・絵を描く
などの活動は
▶子供が感情を整理し
▶別れを受け入れるのを助けます。
◇ルーティンの維持
・子供の生活リズムを大きく変えない配慮
・安心できる環境を保つこと
が大切です。
●高齢者へのケア
高齢者にとって愛犬は
・孤独感を埋め
・生活にハリを与える
非常に重要な存在です。
その喪失は
・生きる意欲を失わせる
・認知機能の低下を招く
などの可能性もあります。
◇継続的な見守り
・食事
・睡眠
・外出など
日常生活の様子を注意深く見守ります。
◇思い出話の傾聴
愛犬との思い出話に
何度でも
耳を傾けましょう。
同じ話を繰り返しても
▶否定せずに
▶受け止めること
が大切です。
◇社会的な繋がり
愛犬を失ったことで
・外出機会が減る
・社会との接点が失われる
などの場合があります。
・地域コミュニティ
・友人との交流
を促し、孤立させないよう配慮します。
4-3.多頭飼育の場合:残された犬へのケア
愛する犬を亡くした時、
飼い主さんが深い悲しみに暮れる
のはもちろんです。
そして共に暮らしていた
他の犬たち
もまた、深い影響を受けています。
彼らは言葉を話せませんが
▶家族の一員を失ったことを敏感に察知
▶その悲しみや不安を様々な行動で表現
することがあります。
残された犬たちに見られる
具体的な変化
として以下のような行動が挙げられます。
◇飼い主さんへの依存度が増す
これまで以上に飼い主さんの
・注意を引こうとしたり
・後をついて回ったり
することがあります。
これは
・寂しさ
・不安
から安心できる存在に強く寄り添おうとする表れです。
◇遊びや活動の減少
元気がなくなり
・好きだった遊びに興味を示さなくなる
・散歩を嫌がったりする
など、全体的な活動レベルが低下する場合があります。
◇睡眠や行動の変化:
・眠る時間が増える
・理由もなく怖がる
あるいは
・無気力な状態になる
こともあります。
◇食欲の低下
・ストレス
・心の状態
が影響し
▶食べる量が減ってしまう
ことがあります。
◇発声行動の変化
不安やストレスから
・吠える頻度が増える
・亡くなった犬を探すように鳴く
こともあります。
これらの行動は、残された犬たちが
ペットロス
を経験しているサインです。
彼らの心のケアも、飼い主さん自身の悲しみを乗り越える上で非常に重要です。
●残された犬への具体的なケア方法
◇亡くなった犬の存在を理解させる
(強制ではない、逆効果も)
可能であれば
・亡くなった犬の遺体と
・残された犬
が対面する機会を設けることがあります。
これにより、残された犬が
「なぜ突然いなくなった?」
という混乱を少しでも減らし
▶死を理解する手助けになる
とも言われています。
しかしこれは
・犬の性格
・状況
によって判断が分かれるため
無理にさせる必要はありません。
犬によっては
より強いストレス
になる可能性もあるため、慎重に検討しましょう。
◇変化を察知し、注意深く見守る
・食欲
・睡眠
・排泄
・活動レベル
・遊びの様子など
日々の変化
を注意深く観察しましょう。
いつもと違う行動が続く場合は
▶心身に何らかの不調を抱えている
可能性があります。
◇安心できる環境を提供する
◎一貫したルーティン
・環境の変化
・喪失
で不安になっているため
・食事の時間
・散歩のルート
・遊びの時間など
可能な限り生活ルーティンを維持し
▶安定した環境を提供しましょう。
◎安心できる場所
亡くなった犬のスペースをすぐに片付けず
残された犬がこれまで通り安心できる場所を確保してあげることも大切です。
◎匂いを残す
亡くなった犬のお気に入りの
・おもちゃ
・毛布など
匂いのついたもの
をすぐに処分せず
▶残してあげることで
▶安心感につながる
場合があります。
◇積極的なコミュニケーション
残された犬たちは
飼い主さんの注意
を強く求めています。
普段以上に
・たくさん話しかけ
・撫でてあげ
・一緒に過ごす時間を増やす
温かいスキンシップは
▶彼らの不安を和らげ
▶安心感を与えます。
◇遊びや運動の時間を増やす
・遊びが減っている
・活動レベルが低下している
などの場合でも
▶飼い主さんが積極的に誘い
▶体を動かす機会を作りましょう。
・おもちゃで遊ぶ
・散歩の時間を少し長くするなど
気分転換になる活動
を促すことで
▶ストレス軽減にもつながります。
◇新しい刺激や喜びを提供する(徐々に)
悲しみが落ち着いてきたら
・少しずつ新しいおもちゃを与える
・これまで行かなかった場所に散歩に行く
など彼らの気分転換を図りましょう。
新しい出会いや活動が
▶心の回復を促すこともあります。
◇必要に応じて専門家のサポートを検討
もし
残された犬の行動の変化が著しく
・極端な食欲不振が続く
・異常な分離不安
・攻撃的になるなど
改善が見られない場合は
・獣医師
・動物行動学の専門家
・ドッグトレーナー
に相談することを検討しましょう。
・投薬
・行動療法
が必要となる場合もあります。
多頭飼育でのペットロスは
・飼い主さんの悲しみ
・残された犬たちの悲しみ
が複雑に絡み合い
▶より困難な状況になる
ことがあります。
しかし、残された犬をケアすることは
飼い主さん自身の心の回復
にも繋がります。
彼らはお互いにとって、かけがえのない存在なのです。
4-4.「お焚き上げ」や「メモリアルグッズ」の活用
愛犬の遺品は
・悲しみを深める原因
にも
・癒しとなる源
にもなりえます。
家族で相談し、
・いつ
・何を
・どうするか
を決めましょう。
●無理に処分しない
悲しみが深い時期に無理に片付ける必要はありません。
●メモリアルグッズ
遺毛や歯、爪を使った
・メモリアルジュエリー
遺灰を混ぜた
・オブジェなど
様々な形で愛犬との繋がりを感じられるグッズがあります。
これらを通じて
愛犬が常にそばにいる
と感じられることは、心の癒しになることがあります。
●お焚き上げ
心の準備ができた時に
遺品を供養する
お焚き上げ
を行うことも、区切りをつける一つの方法
4-5.予期悲嘆への視点
・愛犬の最期が近いことを知った時
または
・慢性疾患などで苦しむ姿を見た時
既に悲しみを感じ始めること。
これを「予期悲嘆」と呼びます。
●予期悲嘆の理解
これは実際に喪失が起こる前に
その喪失に対する
・悲しみ
・不安
・怒り
・罪悪感
などを経験するプロセスです。
最期の時を迎える前のケアも、グリーフケア(後述)の重要な一部です。
●積極的な関わり
愛犬が生きているうちに
・最大限の愛情を注ぎ
・共に時間を過ごす
ことは
・後悔を減らし
・死後の悲しみを軽減する
効果があります。
●ありがとう・大好きだよを伝える
最期の瞬間まで、愛犬に
・感謝と
・愛情
の言葉を伝えましょう。
●悲しみが特に大きくなるケース
・予期悲嘆の過程を経られない場合
・精神的負担が大きい選択の場合
悲しみが特に大きくなる
ことがあります。
◇突然死(事故死、急病など)
予期せぬ出来事であるため
▶心の準備ができておらず
・強いショック
・混乱
そして
「なぜもっと早く気づかなかったのか」
という自責の念が強くなる傾向。
◇安楽死の選択
重篤な病気で苦しみが大きい場合
安楽死
という選択肢を獣医師と相談することもあります。
この選択は
・非常に重く
・飼い主に深い罪悪感を残す
ことがあります。
しかし
愛犬の苦しみを終わらせるための
最後の優しさ
であるという側面も理解し
▶家族で話し合うことが大切です。
この時、獣医師からの
・十分な説明
・心理的サポート
が不可欠です。
5.ペットロスケアに関する社会的な動きと取り組み:多様化するサポートの形
ペットが
家族の一員
として深く愛される現代社会において
ペットロスは
・個人の問題
にとどまらず
・社会全体で取り組むべき課題
として認識され始めています。
5-1.法制度・資格の整備と専門職の誕生
●愛玩動物看護師国家資格化の意義
2023年春に「愛玩動物看護師」が
国家資格
となったことは
日本の動物医療における
大きな転換点
です。
この資格のカリキュラムには
・動物のターミナルケア(終末期医療)
・グリーフケア(悲嘆ケア)
に関する内容も含まれており
飼い主の心のケア
も医療の一環として重要である
という社会的な認識が高まっています。
●民間資格の多様化と専門性の向上
ペットロスケアマネージャー
などペットに関連する民間資格は多岐にわたります。
これらの資格は
・カウンセリング技術
・コミュニケーションスキル
・グリーフケアの理論など
▶心理学的な要素を重視し
▶専門的な知識を持って飼い主に寄り添える人材の育成を進めています。
5-2.サービス・施設の進化とグリーフケアの浸透
●ペット葬儀・霊園の専門化とホスピス
・人間の葬儀に近い形式で執り行われる
=葬儀施設
・終末期を穏やかに過ごすための
=ペットホスピス
などが登場しています。
これらは単に物理的な見送りだけでなく
・飼い主が悲しみを表現し
・心の整理をつけるための「場」
としての機能も果たしており、グリーフケアの観点から重要視されています。
●動物病院のホスピス・グリーフケア導入
・獣医師
・動物看護師
が終末期の動物に対する
・緩和ケア
・疼痛管理
だけでなく
飼い主への精神的なサポート
も積極的に取り入れる病院が増えています。
●様々なコミュニティ
SNSの普及により
・地域
・時間
に関わらず
ペットロスを経験した人々
が繋がれる
・オンラインコミュニティ
・フォーラム
が数多く存在します。
・匿名で悩みを打ち明ける
・経験を共有する
などすることで
・孤立感を和らげ
・共感を得られる
場となっています。
また、各地で開催される
対面式のサポートグループ
では、実際に顔を合わせ
▶互いの悲しみに寄り添い
・具体的なアドバイス
・情報交換
を行うことができます。
5-3.社会的・文化的な背景の変化
●高齢化社会とペットの役割
高齢者にとってペットは
精神的な支え
であり、その喪失は
高齢者の心身に大きな影響
を与えるため、社会的なケアの必要性が高まっています。
●「家族」という認識の深化
かつての日本では、犬や猫は
「番犬」
「鼠捕り」
といった役割を持つ動物であり、
屋外で飼育されること
が一般的でした。
しかし現在では
・住宅環境の変化
・ライフスタイルの多様化
により室内で共に生活し
人間の「パートナー」
として迎え入れられることが主流です。
・SNSでのペットの投稿
・ペット関連商品の市場拡大
は、ペットが「家族」としての地位を確立したことを物語っています。
この認識の変化がペットロスを
より深刻な問題
として捉える社会の動きを後押ししてます
●死生観の多様化
・伝統的な仏教的な死生観
に加え、ペットの供養においても
「お骨を身につける」
「遺品を大切に保管する」
など個々人の
・死生観
・価値観
に合わせた多様な選択肢が生まれています。
社会が
▶個人の悲しみを尊重し
▶様々な形での悼み方を受け入れる方向へと変化している
と言えます。
6.関連する心理学の知識:悲しみを理解し、寄り添うために
ペットロスケアにおいて
・悲嘆のプロセス
・個人の心の動き
を理解するためには
心理学の基礎知識
が不可欠です。
6-1.愛着理論
●愛着の形成
愛着理論とは?
人間が特定の対象
・親
・パートナーなど
との間に築く
情緒的な絆=愛着
に関する理論です。
この愛着は人が
・安心感
・安全基地
を得るための基盤となります。
子供が安心して外界を探索できるのは
安全な基地(=愛着対象)
があるからこそ、とされています。
愛犬との関係において
飼い主は愛犬に対して
深く安定した愛着
を形成します。
愛犬は飼い主にとって
条件なしに愛情を注いでくれる存在
であり
時に人間関係では得られない
・安らぎ
・充足感
を与えてくれます。
●喪失と愛着の断絶
愛するペットの死は、この
深く形成された愛着の
「断絶」
を意味します。
愛着の対象が失われることで
人は
・強い不安
・苦痛
・分離不安
を感じます。
これは
幼い子どもが母親と離れて不安になる
のと同じ心理的メカニズムが働くため。
飼い主にとって愛犬は
単なる「飼育動物」
ではなく
「かけがえのない存在」
「心の支え」
「生きがい」
であったのです。
そのためその喪失は
自身のアイデンティティの一部を失う
かのような感覚に陥ることもあります。
家族の中でも
特に愛犬に深い愛着を抱いていた人が
▶他の家族よりも深刻なペットロスに陥りやすい
のは、この愛着の深さに起因すると考えられます。
6-2.グリーフケア
グリーフケアとは?
愛する存在の喪失によって生じる
深い悲嘆=グリーフ
に対し
・心理的
・社会的
・精神的
な側面から包括的にサポートするアプローチです。
悲しみを
「病気」
としてではなく
誰もが経験しうる
「自然なプロセス」
として捉え
▶その人が悲しみを乗り越え
▶新しい人生を再構築できるよう支援する
ことを目的とします。
●悲嘆(グリーフ)のプロセス
~心の回復への道筋
ペットロスで経験する心の動きは
一般的に
悲嘆のプロセス
として理解されています。
これは
段階的に進む
とされていますが
・必ずしも直線的に進む
わけではなく
・行ったり来たりする
こともよくあります。
このプロセスを知ることで
▶自分や家族の心の状態を理解し
▶不安を軽減することができます。
●悲嘆の5段階説
(キューブラー・ロスモデル)
死の受容の5段階説
※エリザベス・キューブラー・ロス提唱
はペットロスにも当てはまると言われます
1.否認
「嘘だ」
「信じられない」
など現実を受け入れられない段階。
▶一時的に感情を麻痺させ
▶心の防御壁を築きます。
2.怒り
悲しみや苦しみを
・周囲の人
・獣医師
・神様
あるいは
・亡くなった愛犬自身
など何かに向けてぶつける段階。
「なぜ私だけがこんな目に」
「もっと早く気づいていれば」
といった感情が噴き出します。
3.取引
「もしあの時こうしていれば」
「もし元気になってくれたら何でもする」
といった
失ったものを取り戻したい
という気持ちから
▶何らかの条件と引き換えに
▶現実を変えようとする段階。
4.抑うつ
現実を受け入れ始め
・深い悲しみ
・絶望感
に打ちひしがれる段階。
無気力になり、ひどい場合は
・食欲不振
・睡眠障害
を伴うこともあります。
この段階で最も
心理的なサポート
が必要となることが多いです。
5.受容
最終的に
▶喪失の現実を受け入れ
▶悲しみと共に生きていくこと
を見出す段階。
これは「忘れる」のではなく
悲しみを乗り越えて、亡き愛犬との思い出を心の中で大切にする
という意味です。
●悲嘆は「仕事」である
(グリーフワーク)
ノルウェーの精神科医
ヨハン・サザーランドは悲嘆を
グリーフワーク(悲嘆の仕事)
と呼びました。
これは悲しみを癒すためには
▶意識的に心と向き合い
▶様々な「仕事」をする必要がある
という意味です。
グリーフワークには、以下のような要素が含まれます。
◇喪失の現実を認める
亡くなった事実から目を背けず、受け入れること。
◇悲しみの感情を経験する
・泣くこと
・怒ること
つらい気持ちを我慢せずに感じること。
◇環境への適応
愛犬のいない生活に慣れ
・役割
・生活習慣
の変化に対応すること。
◇感情の再投資
亡くなった愛犬に注いでいた
・愛情
・エネルギー
を新たな対象
・人
・趣味
・活動など
に向けていくこと。
この「仕事」には個人差があります。
完了するまでの期間も人それぞれ。
焦らず、ご自身とご家族のペースで進めることが大切です。
●グリーフケアの役割
グリーフケアは
グリーフワークを円滑に進める
ための手助けをします。
◇共感と傾聴
グリーフケアの基本は
悲しむ人に
・寄り添い
・傾聴する
ことです。
・安易な慰め
・励まし
はせずに
▶相手の言葉にならない苦しみを受け止め
▶感情を吐き出せる安全な空間を提供する
「つらいね」
「よく頑張っているね」
といった共感の言葉が、何よりも相手の心を癒します。
◇感情の表出と受容の促進
・感情の表出を促し
喪失の現実を受け入れられるよう
・ゆっくりと見守り
過去の思い出を再評価し
▶未来に向けて感情を再投資できるよう導きます。
◇多様な悲嘆への対応
悲嘆が必ずしも
一定の段階を踏む
わけではないこと、また
複雑性悲嘆
に陥る可能性があることを理解します。
このような場合
・専門的な心理療法
・精神科医
の介入が必要となることがあります。
◇文化的・社会的背景の考慮
その人の
・文化的背景
・社会的状況
・周囲の理解が得られにくい
・一人暮らしであるなど
も考慮に入れます。
ペットロスはまだ社会的に
軽視されがち
な側面があります。
そのため、その中で悲しむ人が
孤立しないよう
配慮することも重要です。
6-3.感情焦点型コーピングと問題焦点型コーピング
ストレス対処法=コーピング
の観点からも、ペットロスを理解することができます。
●感情焦点型コーピング
・悲しみ
・苦しみ
といった
「感情」そのもの
に焦点を当て
▶その感情を調整しようとする対処法。
ペットロスにおいては
悲しみを表現すること
がこの
感情焦点型コーピング
に当たります。
これは
感情を健康的に処理
するために非常に重要です。
例えば
・泣く
・故ペットの思い出を語る
・誰かに話す
・日記をつける
・気分転換をする
・お酒を飲む など
(一時的な逃避にもなりうるので注意)
●問題焦点型コーピング
悲しみの原因となっている
「問題」そのもの
に焦点を当て
▶その問題を解決しようとする対処法。
例えば
・ペットの供養について調べる
・ペットロスに関する書籍を読む
・サポートグループに参加する
・新しい愛犬を検討する。
家族のペットロスを支えるあなたが
・情報収集
・具体的なケアの方法を模索
などしているのは、この問題焦点型コーピングの一例と言えます。
ペットロスにおいては
・両方のコーピングを
・バランス良く用いること
が重要です。
①まずは感情を十分に表現し
その後
②少しずつ具体的な行動に移す
ことで、回復への道筋が見えてきます。
7.あなたのサポートと専門家の役割:連携がもたらす最善のケア
あなたがここで培われた
・知識
・スキル
はご家族という
最も身近で大切な存在
を支える上で
・最大限の効果を発揮する
・かけがえのないもの
です。
それは、専門家には提供できない
深い愛情と絆に基づくサポート
なのです。
しかし、時には
専門家の介入
が必要となる場面もあります。
あなたがご家族を支える上で

どんな状況になったら専門家に相談すべきなの?
その判断基準を知っておくこと
は非常に重要です。
また専門家との連携は
▶最善のケアへと繋がります。
7-1.専門家が介入すべきシーンの例
以下のような状況が見られる場合
それは専門家のサポートを検討すべきサインです。
あなたの愛情深いサポートだけでは、対処が難しい段階に入っているかもしれません
●悲嘆が非常に長期化・慢性化して
◇愛犬を亡くしてから
・半年~1年以上経っても
・悲しみがほとんど軽減せず
・日常生活に著しい支障が出ている
・仕事に行けない
・学校に行けない
・家事が全くできないなど
◇食欲不振や不眠が続き
▶体重が著しく減少している
または
▶心身の不調が慢性化している。
◇亡くなった愛犬のことで頭がいっぱいで
他のことに全く興味を示さない
◇特定の症状が長期化し
亡くなってから数年経っても
その時の
・情景
・感情
が今そこで起こっているかのように
・鮮明に
かつ
・突然
フラッシュバックとして蘇る。
●精神疾患の兆候が見られる
◇重度の抑うつ状態
・強い無気力
・絶望感
・趣味への関心の喪失など
が続き、うつ病の可能性が高い。
◇極度の不安感・パニック発作
が頻繁に起こる。
◎幻覚や妄想
・亡くなったペットが本当にそこにいると信じ込む
・誰かに監視されていると感じるなど
が見られる。
◎自傷行為
リストカットなど
◎自死念慮
「いっそ死んでしまいたい」
「愛犬のところに逝きたい」
と口にする
具体的な計画を立てようとするなど
あるいはそうした行動の兆候が見られる。
●日常生活や社会生活への適応が困難
◇仕事や学業、家庭での
役割を全く果たせない。
◇人間関係を完全に断ち
▶引きこもりがちになっている。
◇アルコールや薬物への依存が見られる。
●家族のコミュニケーションが破綻
◇ペットロスを巡って
▶家族間の対立が激しく
▶話し合いができない。
◇特定の家族の精神状態が
▶他の家族にも深刻な影響を与えている。
7-2.専門家との連携がもたらす最善のケア
上記の状況が見られる場合
・公認心理師
・臨床心理士
・心療内科医
・精神科医
または
ペットロス専門のカウンセラー
など専門家への相談を強く推奨します。
●正確な診断と適切な治療
専門家は
・単なる悲嘆反応なのか
それとも
・医学的治療が必要な精神疾患なのか
を鑑別し、必要に応じて薬物療法を含む
適切な治療計画
を立てることができます。
●専門的な介入技法
・複雑性悲嘆
・トラウマ
・うつ病など
特定の精神症状に対しては
・感情焦点型カウンセリング
だけでなく
・認知行動療法
・EMDRなど
より専門的な心理療法が有効な場合があります。
ストレスを感じた出来事に対する
・考え方を見直す
・行動パターンを改善する
などで
・気分
・感情
を楽にすることを目指す療法
※EMDR
トラウマとなる出来事を思い出しながら
▶眼球運動などの刺激を体験することで
▶記憶の処理と統合を促進します
●危機介入と安全確保
自死念慮など
緊急性の高い状況では専門家の
・迅速な危機介入
・安全確保
が不可欠です。
●守秘義務と倫理
専門家は
守秘義務
を負っています。
そのため
・安心して
・深い悩みを打ち明けられる
安全な場を提供できます。
あなたの
愛情深く、寄り添うサポート
はご家族の心の土台です。
専門家との連携をスムーズにする上でも非常に役立つはずです。
専門家は、あなたのサポートを
否定するのではなく
その上に
▶より高度なケアを提供し
▶ご家族が再び心の平穏を取り戻す手助けをしてくれるでしょう。
8.ペットロスにならないための予防策:悲しみを和らげ、後悔を減らすために
ペットロスは
愛する家族を失うことによる
自然な悲しみのプロセス
であり
完全に予防することは難しい
のが現実です。
しかし
・その悲しみを和らげ
・回復への道のりをスムーズにする
ための
・準備
・心構え
はたくさんあります。
大切なのは
・後悔を減らし
愛犬との時間を
・最大限に豊かなものにする
ことです。
8-1.生前からできる心の準備:後悔を減らすために
ペットロスで苦しむ要因の一つに

もっと何かできたのでは?
という
・後悔
・罪悪感
があります。
これを軽減するためには
生前からの心の準備
が重要です。
●今この瞬間の時間を大切にする
日常の中で、可能な限り
愛犬との触れ合いの時間
を増やしましょう。
・たくさん撫でる
・声をかける
・一緒に遊ぶ
・散歩に行くなど
愛情を惜しみなく表現すること
が、何よりも後悔を減らすことにつながります。
「いつかやろう」
ではなく
「今すぐ」できること
を実践しましょう。
●コミュニケーションを深める
愛犬の
・気持ち
・表情
をよく観察し
何を求めているのか?
理解しようと努めましょう。
信頼関係を築き
深い心の繋がりを感じられる時間
は、かけがえのない財産となります。
●健康管理とケアを徹底する
定期的に動物病院で健康診断を受け
▶病気の早期発見に努めましょう。
・適切な食事
・運動
・ストレスの少ない環境を整えること
も愛犬の健康寿命を延ばすために不可欠。
●終末期のケアを知る
もし愛犬が
・高齢になったり
・病気になったり
した場合は
終末期のケア
・ターミナルケア
・緩和ケア
について獣医師と相談し、知識を得ておくことが大切です。
・愛犬の苦痛を和らげ
最期まで
・その子らしく過ごせるよう
できる限りのことをしてあげる準備をしておきましょう。
●思い出を記録し、形に残す
楽しかった瞬間を
・写真
・動画
にたくさん収め
・日記
・ブログ
にエピソードを残すことも、後で振り返る良い方法です。
遺毛や歯を使った
メモリアルグッズ
についても、生前から検討する時間を持てると良いでしょう。
●命の終わりを受け入れる心構え
愛犬は
人間よりも寿命が短い
ことを改めて認識し
いつか別れが来ること
を心のどこかで覚悟しておくことが重要。
これは悲しいことですが、現実を受け入れる準備になります。
8-2.もしもの時への具体的な準備:心の整理のために
愛犬との別れは突然訪れることも。
それでも
事前に具体的な準備
をしておくことで
▶その時の混乱を少しでも減らし
▶心の整理につながります。
●葬儀・供養について話し合う
どのような形で見送りたいか?
・火葬
・土葬
・自宅供養など
家族で事前に話し合い、それぞれの希望を共有しておきましょう。
信頼できる
・ペット葬儀社
・霊園
を調べておくことも、いざという時に慌てずに済むポイントです。
●周囲の理解とサポート体制を整える
・犬を飼っている友人や知人
・地域のコミュニティ
などでペット仲間を作っておくことは非常に有効です。
また、ペットロスは
精神的な苦痛
を伴うもの。
必要に応じて
・カウンセリング
・心理的サポート
を受けられる専門機関があることを知っておきましょう。
ペットロスは
悲しくてつらい経験
ですが
・愛犬が与えてくれた深い愛情
・共に過ごしたかけがえのない時間
を再認識する機会でもあります。
悲しみが癒えるまでの時間は人それぞれですが、必ず穏やかな日が訪れます。
この記事が、あなたとご家族がこの困難な時期を乗り越え
・再び前向きな気持ちで
・愛犬との思い出を大切にできるよう
少しでもお役に立てれば幸いです。
もし、この他に何か気になることがあれば、いつでもお声がけくださいね。




コメント