ビタミン・・・K?
他のビタミンほど馴染みがないかも。
しかし、愛犬の健康にとって
特に
・万が一の出血時
・骨の健康維持
において、非常に重要な役割を担う
“縁の下の力持ち”
的な栄養素!
今日は、知られざるビタミンKの世界を深掘りしていきましょう。
ビタミンKとは?3つの顔を持つ脂溶性ビタミン
ビタミンKは脂溶性ビタミンの一つで、大きく分けて以下の3つの主要な形が存在します。
●ビタミンK1(フィロキノン)
主に
・緑黄色野菜
・植物油
に含まれる天然のビタミンK。
食事から摂取するビタミンKの主要な形の一つ。
●ビタミンK2(メナキノン群)
主に
・動物性食品(肉類、卵、乳製品)
・発酵食品
に含まれます。
特に納豆にはMK-7という強力な形が豊富です。
健康な犬の腸内細菌によっても合成されますが
・利用効率
・必要量をどれだけ賄えるか?
については、まだ議論の余地があり。
特に盲腸が小さい犬では、人間ほど効率的ではない可能性があるとされています。
●ビタミンK3(メナジオン)
人工的に合成されたビタミンKで、水溶性のものもあります。
かつてはペットフードにも添加されていましたが、
高用量での毒性リスク
が問題視されています。
現在ではAAFCOの基準では
ペットフードへの使用は
・禁止
・または厳しく制限
されています。
愛犬に対するビタミンKの期待される効果:血液凝固から骨の健康まで
ビタミンKの「K」は
血液凝固=Koagulation
に関わるビタミンとして、その頭文字から名付けられたもの。
その名の通り、ビタミンKの最もよく知られた役割は、正常な血液凝固の維持です。
●止血作用(血液凝固因子の活性化)
怪我をしたときや手術時に
▶出血を止めるため
には
▶血液中の凝固因子が正常に働く必要があります。
ビタミンKは、これらの凝固因子が機能するために不可欠な補酵素として働きます。
具体的には特定のタンパク質を、Glaタンパク質に変換する酵素を助けます。
このGlaタンパク質がカルシウムイオンと結合することで、血液凝固プロセスが進みます。
ビタミンKの役割はそれだけではありません。
●骨の健康維持
骨の形成に関わる重要なタンパク質
オステオカルシン
も先のGlaタンパク質の一つ。
ビタミンKはオステオカルシンを活性化し、カルシウムが骨に沈着するのを助けることで
・骨密度を高め
・骨を丈夫にする
働きに関与していると考えられています。
●血管の健康維持
血管壁にカルシウムが沈着する血管石灰化は動脈硬化のリスク因子。
ですが
ビタミンK依存性タンパク質である
MGP(マトリックスGlaタンパク質)
は、この血管石灰化を抑制する働きがあることが近年の研究で注目されています。
犬における詳細な研究はまだ少ないですが、将来的に重要な役割が明らかになるかもしれません。
ビタミンKの不足と過剰:愛犬に起こりうること
ビタミンKが不足するとどうなる?
●血液凝固異常(出血傾向)
・軽微な打撲でも内出血ができやすい。
・鼻血、血便、血尿が見られる。
・歯茎からの出血。
・手術や採血の際に血が止まりにくい。
◇ 重度の場合、生命を脅かす脳内出血や消化管内大出血を引き起こすことも。
●骨形成への影響
理論的には骨がもろくなる可能性も考えられますが、犬でビタミンK単独の欠乏による骨粗しょう症が明確に報告されることはほとんどありません。
健康な犬が通常のバランスの取れた総合栄養食を食べていれば、ビタミンKが深刻に不足することは稀です。
しかし、以下のような状況では欠乏する可能性があります。
【不足する主な原因】
●食事からの摂取不足
極端に偏った手作り食などで、ビタミンKが豊富な食材が長期間不足した場合。
●腸内細菌叢の乱れ
広域スペクトルの抗生物質を長期的に服用した場合、腸内細菌によるビタミンK2産生が低下する可能性があります。
多くの種類の細菌に効く抗生物質
●吸収不良
・肝疾患
(特に胆汁うっ滞を伴うもの)
・胆管閉塞
・膵外分泌不全など
脂溶性ビタミンの吸収に必要な胆汁酸の分泌や脂肪の消化吸収がうまくいかない場合。
●肝機能障害
ビタミンK依存性凝固因子は肝臓で産生されるため、重度な肝機能障害があると、ビタミンKが十分にあっても凝固因子を作れなくなります。
●特定の毒物の摂取
ワルファリン系の殺鼠剤は
▶ビタミンKの作用を阻害し
▶体内でビタミンKが再利用される「ビタミンKサイクル」をブロック
することで、重篤なビタミンK欠乏状態を引き起こし、致死的な出血を引き起こします。
誤食を発見したり疑ったりした場合は、絶対に様子を見ずに、直ちに動物病院を受診してください。
ビタミンKが過剰になるとどうなる?
●天然のビタミンK1(フィロキノン)およびK2(メナキノン群)の過剰
これらは比較的毒性が低いとされており、通常の食事や適切に配合された総合栄養食からの摂取で過剰症が問題になることはほとんどありません。
過剰に摂取された分は体外に排出されやすいと考えられています。
●合成のビタミンK3(メナジオン)の過剰
これが最も注意すべき点!
ビタミンK3は、高用量で以下のような深刻な毒性を引き起こすリスクがあります。
◇溶血性貧血
赤血球が破壊される貧血。
◇高ビリルビン血症(黄疸)
肝臓への負担。
◇肝障害、腎障害
このため、前述の通り、AAFCOではペットフードへのビタミンK3の使用を
・禁止
・または厳しく制限
しています。
市販のサプリメントを選ぶ際も
・ビタミンK3が含まれていないか
含まれている場合は
・その形態と量
に注意が必要です
※基本的には健康な犬へのビタミンK3の積極的な投与は推奨されません
その他、ビタミンKについて
●ビタミンKサイクル
体内では、ビタミンKは
・酸化
・還元
を繰り返すビタミンKサイクルという仕組みによって効率的に再利用されています。
ワルファリン系殺鼠剤は、このサイクルの還元酵素を阻害することで効果を発揮します。
●生まれたての子犬での重要性
生まれたばかりの子犬は
・腸内細菌叢が未発達
・母乳からのビタミンK供給も十分でない
場合があります。
そのためビタミンK欠乏による出血症(新生児メレナなど)のリスクが成犬より高いことがあります。
●納豆のMK-7の力
ビタミンK2の一種である
メナキノン-7(MK-7)
は、特に納豆に豊富に含まれます。
他のビタミンKに比べて
・体内での半減期が長く
・持続的に効果を発揮する
と言われています。
ただし犬に納豆を与える場合は、タレやからしは避け、少量に留めましょう。
●アンチビタミンKの存在
ワルファリン以外にも
・一部の抗生物質(特にセフェム系の一部)
・特定の種類のサルファ剤
なども、ビタミンKの作用を弱める可能性があります。
微生物の葉酸合成を阻害することで抗菌作用を示す合成抗菌薬
他の栄養素との組み合わせで相乗効果は?
●ビタミンDとカルシウム
骨の健康において、ビタミンKは
・ビタミンDや
・カルシウム
と密接に関連しています。
▶ビタミンDは
カルシウムの吸収を助け
▶ビタミンKは
カルシウムが骨に沈着するのを助けるオステオカルシンを活性化します。
これらの栄養素がバランス良く働くことで、より効果的に丈夫な骨が作られます。
●脂質(脂肪):
ビタミンKは脂溶性ビタミンのため、吸収には適度な脂質が必要です。
食事中の脂質が極端に少ないと、ビタミンKの吸収効率が低下する可能性があります。
ビタミンKの吸収をよくするためには?
●適度な脂質と一緒に摂取する
バランスの取れた総合栄養食には通常、吸収に必要な量の脂質が含まれています。
●腸内環境を整える
健康な腸内細菌叢はビタミンK2の産生に関与する可能性があるため
・プロバイオティクス
・プレバイオティクス
を含む食事も間接的に寄与するかもしれません。
●胆汁酸の正常な分泌
肝臓や胆道系の健康を維持し、脂質の消化吸収をスムーズに行うことが、脂溶性ビタミンであるビタミンKの吸収には不可欠です。
サプリとしてビタミンKを摂取するときの注意点
●基本は総合栄養食
AAFCOなどの栄養基準を満たした総合栄養食を与えていれば、健康な犬では通常ビタミンKが欠乏することも過剰になることもありません。
●自己判断での使用は避ける
特にビタミンK3のサプリメントを獣医師の指示なしに与えるのは危険です。
過剰症のリスクや、他の栄養素とのバランスを崩す可能性があります。
●肝疾患や胆道系疾患のある子
これらの疾患を持つ犬は、
ビタミンKの
・吸収不良
・利用障害
を起こしやすい状態にあります。
獣医師による適切な管理が必要です。
●殺鼠剤誤食時の対応
ワルファリン系の殺鼠剤を誤食した場合
▶ビタミンK1を解毒剤として獣医師から処方。
この場合、非常に高用量のビタミンK1を長期間投与する必要があります。
投与量や期間は
・摂取した殺鼠剤の種類や量
・犬の状態
によって大きく異なります。
必ず獣医師の指示に厳密に従ってください。
ビタミンKの薬の服用との兼ね合い
ビタミンKはいくつかの薬剤と相互作用を起こす可能性があります。
●抗生物質
広域スペクトルの抗生物質。
特に経口投与では、
▶腸内細菌叢に影響を与え
▶ビタミンK2の産生を低下させる
可能性があります。
長期連用する場合は注意が必要です。
●抗凝固剤(ワルファリンなど)
ワルファリン
=ビタミンKの作用を阻害することで血液を固まりにくくする薬。
これらを併用すると
・ビタミンKの効果が打ち消される
・逆にワルファリンの効果が減弱
の可能性があります。
●一部の抗てんかん薬
一部の抗てんかん薬は
(フェノバルビタールなど)
▶肝臓での薬物代謝酵素を誘導
▶ビタミンKの代謝を早める
可能性が指摘されています。
●胆汁酸吸着剤
コレスチラミンなどの薬
=胆汁酸を吸着して排泄を促す
▶脂溶性ビタミンであるビタミンKの吸収を阻害する可能性があります。
●非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
一部のNSAIDsは、長期使用により消化管出血のリスクを高めることがあります。
この際、正常な血液凝固機能=ビタミンKの関与が重要になります。
ビタミンKを多く含む食品の例
愛犬の食事で
・手作り食を取り入れている
・栄養バランスを考慮する
上で参考になる食品です。
これらを与える際は
犬にとって
・安全な量
・安全な調理法
をしっかり守りましょう。
ビタミンK1(フィロキノン)が豊富な食品
●緑黄色野菜
パセリ、ケール、ほうれん草、ブロッコリー、キャベツ、春菊、カブの葉、小松菜など。
犬に与える際は
・消化しやすいように細かく刻む
・加熱したりする
・アクの強い野菜は下茹で
などの調理が必要です
●植物油
大豆油、菜種油(キャノーラ油)、オリーブオイルなど。
ビタミンK2(メナキノン群)が豊富な食品:
●発酵食品
納豆(MK-7が特に豊富)、チーズなど
ネバネバ成分が腸内環境に良い影響を与える可能性も。
●動物性食品
鶏肉(特に皮や内臓)、卵黄、レバー(牛・豚・鶏)、バターなど
総合栄養食のドッグフードには、栄養基準を満たすために、多くは安全性の高いビタミンK1が添加されています。
サプリメントとしてビタミンKを摂取した時の弊害
前述の通り、健康な犬がバランスの取れた食事をしている場合、ビタミンKのサプリメントは通常不要です。
●ビタミンK3の毒性リスク
これが最大の懸念事項です。
・溶血性貧血
・肝障害
・腎障害
などを引き起こす可能性があります。
絶対に自己判断で与えないでください。
●天然ビタミンK1、K2の過剰摂取
通常のサプリメントの範囲では大きな問題は起きにくいとされます。
が、極端な過剰摂取は
・他の脂溶性ビタミンの吸収を妨げる
・栄養バランスを崩す
などの可能性があります。
●基礎疾患が隠れてしまう
ビタミンKサプリメント
▶出血傾向が一時的に改善!
しかし、その背景に
・肝疾患
・吸収不良
などの根本的な問題が隠れている場合、診断が遅れる可能性があります。
まとめ
ビタミンKは、目立たないながらも愛犬の生命維持と健康に不可欠な栄養素です。
正しい知識を持ち、適切な食事管理を心がけることで、愛犬の「隠れた守護神」をしっかりとサポートしてあげましょう。


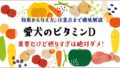

コメント