犬の肝臓病とは?
肝臓に影響を及ぼす
さまざまな病気の総称です。
病気の
・原因
・種類
は多岐にわたり、それぞれで
・治療法
・予後
も異なります。
犬の肝臓は
体内の化学工場
とも呼ばれる
体内で最も重要な臓器
の一つです。
・栄養素の代謝
・有害物質の解毒
・タンパク質の合成
・ビタミンやミネラルの貯蔵など
500以上の働きを担っています。
肝臓病の全体像と肝臓の役割
実は肝臓は
単なる化学工場の域を超え
まるで全身を管理する
司令塔
のような役割を果たしています。
主な働きとして
●有害物質の解毒
・外部から侵入する毒素
だけでなく
・体内で生じるアンモニア
などの老廃物を無害化。
体外へ排出する
浄水器のような役割
を担っています。
この機能が衰えると
▶体中に毒素が巡り
▶特に脳に影響を及ぼし
肝性脳症
という
恐ろしい神経症状
を引き起こします。
●免疫機能
・細菌
・ウイルス
を捕食する
クッパー細胞
※肝臓に存在するマクロファージの一種
が豊富に存在。
血液を病原体から守る
最前線の防衛隊
でもあります。
肝臓の機能が低下すれば
▶感染症への抵抗力も著しく弱まります
●栄養の分配
食事から得た栄養素
▶エネルギーとして使える形に変換
▶必要な臓器へと送り届ける
エネルギー供給ステーション
のような役割も担っています。
この働きが滞ると
▶全身の細胞が栄養不足に陥り
▶健康な体を維持できなくなります。
肝臓病の恐ろしさは、この
▶司令塔の機能が少しずつ失われ
▶最終的には全身の臓器が影響を受ける
ことにあります。
初期の肝臓病では
自覚症状が少ないため
気づいた時にはすでに深刻な状態
になっていることも少なくありません。
もし愛犬が肝臓病と診断された場合
それは単に
・一つの臓器の問題ではなく
・全身の健康が危機に瀕している
サインなのです。
しかし、早期に
・適切な治療
・食事管理
を行えば
▶その進行を遅らせ
▶愛犬の生活の質を保つ
ことは十分に可能です。
肝臓病は
・急激に発症する急性肝炎
・ゆっくりと進行する慢性肝炎
に大別されます。
慢性肝炎が進行すると
肝臓の組織が
・硬くなり
・線維化する
肝硬変へ移行します。
肝硬変になると
▶肝臓の機能はほとんど失われてしまい
▶命に関わる状態になります。
肝臓は再生能力が高く
▶ダメージを受けても
▶残った部分がその働きを補う動き
そのため
・初期の段階ではほぼ症状が現れず
・病気がかなり進行してから気づく
ケースが少なくありません。
これは、人間で
沈黙の臓器
と呼ばれるのと同じ理由です。
代表的な犬の肝臓病
肝炎(急性・慢性)
犬の肝臓病で最も一般的。
肝細胞に炎症が起きる病気です。
●急性肝炎
突然発症し、急激に症状が悪化します。
◇原因
・ウイルス(犬伝染性肝炎ウイルスなど)
・細菌(レプトスピラなど)
による感染、あるいは
・毒物(キシリトール、人間用の風邪薬など)
・薬物の摂取
が主な原因です。
◇特徴
早期に適切な治療を行えば回復する可能性があります
しかし重症化すると
命に関わります。
・発熱
・激しい嘔吐
・脱水
といった、急性的な症状が見られます。
●慢性肝炎
炎症が数ヶ月から数年にわたってゆっくりと進行します。
◇原因
急性肝炎が移行する場合もありますが
原因不明のケース(特発性)
が多いです。
特定の犬種に
遺伝的に発症しやすい
傾向が見られることもあります。
・ドーベルマン・ピンシャー
・アメリカンコッカー・スパニエル
・イングリッシュコッカー・スパニエル
・ミニチュア・シュナウザーなど
ではより一層の注意が必要です
◇特徴
初期は無症状のことが多く
健康診断の血液検査で
偶然、肝臓の数値が高い
ことが見つかるケースがほとんどです。
放置すると、不可逆的な変化である
▶肝硬変へと進行します。
銅蓄積性肝臓病
肝臓で
銅をうまく代謝・排泄できず
▶肝細胞内に過剰に蓄積してしまう
遺伝性の病気です。
◇原因
遺伝的な代謝異常。
特に
・ベドリントン・テリア
・ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア
・ドーベルマン・ピンシャー
・ラブラドール・レトリーバー
などで発症が多いとされています。
◇特徴
銅の蓄積により
▶慢性的な肝炎を引き起こし
▶最終的には肝硬変に至ります。
若齢期に発症することが多く
犬種的なリスク
を知っておくことが
・予防
・早期発見
につながります。
食事療法では
銅の含有量を極力抑えること
が重要になります。
門脈体循環シャント(PSS)
肝臓に流れるべき血液が
異常な血管=シャント血管
を通って全身を循環してしまう
・先天性
あるいは
・後天性
の病気です。
◇原因
生まれつきシャント血管がある
先天性の場合がほとんどです。
後天性では、肝硬変などによって
▶肝臓内を血液が流れにくくなった結果
▶シャント血管が新しく形成される
ケースがあります。
◇特徴
肝臓を迂回するため
腸で吸収されたアンモニア等の有害物質が
▶解毒されずに脳に届き
▶肝性脳症を引き起こします。
・食後のふらつき
・痙攣
・発育不良
などが典型的な症状です。
肝臓腫瘍
肝臓に発生する腫瘍で
・良性
・悪性
があります。
犬では
悪性腫瘍の発生率が高い
傾向にあります。
◇原因
発生原因は完全には解明されていません。
慢性的な炎症
などが影響していると考えられています。
◇特徴
早期発見が難しく
多くは進行してから
・食欲不振
・体重減少
・腹水
などの症状が見られます。
肝臓以外の臓器から
転移してくるケース
もあります。
治療法は
・外科手術
・抗がん剤治療
などがありますが
・腫瘍の種類
・進行度
によって予後が大きく異なります。
脂肪肝の隠された恐怖:万病の入り口
多くの飼い主さんは
愛犬の健康問題といえば
「腎臓病」
「心臓病」
を思い浮かべがちです。
しかし、実は
脂肪肝
こそが
▶知らず知らずのうちに進行し
▶全身の健康を蝕む
「万病の入り口」となり得ます。
脂肪肝が怖いのは、その
「静かなる進行性」です。
人間でいう沈黙の臓器である肝臓が
脂肪という見えない爆弾
を抱え込んでしまうようなもの。
初期には目立った症状がほとんどなく
血液検査の異常で初めて気づく
ことが大半です。
肝臓への脂肪の蓄積は
単なる肝臓の機能低下
だけにとどまりません。
肝臓の機能が低下すると
▶インスリンの働きが悪くなり
▶糖尿病の発症リスクが高まります。
また、脂肪肝は
▶慢性的な炎症を引き起こし、
▶膵炎などの他の臓器の病気にもつながる
可能性があります。
脂肪肝の原因としての「糖分」
健康な犬の体は
摂取したカロリーを
エネルギー
として効率よく使います。
しかし
・摂取カロリーが
・消費カロリーを上回る
ことによる
カロリーオーバーが続くと
余ったエネルギーは
▶肝臓で脂肪として蓄積され
▶やがて脂肪肝へと進行します。
この
カロリーオーバーの一番の原因
になりがちなのが
ドッグフードに含まれる糖質
なのです。
犬は本来肉食動物であり
人間に比べて
炭水化物の消化が苦手です。
そのため
▶高炭水化物の食事を摂取すると
▶消化器系に負担がかかり
▶代謝しきれなかった糖質が
▶肝臓に過剰な負荷をかけてしまいます。
特にドッグフードの原材料表示で
穀物(米、小麦、トウモロコシなど)
が先頭に記載されている場合
そのフードは
糖質中心の設計
になっている可能性が高いです。
また人間では
果糖(フルクトース)は
直接的に肝臓で代謝されるので
過剰な果糖は
▶すぐに肝臓で中性脂肪になりやすい
ことが知られています。
これは犬にも当てはまり
過剰な果糖の摂取は
▶脂肪肝のリスクを最も高める
要因となります。
一般的な糖質である
・ブドウ糖が
インスリンを介して
エネルギーとして利用される
のに対し
・果糖は
ほとんどが肝臓に直接運ばれ
▶中性脂肪に変換されやすい
という特性を持っています。
このため、犬の肝臓にとって
果糖はブドウ糖以上に負担が大きい
成分だと言えます。
糖質が多い
市販のドッグフード・おやつでも
果糖が直接的に添加される
ことは、さすがにあまり聞かないです。
しかし安価な糖質源として
・異性化糖(コーンシロップ)
などが使われる可能性は否定できません。
こうした成分は
・添加物
・原材料
の記載を細かく確認しなければ見落とされがちです。
甘い果物とおやつ
毎日のように
甘い果物をおやつとして与える
ことは、犬の肝臓にとって負担になる可能性が高いです。
これは
果物に含まれる果糖が
▶直接的に肝臓で脂肪に変わりやすい
性質を持つためです
特に
・バナナ
・リンゴ
・イチゴなど
は比較的多くの糖分を含んでいます。
人であれば
フルーツジュースとしてではなく
果物をそのまま食べるなど
ゆっくりとした果糖の摂取
であれば
果糖の一部をブドウ糖に変換
できます。
しかし、犬はその能力が劣ります。
そのため、犬が摂取した果糖の多くは
「果物」の形であれ
▶直接肝臓に運ばれ
▶中性脂肪として蓄積
されやすくなります。
これは、犬が
人間とは異なる代謝機能
を持つためで、過剰な果糖は
どんな形であれ
▶肝臓に大きな負担をかけ
▶脂肪肝のリスクを高めてしまうのです。
したがって
果物をおやつとして与えること自体は
NGというわけではありません
が、それでも
量と頻度には注意が必要です。
少量であれば問題ありませんが
毎日大量に与えるのは避けるべき
です。
また果物だけでなく
糖度の高い
・かぼちゃ
・さつまいも
なども
果糖ではなくても糖質が多い
ため与えすぎに注意が必要です。

安納芋とか…美味しいんだけどねぇ~
肝臓病の主な症状
肝臓病の症状は多岐にわたります。
初期では
・食欲不振
・元気がない
・下痢や嘔吐
など、他の病気でも見られるような
非特異的なもの
が多いです。
病気が進行すると、より特徴的な症状が現れるようになります。
●軽度〜中程度の症状
◇食欲不振、元気がない
最も一般的で
見過ごされがち
な初期症状です。
◇嘔吐、下痢
・消化機能の低下
・有害物質の蓄積
が原因で起こります。
◇多飲多尿
肝臓の機能低下により
▶尿を濃縮する働きが落ちるためです。
●進行した際の症状
◇黄疸
・目の白目の部分(結膜)
・歯茎
・皮膚など
が黄色くなります。
肝臓で処理しきれなくなった
ビリルビンという色素
が体内に蓄積するためです。
これは肝臓病の
非常に特徴的なサインです。
◇腹水
お腹が膨らみ
ぽっこりと出ている
ように見えます。
肝臓で合成される
タンパク質=アルブミン
が減少し、血管内の水分を保てなくなるためです。
◇肝性脳症
アンモニアなどの有害物質が
▶肝臓で十分に解毒されず
▶脳に影響を及ぼす
ことで起こります。
・ふらつき
・旋回
・意識の混濁
・痙攣
などの神経症状が見られます。
肝臓病予防するためには?
1. バランスの取れた食事
犬の栄養ニーズに合った、質の高い食事を与えることが基本です。
特に市販のドッグフードを選ぶ際は
・添加物
・消化しにくい高タンパク質
・穀物などの糖質
が多く含まれていないか?
を確認しましょう。
手作り食の場合は、栄養バランスに特に注意が必要です。
2. 定期的な健康チェック
初期症状が出にくい肝臓病だからこそ
定期的な健康診断
が何よりも重要です。
年に一度は血液検査を受け
肝臓の数値
・ALT
・AS
・ALPなど
を確認しましょう。
シニア期に入ったら
半年に一度の検査
が推奨されます。
3. 中毒に注意
・タマネギ
・ニンニク
・チョコレート
・キシリトールなど
犬にとって有毒なものを絶対に与えないようにしましょう。
また
・人間用の薬(アセトアミノフェンなど)
・カビの生えた食べ物
も肝臓に大きな負担をかけます。
4. 適切な体重管理
肥満は
▶肝臓に脂肪を蓄積させ
▶脂肪肝を引き起こす
リスクを高めます。
適切な運動と食事で、健康的な体重を維持することが予防につながります。
犬の肝臓病の治療と処方薬、食事との兼ね合い
肝臓病の治療は
・病気の原因
・進行度合い
によって異なります。
原因となる病気
・感染症
・中毒など
があればその治療を優先し
同時に
・肝臓の保護
・機能回復
を目指します。
肝臓病の治療薬の例と注意点
1. 肝臓保護剤
◇ウルソデオキシコール酸(UDCA)
胆汁の流れを改善し
▶肝臓の負担を軽減します。
副作用はほとんどありませんが、まれに下痢が見られることがあります。
◇S-アデノシルメチオニン(SAMe)
抗酸化作用があり、肝細胞を保護。
消化器系への負担が少ないとされます。
2. 食事との兼ね合い
多くの肝臓保護剤は
食事の影響を受けにくい
ため、通常は
食事の前後どちらでも
問題なく投与できます。
しかし、サプリメントの形態で販売されているSAMeは、空腹時に吸収されやすい製品もあります。
獣医師の指示に従い、適切なタイミングで与えましょう。
肝臓病の治療で使われるその他の重要な薬
1. 抗線維化薬(こうせんいかやく)
慢性肝炎が進行すると、肝臓は
▶線維化して硬くなり
▶肝硬変へと移行します。
この線維化を防ぐ目的で
▶抗線維化薬が使われることがあります。
◇コルヒチン
本来は痛風の薬ですが、犬では
肝臓の線維化を抑える効果
が期待されています。
しかし
・吐き気
・下痢
などの副作用が出ることもあるため、注意が必要です。
2. 免疫抑制剤(めんえきよくせいざい)
肝臓病の中には
▶自己の免疫
▶肝臓を攻撃してしまう
免疫介在性肝炎
という病気があります。
この場合
免疫の過剰な働きを抑える薬
が治療の中心となります。
◇プレドニゾロンなどのステロイド
肝臓の炎症を強力に抑えます。
ただし
・多飲多尿
・食欲増進
・体重増加
・感染症になりやすい
などの副作用が長期使用で現れることがあります。
◇アザチオプリン、シクロスポリン
・ステロイドだけで炎症をコントロールできない
・副作用を抑える目的
で併用されることがあります。
3. 胆汁うっ滞を改善する薬
胆汁の流れが滞る胆汁うっ滞は、肝臓に大きな負担をかけます。
◇ウルソデオキシコール酸(UDCA)
胆汁の流れを改善する代表的な薬です。
胆汁うっ滞の治療に不可欠です。
4. 肝性脳症の治療薬
肝臓の解毒機能が低下し
アンモニアなどの毒素が
▶脳に影響を及ぼす
肝性脳症では
・毒素の生成
・毒素の吸収
を抑える薬が重要です。
◇ラクツロース
腸内で
・アンモニアが吸収されるのを防ぎ
・便と一緒に排出するのを促します。
◇抗生物質
(メトロニダゾール、アンピシリンなど)
細菌感染が原因の場合
に処方されますが、他にも
腸内の
アンモニアを生成する細菌
を減らす目的でも使われます。
これらの薬は
・愛犬の症状
・血液検査の数値
・診断された病態
に応じて、獣医師が慎重に選定します。
自己判断で
・投薬を中止したり
・量を変更したり
すると
病状が急激に悪化する可能性
があるため、必ず獣医師の指示に従ってください
ヒッポのごはんでの肝臓病に対する栄養対策
肝臓病の治療において
食事療法は
薬物療法と同じくらい重要です。
ごはんづくりのコンセプトと方向性
・個体ごとの病態に合わせた
・臨機応変な食事調整
によって
・肝臓の負担を最小限に抑えつつ
・肝機能の再生を強力にサポートする
肝臓は代謝の中心であり
▶その機能が低下した状態では
▶通常の食事を与えることができません
単に特定の栄養素を制限するのではなく
・血液検査の数値を読み解き
・各病態に合わせた最適な栄養バランスで
・有害物質の蓄積を防ぎ
・肝臓本来の働きを助ける
ことを目指します。
具体的な栄養対策
●タンパク質:制限と選択の使い分け
タンパク質は
肝細胞の修復に不可欠
ですが
過剰な摂取は
▶アンモニアを発生させ
▶肝性脳症のリスクを高めます。
◇制限の必要性
・血液検査で高ALT
・高アンモニア血症
が見られる場合は
▶タンパク質の量を制限し
▶肝臓への負担を軽減します。
・肝性脳症
・胆管閉塞
の場合は、特に厳格な制限が必要です。
◇アミノ酸の調整
慢性肝炎では
・チロシン
・フェニルアラニン
・トリプトファンなど
芳香族アミノ酸
が過剰になる傾向があるため
▶これらの摂取を控えめにします。
一方で不足がちになる
分岐鎖アミノ酸(BCAA)は
・アンモニアの解毒
・エネルギー産生
・血中アルブミンの増加
に重要なため、積極的に補給します。
◇高品質なタンパク質
タンパク質を制限する場合でも
体内で効率よく利用される
高消化性タンパク質
・鶏むね肉
・白身魚
・卵
・ヤギホエイプロテインなど
を厳選して用います。
これにより、体内のタンパク質が分解されるのを防ぎます。
●脂質=ALPの数値で判断する
「脂肪は肝臓に悪い」
と安易に制限すべきではありません。
血液検査の
ALPの値に注目し
脂質代謝に問題がないか?
を確認することが重要です。
◇脂質を制限すべき場合
・ALPが高く
・脂質代謝に問題がある
・胆管閉塞がある
場合は、脂肪が負担となります。
この場合は、粗脂質10%以下を目安に
低脂肪食にします。
◇脂質を補給すべき場合
・ALPに異常がなく
・脂質代謝に問題がない場合
良質な脂質をむしろ積極的に補給します。
これにより
・タンパク質の温存
・糖質代謝の負担軽減
・脂溶性ビタミンの吸収率を高める
などの効果が期待できます。
特にオメガ3脂肪酸
・新鮮な青魚
・サチャインチオイルなど
は炎症を抑えるために重要です。
◇鶏卵の活用
卵黄は
・脂質代謝を改善し
・肝臓への不要な脂質蓄積を抑制する
抗脂肪肝作用
が期待できるため、積極的に活用します。
●炭水化物:エネルギー源と食物繊維
◇GI値にも配慮した選択
肝臓病では
・タンパク質の代謝負担を減らす
ため
・炭水化物を主たるエネルギー源
としますが
脂肪肝がある場合
その糖質の質にも注意が必要です。
血糖値を急激に上昇させる
・高GI値の炭水化物は
▶インスリンの過剰分泌を促し
▶余った糖質が
▶肝臓で脂肪に変わりやすくなります。
そのため
血糖値が緩やかに上昇する
・低GI値の食材(GL値にも注目)
を選ぶことが、脂肪肝の
・予防
・改善
に効果的です。
◇低GI値の炭水化物
・玄米
・もち麦
などがこれにあたります。
これらの食材は、白米に比べて
・食物繊維も豊富で
・血糖値の上昇を緩やかにする
効果が期待できます。
◇調理法
炭水化物は、冷やすことで
消化されにくい
レジスタントスターチが増え
▶GI値を下げることができます。
例えば
・一度炊いたご飯
・イモ類
を冷ましてから与えるなどの工夫も有効。
◇食物繊維の活用
・βグルカン(きのこ、もち麦など)
・難消化性オリゴ糖
・レジスタチスターチ(サツマイモなど)
といった
主に水溶性食物繊維
をバランスよく与えることで
・腸内環境を整え
アンモニアの発生源となる
・腸内窒素の減少
を図ります。
●肝臓を助ける「守り」の栄養素
・肝臓の働きをサポートし
・再生を促す
ための栄養素を意識的に強化します。
◇抗酸化物質
肝臓の解毒過程で発生する
活性酸素
を除去するために
・ビタミンE・C
・亜鉛
・セレン
・抗酸化物質
などを幅広い食材から補給します。
例えば
・舞茸のグルタチオン
解毒の各フェーズ
で発生する活性酸素の除去に重要
また自身が毒素を抱合する働きもします。
・ブロッコリーのインドール
解毒を助けます。
◇オルニチン
オルニチンサイクルにおいて
▶アンモニアの解毒を促進し
▶アンモニアを減らす
その作用により
・TCAサイクル
・糖新生の代謝
を円滑にすることで
エネルギー産生
も助けています。
主にしめじなどを活用します。
◇肝臓保護成分
慢性肝炎などで不足しがちな
・亜鉛
・アルギニン
・L-カルニチン
・カリウム
・リジン
・セレン(水銀中和)
などを意識的に補給します。
特に亜鉛は
・慢性肝炎
・肝硬変
の個体で
亜鉛濃度が低下している
ことが知られています。
◇タウリン
胆汁の合成と代謝に不可欠
なタウリンを強化します。
タウリンは胆汁から毒素を排泄する
解毒作用も促します。
タウリンを直接摂取することに加え
タウリンの合成に必要な
システイン
をヤギホエイプロテインから供給します。
またシステインは
防御たんぱく質と呼ばれ
カドミウムなど有害な重金属を排出する
メタロチオネイン
の主要な構成成分でもあります。
◇その他
低アルブミン血症では
ナトリウムも制限する
必要があります。
・門脈高血圧
・腹水
がある場合は特に重要です。
●鉄とビタミンの調整
◇鉄
鉄関連性肝障害では
鉄が過剰になるため
▶制限が必要です
しかし肝疾患による出血で
貧血がある場合は
▶鉄を補給する
など、状況に応じて調整します。
◇ビタミン
慢性疾患ではビタミンが不足しがちです。
特に
・ビタミンK
は肝臓で合成されるため
▶意識的に補給します。
・鶏レバー
・卵黄
・ブロッコリー
などの食材をバランスよく配合。
・ビタミンB群
も尿中に排出されやすいため、補給が必要です。
ヒッポのごはんでは
これらの多角的な視点から
愛犬の個別の状態に合わせて
最適な栄養対策を提供します。
その他、犬が肝臓病になったときに気を付けてあげること
肝臓病と診断された愛犬のケアは
・単なる投薬
・食事制限
だけではありません。
日常生活における細やかな配慮が、愛犬の生活の質(QOL)を大きく左右します。
投薬の工夫と食事療法の両立
処方された薬をきちんと飲ませることは
治療の基本です。
しかし
食事療法も同時に行っている場合
▶投薬方法には注意が必要です。
●食事に混ぜる際の注意点
投薬用の
・ポケット
・おやつ
は便利ですが
・高脂肪
・高糖質
のものは
食事療法の妨げ
になる可能性があります。
肝臓病用の療法食は
厳密な栄養バランスで設計
されているため、余計なものを加えると効果が薄れてしまいます。
●肝臓保護剤のタイミング
SAMeなどの一部の肝臓保護剤は
食事と一緒だと吸収率が低下する
ことがあるため、食前や食間など、獣医師の指示に従って空腹時に与えましょう。
水分補給と脱水予防の重要性
肝臓の機能が低下すると
▶体内の水分バランス保持が難しくなり
▶脱水に陥りやすくなります。
●常に新鮮な水を
飲み水をこまめに交換し
常に新鮮で清潔な水が飲める環境
を整えましょう。
●フードの工夫
・ドライフードをぬるま湯でふやかす
・ウェットフードを与えるなど
で食事からの水分摂取量を増やせます。
特に
・食欲がない時
・暑い時期
には有効な手段です。
ストレスマネジメント:肝臓への間接的な影響
ストレスは
▶免疫機能の低下を招き
▶病気の進行を早める
可能性があります。
●環境の変化を最小限に
・引っ越し
・家族構成の変化など
犬にとって大きなストレスとなる環境の変化はできる限り避けましょう。
●穏やかな運動と遊び
激しい運動は避け
・散歩の時間を短くする
・室内での穏やかな遊びを取り入れる
など、愛犬の体調に合わせた無理のない生活を心がけましょう。
脂肪肝の予防:日々の食事の再点検
「脂肪肝は万病の元」
という認識を持つことが、愛犬の健康を守る上で最も重要です。
●「隠れ糖質」に注意
ドッグフードの原材料表示を確認し
・トウモロコシ
・米など
穀物が主原料になっているフードは
▶脂肪肝のリスクを高める
可能性があります。
特に
果糖は肝臓に直接負担をかける
可能性が高いため
甘い果物のおやつ
は控えるようにしましょう。
●適正体重の維持
肥満は脂肪肝の最大の原因です。
日頃から体重をチェックし、獣医師と相談しながら適正体重を維持しましょう。
肝臓は「沈黙の臓器」:定期的な健康診断の重要性
肝臓は再生能力が高く
▶ダメージを受けても症状が出にくい
「沈黙の臓器」です。
そのため、症状が出てからでは手遅れになることも少なくありません。
●定期的な血液検査
・年に一度
・シニア犬であれば半年に一度
肝臓関連の血液検査
を必ず受けましょう。
・ALP
・ALT
これらの数値が
正常範囲内であっても
過去のデータと比較して
わずかでも上昇傾向が見られる
場合は注意が必要です。
わずかな変化でも、肝臓に
何らかの負担がかかり始めている
サインかもしれません。
また、肝臓病は
炎症と密接に関わっているため
・WBC(白血球数)
・CRP(C反応性タンパク)
などの炎症マーカーにも注目しましょう。
これらの数値の上昇は
肝臓で炎症が起きている
可能性を示唆します。
愛犬の健康を長く保つためには
・一度の検査結果だけでなく
・経時的な数値の変化
を獣医師と一緒に確認することが非常に重要です。
数値の変化を早期に発見することで、治療の選択肢が広がります。
●獣医師との連携
血液検査の結果だけでなく
・愛犬の些細な食欲の変化
・行動の異常など
気になることがあればすぐに獣医師に相談しましょう。
愛犬の体のサインを見逃さない
ことが、早期発見と長寿につながります。

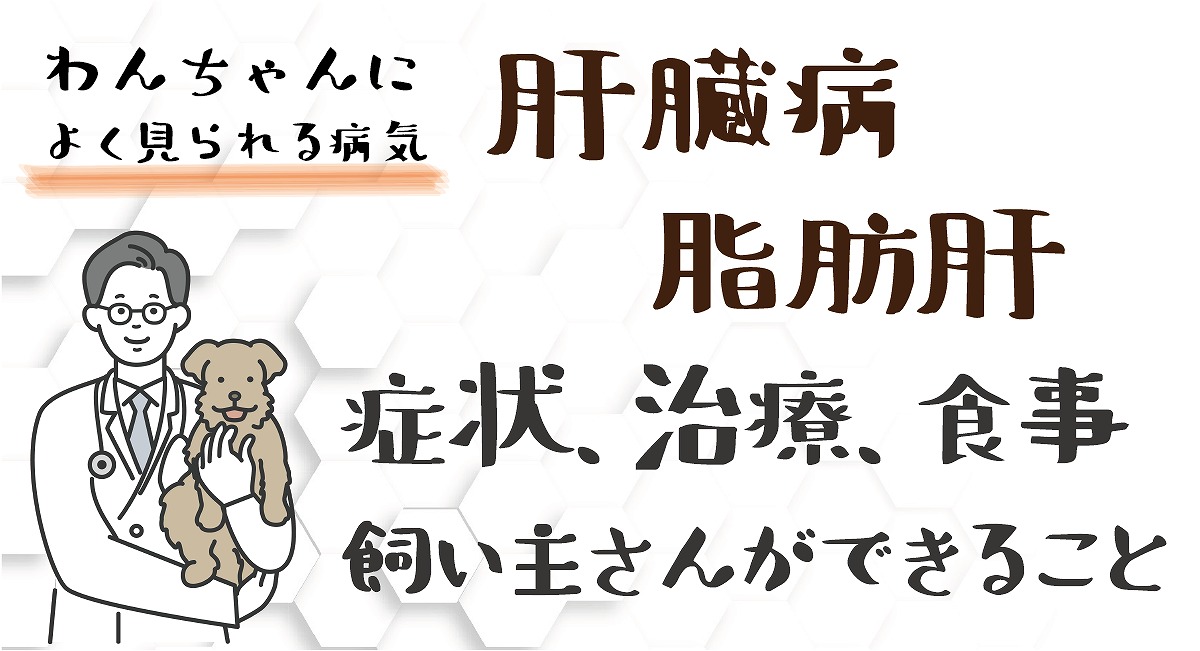
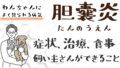

コメント