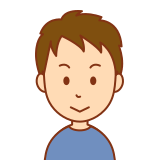
なんか最近、うちの子めっちゃ水飲むようになったわ
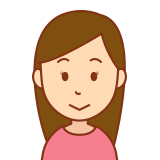
うちの子は食欲がちょっと落ちたかも
些細に見えるそんな変化
実は
沈黙の臓器
とも呼ばれる腎臓からの
SOSサイン
かもしれません。
犬の腎臓病は
・初期には症状が現れにくく
・気づいた時には進行している
ことも少なくない病気です。
この記事では犬の腎臓病の
・原因
・症状
・治療法
そして飼い主さんが最も気になる
・食事療法
・日常生活でのケア
まで徹底的に解説します。
愛犬の腎臓を守り、健やかな毎日をサポートするための知識を深めましょう。
1. 犬の腎臓病ってどんな病気? 急性と慢性、その違いとは
腎臓は
・体内の老廃物を尿として排泄
・水分や電解質のバランスを調整
さらには
・エリスロポエチンを産生する
血圧調整や赤血球を作るホルモン
など、生命維持に不可欠な多くの役割を担っています。
犬の腎臓病とは、これらの腎臓の機能が何らかの原因で低下してしまう状態を指します。
腎臓病には、大きく分けて
・急性
・慢性
の2種類があります。
急性腎臓病(AKI)
数時間から数日の間に
急激に腎機能が悪化
する状態です。
●原因
・中毒
(ぶどう、ユリ科植物、不凍液、特定の薬剤など)
・感染症(レプトスピラ症など)
・重度の脱水
・ショック
・尿路閉塞
などが原因となります。
早期に適切な治療を行えば回復する可能性もあります。
しかし手遅れになると
・命に関わる
・慢性腎臓病へ移行
などすることもあります。
慢性腎臓病(CKD)
数ヶ月から数年かけて
ゆっくりと腎機能が低下していく
進行性の病気です。
多くの場合
一度失われた腎機能が回復することは難しいです。
治療は
・病気の進行を遅らせ
・症状を緩和し
・QOL(生活の質)を維持
することを目的とします。
腎臓は予備能力が高く
全体の約75%の機能が失われるまで明らかな症状が出にくい
ため沈黙の臓器と呼ばれています。
●原因
加齢による機能低下が最も一般的
ですが他にも
・遺伝的素因
・シー・ズー
・ミニチュア・シュナウザー
・サモエド
・ブル・テリア
・イングリッシュ・コッカー・スパニエル
など
・過去の急性腎臓病
・免疫介在性疾患
・腫瘍
・高血圧
・歯周病などの慢性炎症
・先天的な腎奇形
などが関与することもあります。
●ステージ分類
国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS)によって提唱された分類。
主に
・血中クレアチニン値
・SDMA値(後述)
・尿タンパクの量
などに基づいて、慢性腎臓病の重症度を
ステージ1からステージ4
に分類します。
ステージが進むほど腎機能は低下しており、治療法や予後も異なってきます。
●SDMAの重要性
SDMA(対称性ジメチルアルギニン)とは
従来のクレアチニンよりも
★早期に腎機能低下を検出できる
血液検査マーカーです。
腎機能が
約40%低下した段階
で上昇し始めるとされます
そのため慢性腎臓病の
・早期発見
・早期介入
に非常に役立ちます。
定期的な健康診断に含めることを推奨。
●腎臓と高血圧の悪循環
腎臓病は
▶高血圧を引き起こしやすく
▶その高血圧がさらに腎臓にダメージ
▶さらに腎臓の病状を悪化させる
という負のループに陥ることがあります。
血圧の
・モニタリング
・管理
が腎臓病治療において非常に重要です。
2. 見逃さないで!愛犬が出す腎臓病のサイン
初期には気づきにくい腎臓病の症状
以下のような変化に注意しましょう。
●初期症状(気づきにくいことが多い)
◇多飲多尿
最もよく見られる初期症状の一つ。
・水を飲む量が増え
・おしっこの回数や量が増える。
◇食欲不振
・軽度
・ムラがある
◇体重減少
徐々に痩せてくる
◇毛ヅヤが悪くなる
被毛がパサつく
◇なんとなく元気がない
疲れやすい
●進行期の症状
◇明らかな食欲不振
または全く食べない
◇嘔吐、下痢
◇脱水症状
・皮膚の弾力低下
・口の中の乾燥
◇貧血
※腎臓からのエリスロポエチン産生低下による
・粘膜が白っぽくなる
・息切れしやすい
◇口臭
・アンモニア臭
・尿臭いような臭い
◇口腔内潰瘍
舌炎
◇削痩
筋肉が落ちて痩せこける
◇高血圧による症状
・突然失明する
・ふらつくなど
◇神経症状
・痙攣
・意識障害など
※末期に尿毒症が進行した場合。
歯周病との関連
重度の歯周病を持つ犬は
・口腔内の細菌
・炎症性物質
が血流を介して腎臓に影響を与え
▶腎臓病のリスクを高める可能性がある
という研究報告があります。
日頃のデンタルケアも腎臓の保護につながるかもしれません。
3. 腎臓病の予防:家庭でできること、定期健診の重要性
残念ながら
一度発症した慢性腎臓病を完全に治癒させることは困難です。
加齢によるものはある程度避けられません。
しかし
・発症リスクを軽減
したり
・早期発見
・早期介入
によって進行を遅らせたりするためにできることはあります。
●定期的な健康診断: 最重要!
◇若齢期(1~6歳)
年に1回
◇中高齢期(7歳以上)
半年に1回程度を目安に
・血液検査
・BUN
・クレアチニン
・SDMA
・電解質など
・尿検査
・尿比重
・尿タンパク
・クレアチニン比など
・血圧測定
を受けましょう。
●適切な食事管理
◇健康な犬には
・年齢
・活動量
に合ったバランスの取れた総合栄養食を与えましょう。
◇質の悪い物を避ける
過剰な
・タンパク質
・リン
・ナトリウム
の長期的な摂取は、腎臓負担の可能性
・質の悪いフード・おやつ
・人間用の加工食品
などは避けましょう
◇新鮮な水
を常に十分に飲める環境を用意しましょう。
●中毒物質の回避
◇犬にとって中毒性のある
・食品(ぶどう、レーズンなど)
・植物(ユリ科植物など)
・化学物質
(不凍液に含まれるエチレングリコール、殺鼠剤など)
・特定の人間用医薬品(痛み止めなど)
を誤って摂取しないように
厳重に管理
しましょう。
●感染症の予防と早期治療
◇歯周病を放置せず
・定期的なデンタルケア
・必要に応じた治療を受けましょう。
◇感染症予防
レプトスピラ症など
・腎臓に影響を与える感染症
のワクチン接種も検討しましょう
(獣医師と相談)
●適度な運動と体重管理
◇肥満は大敵
肥満
・高血圧
・糖尿病
などのリスクを高め
▶間接的に腎臓に負担をかける可能性。
適切な体重を維持しましょう。
●遺伝的素因のある犬種への配慮
◇腎臓病を発症しやすいとされる犬種
の場合は、より早期からの
・スクリーニング検査
を獣医師と相談。
計画的に行うことをおすすめ。
特定の疾患の検出を目的として、症状のない犬を対象に行う検査
「腎臓に優しい」サプリ・フード
「腎臓に優しい」
という謳い文句の
・フード
・サプリメント
が市販されています。
ですが健康な犬に早期から極端な
・タンパク質制限
・リン制限
を行うことは、逆に
・栄養不足
・筋肉量の低下
を招く可能性があります。
あくまで獣医師の診断と指導のもと、その子の状態に合わせた食事管理を行うことが重要です。
4. 腎臓病の治療法:薬や療法食、輸液について
腎臓病の治療は
・急性か?慢性か?
・原因
・ステージ
・併発疾患の有無
などによって異なります。
急性腎臓病(AKI)の治療
・原因の特定と除去
そして
・集中的な支持療法
が中心となります。
●静脈輸液療法
・脱水の補正
・腎臓への血流改善
・尿毒素の排泄促進
●電解質バランスの補正
体内の電解質
・ナトリウム
・カリウム
・カルシウム
・マグネシウムなど
の濃度を適切な状態に戻す。
・点滴
・内服薬
・食事療法など
●尿道閉塞の場合
その解除
●中毒の場合
原因物質の除去
・催吐処置
・活性炭投与など
●感染症が原因の場合
抗菌薬投与など
慢性腎臓病(CKD)の治療
慢性腎臓病の治療は
・病気の進行を最大限に遅らせ
・症状を緩和し
・QOL(生活の質)を最大限高く維持
を目標とします。
残念ながら完治は望めません。
●食事療法
慢性腎臓病治療の
根本
とも言える最も重要な治療法です。
詳細は後述します。
●輸液療法
◇脱水や食欲不振がある場合
尿毒素の
・希釈
・排泄
を促すために行います。
◇状態に応じて
・通院での静脈輸液
・自宅または通院での皮下輸液
が行われます。
薬物療法(主なもの)
●ACE阻害薬
(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)
●ARB
(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)
◇効果
糸球体にかかる圧力を下げて保護
▶腎臓にかかる負担を減らし
▶尿中のタンパク質を減らし
▶腎臓病の進行を遅らせる
効果が期待されます。
血圧を下げる作用もあります。
腎臓の中で血液をろ過する役割を担う、毛細血管の塊
◇主な薬
・ベナゼプリル
・エナラプリル
・テルミサルタンなど
◇副作用の可能性
・低血圧
・高カリウム血症
(特に腎機能が著しく悪い場合)
・食欲不振
・嘔吐
・下痢
・まれに腎機能の一時的な悪化
(特に脱水時やNSAIDsとの併用時)
◇注意点
ナトリウムを制限した食事
と併用すると
・降圧効果
・腎保護効果が高まることがあります。
しかし過度なナトリウム制限は
・脱水につながる可能性
もあります。
また
・ACE阻害薬
・ARB
には
高カリウム血症のリスクがあります。
そのため
・カリウムの多いサプリメント
・カリウムの多い食事
との併用には注意が必要です。
獣医師の指示に従ってください。
◇尿にタンパク質が漏れ出る
タンパク尿
は、それ自体が
▶腎臓にダメージを与え
▶慢性腎臓病の進行を加速させる
リスク因子です。
・ACE阻害薬
・ARB
には、このタンパク尿を減らす効果も期待
●リン吸着剤
◇効果
食事中のリンと消化管内で結合
▶リンが体に吸収されるのを防ぎます。
注)血液中のリン濃度が高い
=腎臓病の進行が早まる
なのでリンのコントロールは非常に重要。
◇主な薬
・炭酸カルシウム
・水酸化アルミニウム
・炭酸ランタン(レンジアレンなど)など
◇副作用の可能性
・便秘(特にアルミニウム系)
・食欲不振
・高カルシウム血症
(カルシウム含有製剤の場合)
・低リン血症(まれ)
◇注意点
食事と一緒に、または食直後
に投与することで効果を発揮します。
食事中のリン
と結合して効果を発揮するので
タイミングが非常に重要です。
●カリウム製剤
●カリウム調整薬
◇効果
腎臓病では、血液中のカリウムが
・低くなったり
・高くなったり
することがあり
・低カリウム血症
・高カリウム血症
のどちらもが起こり得ます
血液検査の結果に応じて
カリウムを
・補給する薬を使う
・排泄を促す薬を使う
など調整します。
◇注意点
カリウムのバランスは非常に重要。
自己判断せず獣医師の指示に従うこと。
●制吐剤・消化管運動改善薬
◇効果
尿毒症で
老廃物が体に溜まることによる
・吐き気
・嘔吐
を抑え、食欲不振を改善。
◇主な薬
・マロピタント(セレニア)
・オンダンセトロンなど
●消化管粘膜保護剤
●胃酸分泌抑制剤
◇効果
尿毒症で
老廃物が体に溜まることによる
・胃炎
・消化管の潰瘍
から胃腸を守ります。
◇主な薬
・スクラルファート
・ファモチジンなど
●造血ホルモン剤(エリスロポエチン製剤)
◇効果
腎性貧血を改善します。
腎臓で赤血球を作るホルモンが作られにくくなることで起こる貧血
◇主な薬
ダルベポエチンアルファなど
◇副作用の可能性
・抗エリスロポエチン抗体の産生
投与している
・エリスロポエチン製剤
自身が効かなくなる。
それだけでなく
・自分自身のエリスロポエチン
にも反応して重度の貧血
赤芽球癆(せきがきゅうろう)
※脊髄で血液が作られなくなる病気
を引き起こすことがある
・高血圧
・鉄分不足
◇注意点
貧血改善のため鉄分も必要になることも
・食事からの鉄分摂取
・鉄剤の補給
が必要になることがあります。
●経口吸着炭
◇効果
消化管内で
・尿毒素や
・その元になる物質
を吸着し
▶便と一緒に体の外に出す
▶体内に尿毒素が溜まるのを減らす。
◇主な薬
活性炭
・クレメジン
・コバルジンなど
◇副作用の可能性
・便秘
・他の薬や栄養素も吸着する可能性。
◇注意点
・他の薬
・サプリメント
・食事中の栄養素
も吸着する可能性がります。
そのため
・他の薬
・食事のタイミング
と2時間程度ずらして投与することが推奨されます。
●降圧剤
◇効果
腎臓病に伴う高血圧を管理し
・腎臓
・他の臓器
へのさらなるダメージを防ぐ
◇主な薬
・アムロジピン
・ACE阻害薬
・ARBなど
●幹細胞治療(研究段階・先進医療)
近年
間葉系幹細胞
を用いた治療が
・腎機能の修復
・炎症抑制効果
を期待して研究・試みられています。
まだ確立された治療法ではありませんが、今後の発展が期待される分野です。
腸-腎連関
腸内環境が悪化すると
▶腸内で作られる老廃物が増える
▶それが血液を通して腎臓に負担
▶腎臓病の進行を早める
という考え方です。
そのため
・プロバイオティクス(善玉菌)
・プレバイオティクス(そのエサ)
などを活用して腸内環境を整えることが、腎臓を守ることにつながる可能性が示唆されています。
5. 腎臓病の食事療法:何をどう与える?療法食の役割
食事療法は
慢性腎臓病の管理において
最も重要な治療法の一つです。
・生存期間を延長し
・QOLを改善する
ことが科学的に証明されています。
食事で気を付ける基本ポイント
※慢性腎臓病の
・ステージ
・状態
によって調整が必要
●リンの制限
最も重要です。
血中のリン濃度が高い
▶慢性腎臓病の進行が早まる
ので厳密に&早期から制限します。
●タンパク質の制限
尿毒症の原因となる
窒素性老廃物の産生
を抑えるために制限します。
しかし、制限しすぎると
▶筋肉が落ちて栄養不良になります。
そのため
▶質の高いタンパク質
(アミノ酸バランスが良いもの)を
▶適切な量で摂取する
ことが重要です。
ステージ初期では
過度な制限は不要
な場合もあります。
●ナトリウムの制限
・高血圧の管理
・体液貯留
を防ぐために制限します。
こちらも制限というよりは、的確な範囲に収めることが重要です
●オメガ3脂肪酸(EPA、DHA)強化
腎臓の炎症を抑え
▶糸球体を保護し
▶血流を改善する
効果が期待されます。
●カリウムの調整
慢性腎臓病では
・低カリウム血症
・高カリウム血症
のどちらもが起こり得るため
▶血液検査の結果に基づいて
▶食事中のカリウム量を調整します。
●ビタミンB群の補給
多尿により
▶水溶性のビタミンB群が失われやすい
ため、補給が推奨されます。
●十分なカロリー摂取
食欲不振になりやすいため
・少量で効率よくエネルギーを摂取できる
・嗜好性の高い食事
が重要です。
痩せさせないことが大切です。
●食物繊維の適切な配合
水溶性食物繊維は
▶腸内環境を整えることで
・尿毒素の産生を抑制
・便通を改善する
などの効果が期待されます。
●抗酸化物質の配合
・ビタミンE
・ビタミンC
・ベータカロテン
・セレンなどが
酸化ストレスから腎臓細胞を保護するのに役立ちます。
嗜好性の重要性
どんなに栄養バランスが優れていても
食べてくれなければ意味がありません。
特に腎臓病の犬は食欲が低下しやすく
療法食の「嗜好性」
は非常に重要です。
・色んなサンプルを試す
・ウェットとドライフードを混ぜる
・少し温めたりする
などの工夫が必要になることも
手作り食の難しさ
腎臓病の食事療法は
非常にデリケートな栄養バランス
が要求されます。
手作り食で完璧に管理するのは
・専門的な知識
・細心の注意
が必要です。
もし手作り食を希望する場合は
▶必ず獣医栄養学に詳しい獣医師に相談
▶個別のレシピを作成
してもらいましょう。
ヒッポのごはんでも専門家がご相談を受け付けています。
自己流は危険です。
6. 腎臓病の治療費:どれくらいかかる? (目安)
腎臓病の治療は
・長期にわたることが多く
・費用も継続的に発生します。
あくまで一般的な目安として参考にしてください。
●初期~中期
(定期的な検査、療法食、内服薬が中心)
◇診察料:
数千円/回
◇血液検査・尿検査:
5,000円~20,000円/回
(検査項目、SDMA検査の有無による)
◇療法食:
5,000円~15,000円/月
(犬の体重やフードの種類による)
◇内服薬:
数千円~20,000円/月
(薬剤の種類や量による)
◇定期的な皮下輸液
(通院または自宅):
数百円~数千円/回
◇年間:
数十万円程度かかることも珍しくありません。
●進行期~末期
(入院、頻繁な処置、集中的な治療が必要)
◇入院費:
10,000円~30,000円/日
◇費用が大きく跳ね上がる
・静脈輸液
・特殊な薬剤の使用
・透析治療(実施施設は限られ非常に高額)
などが必要になる場合
◇年間:
状態によっては百万円を超えることもあります。
腎臓病は生涯付き合っていく病気
そのため、治療費だけでなく
・通院の時間的・精神的な負担
も考慮に入れる必要があります。
無理のない範囲で、愛犬と飼い主さん双方が穏やかに過ごせる治療計画を獣医師と相談しましょう。
7. 愛犬が腎臓病になったら:飼い主さんが家庭でできること、心構え
腎臓病の診断を受けたら・・・
・ショック
・不安
でいっぱいになるかもしれません
しかし、悲しみ嘆くより前に、飼い主さんができることがたくさんあります。
●獣医師との良好なコミュニケーション
◇コミュニケーション
・診断内容
・治療方針
・予後に
ついて
納得いくまで
説明を受けましょう。
疑問や不安は遠慮なく伝えましょう。
◇指示された治療計画
・投薬
・食事療法
・輸液など
をきちんと守りましょう。
◇定期的な通院と検査
を必ず受け
・治療効果の判定
・副作用のチェック
・治療方針の見直し
をしてもらいましょう。
●飲水量の確保
◇新鮮な水
を常に複数箇所に用意。
いつでも飲めるようにしましょう。
◇水分確保
・ウェットフードを活用
・ドライフードをふやかす
・飲み水に風味をつける
(獣医師に相談の上)
などの工夫で飲水量を確保しましょう。
●食事の工夫
◇腎臓病と「香り」
尿毒症が進行すると
▶嗅覚が変化し
▶普段好きだったフードの匂いを嫌がる
ようになることがあります。
食事の工夫の一つとして
・香りの少ないフードを選ぶ
・逆に嗜好性の高い香りのトッピングを少量試す
(ただし腎臓に配慮した範囲で)
ことが有効な場合があります。
◇食欲が落ちやすいため
・療法食を少し温める
・手から与える
・食器を変えてみる
・複数種の療法食をローテーション
(ドライフードの酸化には注意)
など、食べてくれる工夫を根気強く試みましょう。
◇トッピング
をする場合は
▶必ず獣医師に相談し、
▶腎臓に負担のかからないものを選びましょう。
●記録をつける
□体重
□食欲
□飲水量
□尿の回数や量
□元気の度合い
□嘔吐の有無
などを毎日記録しておくと
・体調変化に気づきやすく
・獣医師への情報提供にも役立ちます。
●ストレスの少ない環境づくり
◇静かで安心できる寝床を用意し
室温管理にも気を配りましょう。
◇生活環境
・大きな音
・急な環境変化
を避け、穏やかに接しましょう。
●口腔ケア
◇尿毒症により
・口内炎ができやすくなる
・歯周病が悪化する
などすることがあります
可能な範囲で
・歯磨き
・口腔内チェック
を行いましょう。
●保温
◇腎臓病が進行すると
▶体温調節機能が低下しやすくなります
そのため特に寒い時期は
・ペットヒーター
・毛布
などで暖かくしてあげましょう。
●自宅での皮下輸液
獣医師から指示された場合は
・正しい手技
・衛生管理
・犬への声かけ
などを動物病院でしっかり指導してもらい、落ち着いて行いましょう。
最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れれば愛犬の負担を軽減できる有効なケアです。
●QOL(生活の質)の維持を最優先に
◇治療は愛犬のために行うものです
しかしその治療が
・過度な苦痛
・ストレス
を与えていないか?
常に愛犬の様子を見ながら獣医師と相談しましょう。
その子にとって
何が一番幸せか
を考えることが大切です。
●飼い主さん自身のケアも忘れずに
◇長期的なケアは
飼い主さんにとっても心身ともに大きな負担となります。
一人で抱え込まず
・家族や獣医師
・動物看護師
・同じ病気を持つ犬の飼い主さん
・ヒッポのごはん
など
・頼れる人に相談したり
・情報を共有したり
しましょう。
看取り期(ターミナルケア)の考え方
残念ながら
▶病気が進行し
▶積極的な治療が困難になる
そんな時間がやってきます。
そんな時でも緩和ケアによって
・愛犬の苦痛を和らげ
・穏やかに過ごせるように
サポートすることは可能です。
・食事が摂れなくなった時の栄養補給方法
・痛みのコントロール
・精神的なケア
などについて、獣医師とよく話し合い
愛犬にとって最善の選択
をしてあげましょう。
最後に
犬の腎臓病は
・早期発見
・適切な管理
が非常に重要な病気です。
・愛犬の小さな変化に気づき
・定期的な健康診断を欠かさず
・獣医師と二人三脚で治療に取り組む
ことで
・病気の進行を遅らせ
・愛犬との大切な時間を少しでも長く
そして
・穏やかに過ごす
ことができます。
この記事が、腎臓病と闘う全ての愛犬と飼い主さんの一助となることを心から願っています。

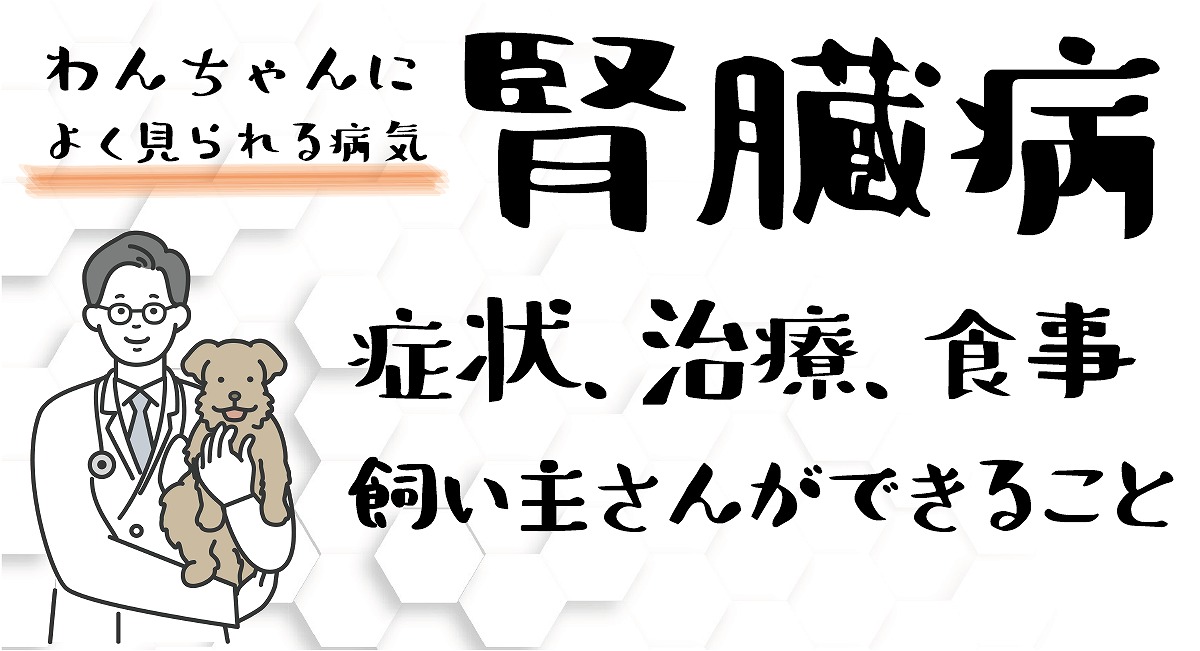


コメント