犬の分離不安症とは?
飼い主と離れることに対して
・過度な不安
・過度なストレス
を感じる精神疾患です。
単なる
お留守番が苦手
というレベルを超え
犬にとって
非常に苦痛な状態
であり、放置すると
QOL(生活の質)
が著しく低下します。
この病気は犬が
・飼い主を安全基地として認識しすぎ
あるいは
・過去のトラウマ(例:捨てられた経験)
が影響しているなど
さまざまな要因
が絡み合って発症すると考えられます。
人間で言うと
・重度のパニック障害
・広場恐怖症
に近い状態だとイメージすると、その深刻さが伝わるでしょう。
もしこの記事を読んでいるあなたが
▶愛犬の様子に心当たりを感じているなら
▶それは気のせいではないかも。
もしかすると、愛犬は私たちには見えない
「不安」
と日々闘っている可能性があります。
もしかして分離不安?愛犬の心のサインを見つけるために
この病気のサインは
日頃のちょっとした行動
に隠れていることが多く
▶飼い主さんが気づいてあげることで
・早期のケア
・適切なサポート
へと繋がります。
愛犬の心の状態を理解するために
以下のチェックシート
であなたの愛犬の分離不安度を測ってみませんか?
「はいorいいえ」で答えるだけで
・愛犬が必要としていること
そして
・あなたができること
が見えてくるはずです。
このチェックシートの結果が
愛犬の分離不安の傾向
を示していたとしても
どうかご安心ください。
・適切な予防策
・獣医師や専門家による治療法
を実践することで
▶愛犬の不安を軽減し
▶健やかな毎日を取り戻す
ことが可能です。
このページの下部では
・分離不安症の具体的な症状
・予防法
・薬や食事を含めた治療法
まで、幅広く解説しています。
ぜひ、この機会に愛犬の心に寄り添い、最善のサポートをしてあげましょう。
愛犬の分離不安度チェックシート
以下の質問に「はい」または「いいえ」で答えてください。
1. あなたが外出の準備(鍵を持つ、コートを着るなど)を始めると、ソワソワし始めますか?
2. あなたが家の中で部屋を移動する際、後を付いて回りますか?
3. あなたが出かけると、5分以内に吠えたり、鳴いたりし始めますか?
4. あなたがいない間、吠えや鳴きが30分以上続きますか?
5. あなたがいない間に、トイレ以外の場所で排泄をしてしまいますか?
6. あなたがいない間に、家の中の物を噛んだり、壊したりしますか?
7. あなたがいない間に、脱走を試みた形跡(ドアや窓の傷など)がありますか?
8. あなたがいない間、水も飲まず、おやつも食べないことがありますか?
9. あなたがいない間、自分の体を舐めたり、噛んだりして、皮膚に異常が出たことがありますか?
10. あなたが帰宅すると、異常なほど(興奮しすぎておしっこを漏らすなど)喜びますか?
11. あなたがいない間、過剰なよだれ(口の周りが濡れるほど)やパンティング(ハァハァと荒い呼吸)が見られますか?
12. 雷や花火などの大きな音に対して、極端に怖がったりパニックになったりすることがありますか?
13. あなたが寝ている間に、愛犬がいつもあなたのすぐそばで寝ていますか?
14. 新しい場所や初めての人に会うと、極端に緊張したり隠れたりしますか?
15. あなたの外出中、近所の人から愛犬の吠えや破壊行動について苦情を言われたことがありますか?
主な症状:あなたの愛犬は「お留守番が苦手」?それとも「分離不安症」?
分離不安症の症状は多岐にわたります
しかし特に
飼い主が不在の際
に顕著に現れるのが特徴です。
ここでは
・単なる
「お留守番が苦手」
な場合と
・専門的なケアが必要な
「分離不安症」
の症状を見分けるためのポイントも交えて解説します。
●破壊行動
・家具を噛む
・壁をひっかく
・物を壊すなど
家の中を荒らす行動が見られます。
これは
・ストレス
・不安
を発散しようとする行為です。
◇留守番が苦手な場合
・飼い主の衣類を運ぶ
・軽いかじり跡がある程度
時間が経てば落ち着くことが多いです。
◇分離不安症の場合
・ドアや窓の周りの破壊を試みる
・壁を削る
・家具を原型がなくなるほど噛み続ける
など
▶脱走を試みる意図が強く
▶破壊の程度も深刻です。
●吠え続ける・鳴き続ける
飼い主がいない間
・吠えたり
・遠吠えしたり
・クーンクーンと鳴き続けたり
近所迷惑になることもあり、飼い主にとっても大きな悩みとなります。
◇留守番が苦手な場合
出かけた直後の
数分〜20分程度で止まるなど
比較的短時間で収まることが多いです。
◇分離不安症の場合
飼い主がいない間
・数時間以上途切れることなく吠え続ける
・遠吠えが止まらない
など、明らかにコントロールが効かない状態です。
●不適切な排泄
普段はトイレのしつけができているにも関わらず、留守中だけ粗相をするなど。
これも不安によるストレスが原因です。
◇留守番が苦手な場合
・たまに
あるいは
・興奮した時に
見られる程度です。
◇分離不安症の場合
・毎回
あるいは
・非常に頻繁に
粗相が見られ
・その量が異常に多い
・下痢を伴うなど
ストレスによる身体反応が顕著です。
●過剰なよだれ・パンティング
ストレスによって
・唾液の分泌量が増える
・呼吸が荒くなる
などします。
◇分離不安症の兆候
飼い主の不在時に
・口の周りがびしょ濡れになるほどの大量のよだれ
・暑くないのにパンティングが続く
※舌を出してハァハァと荒い呼吸
などの場合は
強いストレス
のサインです。
●脱走を試みる
・ドアや窓を引っかく
・網戸を破る
などして飼い主を探そうとします。
◇分離不安症の兆候
必死に外に出ようとする行動
=パニック状態
の表れであり、非常に危険です。
●食欲不振
ストレスから食欲が低下することもあります。
◇分離不安症の兆候
留守中に与えられた
・おやつ
・フード
に一切口をつけない
・水も飲まない
といった行動が見られることも。
●自傷行為
自分の体を
・舐めたり
・噛んだり
して、皮膚炎などを起こすことも。
◇分離不安症の兆候
・不安
・ストレス
からくる
自己刺激行動で
・特定の部位を舐めすぎて毛が抜ける
・皮膚が赤くなる
・傷になる
などの場合、分離不安症が強く疑われます。
●家を出る・帰宅時の行動
分離不安症の犬は
▶飼い主が帰宅すると
▶まるで数年ぶりに会ったかのように
▶過剰に喜びます。
これは
不在中の不安が大きかったこと
の裏返しでもあります。
また
▶飼い主の出かける準備だけで
すでに不安の兆候
・震える
・落ち着きがなくなる
・飼い主にべったりになる
を見せることもあります。
チェックシートの結果に応じた対策:愛犬に最適なサポートを
先のチェックシートの合計点数別に
愛犬にどう接していくべきか
具体的な対策を見ていきましょう。
0~5点:心配なし!
愛犬は
比較的お留守番が得意
なタイプです。
素晴らしいですね!
この状態を維持するためにも
引き続き
※クールな見送り
※クールな出迎え
を意識し、お留守番をポジティブな経験として積み重ねてあげましょう。
一人の時間も充実できるよう
・知育玩具の活用
・安心して過ごせるハウス
・クレート
・ケージ
を用意してあげることも大切です。
6~10点:やや不安傾向
お留守番に少し苦手意識
があるようです。
まだ初期段階ですので
▶早期の対策で
分離不安症への進行を防ぐことができます。
●お留守番練習の強化
最初は
・数分間部屋のドアを閉めるだけ
・家の外に出てすぐ戻る
など
▶ごく短い時間から始めて
▶愛犬が落ち着いていられたらすぐに戻り
▶褒めてご褒美を与えます。
徐々に時間を延ばしていきましょう。
●出かける合図への過敏反応を和らげる
・鍵を持つ
・コートを着る
など、愛犬が不安を感じる
出かける合図
の行動を
実際には出かけずに
繰り返し行います。
これを繰り返すことで

この行動が必ずしも外出に繋がるわけではないんだワン
と愛犬に学習させ
▶不安反応を和らげます。
●独立心を育む遊び
飼い主といっしょにする遊び
だけでなく
▶一人で集中できる知育玩具を与え
▶一人遊びの時間を増やしてあげましょう。
11~20点:分離不安の初期段階の可能性
愛犬は分離することに
ストレスを感じ始めている
かもしれません。
この段階になるとすでに
飼い主さん一人での対応
には限界がある場合もあります。
●専門家への相談
まずは獣医師に相談し、分離不安症の可能性について話し合いましょう。
必要であれば
・動物行動学を専門とする獣医師
・分離不安症に詳しいドッグトレーナー
を紹介してもらい
具体的な行動修正プログラム
を組んでもらうことが非常に有効です。
やや不安傾向で取り上げた対策を
・より計画的に
・より段階的に
進める必要があります。
愛犬に合わせたペースで焦らず取り組みましょう。
留守番中の様子を
▶動画で録画し
▶専門家に見せる
ことで、より正確な
・診断
・アドバイス
が得られます。
21~30点:分離不安症の可能性が高い
愛犬は
分離不安症を発症している
可能性が高いです。
愛犬自身が
非常に辛い状態にある
と考えられます。
この段階では専門家の
・診断
・指導
のもと、本格的な行動療法を開始する必要があります。
症状が重い場合は
▶行動療法をスムーズに進めるため
▶薬物療法が併用される
こともあります。
しかし
薬はあくまで治療の補助
であり、獣医師の指示のもとで適切に使用しましょう。
何よりも
愛犬を叱ることは
絶対に避けてください。
不安からくる行動を叱っても
犬は
自分がなぜ叱られているのか?
理解できず
▶さらに不安を増幅
させてしまいます。
31点以上:重度の分離不安症の可能性
愛犬は
重度の分離不安症に苦しんでいる
可能性が極めて高いです。
これは緊急性の高い状態です。
すぐに専門家に相談し、適切な治療を受けるようにしてください。
この段階では
・獣医師による診察
・薬物療法
が不可欠な場合が多いです。
飼い主さん一人で抱え込まず
▶専門家のサポートを積極的に求める
それが愛犬の苦痛を和らげる最善の道です。
分離不安症を予防するためには?愛犬の心を強く育む秘訣
分離不安症は一度発症すると
治療に時間がかかります
そのため
予防
が非常に重要です。
子犬の頃からの適切な関わりが、将来の愛犬の心の安定を左右します。
●子犬の頃からの適切な社会化
生後3週〜16週頃の
社会化期
は特に重要です。
この時期に
・さまざまな人
・老若男女
・場所
・公園
・動物病院など
・音
・生活音
・車の音など)
に慣れさせ、多様な経験を
ポジティブなもの
として体験させましょう。
・知らないこと
・新しい環境
への「慣れ」を促すことで
▶予期せぬ変化にも動じにくい心を育みます。
●お留守番のポジティブな経験作り
最初から長時間の一人にせず
▶短時間から「お留守番」を始め
▶成功したらご褒美を与える
などして
良い経験
として積み重ねます。
例えば
▶最初は数秒、数分から始め
▶愛犬が落ち着いていられたら
▶すぐ戻り
▶優しく褒めてあげましょう。
お留守番中に楽しめる
・知育玩具(コングなどにおやつを詰める)
・噛むおもちゃ
などを与え、お留守番の時間を
「楽しい時間」
と結びつける工夫も有効です。
●出かける前と帰宅後の関わり方
・出かける直前に
▶過剰に構いすぎる
・帰宅時に
▶過剰に喜ぶ
などはしないようにしましょう。
これは、犬に
出かけること=大きなイベント
と認識させてしまい
▶不安を煽る可能性があります。
出かける前は
・さりげなく
・特別に声をかけずに
家を出ます。
帰宅後も
・すぐに声をかける
・なでる
などはせず、落ち着いてから
=犬が興奮から覚めてから
声をかけるようにします。
この
・クールな見送り
・クールな出迎え
が、犬にとって
・飼い主の出入りは日常の一部であり
・特別なことではない
と教えてあげる重要なポイントです。
●独立心を育む遊びと学習
飼い主とべったりではなく
・一人で遊べるおもちゃを与える
・ハウスで落ち着いて過ごす練習をさせる
ことも大切です。
ハウスを
・安全で
・落ち着ける場所
と認識させることで、留守番時の安心感につながります。
「待て」
「伏せ」
などの基本的な指示だけでなく
「ハウス」
「お座りして待つ」
といった自立を促す練習も積極的に取り入れましょう。
●ルーティンの確立
・食事
・散歩
の時間をある程度一定にすることで
▶犬は生活のリズムを把握しやすくなり
▶予測できないことへの不安を軽減。
日々のルーティンは、犬に
・安心感
・安定感
を与えます。
予測可能な生活は
犬のストレスを大きく減らす
効果があります。
治療や処方される薬の例:専門家との二人三脚で
分離不安症の治療は
▶あくまで行動療法を軸に
▶必要に応じて薬物療法を併用
して行われます。
・飼い主さんの根気
・専門家との連携
が成功の鍵です。
行動療法:段階的に不安を克服する
行動療法は、分離不安症の
根本的な治療
であり、最も重要です。
時間をかけて
・犬の不安を和らげ
・飼い主と離れた時のポジティブな経験
を積み重ねさせます。
●段階的慣らし
最も基本的な治療法です。
飼い主が少しずつ離れる時間を長くしていく練習です。
◇具体的なステップ
①最初は数秒の分離から始め
犬が落ち着いていられる範囲で
成功体験
を積ませます。
例えば
▶別の部屋へ数秒だけ移動し
▶犬が落ち着いていたらすぐに戻って
▶褒めます。
②数秒→数十秒→数分→数十分と
徐々に分離する時間を延ばしていきます。
③慣れてきたら
・玄関のドアを開けて閉めるだけ
・ゴミ出しに行くふりをする
など実際の外出に近いシチュエーションを取り入れていきます。
◇成功のコツ
愛犬が不安を感じるサインを見せたら
▶すぐに分離を中止し
▶落ち着かせてから再開します。
決して急がず、愛犬のペースに合わせることが大切です。
●出かける合図への過敏反応を和らげる
犬は
飼い主が出かける際の特定の行動
・鍵を持つ音
・コートを着る
・バッグを持つなど
を飼い主がもうすぐいなくなるという
不安の合図
として認識しています。
・これらの合図と
・不安を結びつける反応
を弱めるために
▶飼い主が出かける準備をしても
▶実際には出かけない
という練習を繰り返します。
例えば
・鍵を持って▶ソファに座る
・コートを着て▶新聞を読む
・靴を履いて▶すぐ脱ぐ
など。
これを日常的に何度も繰り返すことで

この合図があっても絶対出かけるわけじゃないんだワン
ということを学習させます。
●ハウストレーニング
犬が安心して過ごせる場所
・クレート
・ケージなど
を用意し、そこを
・安全で
・ポジティブな場所
と認識させます。
◇練習方法
ハウスの中で
・おやつをあげる
・お気に入りのおもちゃで遊ばせる
・リラックスして寝る練習をさせる
などします。
決して無理強いせず

ハウスって心地いいワン♬
と感じさせることが重要です。
留守番中もこのハウスで過ごせるようにすることで、安心感を与えられます。
●遊びと運動の充実
十分な運動と思考を要する遊びで
・知育玩具
・宝探しゲームなど
▶エネルギーを発散させ
▶心身ともに満たされた状態を保つ
ことがストレス軽減につながります。
疲労は留守番時の
過剰な不安行動
を抑制する効果も期待できます。
ノーズワークもおすすめです。
犬の優れた嗅覚を活かして
・食べ物
・おもちゃ
などの匂いを
・追跡
・発見
する遊びやトレーニングのこと
匂いを嗅ぐことは犬にとって
本能的な行動
であり
・ストレス解消
・精神的な満足感
につながります。
薬物療法:行動療法をサポートする選択肢
獣医さんが処方する薬は
・犬の不安を和らげ
・行動療法をスムーズに進める
ための補助的な役割を果たします。
薬だけで分離不安症が治る
わけではありません。
行動療法と併用
することで最大の効果を発揮します。
●抗不安薬
◇クロミプラミン
三環系抗うつ薬の一種
犬のセロトニン系に作用
不安を軽減します。
◇フルオキセチン
選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)の一種。
人間にも使われる抗うつ薬です。
・不安
・強迫行動
を抑える効果が期待できます。
◇デキスメデトミジン
・不安
・恐怖
に起因する興奮を鎮める効果があります。
・短期的な使用
・特定の状況下での不安軽減
に用いられることがあります。
●フェロモン製剤
◇ADAPTIL
母犬が子犬に与える
鎮静フェロモン
を合成したもの
・ディフューザー
・首輪
・スプレー
として使用します。
薬というよりは、犬に安心感を与える
環境改善ツール
に近い位置づけです。
比較的副作用のリスクが低く、多くの犬に有効とされています。
薬はあくまでも補助。
根本的な解決には
行動療法
が不可欠です。
薬で一時的に症状が和らいでも
▶行動療法を怠れば
▶再発する可能性が高いです。
また、犬の
・性格
・状態
によって効果的な薬は異なります。
必ず獣医さんと密に連携し
▶最適な治療計画を立て
▶定期的な診察を受けること
が重要です。
自己判断での
・投薬
・中止
は絶対に避けてください。
薬の副作用や食事との兼ね合い:知っておくべきこと
薬物療法を行う際には
・副作用
・食事との兼ね合い
も理解しておく必要があります。
副作用
●消化器症状
・嘔吐
・下痢
・食欲不振など。
特に
・治療開始初期
・薬の量が合わない場合
に見られることがあります。
●鎮静作用
・眠気
・活動性の低下
が見られることがあります。
・犬がぼーっとする
・活気がなくなる
などの場合は
薬の量が多すぎる
可能性があります。
●行動の変化
ごくまれに
・攻撃性が増す
・興奮する
などの予測できない行動変化が見られることがあります。
●肝機能への影響
長期投与の場合
肝機能に影響を与える可能性があります。
そのため、薬を続ける際には
定期的な血液検査
で肝臓の数値などをモニタリングすることが推奨されます。
食事との兼ね合い
ほとんどの抗不安薬は、食事の有無にかかわらず投与できます。
しかし胃腸が敏感な犬の場合
▶食後に与える方が
▶胃への負担が少なく
▶吐き気を軽減できる
場合があります。
人間用の抗うつ薬の一部では
特定の食品
・チラミンを多く含むチーズ
・発酵食品など
との併用で副作用が強まる可能性。
しかし犬に処方される抗不安薬ではそこまで厳密な食事制限は少ないです。
しかし、念のため、獣医さんの指示に必ず従いましょう。
治療費の例:経済的な側面も考慮に
※あくまで参考程度
分離不安症の治療費は
・症状の重さ
・治療期間
・選択する治療法
・行動療法のみか
・薬物療法併用か
・通院回数
などによって大きく異なります。
◇初診料・再診料
数千円程度。
獣医行動学専門医の場合は
▶通常の獣医よりも高額になることも
(初診で1〜3万円程度)
◇行動療法
・専門のトレーナー
・獣医行動学者
による
・カウンセリング
・トレーニング
は1回あたり数千円~数万円と大きな幅。
複数回にわたるセッション
が必要になることが多く
▶トータルで数万円〜数十万円かかることもあります。
オンラインカウンセリングを提供する専門家も増えています。
◇薬物療法
・薬の種類
・犬の体重
によって異なります。
1ヶ月あたり数千円~1万円程度かかることが多いです。
治療期間が長引くこともあります。
◇検査費用
肝機能検査などの血液検査
(薬の効果や副作用のモニタリングのため)
を行う場合、数千円~1万円程度。
◇その他
・留守番中のモニタリングカメラ
・知育玩具
などの購入費用も考慮しましょう
◇総額
・軽度の分離不安症
=短期間の治療で済む場合でも数万円
・重度で長期にわたる場合
=数十万円以上かかることも珍しくありません。
ペット保険に加入している場合は
補償の対象となるか?
契約内容を事前に確認しておくことをおすすめします。
経済的な負担も考慮に入れ、獣医師と相談しながら無理のない治療計画を立てましょう。
分離不安症でのヒッポのごはん:心と体をサポートする栄養
分離不安症そのものを食事だけで治療することはできません
しかし精神状態安定のためのサポートとして、食事は重要な役割を果たします。
●強化する栄養素
◇トリプトファン
セロトニンの前駆体となる必須アミノ酸
セロトニンは
「幸せホルモン」
とも呼ばれ
・精神安定作用
・リラックス効果
・睡眠の質向上
に寄与します。
・鶏むね肉
・卵
・カツオ
・サーモン
・ヤギホエイプロテイン
などの食材を
・バランスよく
・好き嫌いに合わせて
配合することを検討します。
◇オメガ-3脂肪酸(DHA, EPA)
・脳の健康をサポート
・炎症を抑える効果
があります。
精神安定にも寄与すると考えられており
・不安行動の軽減
・認知機能のサポート
に役立つ可能性があります。
・新鮮な旬の魚
・あじ
・イワシ
・サーモン
・いさきなど
・サチャインチオイル
などを酸化に細心の注意を払い配合します
◇ビタミンB群
神経系の機能を正常に保つために不可欠な栄養素。
ストレス対抗ビタミン
とも呼ばれます。
・神経伝達物質の合成に関わり
・精神的な安定をサポート
します。
・豚肉
・レバー
・玄米
・緑黄色野菜
など幅広い食材から、バランスよく配合。
◇腸内環境に配慮
人間と同様に犬も
・腸内環境
・精神状態
には密接な関係があると言われています。
健康な腸内環境は、セロトニンなどの神経伝達物質の合成にも影響を与えます。
プロバイオティクス
・乳酸菌
・乳酸発酵発芽玄米甘酒
プロバイオティクス
・きのこのβグルカン
・もち麦
を自然な食品から取り入れます。
分離不安になったときにしてあげられること:愛犬に寄り添う心
分離不安症は、愛犬にとって
非常に苦痛な状態です。
飼い主さんの
・理解
・愛情深いサポート
が愛犬の回復には不可欠です。
※重要なことは再度まとめとして掲載しています
気を付けてあげるべきこと
●叱らない
不安からくる行動
・吠える
・粗相
・破壊など
を叱っても、犬は
自分がなぜ叱られているのか?
理解できません。
むしろ
▶飼い主からの否定的な反応によって
▶さらに不安を増幅させてしまい
▶症状が悪化する
可能性があります。
愛犬の行動は、不安のサインであると理解し、優しく接しましょう。
●無視しない
不安な犬を放置すると
▶状態が悪化する
可能性があります。
適切な対応をとらないまま
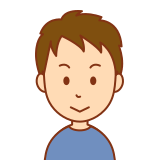
そのうち慣れるやろ
と無視することは
愛犬の苦痛を長引かせる
だけです。
早期に専門家と連携し、適切な介入を心がけましょう。
●過剰なスキンシップを避ける
・出かける前
・帰宅時
に過剰にスキンシップをとると
▶犬が飼い主の行動に一喜一憂
▶飼い主への依存心を強め
▶分離不安を助長する
ことがあります。
・クールな見送り
・クールな出迎え
を徹底し、感情的にならないよう注意しましょう。
●環境の変化に配慮する
・引っ越し
・家族構成の変化
・新しいペット
・赤ちゃんの誕生など
・飼い主の生活リズムの変化など
犬を取り巻く環境が大きく変わる際には、分離不安症が悪化しないよう、特に注意が必要。
急な変化は避け
▶段階的に慣れさせる工夫をしましょう。
してあげられること
●安全な場所の提供
犬が安心して過ごせるハウス
・クレート
・ケージなど
を用意し、そこを
自分だけの安全な場所
と認識させましょう。
・毛布をかける
・お気に入りのおもちゃを入れる
・飼い主の匂いがついたを入れる
などして、落ち着けるプライベートな空間にしてあげてください。
●知育玩具の活用
飼い主がいない間も
犬が退屈しないよう
▶コングなどにおやつを詰めて与える
▶長時間集中して遊ぶ時間ができる
▶不安を紛らわせることがでる。
これは
お留守番=楽しいこと
というポジティブな連想にもつながります。
●リラックスできる音楽や香り
犬が落ち着くとされる
・クラシック音楽
(特にゆったりとしたテンポの曲)
・犬用のリラックス音楽
(例:Through a Dog's Ear)
を流すのも有効です。
また
アロマディフューザーで
リラックス効果のある香り
を使用するのも一案です。
リラックスできる
・音楽
・香り
は犬の分離不安症の行動療法において
有効な補助手段
となり得ます。
多くの
・研究
・臨床現場での経験
からその効果が支持されています。
しかし
特に香りに関しては
・犬の嗅覚の特性
・精油の安全性
を十分に理解し
・獣医師
・アロマの専門家
と相談の上、慎重に使用することが不可欠です
◇香りの注意点
犬は人間よりも
はるかに優れた嗅覚
を持つため
香りが強すぎると逆効果。
また犬にとって
有害となる精油
・ティーツリー
・ユーカリ
・ペパーミントなど
は絶対に避けてください。
比較的安全とされる
・ラベンダー(真正ラベンダー)
・カモミール(ローマンカモミール)
を使用する際も、必ず
・獣医師
・ペットアロマの専門家
と相談し
・少量から
そして
・換気の良い場所
で利用しましょう。
犬が
不快なサイン
を見せたらすぐに中止してください。
●定期的な運動と散歩
十分な運動は
=犬のストレス発散に役立ちます。
特に、ただ歩くだけでなく
▶頭を使うような散歩
・匂い嗅ぎに集中させるノーズワーク
・新しい場所の探索など
は心身の満足度を高め
▶お留守番時の不安軽減につながります。
●動画でのモニタリング
留守中の犬の様子をカメラで確認。
動画を撮影しておくことは
・症状のパターン
・重症度
を客観的に把握できます。
これは
・獣医さんへの説明
・行動療法の計画を立てる
時に非常に貴重な情報となります。
●忍耐と愛情
分離不安症の治療は
・時間
・根気
を要します。
すぐに効果が出なくても焦らず
・愛犬に寄り添い
・根気強く愛情を持って接する
ことが何よりも大切です。
改善の兆しが見えなくても、諦めずに専門家と連携し続けることが、愛犬の未来を拓きます。
分離不安症は
・愛犬
・飼い主
の関係性を見つめ直す良い機会。
・過保護になっていないか?
逆に
・十分な愛情を注げているか?
など飼い主自身の行動も振り返ります。
そして
・獣医さん
・専門家
と協力し、チームとして愛犬をサポートしていく意識が非常に重要です。

分離不安症になったのは私のせいかも…
と自分を責める必要はありません。
大切なのは
今からどう改善していくか
なのです。
この情報が、愛犬の分離不安症に悩む飼い主さんの助けになれば幸いです。
さらに詳しい情報や個別の相談が必要な場合は、獣医師や動物行動学の専門家にご連絡ください。




コメント