我が家の愛犬が
・突然ぐったり
・何度も嘔吐
そんな姿を見るのは、飼い主さんにとって非常につらいものです。
その原因の一つとして考えられるのが
膵炎
早期発見と適切な治療、そして何よりも再発させないための日々のケアが重要となる病気です。
犬の膵炎とはどんな病気か? – 自分の消化酵素で自分を溶かす!?
膵炎とは、その名の通り
膵臓(すいぞう)に炎症が起こる
病気です。
膵臓は、胃と十二指腸の近くにあり、大きく分けて2つの重要な役割を担います。
●膵炎の重要な2つの役割
①外分泌機能
食べ物の消化に必要な様々な消化酵素
・タンパク質分解酵素
・脂肪分解酵素
・炭水化物分解酵素など
を合成。
膵管を通じて十二指腸へ分泌します。
②内分泌機能
・インスリン
・グルカゴン
といった血糖値を調節するホルモンを血液中に分泌します。
通常、膵臓内で作られる消化酵素は
▶不活性な状態で蓄えられ
▶十二指腸に分泌されてから活性化
しかし、何らかの原因で膵臓内でこれらの消化酵素が異常に活性化してしまうことで
▶膵臓自体が消化酵素によって自己消化
▶強い炎症
=膵炎を引き起こしてしまうのです。
膵炎には「急性」と「慢性」があります
膵炎の症状は、炎症の程度や急性か慢性かによって大きく異なります。
どんな症状が出るのか?
見逃したくないSOSサインを知っておきましょう
●急性膵炎
命に関わることもあり、迅速かつ適切な治療が必要です。
また、炎症が膵臓だけでなく
周囲の臓器
・肝臓
・胆嚢
・腸など
や全身に波及し、多臓器不全などの深刻な合併症を引き起こすこともあります。
◇急性膵炎の典型的な症状
━激しい腹痛
最も特徴的な症状の一つ。
・祈りのポーズ
(前足を伸ばし、お尻を高く上げる姿勢)

・お腹を触られるのを極度に嫌がる
・震える
・落ち着きがない
・呼吸が速くなる
などが見られます。
━繰り返す嘔吐
食べていないのに黄色い胃液や泡を何度も吐くことがあります。
━下痢
黄色っぽい脂肪便や、時には血が混じった下痢をすることもあります。
━食欲不振・元気消失
急にご飯を食べなくなり、ぐったりと動かなくなる。
━発熱、脱水症状
▶重症化すると
・呼吸困難
・黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
・ショック状態(虚脱、低体温、頻脈など)
に陥ることもあります。
●慢性膵炎
軽度な炎症が持続したり、急性膵炎を繰り返したりします。
◇慢性膵炎の典型的な症状
━軽度の嘔吐や下痢が時々見られる。
━ 食欲にムラがある、なんとなく元気がない。
━徐々に体重が減少する。
━慢性膵炎は
症状がはっきりしないことも多く、他の消化器疾患との区別が難しい場合があります。
その分「静かなる進行」をすることがあり、飼い主さんが気づかないうちに徐々に膵機能が低下していくことも。
定期的な健康診断での早期発見が重要!
━急性増悪
急性膵炎のような激しい症状を繰り返すこともあります。
膵炎を予防するためには? – 日常生活でできること
膵炎多くは、正確な原因は特定できない特発性膵炎
ですが、以下の点はリスクを高めると考えられており、予防のために重要です。
●【最重要】高脂肪食を避ける
脂肪分の多い食事は
▶膵臓からの消化酵素の分泌を過剰に刺激
▶膵炎の最大の引き金!
人間の食事
(特に揚げ物、肉の脂身、中華料理など)
のおすそ分けは絶対にやめましょう。
ドッグフードも脂肪分が高すぎないか確認しましょう。
●肥満の予防と解消
肥満は高脂血症を引き起こしやすく、膵炎のリスクを高めます。
適正体重を維持することが大切です。
●適切な食事管理
・決まった時間に
・決まった量の
・バランスの取れた
総合栄養食を与えることが基本です。
おやつの与えすぎにも注意し、与える場合は低脂肪のものを選びましょう。
●定期的な健康診断
血液検査で膵臓の数値
・特に犬膵特異的リパーゼ
(cPLIやvLIPAなど)
・中性脂肪、コレステロール値
などをチェックすることで、異常の早期発見に繋がります。
膵炎や高脂血症の好発犬種
・ミニチュア・シュナウザー
・ヨークシャー・テリア
・コッカー・スパニエル
・ミニチュア・プードル
・シェットランド・シープドッグ
などは特に注意が必要です
●ストレス管理
直接的な原因となるかは明確ではありませんが、過度なストレスは
・免疫力の低下
・消化機能の不調
を招く可能性があるため、穏やかな生活環境を整えてあげることも大切です。
●基礎疾患の管理
・クッシング症候群
・甲状腺機能低下症
・糖尿病
・高脂血症
などの基礎疾患がある場合
それらの適切な治療と管理が膵炎予防にも繋がります。
●薬剤の慎重な使用
一部の薬剤
・特定の利尿剤
・高用量のステロイド剤
・一部の抗てんかん薬
・L-アスパラギナーゼなどの抗がん剤
は膵炎を引き起こす可能性が報告されています。
これらの薬剤を使用する際は、獣医師とリスクについてよく話し合い、必要最小限の使用に留めることが重要です。
治療法や処方される薬の例 – 膵臓を休ませ、全身をサポート
膵炎の治療は
・膵臓の炎症を鎮め
・膵臓を休ませ
・脱水や電解質の異常を補正
・痛みをコントロール
・合併症を防ぐための対症療法
が中心となります。
膵炎に特化した薬は
現時点では存在しない
というのが一般的な認識です。
●入院管理
特に急性膵炎や重症例では、集中的な治療とモニタリングのために数日間の入院が必要となることが一般的です。
●輸液療法(点滴)
最も重要な治療の一つ。
・脱水状態を改善し
・電解質バランスを整え
・全身の循環を維持
これにより
・膵臓への血流を確保し
・炎症物質の希釈と排泄を促し
膵臓の回復を助けます。
◇点滴に使われる主な成分
ー生理食塩水
・ナトリウム
・クロール
を含み
・脱水
・低血圧
を改善します。
ー乳酸リンゲル液
生理食塩水に
・乳酸ナトリウム
・カリウム
・カルシウム
などが含まれており
・電解質の補正
・アシドーシス(血液が酸性に傾く状態)
の改善に役立ちます。
ーブドウ糖
・血糖値が低下している場合
・エネルギー補給が必要な場合
に追加されます。
ービタミンB群
特にビタミンB12は
慢性的な消化器疾患で不足しやすいため、補充されることがあります。
●絶食・絶水(初期)
かつては膵臓を休ませるために数日間の絶食・絶水が推奨されました。
現在も嘔吐が激しい場合などには行われます。
最近では早期栄養サポート
つまり嘔吐がコントロールでき次第、できるだけ早期に少量ずつ水分や栄養補給を開始することが
・腸管粘膜のバリア機能の維持
・腸内細菌の異常増殖や体内移行の防止
・免疫力の維持
・そして早期回復に繋がる
という考え方が主流になりつつあります。
ただし、これは獣医師が個々の状態を判断して決定します
●痛み止め
膵炎は非常に強い痛みを伴うため、積極的な疼痛管理が不可欠です。
◇オピオイド系鎮痛薬
ブトルファノール、トラマドール、フェンタニル、モルヒネなど
中等度~重度の痛みに使用。
━副作用
眠気、ふらつき、便秘、呼吸抑制、吐き気、食欲不振。
食事量が減ることがあります。
◇非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
メロキシカム、カルプロフェン、フィロコキシブなど
炎症と痛みを抑えますが、消化管や腎臓への負担があるため、脱水時や消化器症状が強い急性期には慎重に使用されます。
━副作用
胃腸障害(嘔吐、下痢、消化管潰瘍、黒色便)、腎障害、肝障害。
空腹時を避け、食後の投与が推奨されることが多いです。
脱水時には使用を避けるか、慎重なモニタリングが必要です。
◇その他
ガバペンチン、アマンタジン、リドカイン持続点滴など
複数の鎮痛薬を組み合わせる
マルチモーダル鎮痛
により、各薬剤の副作用を抑えつつ、より効果的な疼痛管理を目指します。
●消化酵素製剤
膵臓の消化酵素
・アミラーゼ
・リパーゼ
・プロテアーゼなど
を補い、食物の消化吸収を助け
・栄養不足
・下痢
を改善することを目的とした
・サプリメント
または
・医薬品です。
膵臓の機能が著しく低下し
▶食物を十分に消化できなくなった
・膵外分泌不全(EPI)
あるいは
・慢性膵炎
の犬に特に有効です。
外部から消化酵素を補給することで
▶膵臓自身の消化酵素分泌を抑え
▶膵臓を「休ませる」
効果が期待されます。
◇主な商品名と成分例
ーパンクレアチン
(パンクレアザイム、パンクレアチン製剤)
膵臓から抽出された
天然の消化酵素の混合物です。
多くの製品に含まれる主成分です。
ーヴィオカゼ
動物用の消化酵素製剤で、パンクレアチンを主成分としています。
◇効果
ー栄養状態の改善
消化吸収が良くなることで
・体重増加
・毛並みの改善
が見られることがあります。
ー下痢の軽減
未消化の
・脂肪
・タンパク質
が減ることで
・脂肪便
・下痢
が改善します。
◇副作用
ごくまれに、大量に与えすぎた場合に
・口内炎
・口周りの皮膚炎
が見られることがあります。
また最初のうちは
・軟便
・下痢
が一時的に生じることがあります。
消化酵素は熱に弱いため
熱い食べ物に混ぜると効果が失消
必ず食事の温度が冷めてから混ぜる必要があります。
●制吐剤(吐き気止め)
マロピタント・オンダンセトロン・メトクロプラミドなど
嘔吐をコントロールし、脱水や電解質異常の悪化を防ぎ、早期の経口摂取を可能にするために重要です。
━副作用
副作用は比較的少ないです
注射部位の痛み、まれにアレルギー反応。
嘔吐が治まれば食欲改善に繋がり、食事が摂りやすくなります。
●胃酸分泌抑制薬
H2ブロッカー・プロトンポンプ阻害薬など
・胃酸による膵臓への刺激を軽減する目的
・ストレスによる胃粘膜障害の予防
に使用されることがあります。
━副作用
長期使用により胃内pHが上昇
・消化能力の低下
・腸内細菌叢のバランスに影響を与える可能性
が指摘されています。
●抗生物質
・細菌感染が強く疑われる場合
・重症例で二次的な細菌感染を予防
などの目的で使用されることがありますが、全ての膵炎にルーチンで使用されるわけではありません。
━副作用
腸内細菌叢のバランスを崩し、下痢を引き起こすことがあります。
食欲不振の原因になることも。
●新鮮凍結血漿(FFP)の輸血
重症例で
・タンパク質分解酵素阻害物質の補充
・血液凝固因子の補給
・循環血液量の改善
・低アルブミン血症の改善
などを目的に行われることがあります。
効果については議論もありますが、救命の一つの選択肢です。
●低分子ヘパリン
播種性血管内凝固症候群(DIC)という重篤な合併症の予防や治療のために使用されることがあります。
何らかの病気によって血液が固まりやすくなり、全身の細い血管の中で血液の塊(血栓)が多発してしまう病気
●ステロイド剤
一般的な細菌感染や薬剤誘発性ではない膵炎の場合
・炎症を強力に抑える目的で
・獣医師の慎重な判断のもと
・短期間使用される
ことがあります。
特に
・自己免疫が関与の可能性のある慢性膵炎
・重度の全身性炎症反応症候群(SIRS)
を伴う場合など。
ですが、使用には賛否両論あります。
━副作用
・多飲多尿
・食欲増進(膵炎の食事療法中はコントロールが難しい場合も)
・体重増加
・血糖値上昇
・易感染性(免疫抑制)
・消化管潰瘍のリスク
(特にNSAIDsとの併用は禁忌)
長期使用で
・医原性クッシング症候群
・糖尿病
のリスク
食事の嗜好性が変わることも。
◇ステロイドと膵炎・糖尿病の関係
ーステロイドと膵炎
ステロイドは
▶脂質代謝に影響を与え
▶血液中の脂質濃度を上昇させる
ことが知られています。
これは、膵炎の
・発症
・悪化
のリスク要因となります。
ーステロイドと糖尿病
ステロイドは
インスリン抵抗性
を引き起こします。
これにより、体の細胞が
▶インスリンにうまく反応できなくなり
▶血糖値が上昇します。
膵炎は
▶膵臓のインスリン産生細胞を損傷し
▶糖尿病を引き起こす
可能性があるため
ここにステロイドが加わると
糖尿病を発症する危険性
がさらに高まります。
・膵炎の犬に
・ステロイド剤を与える
ことは、一般的に推奨されません。
・糖尿病のリスクをさらに高め
・膵炎を悪化させる可能性
があるため、非常に危険な場合があります。
●消化酵素サプリメント
パンクレリパーゼ、パンクレアチンなど
・膵臓の機能が低下し、消化吸収不良が見られる慢性膵炎
・膵外分泌不全(EPI)を併発している場合
消化を助けるために生涯にわたり使用されます。
━副作用
通常は安全性が高いです
が、まれに口内炎や下痢、高用量で高尿酸血症のリスク。
フードによく混ぜて与えます。
●薬と食事との兼ね合い全般
嘔吐が治まり食事が開始されたら、多くの経口薬は
・食事と一緒に
・または食直後に与える
ことで、胃腸への刺激を軽減できます。
ただし、薬剤によっては空腹時投与が指示される場合もあるため、必ず獣医師の指示に従ってください。
絶食・絶水期間中は、必要な薬剤は注射や点滴で投与されます。
犬の膵炎に対する「ヒッポのごはん」の栄養対策
膵炎の治療と再発予防において
食事管理
は最も重要な柱の一つです。
ヒッポのごはんでは、この考えに基づき、
・愛犬の膵臓に負担をかけず
・健康維持をサポートする
食事づくりを心がけています
●コンセプト
・膵臓への負担を最小限に抑え
多角的なアプローチで
・体調回復をサポート
ヒッポのごはんでは、以下の3つの柱で膵炎対策の食事を提供します。
①超低脂肪食の徹底
膵臓への刺激を最小限に抑えます。
②高消化性の栄養バランス
・消化器への負担を軽減し
・必要な栄養を効率的に吸収します。
③個体差に合わせたレシピ
・犬種
・体質
・併発疾患など
を考慮し、その子に最適な食事を提案します。
具体的な対策:食事の内容と栄養素
●【絶対厳守】超低脂肪食
脂肪は膵臓を最も強く刺激する栄養素。
・急性期
はもちろん
・回復後も
生涯にわたり
徹底した低脂肪食を続ける
必要があります。
◇目標脂肪含有量(乾物重量あたり)
・急性期や重症例では5-8%以下
・維持期でも10-15%以下
を目指すことが多いです。
・犬種や個体差
・併発疾患
によって目標値は異なります。
ミニチュア・シュナウザー
などはより厳格な脂肪制限が必要な場合があります。
◇脂質の質
高脂血症がない場合は
・良質な脂質を
・適度に
摂取します。
・酸化した脂肪
・悪質な動物性脂肪
は避け
主に新鮮な魚などを活用して
抗炎症作用
が期待できるオメガ3脂肪酸を供給します
卵黄コリン
による脂質代謝改善効果にも期待。
血中コレステロールを低下することで
▶脂肪蓄積の抑制
乳製品
・牛乳
・チーズ
など高脂肪のものは
・下痢
・脂肪過多
の原因なので避けます。
・低脂肪カッテージチーズ
は例外的に使用可な場合も。
●高消化性で良質なタンパク質
高たんぱく・高脂肪は
・膵臓負担が大きく
・アンモニア生成量増やす可能性。
たんぱく質は
・中程度
・高消化性
に仕上げます。
タンパク質源として
・鶏胸肉
・タラなどの白身魚
・卵黄
などを使用しさらに
・変性させないよう高温加熱を避け
・低温調理にて仕上げます。
◇小麦グルテンを避ける
強い粘り気のある性質が、
犬の消化器系では消化されにくい
ことが指摘されています。
また
・グルテンアレルギー
・不耐症
を持つ犬がグルテンを摂取すると
・慢性的な下痢や嘔吐
などの消化器症状、または
・皮膚のかゆみや湿疹
といったアレルギー反応
を引き起こす可能性があります。
これらの症状は
膵炎の症状と重なる
こともあり
体の炎症状態を悪化させる
原因にもなり得ます。
◇膵臓に負担をかけない消化性の重要性
膵炎の食事療法では
脂肪を制限すること
が最も重要とされていますが、実は
タンパク質の「消化性」
も同じくらい大切です。
食物が小腸に入ると
▶膵臓は消化酵素を分泌して
▶消化を助けます。
この分泌を促す刺激は、主に
・脂肪
・特定の遊離アミノ酸
・フェニルアラニン
・トリプトファン
・バリンなど
によって引き起こされます。
ここで鍵となるのが
「消化のスピード」
消化性の悪いタンパク質
を摂取すると
▶消化に時間がかかり
▶これらのアミノ酸が小腸に長く留まる
ことになります。
その結果
▶膵臓への刺激が長時間続き
▶消化酵素の過剰な分泌を招いて
▶膵炎の症状を悪化させるリスクが高まります。
このメカニズムは、場合によっては
脂肪以上に膵臓に負担をかける
可能性があるため
単純に脂肪を減らす
だけでなく、使用するタンパク質の
「質」と「消化性の高さ」
を徹底的に考慮する必要があるのです。
●適度な炭水化物
低糖質・低GI食品が基本。
糖尿病を併発しやすいので
血糖値に配慮。
消化の良い炭水化物
・玄米
・ジャガイモ
・カボチャなど
をエネルギー源として利用します。
ヒッポのごはんでは
発酵発芽玄米甘酒
を使用することもあります。
また
・適度な食物繊維は
消化管の健康維持に役立ちますが
・過剰な不溶性食物繊維
は消化吸収を妨げる可能性もあるため、バランスが重要です。
●腸内環境とビタミンのケア
膵炎の回復を促すために
腸内環境を整えること
も重要です。
また、低脂肪食は
脂溶性ビタミンの吸収を悪くする
可能性があるため、不足しがちなビタミンを補給することも考慮に入れます。
●併発疾患に合わせた柔軟な対応
膵炎は他の病気を併発することが多く、それぞれのケアを同時に行う必要があります。
◇高脂血症・糖尿病
脂肪や糖質をさらに厳しく管理します。
◇腎臓病と膵炎の食事療法の違い
腎臓病食
・低タンパク質
腎臓の機能が低下すると
▶タンパク質の代謝産物(老廃物)をうまく排出できなくなります。
これを減らすために
▶タンパク質の量を制限します。
・高カロリー
タンパク質を制限する分
必要なエネルギーを確保するため
・脂質
・炭水化物
の量を増やすことが一般的です。
膵炎食
・超低脂肪
脂肪は膵臓を最も強く刺激し
▶膵炎の原因や悪化につながるため
徹底した脂肪制限が基本です。
・高消化性
消化器への負担を減らすため、高消化性のタンパク質や炭水化物を選びます。
なぜ「正反対」になるのか?
腎臓病食は
タンパク質を減らし、脂肪を増やす
傾向にあります。
一方、膵炎食は
脂肪を徹底的に減らす
ことが大前提です。
したがって
・腎臓病
・膵炎
を併発している犬の食事は、
どちらか一方の病気に特化した療法食を与えるわけにはいきません。
個々の犬の病態
・どちらの症状がより深刻か?
・体重の減少が著しいか?
などを慎重に判断し、
・両方の病気に対応できるような
・バランスの取れた食事を組み立てる
必要があります。
この場合
・低タンパク質
・低脂肪
の両方を満たすことが目標となります。
その上で、エネルギー不足を補うために
・消化性が高く
・血糖値に配慮した
炭水化物を適切に活用することが一般的です。
◇クッシング症候群
◇甲状腺機能低下症
これらの病気は
膵炎の食事療法と共通する点が多い
ため、比較的調整しやすいと言えます。
ただし
それぞれの病気特有の注意点
を考慮する必要があります。
◇小腸脂肪便との関係
小腸脂肪便は
脂肪が適切に消化・吸収されずに
▶便として排出される状態です。
これは膵臓の機能不全
特に膵外分泌不全(EPI)
が原因で起こることがあります。
EPIでは、膵臓が
▶リパーゼ(脂肪分解酵素)を十分に分泌できず
▶食べた脂肪がそのまま便として出てしまいます。
慢性膵炎が進行すると
▶膵臓が徐々に破壊され
▶最終的にEPIを併発する
ことがあります。
このため、そもそも
脂肪の摂取量を制限
することが重要となります。
◇腸リンパ拡張症との関係
腸リンパ拡張症は
▶腸のリンパ管が拡張し
▶リンパ液が漏れ出すことで
・タンパク質
・脂肪
・リンパ球
などが便中に失われる病気です。
この状態が続くと、体内で
脂肪の代謝異常が生じ
▶高脂血症を招くことがあります。
この病気も
・膵炎
・他の炎症性腸疾患
と同時に発症することがあります。
腸リンパ拡張症では
脂肪の吸収経路であるリンパ管
に異常があるため
▶食べた脂肪が適切に吸収されません。
腸リンパ拡張症でも
吸収経路に負担をかけないように
低脂肪食が基本となります。
また
中鎖脂肪酸(MCT)
はリンパ管を通らずに吸収されるため、食事に取り入れられることがあります。
●削痩している場合の対応
消化吸収力が低下していると考えられ
給与量をいきなり増やすと
▶下痢や栄養吸収不良が悪化する
ことがあります。
最初の2〜3ヶ月は
・下痢をしないこと
・体重が減少しないこと
を目標に
・レシピ
・給与量
を調整します。
膵炎で強化すべき栄養素
●オメガ3脂肪酸(EPA、DHA)
新鮮な魚などに含まれ
・炎症を抑制
・膵炎の回復を助ける
可能性があります。
ただし脂肪の一種なので、非常に慎重に追加する必要があります。
●ビタミンB群(特にビタミンB12)
慢性的な消化器疾患では、吸収不良により
ビタミンB12
をはじめとする、ビタミンB群が欠乏しやすくなります。
・食欲不振
・元気消失
・体重減少
などに関与します。
●抗酸化物質
・ビタミンE
・ビタミンC
・セレン
・ポリフェノールなど
膵炎による強い炎症は
▶体内で大量の活性酸素を発生させ
▶酸化ストレスを引き起こします。
これらの抗酸化物質は
・細胞のダメージを軽減し
・回復をサポートする可能性があります。
※ただし、ビタミンCは犬自身が体内で合成できるため、過剰な補給は必ずしも必要ではありません
その他注意点
●食事の与え方
・1回の食事量を減らし
・食事回数を増やす(1日3~4回など)
ことで、消化器への負担を軽減できます。
●おやつは原則禁止
どうしてもの場合は
超低脂肪のものをごく少量。
・ジャーキー
・チーズ
・ソーセージ
・ビスケットなど
市販の多くのおやつは高脂肪です。
おやつを与える場合は
・茹でた野菜
(ブロッコリー、ニンジンなど少量)
・専用の低脂肪トリーツ
などを専門家に相談の上で選びましょう。
●人間の食べ物は絶対に与えない。
●手作り食の場合
非常に厳密な栄養計算と知識が必要です。
必ず栄養学に詳しい
・獣医師
・専門家
の指導のもとで行い、
血液検査などで、定期的な栄養バランスのチェックを受けてください。
自己流は極めて危険です。
ヒッポのごはんでは無料でレシピ相談もできます。
膵炎の治療費の例 – あくまで目安です
犬の膵炎の治療費は
・重症度
・治療期間
・入院の有無
・合併症の有無
・動物病院の規模や地域
などによって大きく変動します。
以下はあくまで一般的な目安として参考にしてください。
●軽症
通院治療のみ、数日~1週間程度
◇1日あたり:
5,000円~20,000円程度
(診察料、血液検査、皮下輸液、注射(制吐剤・鎮痛剤など)、内服薬など)
◇総額:
数万円程度
●中等症~重症
入院治療が必要、3日~1週間程度の入院
◇入院1日あたり:
20,000円~80,000円程度
(入院費、静脈輸液、各種検査(血液検査、超音波検査など頻回に)、各種注射薬、酸素吸入、疼痛管理、栄養管理など)
◇初期集中治療期間(最初の数日間)は特に高額になる傾向があります。
◇総額:
10万円~50万円程度。
・合併症(DIC、腎不全、糖尿病など)を併発
・手術が必要
・入院が長期化
では100万円を超えるケースも珍しくありません。
●慢性膵炎の維持管理
生涯にわたる場合も
◇月額:
数千円~数万円程度
(定期的な診察・血液検査、療法食代、内服薬(消化酵素、ビタミン剤など)代)
※ペット保険に加入している場合は、補償内容に応じて自己負担額を軽減できます。
膵炎は
・再発しやすく
・治療が長期にわたる
こともあるため、保険の有用性が高い疾患の一つと言えます。
ただし、加入前に発症していた場合は補償対象外となることがほとんどです。
その他、愛犬が膵炎になったときにしてあげられること
愛犬が膵炎と診断されたら、飼い主さんは不安でいっぱいになると思いますが、前向きにケアに取り組むことが大切です。
●獣医師の指示を守る
・食事療法
・投薬
・通院スケジュールなど
獣医師の指示を自己判断で変更したり中断したりしないこと。
疑問があれば遠慮なく質問しましょう。
ヒッポのごはんでも相談は受け付けています。
●徹底した食事管理
家族全員で情報を共有し、誰か一人がこっそりおやつを与えたりしないようにルールを徹底します。
「かわいそうだから」という気持ちは禁物です。
●安静な環境の提供
特に急性期や体調が悪い時は、静かで落ち着ける場所でゆっくり休ませてあげましょう。
散歩も体調に合わせて無理のない範囲で。
●ストレスの軽減
・穏やかな声かけ
・優しいスキンシップ
で安心感を与えましょう。
ただし、お腹を痛がっている時は無理に触らないように。
●日々の症状の注意深い観察と記録
□嘔吐の有無、回数、内容物
□便の状態
(形、色、量、脂肪便や血便の有無)
□食欲、飲水量
□元気、活動量
□腹痛のサイン
(祈りのポーズ、お腹を丸める、震え、触られるのを嫌がるなど)
□体重の変化
これらの情報を記録しておくと、獣医師とのコミュニケーションがスムーズになり、治療方針の決定にも役立ちます。
●定期的な通院と検査の継続
症状が落ち着いても、膵炎は再発しやすい病気です。
定期的な健康チェック
・血液検査
・超音波検査など
を受け、再発の兆候を早期に捉えることが重要です。
●体重管理の徹底
肥満は膵炎の大きなリスク因子です。
適正体重を維持するように心がけましょう。
●口腔ケア
嘔吐が多いと口腔内環境が悪化しやすいです。
可能な範囲で歯磨きなどのケアも行いましょう。
●愛情と根気を持ったケア
膵炎の治療や管理は長期にわたることがあります。
愛犬を
・励まし
・寄り添い
・根気強く
ケアを続けてあげてください。
●飼い主さん自身のメンタルケア
愛犬の闘病は
・精神的にも
・経済的にも
負担が大きいものです。
一人で抱え込まず
・家族や獣医師
・信頼できる友人
・ヒッポのごはん
に相談したり、同じ病気の犬の飼い主さんのコミュニティなどで情報を交換したりすることも支えになるかもしれません。
その他、膵炎についてまとめ
●診断の難しさと特異的検査
膵炎の症状は非特異的なことが多い
=他の消化器疾患との鑑別が重要。
血液検査では、
・犬膵特異的リパーゼ
(cPLIやSpec cPL、vLIPAなど)
の測定が、従来の
・血清アミラーゼ
・リパーゼ
よりも膵炎診断の特異性が高いとされています。
超音波検査は膵臓の状態を視覚的に評価するのに非常に有用。
ですが、検査者の
・技術
・経験
に左右される側面もあります。
CT検査が用いられることもあります。
●膵炎を疑うべき血液検査の微細な変化
膵炎の診断において
血液検査
は非常に重要な手がかりとなります。
最終的な診断は
犬膵特異的リパーゼ
・cPLI
・cPL
が最も信頼性が高いです。
しかしそれに至るまでの
「怪しい」兆候
はいくつか存在します。
以下の項目は
・正常範囲内であっても
・下痢や嘔吐などの臨床症状と合わせて
前回検査時より数値が上昇している
などの場合に
膵炎の可能性を疑うきっかけとなります。
◇リパーゼ(LIP)とアミラーゼ(AMY)
ー一般的な変化
これらの数値は
膵臓から分泌される消化酵素
であり、膵炎で上昇することが多いです。
・正常範囲の上限に近い
または
・前回よりわずかに上昇している
場合に注目すべきです
ー注意点
・リパーゼ
・アミラーゼ
は膵臓以外からも分泌されるため
・腎不全
・肝臓病
・腸疾患
などでも上昇することがあり
これだけで膵炎と断定はできません。
しかし臨床症状
・食欲不振
・嘔吐、下痢など
と合わせて上昇傾向が見られる場合は
cPLIの検査を検討する
重要な手がかりとなります。
◇CRP(C反応性タンパク質)
ー一般的な変化
CRPは
体内の炎症を反映するマーカー
で、膵炎では通常、著しく上昇します。
炎症性腸疾患など
他の炎症でも上昇します。
しかし前回より上昇傾向がある場合は
▶体内で何らかの炎症が起きている
ことを示唆します。
膵炎の可能性も視野に入れるべきです。
◇ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)
ー一般的な変化
ALTは肝臓の酵素ですが
重度の膵炎では
▶肝臓にも炎症が波及することがあり
ALTが上昇することがあります。
膵炎の
・初期
・軽度
の場合でも、わずかに上昇することがあります。
◇血中脂質(コレステロール、中性脂肪)
#一般的な変化
高脂血症は
膵炎の大きなリスク要因であり、膵炎の犬では高値を示すことがよくあります。
正常範囲内であっても
特に中性脂肪の値
が前回より上昇している場合、注意が必要です。
特にミニチュア・シュナウザーなどの
高脂血症になりやすい犬種
では、わずかな上昇でも膵炎の引き金になる可能性があります。
◇血糖値
#一般的な変化
膵炎が進行して
▶インスリン産生細胞にダメージが及ぶと
▶血糖値が上昇し
▶糖尿病を併発します。
・正常範囲の上限に近い
・または前回よりわずかに上昇
している場合
膵臓がすでに何らかのストレス
を受けているサインかもしれません。
◇早期発見のためのポイント
#複数の数値を合わせて見る
単一の数値だけでなく
・リパーゼ
・CRP
・脂質
の数値が同時に上昇傾向を示している場合、膵炎の可能性はより高まります。
#臨床症状と照らし合わせる
獣医師は、血液検査の結果だけでなく
・嘔吐、下痢
・食欲不振
・腹部の痛み
などの臨床症状と合わせて総合的に判断します。
#経過観察
正常範囲内の数値であっても
▶症状が続く場合は
▶数週間後に再検査を行い
▶数値の推移を確認すること
が重要です。
これらの「怪しい」変化が見られた場合
より特異的な検査である
▶cPLIを実施することで
膵炎の
・早期発見
・早期治療
につなげることができます。
●高脂血症との密接な関係
特にミニチュア・シュナウザーで
遺伝的に高トリグリセリド血症(中性脂肪が高い状態)になりやすく、これが膵炎の強力なリスク因子となります。
高脂血症のコントロールが膵炎予防・再発防止に不可欠です。
●糖尿病・膵外分泌不全(EPI)の関連
重度の急性膵炎や慢性膵炎を繰り返すことで、膵臓の組織が広範囲にダメージを受けると
▶インスリンを分泌するランゲルハンス島が破壊されて糖尿病を続発
▷消化酵素を産生する腺房細胞が減少して、膵外分泌不全(EPI)を発症
したりすることがあります。
これらは生涯にわたる管理が必要となります。
膵炎の最新の治療アプローチの動向
●早期経腸栄養
前述の通り、嘔吐がコントロールでき次第、早期の栄養補給が推奨される傾向にあります。
●血漿交換
・一部の重症例
・背景に重度な高脂血症
などがある場合、血液中から過剰な脂質や炎症性物質を除去する治療法として、限られた施設で試みられています。
●新しい薬剤の研究
・炎症をより効果的に抑制する薬剤
・膵臓の線維化を抑制する薬剤
などの研究が進められています。
●「無症候性膵炎」の存在
明確な臨床症状を示さないものの
特に慢性膵炎で
・血液検査
・画像検査
で膵炎の所見が見られるケースもあります。
これが将来的に急性増悪したり、他の疾患に影響したりする可能性も考慮されます。
犬の膵炎は
・飼い主さん
・愛犬
・獣医師
がチームとなって向き合っていく必要のある病気です。
正しい知識を持ち、日々のケアを丁寧に行うことで、愛犬のQOLを維持し、穏やかな時間を長く過ごせるようにサポートしてあげましょう。

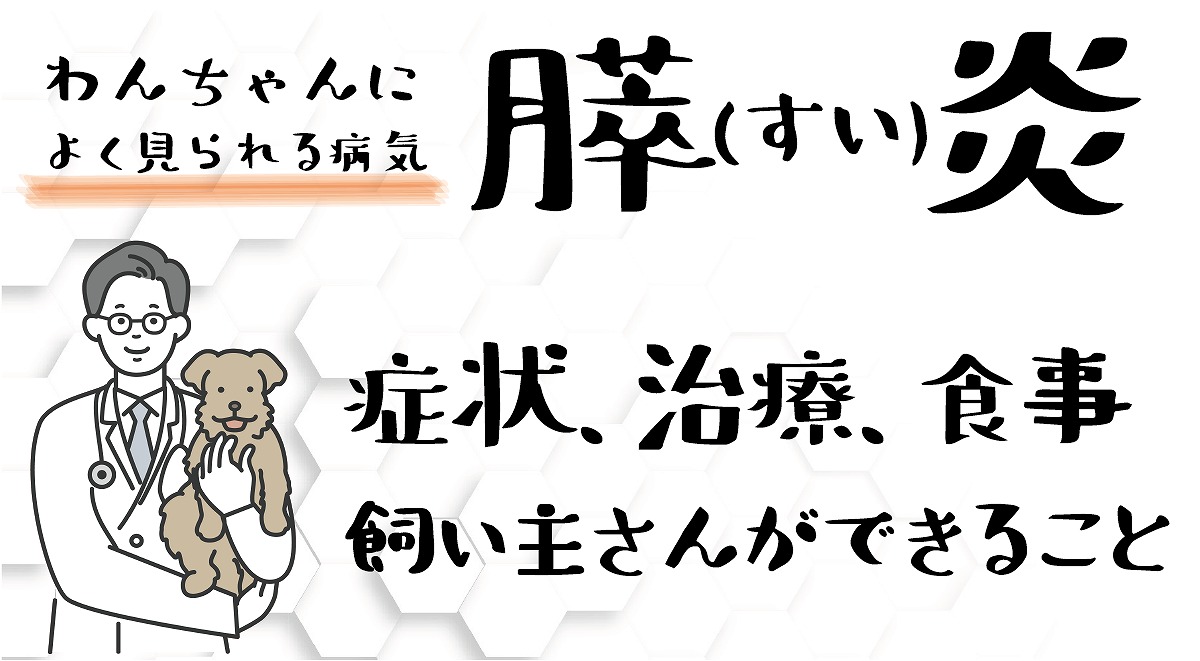


コメント