犬
特に小型犬
において最もよく見られる心臓病が
この僧帽弁閉鎖不全症です。
進行性の病気ではありますが
・早期発見
・適切な治療・ケア
によって、愛犬が穏やかに過ごせる期間を長くすることができます。
僧帽弁閉鎖不全症とはどんな病気?
心臓には
・4つの部屋と
・4つの弁
があります。
僧帽弁は、心臓の左側にある
左心房と左心室の間にある弁
ポンプの役割をする左心室が
▶収縮する際に
▶血液が左心房に逆流しないように
▶フタをする役割
を担っています。
僧帽弁閉鎖不全症は
この僧帽弁が加齢などにより
・厚くなったり
・変形したり
して
左心室が収縮したときに
弁が完全に閉じきらなくなる
病気です。
これにより
▶本来全身に送り出されるべき血液の一部が
▶左心房に逆流してしまいます。
この病気の原因の多くは
「粘液腫様変性」
と呼ばれる弁の組織の変化です。
弁がゼラチン状になり
▶ゴムのように伸びてしまうことで
▶ぴったり閉じることができなくなります
特定の犬種
・キャバリア
・キング・チャールズ・スパニエル
・チワワ
・ミニチュア・ダックスフンド
・マルチーズ
・シーズー
・ポメラニアン
・ヨークシャー・テリアなど
に非常に多く見られ、
遺伝的な要因が大きい
病気だと考えられています。
なぜこれらの犬種に好発するのか?
詳しいメカニズムはまだ研究段階。
ですが、弁を構成する
コラーゲンなどの結合組織に異常
がある可能性が指摘されています。
僧帽弁閉鎖不全症の症状
症状は病気の
進行段階(ステージ)
によって大きく異なります。
国際的な分類(ACVIM分類)では
・B1(心雑音はあるが無症状)
・B2(心拡大があるが無症状)
・C(心不全の症状がある)
・D(難治性の心不全)
に分けられます。
●ステージA, B1, B2(無症状期)
この段階では、見た目にはまったく症状がありません。
しかし、動物病院での聴診で
「心雑音」
が聴取され発見されることがほとんど。
心雑音は、血液が
僧帽弁を逆流
する際に生じる異常な音です。
ステージB2になると
・X線検査
・心臓超音波検査で
心臓が大きくなっている
心拡大
が確認されます。
● ステージC(心不全期)
逆流が増え、心臓が
ポンプ機能を十分に果たせなくなる
と、様々な症状が現れます。
◇咳
特に
・興奮時や運動後
・夜間から朝方にかけて
出やすい
乾いたコンコンという咳
が特徴的。
逆流した血液によって
▶左心房が大きくなり
▶気管を圧迫する
ことが原因の一つと考えられています。
◇息切れ、呼吸が速い・苦しそう
・少しの運動で息切れ
・安静時でも呼吸が速くなる
・お腹を使って呼吸する(努力性呼吸)
などの様子が見られます。
これは肺に水が溜まる
「肺水腫」のサイン
かもしれません。
◇疲れやすい、散歩に行きたがらない
・以前より疲れやすくなったり
・散歩を嫌がるようになったり
します。
◇舌の色が悪い(チアノーゼ)
酸素が十分に体に運ばれず
舌や歯茎が青紫色
になることがあります。
これは非常に危険なサインです。
◇失神
・血圧の低下
・不整脈
により、一時的に意識を失うことがあります。
僧帽弁閉鎖不全症を予防するためには?
前述のように
遺伝的な要因が大きい
ため、病気の発生そのものを予防することは難しいのが現状。
しかし、以下の点に気を付けることで
・発症を遅らせたり
・進行を緩やかにしたり
できる可能性があります。
●早期発見
定期的な健康診断
(特に好発犬種は若いうちから)
を受け
心雑音がないか?
確認してもらいましょう。
・無症状のうちに発見し
・適切な段階から治療を開始すること
が病気の進行を遅らせる上で最も重要です。
●体重管理
肥満は心臓に余計な負担をかけます。
適正体重を維持することが大切です。
●歯周病のケア
・歯周病
・心臓病
には関連があると言われます。
歯周病の原因菌が
▶血流に乗って心臓に運ばれ
▶弁に炎症を起こす
可能性があると考えられています。
日頃からのデンタルケアが
▶心臓病予防にも繋がる
可能性があります。
●ストレスを減らす
過度なストレスは心臓に負担をかけます。
犬にとって
・安心できる環境を整え
・ストレスを軽減する
工夫をしましょう。
僧帽弁閉鎖不全症の治療や処方される薬の例
治療は
・病気のステージ
・個体の状態
によって異なります。
目標は
・症状の緩和
・心臓の負担軽減
・病気の進行抑制
・生活の質の維持
です。
●ステージB1(心雑音のみ)
症状がない場合は
定期的な検査
・半年に一度〜年に一度の聴診
・X線検査
・必要に応じて心臓超音波検査
を行い、病気の進行を観察します。
この段階ではまだ
薬物療法を開始しない
ことが多いですが
・食事療法
・サプリメント
について相談することもあります。
●ステージB2(心拡大がある無症状期)
心臓の拡大が見られるようになったら
▶病気の進行を遅らせるために
薬物療法
を開始することが推奨されています。
◇ピモベンダン
・強心作用
・血管拡張作用
を併せ持つ薬
・心臓の収縮力を高め
・血管を広げて
心臓の負担を軽減します。
無症状の段階から使用
することで
心不全の発症を遅らせる効果
が科学的に証明されています。
◇ACE阻害薬
血管を収縮させるホルモンの
▶働きを抑え
▶血管を広げて
心臓の負担を軽減します。
腎臓を保護する効果も期待できます。
●ステージC(心不全期)
心不全の症状が現れたら、症状を緩和するための薬が追加されます。
◇利尿薬(フロセミドなど)
体内の余分な水分を排出し
▶肺水腫を軽減します。
心臓の負担も減らします。
◇ACE阻害薬
引き続き使用します。
◇ピモベンダン
引き続き使用します。
◇その他
不整脈がある場合は
・抗不整脈薬
・血栓予防薬
などが使用されることもあります。
●ステージD(難治性心不全)
標準的な治療に反応しにくくなった段階で
・利尿薬の増量や種類の変更
・他の薬の併用など
より強力な治療が行われます。
薬の副作用や食事との兼ね合い
●ピモベンダン
副作用は比較的少ないとされています
まれに
・食欲不振
・嘔吐
・下痢
などが見られることがあります。
食事との兼ね合いとしては
・空腹時に投与することで
▶吸収が良くなる
と言われていますが
・消化器症状が出やすい場合は
▶食事と一緒に与える
ことが推奨されます。
●ACE阻害薬
まれに
・食欲不振
・嘔吐、下痢
・元気消失
が見られることがあります。
また
・腎臓病を併発している場合
・脱水している場合
は腎臓の数値が悪化することも。
定期的な血液検査で
腎機能を確認
する必要があります。
●利尿薬(フロセミドなど)
体内の水分とともに
ミネラル(特にカリウム)も排出
してしまうため
・脱水
・電解質バランスの異常
を引き起こす可能性があります。
飲水量や尿量が増えます。
長期使用する場合は
腎臓への負担
も考慮し、定期的な血液検査が必要です。
カリウムが不足した場合は、カリウム製剤を併用することもあります。
重要な注意点
ここで挙げたのは一般的な例であり、
必ず獣医師の指示に従って
薬を与えてください。
薬の量や組み合わせは
・個体の状態
・病気のステージ
・他の病気の有無
によって細かく調整されます。
自己判断での増減薬
は絶対にしないでください。
ヒッポのごはんの僧帽弁閉鎖不全症食
僧帽弁閉鎖不全症食は進行性ですが
適切な栄養管理は
愛犬のQOL(生活の質)を大きく左右します。
ヒッポのごはんでは
愛犬一頭一頭の状態
に合わせた心臓にやさしい
オーダーメイドごはん
を提供しています。
ヒッポのごはんが大切にする3つの柱
ヒッポのごはんでは心臓病食を
単なる栄養制限食
とは捉えていません。
・愛犬が美味しく食事を楽しみ
・いきいきと過ごせる時間を長くする
そのために、以下の3つの柱を基本にレシピを設計しています。
①適正体重の維持
肥満は心臓に大きな負担をかけます。
愛犬の
・年齢
・運動量
に合わせた適切なカロリー設計で
・無理なく
・健康的な
体重を保ちます。
②適切な栄養補給
病気による体重減少
悪液質=カヘキシア
を防ぐため
・嗜好性を重視した良質な食材を選び
・十分なエネルギーと栄養を確保します。
③併発しやすい疾患への配慮
心臓病は
腎臓病を併発しやすい
という特徴があります。
・愛犬の状態を常に把握し
必要に応じて
・タンパク質
・リンの量
を慎重に調整します。
初期からの過度な制限は、かえって
QOLを著しく低下させる
可能性があるため、避けています。
心臓を力強くサポートする特別な栄養素
・心臓の機能を支え
・病気の進行を穏やかにする
ヒッポのごはんでは以下の栄養素を積極的に取り入れています。
●心筋を元気にするアミノ酸
心筋の機能維持に不可欠な
・タウリン
・L-カルニチン
を豊富に含む
・鹿肉
・猪肉
などの赤身肉を積極的に使用しています。
心臓病の進行に伴って、これらの栄養素は不足しがちになることが分かっています。
◇タウリン
心筋の機能維持に不可欠なアミノ酸。
犬は
体内でタウリンを合成できます
が、それでも
心臓病の犬では不足しがち
なため食事からの補給が推奨されます。
◇L-カルニチン
脂肪酸を心筋に取り込み
▶エネルギーとして利用する
ために必要なアミノ酸誘導体です。
心筋のエネルギー産生を助けます。
●筋肉と骨を支えるビタミンD
・筋肉の萎縮を防ぎ
体内の
・カルシウムとリンのバランスを整える
という重要な働きをします。
・トラウトサーモン
・白身魚
・舞茸
※注:白鮭はビタミンDが過剰になる可能性
などを活用し、心臓病と併発しやすい
腎臓の健康
にも配慮します。
●悪液質(カヘキシア)対策
病気の進行によって
筋肉が減ってしまう
悪液質
を防ぐため
・良質なタンパク質
中でも特に
・BCAA(分岐鎖アミノ酸)
を意識的に含めます。
また、筋肉の材料となる
たんぱく質の合成に重要な
ビタミンB6
を含むビタミンB群も積極的に補給し、体重減少を食い止めます。
※ビタミンB群はバランスよく摂取するのが◎
●抗酸化物質で心臓を守る
ビタミンC・E・セレンだけではなく
・レスベラトロール
・アントシアニン
といったポリフェノールは
心筋細胞を
酸化ストレスから守ります。
新鮮な野菜など、様々な食材に加え
ブルーベリー茎
からこれらの成分を補給します。
●腸から心臓をサポート
心臓病では、腸内環境も密接に関わります。
食事中の特定の成分
・L-カルニチン
・コリンなど
が腸内細菌によって代謝され、肝臓で
TMAO(トリメチルアミン-N-オキシド)
という物質が作られることがあります。
研究では
▶TMAOの血中濃度が高いと
▶心血管疾患のリスクが増加する
可能性が示唆されています。
しかしTMAOの生成に関わるとされる
・L-カルニチン
・コリン
といった栄養素は
・心臓のエネルギー源
・血管の健康
に不可欠な栄養素です。
これらの重要な栄養素を単に避けるのはかえって心臓の健康に悪影響。
そのためヒッポのごはんでは、以下の方法でTMAO対策を行います。
◇鍵は「腸内環境のバランス」
TMAOが過剰に作られるかどうかは
・どんな種類の腸内細菌が
・どれだけいるか
に大きく左右されます。
なので
TMAOを生成しにくい腸内環境
にすることで
・心臓に必要なものはしっかり補給し
・不要なものをため込まない体づくり
をめざします。
そのためまずは
・プロバイオティクス(乳酸菌など)
・プレバイオティクス(オリゴ糖など)
の補給により
腸内フローラ
を健康な状態に保ちます。
特に
・もち麦
・キノコ類
に多く含まれる
βグルカン
は腸内の善玉菌のエサとなり
・腸内環境を整え
・TMAOの生成を抑制
する効果が期待できます。
また心臓病の原因の一つに
・血液の汚染
・免疫力の低下
が関与していると考えられています。
腸内環境を整えることは
マクロファージ
※不要物を食べて血管のつまりを防いでくれる細胞
の活性化を促し健康をサポートします。
●血管・血液循環のサポート
心臓病では
心臓だけでなく
血管の健康
も重要です。
◇卵黄コリン
・血中コレステロールを下げ
・血圧を正常に保つ
▶動脈硬化の予防
◇アルギニン
血管を広げる
一酸化窒素(NO)
の産生を促す作用があります。
これにより
・血管がしなやかになり
・血圧のコントロール
を助けます。
メインの肉に
・鶏むね
・豚ヒレなど
◇抗酸化成分
・スルフォラファン(Bスプラウト)
・グルタチオン(きのこ類)
が血管を酸化ストレスから守ります。
心臓に負担をかけないための厳選した食材と配慮
愛犬の心臓に
・負担をかけず
・安心して食べられる
ごはんであるために
以下の点に徹底的にこだわっています。
●ナトリウム(塩分)の調整
ナトリウムは
▶体内の水分量を増やし
▶心臓に負担をかけるため
厳格な制限が必要です。
しかし、進行時でも
極端な制限をすると
身体が
かえって塩分を溜め込もうとする
ため、正確には厳格な調整が必要です。
※乾物換算で0.3%程度で調整
●リンの排泄を助ける亜鉛
リンの過剰摂取
は腎臓に負担をかけます。
リンの排泄に重要な
クロトーたんぱく質
の減少を防ぐために、亜鉛を適切に補給します。
◇無機リンに注意
市販のフードに多く含まれる
無機リン
※表示名はph調整剤、乳化剤など
は腎臓に大きな負担をかける可能性。
市販フードを与えるときは必ず原材料名を確認しましょう。
●カリウムとマグネシウムのバランス
これらは
・心臓の収縮
・不整脈の予防
に重要なミネラルです。
特に
利尿薬の副作用
では血中カリウム濃度が不安定になりやすく
・低カリウム血症
・高カリウム血症
どちらにも傾く可能性があります。
・不整脈
・筋力低下
・治療薬の副作用リスク増
などを防ぐため、愛犬の状態に合わせて適切な量を調整します。
また
マグネシウムは
・心筋の収縮
・神経伝達
に関与し、不整脈予防に役立ちます。
・血管が硬くなるのを防ぎ
・腎臓を守る働き
も期待できます。
ヒッポのごはんが目指すのは
愛犬の
「美味しい喜び」
「健康」
を両立させることです。
専門的な知見をもとに、愛犬に寄り添うごはんで、穏やかな毎日をサポート。
愛犬の食事についてご不安なことがあれば、いつでもご相談ください。
僧帽弁閉鎖不全症の治療費の例
僧帽弁閉鎖不全症の治療は
・病気の進行度や必要な検査
・治療内容
によって大きく異なります。
一般的に、進行するにつれて費用は増加します。
●初期(心雑音のみ、無症状)
◇初診料・再診料
数千円
◇聴診
診察料に含まれることが多い
◇X線検査
数千円~1万円
◇心臓超音波検査
※初期診断や進行評価に重要
1万円~2万円以上
◇血液検査
数千円~1万円
・心臓の数値
・腎機能
・電解質
などを確認
◇薬代
※ステージB2以降で薬物療法が開始される場合
数千円~数万円/月
●中期~後期(症状がある、心不全期)
上記の定期検査費用に加え、薬の種類や量が増えるため薬代が増加します。
◇入院費用
※肺水腫などで入院が必要な場合
数万円~十数万円
◇酸素吸入費用
入院費用に含まれることが多いですが、別途請求される場合もあります。
◇集中治療が必要な場合
さらに高額になります。
注意点
この病気は
生涯にわたる管理
が必要となるため
・検査費用
・薬代
が継続的に発生します。
特にステージが進むにつれて
▶薬の種類が増え
▶費用も増加する傾向
があります。
ペット保険に加入している場合は、補償内容を確認し、保険を最大限に活用しましょう。
その他気を付けてあげること、してあげられること
●日々の観察
自宅でできるケアとして
愛犬の様子を注意深く観察
することが非常に重要です。
◇咳の回数と質
いつ、どのような時に
咳が出やすいか?
記録しておくと、獣医師に状態を伝えるのに役立ちます。
◇呼吸状態
・安静時の呼吸数
(1分間に何回呼吸しているか)
・呼吸の仕方
(お腹を使っていないか、口を開けていないか)
を確認しましょう。
正常な安静時呼吸数は一般的に
1分間に15〜30回程度
ですが、個体差があります。
普段の呼吸数を把握しておくことが大切です。
◇散歩中の様子
・疲れやすくなっていないか
・途中で座り込んだり立ち止まったりしないか
◇舌の色
青紫色になっていないか(チアノーゼ)
◇食欲、元気
・いつも通り食べられているか
・活動性はどうか
●運動制限
病気のステージに合わせて、適切な運動制限が必要です。
獣医師と相談し
どの程度の
・運動量
・運動強度
が良いか指示を受けましょう。
一般的に
・激しい運動や長時間の運動は避け
・短い散歩を複数回行う
などが推奨されます。
●ストレスを減らす
心臓に負担をかけるため
・大きな音
・知らない人、犬との遭遇
など
愛犬が苦手な状況を避けましょう。
●気温・湿度の管理
・暑すぎたり寒すぎたり
・湿度が高すぎたり
する環境は心臓に負担をかけます。
エアコンなどを適切に使用し
▶快適な温度・湿度を保ちましょう。
特に夏場の散歩は
▶涼しい時間帯を選び
無理をさせない
ように注意が必要です。
●体重管理
適正体重を維持することは、心臓への負担を減らすために非常に重要です。
●自宅でのケア
◇心拍数・呼吸数のカウント
落ち着いているときに
・1分間の心拍数
(胸に手を当ててドクドクを感じる)
・呼吸数
(胸やお腹の動き)
をカウントする練習をしておくと、異常を早期に発見できることがあります。
◇家庭用酸素濃縮器
重度の呼吸困難
が頻繁に見られる場合など
獣医師の指導のもと
家庭用酸素濃縮器
のレンタルや購入を検討することも。
しかし、これは
あくまで応急処置
であり、速やかに動物病院を受診する必要があります。
◇獣医師との密な連携
僧帽弁閉鎖不全症は
進行性の病気
であり
・定期的な検査
・獣医師との相談
が不可欠です。
些細な変化でも躊躇せず相談し、病状に合わせて治療計画を調整してもらいましょう。
●夜間の咳は
心不全のサインとして重要です。
横になると
▶肺の血流が増え
▶肺水腫が悪化しやすくなる
ためです。
もし夜間に
・咳が増えたり
・苦しそうにしている
場合は
心不全が進行している可能性が高い
と考え、早めに獣医師に相談してください。
また、病状が進行すると
●病気による痩せ(悪液質)
が見られることがあります。
食欲があっても痩せてくる場合
は単に食事量が足りないだけでなく
病気によるエネルギー代謝の変化
が関与している可能性があります。
このような場合は
・食事内容
・栄養補助
について獣医師と相談することが重要です。
まとめ
犬の僧帽弁閉鎖不全症は、多くの小型犬が罹患する可能性のある心臓病です。
しかし
・早期に発見し
・適切な時期から薬物・食事療法を開始し
・日々の丁寧なケアを行う
ことで、病気の進行を遅らせ
・愛犬が穏やかに
そして
・質の高い生活を送れる時間を長くする
ことができます。
病気と診断されても悲観的にならず、かかりつけの獣医師と密に連携を取りながら、愛犬にとって最善のケアを続けていきましょう。

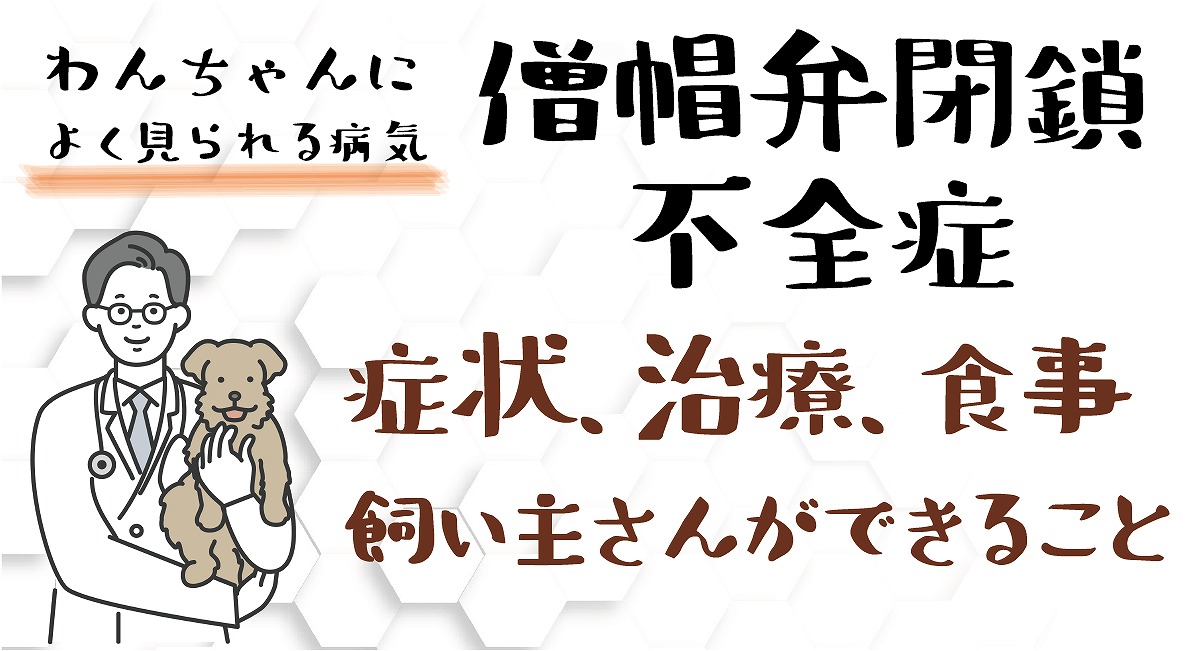


コメント