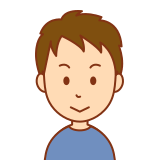
うちの子なんか元気ないし、散歩も行きたがらなくなった…
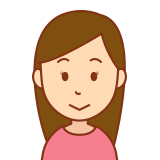
急にごっそり毛が抜けたけど…大丈夫?
愛犬の
・元気がなくなったり
・太りやすくなったり
・皮膚トラブルが増えたり
していませんか?
もしかしたら、それは
甲状腺機能低下症
のサインかもしれません。
この病気は
中高齢の犬
に多く見られますが
・早期発見
・適切な治療
でコントロールが可能です。
ここでは、甲状腺機能低下症について
・その原因
・最新のケア方法
・飼い主さんが知っておくべき豆知識
まで、詳しく解説します。
甲状腺機能低下症ってどんな病気?
甲状腺は
首の気管の左右にある
小さな臓器。
体の新陳代謝を活発にする
甲状腺ホルモン
を分泌しています。
甲状腺機能低下症は、この
▶甲状腺ホルモンの分泌量が
▶何らかの原因で不足してしまう
病気です。
甲状腺ホルモンは
元気のホルモン
とも呼ばれ
全身の細胞の活動を調節する
重要な役割を担っています。
そのため
▶このホルモンが不足すると
▶体のさまざまな機能が低下し
▶多岐にわたる症状が現れます。
実は甲状腺機能低下症の
約95%は
原発性甲状腺機能低下症
で、その多くが
・リンパ球性甲状腺炎
=自己免疫疾患
または原因不明の
・特発性甲状腺萎縮
によって引き起こされます。
つまり
・免疫システムが自分の甲状腺を攻撃
・甲状腺自体が萎縮してしまう
ことが主な原因なのです。
まれに
・二次性甲状腺機能低下症
=脳下垂体の異常
・ヨウ素欠乏
などが原因となることもあります。
好発犬種
・ゴールデン・レトリーバー
・ドーベルマン
・ダックスフンド
・コッカー・スパニエル
・柴犬 などは
甲状腺機能低下症を発症しやすい犬種として知られています。
もちろん他の犬種でも発症する可能性はあります。
見逃さないで!甲状腺機能低下症のサイン(症状)
甲状腺機能低下症の症状は
ゆっくりと進行する
ことが多く
初期には気づきにくい
ことがあります。

年のせいかな?
と見過ごされがちな症状も含まれるため、注意深く観察することが大切です。
主な症状は以下の通りです。
●活動性の低下
・元気がない
・疲れやすい
・寝てばかりいるなど
最も一般的な初期症状の一つです。
・以前より散歩を嫌がるようになった
・遊ぶ時間が減った
などでは注意が必要です。
●体重増加(肥満傾向)
・食事量は変わらない
あるいは
・減っているのに
太りやすくなります。
これは代謝の低下によるものです。
●皮膚のトラブル
◇脱毛
特に
・体の側面
・首
・尻尾などに
対称性の脱毛
が見られることがあります。
※ラットテイルと呼ばれる尻尾の脱毛は特徴的
・毛が薄くなった
・生えにくくなった
などの症状が見られます。
◇新陳代謝異常
皮膚のターンオーバーが乱れるため
・乾燥肌
・フケが多い
・脂っぽい皮膚(脂漏症)
などの症状が見られます。
◇皮膚の色素沈着
皮膚が黒ずんでくることがあります。
◇皮膚感染症の再発
免疫力の低下により
・細菌
・真菌
による皮膚炎を繰り返すことも。
◇傷が治りにくい
●寒がりになる
代謝が低下し
▶体温を維持しにくくなるため
▶暖かい場所を好むようになります。
●悲しそうな顔つき
=悲劇的顔貌
顔の皮膚が
・むくんで
・厚ぼったくなり
▶まぶたが垂れ下がることで
▶悲しそうな表情に見える
ことがあります。
これは
粘液水腫性昏睡
という重篤な状態の前兆であることも。
●心拍数の低下(徐脈)、不整脈
● 便秘
●高コレステロール血症
高中性脂肪血症も
(血液検査で判明します)
●まれに神経症状
・ふらつき
・顔面神経麻痺
・喉頭麻痺
=声がかすれる、呼吸が苦しそう
などが見られることもあります。
●行動の変化
・攻撃的になる
逆に
・臆病になる
などの行動変化が見られることも。
これは
・脳の機能低下
・不快感
からくると考えられています。
甲状腺ホルモンは
神経系の
・発達
・機能維持
にも関与しているため
・行動の変化
・学習能力の低下
が見られることもあります。
また
・繁殖能力の低下
・メスでは無発情や不妊
・オスでは精巣萎縮や性欲減退
を引き起こすこともあります。
甲状腺機能低下症は予防できる?
残念ながら
甲状腺機能低下症の主な原因である
・リンパ球性甲状腺炎
・特発性甲状腺萎縮
は現在のところ
明確な予防法
が確立されていません。
遺伝的要因も関与すると考えられており、好発犬種では特に注意が必要です。
しかしそれでも
・早期発見
・早期治療
が何よりも重要です。
定期的な健康診断(特に中高齢期以降)を受け
血液検査で
▶甲状腺ホルモンの数値をチェックする
ことが症状の重篤化を防ぐ鍵となります。
健康診断の際には、獣医師に
・愛犬の活動量
・皮膚の状態
・体重の変化
などを具体的に伝えることで、より早期の発見につながる可能性があります。
【最新研究情報】遺伝子検査でリスク予測の時代へ?
近年、特定の犬種における
甲状腺機能低下症の発症リスク
に関わる
遺伝子の研究
が進められています。
残念ながら、現時点では一般的な診断には至っていません。
しかし将来的には
・子犬の段階で遺伝的リスクを把握
・より早期からの予防的ケア
へと繋がる可能性も期待されています。
愛犬のルーツに関心がある方は、獣医師に相談してみるのも良いでしょう。
●遺伝子検査によるリスク予測
甲状腺機能低下症の主な原因である
自己免疫疾患
は、その発症を完全には防げません。
しかし近年
▶遺伝子研究が進み
▶親犬の遺伝子検査によって
▶その子が病気を発症するリスクを事前に知る可能性が広がっています。
甲状腺機能低下症に関する
遺伝子検査
はまだ広く普及してはいません。
しかし
優良なブリーダーの間では
血液中の
抗サイログロブリン抗体(TgAA)
などの検査を繁殖前に行い
自己免疫性甲状腺炎の
遺伝的素因の有無
を確認する取り組みも増えつつあります。
甲状腺機能低下症の治療法と処方薬
甲状腺機能低下症の治療は
▶不足している甲状腺ホルモンを
▶合成薬で補う
ホルモン補充療法
が基本です。
処方される薬の例
●レボチロキシンナトリウム
(L-チロキシン)
甲状腺ホルモン製剤で、最も一般的に使用されます。
商品名としては
・チラージンS
・ソルラクトン
・サイロキシン
などがあります
◇投与方法
通常
・日1~2回
・経口投与
します。
投与量は
・犬の体重
・症状
・血液中の甲状腺ホルモン濃度
をモニタリングしながら
獣医師が慎重に
・決定
・調整
します。
治療を開始すると
数週間~数ヶ月
で症状の改善が見られることが多いです。
しかし
生涯にわたる投薬が必要
となるケースがほとんどです。
飼い主さんの根気強いケアが求められます。
◇副作用
適切に投与量が調整されていれば、副作用は稀です。
しかし
過剰投与になると
▶甲状腺機能亢進症のような症状
・多飲多尿
・食欲亢進
・体重減少
・興奮しやすい
・頻脈など
が現れることがあります。
またごくまれに
・アレルギー反応
=皮膚のかゆみなど
が出ることもあります。
何か異常が見られたら、すぐに獣医師に相談しましょう。
投薬時の注意点
●投与タイミング
レボチロキシンナトリウムは、
食事の影響で吸収率が変わる
ことがあります。
一般的には
空腹時
・食事の1時間以上前
・または食後2~3時間後
に投与することが推奨されます。
ただし、獣医師の指示に従ってください。
●吸収を妨げる可能性のあるもの
・カルシウム製剤
・鉄剤
・制酸剤
(アルミニウムやマグネシウムを含むもの)
などは、レボチロキシンの吸収を妨げることがあります。
これらの
・サプリメント
・薬
を併用する場合
投与時間をずらすなどの工夫が必要。
獣医師に必ず相談しましょう。
また
・大豆製品(特にイソフラボン)
・食物繊維
が多い食事も
・薬の吸収を遅らせる
・薬の吸収を妨げる
可能性が指摘されています。
しかし通常のドッグフードに含まれる程度であれば問題ないとする意見もあります。
大量に与える場合は注意が必要です。
●薬の飲み忘れを防ぐ工夫
・ピルケースを活用
・カレンダーに印をつける
などの工夫をしましょう。
また
投薬の時間を毎日同じにする
ことで血中濃度が安定しやすくなります。
診断技術の進歩
甲状腺機能低下症の診断には
血液中の甲状腺ホルモン
(T4、TSHなど)
の測定が不可欠です。
近年では
より精度の高い
・遊離型T4(FT4)の測定
自己免疫疾患の有無を示す
・自己抗体の検査
が一般的に行われています。
これにより
▶症状が軽微な段階で病気を特定しやすい
▶適切な治療を早期に開始する
ことが可能になっています。
ヒッポのごはんでの甲状腺機能低下症の犬の食事方針
「ヒッポのごはん」は
・愛犬の健康を第一に考えた
・専門家監修の手作りごはん
として、甲状腺機能低下症を抱える愛犬にも最適な食事を提供します。
・体重コントロール
・甲状腺の健康維持
を両立させながら、栄養バランスの取れたおいしいごはんを目指します。
ヒッポのごはんの甲状腺機能低下症での基本方針
甲状腺機能低下症の愛犬の食事管理において、ヒッポのごはんでは以下の基本方針に基づき、総合的な栄養ケアを提供します。
●体重コントロールの重視
代謝が低下し
▶太りやすい体質になるため
・低脂肪
・高繊維質
な食材を積極的に使用し。
適切な体重維持をサポートします。
過剰なカロリー摂取を避け
▶肥満による他の健康リスク
・関節疾患
・心臓病など
の予防にも配慮します。
●甲状腺機能のサポート
甲状腺ホルモンの生成に必要な
・ヨウ素
を適切な量で含ませます。
・過剰摂取
・不足
を避けるため
綿密な計算の元、自然の食材で摂取できるように調整しています。
●総合的な健康維持
全身の細胞活動を支える
抗酸化物質
を強化。
・免疫力
・細胞の健康
を維持することで
・皮膚トラブル
・感染症のリスク軽減
にも貢献します。
強化する栄養・食材
●ヨウ素
ヨウ素は甲状腺ホルモンの主成分です。
・昆布
・カツオ
・いわし
などで和出汁を引き、調理することで
適切な量を食事から摂取
できるよう配慮しています。
●チロシン
アミノ酸の一種で甲状腺ホルモンの材料。
良質な
・肉類
・魚介類
・ヤギホエイ
などをバランス良く取り入れ、必要なチロシンを供給します。
●ビタミン・ミネラル
・甲状腺ホルモンの生成&代謝
・抗酸化作用
に関わる
・セレン
・亜鉛
・鉄
・銅
・ビタミンB群(特にB2、B3、B6)
・ビタミンE
・ビタミンC
などを十分に含ませます。
バランスの取れた食材の組み合わせにより、これらの栄養素が不足しないように調整します。
●L-カルニチン
・脂肪の代謝を助け
・体重管理に役立つ
可能性のあるL-カルニチン
・鹿肉
・猪肉
・羊肉
などから自然と摂取できるよう、調整しています。
控える栄養・食材
●過剰な脂肪・カロリー
▶肥満を助長し
▶高脂血症を悪化させる
可能性があるため
・過剰な脂肪分
・過剰なカロリー
は厳しく制限し、体重管理を徹底します。
●ゴイトロゲン
甲状腺ホルモンの
生成を妨げる可能性
のあるゴイトロゲンを含む食材は
▶加熱処理をして
▶過剰摂取に注意します。
一般的には
よほど食べ過ぎない限り大丈夫
と言われますが
ゴイトロゲンが多いアブラナ科の野菜は
必要最低限
にとどめています
●大豆製品
イソフラボンが甲状腺ホルモンの働きを阻害する可能性。
使用量に配慮します。
●グルテン
一部の犬では
▶グルテンが
▶自己免疫疾患を悪化させる
可能性が指摘されることもあります。
しかし
甲状腺機能低下症の犬に
グルテンフリーフードが必須
であるという明確な科学的根拠は現時点では乏しいとされています。
ですが元々ヒッポのごはんは
基本的にグルテンフリー
です。
甲状腺機能低下症の治療費の例
甲状腺機能低下症の治療費は
・検査内容
・処方される薬の種類や量
・通院頻度
・動物病院
によって異なります。
一般的な目安としては以下の通りです。
◇初期診断費用
1万円~3万円程度
・血液検査
・ホルモン検査など.
◇定期的な血液検査
5千円~1万5千円程度
=数ヶ月に1回程度
・モニタリング
◇薬代
=レボチロキシンなど
体重や投与量によりますが
・小型犬で月額数千円~
・大型犬で月額1万円前後~
が目安です。
生涯にわたるため
長期的な費用
を見込む必要があります。
ペット保険に加入している場合
補償内容によって
・治療費の一部
または
・全額
がカバーされることがあります。
加入している保険の契約内容を確認しましょう。
甲状腺機能低下症になったときにしてあげられること
甲状腺機能低下症と診断された愛犬のために、飼い主さんができることはたくさんあります。
●定期的な通院と投薬の徹底
獣医師の指示通りに
・薬を確実に投与し
・定期的な血液検査を受けて
ホルモンレベルを適切にコントロールすることが最も重要です。
◇治療中のモニタリング
血液検査は
治療の羅針盤
甲状腺ホルモン補充療法を開始した後も
定期的な血液検査
が非常に重要です。
治療開始から
・数週間後
そしてその後も
・数ヶ月に一度
(または獣医師の指示に従って)
血液中の甲状腺ホルモン濃度を測定し
▶適切な薬の投与量を維持できているか
を確認します。
これにより
・薬の効きすぎ
・薬が足りない
という状態を防ぎ
▶愛犬が快適な状態を保てるよう調整していきます。
自己判断で
・薬の量を変更
・薬を中断
は絶対しないでください。
獣医師と二人三脚で治療を進めましょう。
●体重管理
代謝が低下
するため太りやすくなります。
・適切な食事管理
・適度な運動
で理想体重を維持しましょう。
肥満は
・関節疾患
・心臓病
など他の病気のリスクも高めます。
●寒さ対策
甲状腺機能低下症の犬は
寒さに弱くなる
傾向があります。
なので特に
冬場
は注意が必要です。
▶体温が低下しやすく
▶症状が悪化する
こともあります。
・暖かい寝床を用意する
・洋服を着せる
などの配慮をしましょう。
夏場でも
クーラーが効きすぎた部屋では震えることがあるため、室温管理には年間を通して配慮してあげましょう。
●皮膚・被毛のケア
・定期的なブラッシング
獣医師に相談の上で
・適切なシャンプーを使用
などして皮膚を清潔に保ちましょう。
・脱毛
・フケ
などの変化に注意し、異常があれば早めに受診してください。
●適度な運動
元気がないから
と運動させないのではなく
・犬の状態に合わせて
・無理のない範囲で
・散歩や遊びなど
適度な運動を取り入れ
・筋力の維持
・気分のリフレッシュ
を促しましょう。
●ストレスの軽減
・穏やかで
・安心できる
生活環境を整え
過度なストレス
を与えないように心がけましょう。
●記録をつける
□体重
□食事内容
□投薬状況
□活動量
□皮膚の状態
□気になった症状
などを記録しておくと
獣医師とのコミュニケーション
がスムーズになり、治療方針の決定にも役立ちます。
●愛情深いコミュニケーション
病気と向き合う愛犬にとって
飼い主さんの
・愛情
・サポート
は何よりの力になります。
▶優しく声をかけ
▶スキンシップを大切にしましょう。
●認知機能への配慮
高齢で甲状腺機能低下症を発症すると
・認知機能の低下と
・甲状腺機能低下症の症状
がオーバーラップすることがあります。
甲状腺ホルモンの補充で
認知機能が改善
することもありますが
▶改善が見られない場合は
▶認知機能低下症のサポート
・生活環境の整備
・サプリメント
・脳トレなど
も並行して行うと
QOLの維持
に繋がります。
●合併症への注意
甲状腺機能低下症は
・高脂血症やそれに伴う膵炎
・ドライアイ(乾性角結膜炎)
・前庭疾患=めまいやふらつき
などを合併することがあります。
これらの兆候にも注意を払い
・早期発見
・早期治療
を心がけましょう。
●サプリメントの賢い活用
・甲状腺の健康維持
・皮膚・被毛のサポート
・関節ケア
などのためにサプリメントを検討する場合は、必ず獣医師に相談しましょう。
・薬との相互作用
・過剰摂取のリスク
があります。
例えば
オメガ3脂肪酸
皮膚の炎症を抑える効果に期待も
・品質
・量
には注意が必要です。
●飼い主さんのメンタルケアも大切
愛犬の病気は飼い主さんにとっても
大きなストレス
となります。
・正しい情報を得て
・獣医師とよく相談し
・一人で抱え込まずに
家族や友人と気持ちを分かち合うことも大切です。
似た症状にご注意!クッシング症候群との鑑別
愛犬が
・太りやすい
・皮膚トラブルが多い
といった症状は、実は
副腎皮質機能亢進症
=クッシング症候群
と共通する部分があります。
この病気も
・中高齢犬に多く
どちらの病気も
・発見が遅れると重篤化する
可能性があります。
正確な診断のためには、獣医師による詳しい検査が不可欠です。
複数の症状が見られる場合は
▶必ず獣医師に相談し
▶適切な鑑別診断を受けましょう。
【愛犬に合わせたオーダーメイド治療】個体差を理解しよう
甲状腺機能低下症の
・症状
・治療への反応
は愛犬それぞれの
・年齢
・犬種
・基礎疾患の有無
など個体によって大きく異なります。
例えば
・皮膚症状が顕著な子
もいれば
・元気なさそうなのだけが目立つ子
もいます。
獣医師は
▶愛犬の状態を総合的に判断し
・最適な薬の量
・食事内容
・ケアプラン
を提案してくれます。
気になることがあればどんな些細なことでも獣医師に伝え
▶愛犬に寄り添った
オーダーメイドの治療
を目指しましょう。
甲状腺機能低下症は
生涯にわたるケア
が必要な病気です。
しかし飼い主さんの
・愛情
・適切な管理
によって愛犬は
快適な生活を送る
ことができます。
・疑問
・不安なこと
があれば、遠慮なく獣医師に相談し、二人三脚で治療に取り組んでいきましょう。

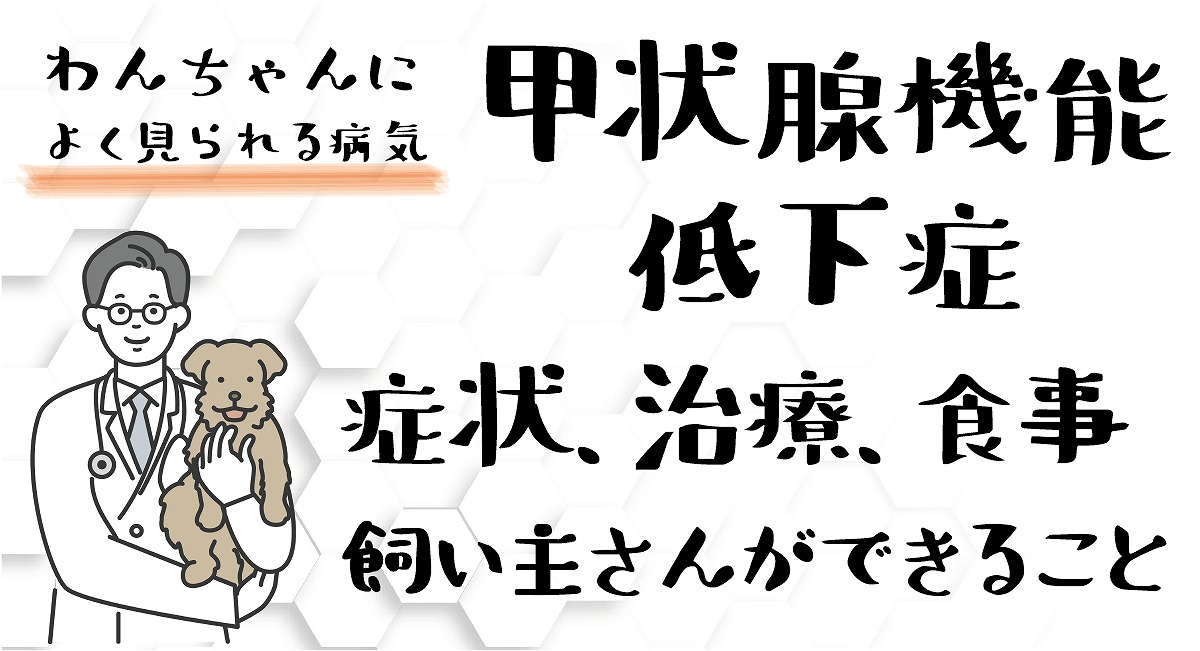


コメント