緑内障は、人間と同じく犬にとっても深刻な目の病気です。
手遅れになると
失明に至る可能性
もあるため
・早期発見
・適切なケア
が非常に重要となります。
犬の緑内障とは?
緑内障とは?目の病気であり、神経の病気でもある
緑内障は
視神経=目の神経が
▶徐々に傷つくことで
▶視野が狭くなる病気です。
一般的に、緑内障は
・目の病気
と認識されていますが、正確には目の病気であると同時に
・神経の病気
でもあります。
視神経は
・網膜が受け取った光の情報を
・脳に伝える
重要な役割を担っています。
この視神経が
・主に眼圧の上昇
・血流不足
・慢性的な炎症
などによってダメージを受けると
▶脳に情報が正しく伝わらなくなり
▶視野が欠けていきます。
一度傷ついた視神経は元に戻らないため
・早期発見
・適切な治療
が非常に重要です。
視神経を保護するために
ダメージの主な原因の一つである
眼圧をコントロールすること
が治療の中心となります。
眼圧が上がる主な原因
眼圧は、目の内部を循環している
房水
という液体の量によって決まります。
房水は
目の栄養を運ぶ
という役割を担っており、常に
・作られる量
・排出される量
のバランスが保たれることで
眼球の
・形
・圧力
が一定に保たれています。
眼圧上昇の主な原因は
このバランスが崩れ
房水の排出
がうまくいかなくなることです。
具体的には、以下のような状況が挙げられます。
●排出路(隅角)の目詰まり
房水の出口である
隅角(ぐうかく)
という部分にある
▶フィルターのような組織が目詰まり
▶房水が外へ流れ出にくくなります。
これが犬の緑内障の多くを占める
原発緑内障
の原因の一つです。
●排出路が物理的に塞がれる
・ぶどう膜炎
・白内障
・眼球内の腫瘍など
他の目の病気や外傷が原因で
隅角が物理的に
・狭くなる
・塞がれる
などすることで
▶房水の流れが妨げられます。
これは「続発緑内障」と呼ばれます。
●房水の過剰な産生
まれに
房水が過剰に作られる
ことで眼圧が上昇することもあります。
犬の緑内障の主な症状と「痛み」について
緑内障のサインは
・急性
・慢性
で異なります。
特に慢性期は
飼い主さんが気づきにくいサインが多い
ため、日頃の観察が非常に重要です。
急性緑内障のサイン
一般的に、緑内障は
痛みを感じることがほとんどない
ため、気づきにくい病気とされています。
ただし
急性緑内障発作
のように急激に眼圧が上昇するタイプでは、以下のような症状が出ることも。
●強い目の痛み
・頭を振ったり
・目をこすったり
・痛そうに鳴いたり
することがあります。
●目の充血
白目=結膜が真っ赤になります。
●瞳孔の異常
瞳孔=黒目が
・大きく開いたままになる
・光への反応が鈍くなる
●目の表面の濁り
眼圧の上昇で
▶角膜がむくみ
▶目の表面が白く濁って見えます。
●全身症状
強い痛みから
・食欲不振
・嘔吐
・元気がない
などの症状が現れます。
慢性緑内障の、見逃しやすいサイン
1.行動の変化
慢性的な眼圧上昇は、犬に常に
・軽い頭痛
・目の不快感
を与えます。
そのため、以下のような
行動の変化
が見られることがあります。
●元気がなくなる
・以前より遊びたがらない
・活動量が減る
●顔を触られるのを嫌がる
頭や目の周りを触ろうとすると
・怒ったり
・逃げたり
する。
これは
触られることで痛みが強くなる
可能性があるためです。
●食欲不振
目の不快感から
・ごはんを食べたがらない
・食が細くなる
●眠っている時間が増える
・痛み
・不快感
を和らげるために、じっとする時間が増えます。
2.目の外見の変化
急性の「目が白く濁る」といった
劇的な変化ではなく
以下のような
微妙な変化
が少しずつ現れます。
●瞳孔(黒目)の大きさの違い
片方の目の瞳孔が
もう一方の目の瞳孔より
▶少し大きいままになっている
ことがあります。
●目の充血が続く
白目(結膜)がわずかに赤く
▶それがなかなか治らない。
●目の潤み
・涙が少し増えたり
・目やにが出やすくなったり
●目のサイズの変化
ごくわずかですが
片方の目が
もう一方の目より
▶少し大きくなっていく
ことがあります。
3.視覚の変化
片目だけが
先に緑内障になることが多いため
▶もう片方の目が正常なうちは
▶視力の低下に気づきにくい
傾向があります。
●暗い場所での動きが鈍る
明るい場所では問題なくても
・夜間
・暗い部屋に入る
などすると
・家具にぶつかる
・動きがぎこちなくなる
などするがあれば
視野が徐々に狭くなっている
サインかもしれません。
●段差や階段を嫌がる
以前は平気で昇り降りしていた
・段差
・階段
の前で、ためらうような仕草を見せることがあります。
●呼びかけへの反応が遅れる
飼い主さんの声は聞こえているのに
▶視覚から得られる情報が少ないため
▶反応が遅くなることがあります。
これらのサインは
・単なる老化
・他の病気の症状
と間違えやすいものです。
もし愛犬にこのような変化が複数見られる場合は、特に注意が必要です。
緑内障の予防策
残念ながら、緑内障を完全に予防する方法はありません。
早期発見が最も重要です。
サインを見逃さないように
普段から愛犬を観察する習慣
を身につけておきましょう。
●定期的な健康診断
定期的に
眼圧測定
を含めた健康診断を受けることで
▶初期の異常を発見しやすくなります。
●遺伝的素因に注意
・柴犬
・シーズー
・コッカー・スパニエル
・ビーグル
・シベリアンハスキー
・シャー・ペイなど
遺伝的に緑内障になりやすい犬種
がいます。
これらの犬種では特に注意が必要です。
また人では
・1親等以内に緑内障の家族がいると
・そうでない人に比べて
発症リスクが約9倍高まる
というデータがあります。
また近年、犬の緑内障発症に関わる
遺伝子の特定
※緑内障感受性遺伝子「SRBD1」
も進んでいます。
これにより
遺伝子検査
によって
▶将来的なリスクを予測
できる可能性も出てきています。
●糖尿病と緑内障の関係
糖尿病は、高血糖状態が続くことで
全身の血管にダメージ
を与えます。
特に目のような
細い血管は影響を受けやすく
▶網膜症などの合併症を引き起こす
ことはよく知られています。
緑内障も例外ではなく
糖尿病の犬は、そうでない犬に比べて
緑内障になるリスクが高い
とされています。
これは糖尿病による血流障害が
▶視神経への血行不良を引き起こし
▶視神経にダメージを与えやすくなる
ためと考えられています。
●肥満防止と緑内障
肥満は
・糖尿病
・高血圧
・脂質異常症
などののリスクを高めます。
これらの病気は
▶全身の血流を悪化させ
結果として
▶視神経への血流不足につながる
可能性があります。
・肥満を防止し
・適正体重を維持すること
は間接的に緑内障のリスクを減らすことになります。
●血流改善と緑内障
視神経は、毛細血管から
・酸素
・栄養
を受け取っています。
血流が悪いと、視神経が
・酸素不足
・栄養不足
に陥り、ダメージを受けやすくなります。
そのため
血流を改善すること
は視神経を保護するために非常に重要。
また
ストレス
も血流悪化につながるので
・安心できて
・リラックスできる
環境を整えてあげることも大切です。
犬の眼圧を測る主な方法
人間のように
目に空気を当てる方法
は犬にとっては
・驚き
・ストレス
が大きいため、動物病院では主に
専用の眼圧計
を使います。
●リバウンド眼圧計
(TonoVetなど)
現在、多くの動物病院で主流になっている方法です。
細い計測器具を
▶角膜に軽く接触させ
▶その反発力を利用して眼圧を測定します。
◇特徴
①点眼麻酔はほとんど不要
・痛み
・不快感も
少ないため、多くの犬が
点眼麻酔なし
で測定できます。
②迅速でストレスが少ない
測定は数秒で完了するため
犬に与えるストレス
を最小限に抑えられます。
③手軽さ
ハンディタイプで持ち運びやすく、犬の様子を見ながら臨機応変に測定できます。
●アプラネーション眼圧計
(Tono-Pen VETなど)
ペン型の機器を
▶目の表面(角膜)に軽く当て
▶その部分を平らにするのに必要な圧力を測定する方法です。
◇特徴
①点眼麻酔を推奨
検査時の不快感を和らげるため
点眼麻酔
をすることが一般的です。
②信頼性が高い
人間の眼科で使われる機器と高い相関性があるため
非常に信頼性の高い結果
が得られます。
より正確に眼圧を測定するために
眼圧は
・一日の間でも変化したり
・その時々のストレスで変動したり
するデリケートな数値です。
正確な測定のためには、飼い主さんの協力が不可欠です。
①落ち着いた状態で受診する
犬が
・興奮したり
・過度に緊張したり
すると
▶血圧が上がり
▶それに伴い眼圧も上昇
することがあります。
動物病院に行く際は、愛犬がなるべく落ち着けるように、時間に余裕をもって行動しましょう。
②首輪やハーネスに注意する
首輪やハーネスがきつすぎると
▶首の血管を圧迫し
▶眼圧が上昇する
可能性があります。
病院に行く際は
首に負担がかからないように
・ゆったりとしたものを選ぶ
・可能であれば外して
測定してもらいましょう。
③日頃の愛犬の様子を伝える
・いつから目の様子がおかしい?
・どんな時に目を気にしている?
など、些細な変化でも獣医師に詳しく伝えましょう。
眼圧の解釈:数字だけでなく「変化」も大切
獣医師は、眼圧の診断を
絶対的な数字
だけで判断するわけではありません。
●個体差と基準値
犬の正常な眼圧は一般的に
10〜20mmHg
とされていますが
個体差があります。
獣医師は、この基準値だけでなく
その犬にとっての正常な眼圧
を知るために、過去のデータとの比較を重視します。
●「変化」を捉える
一度だけの測定で高い数値が出たとしても、それがたまたま一時的なものかもしれません。
定期的な検診で
▶眼圧の推移を追うことで
▶小さな変化にも気づきやすくなります。
●他の検査結果との組み合わせ
獣医師は、眼圧測定だけでなく
・視診
・眼底検査
・超音波検査など
を組み合わせ、緑内障の
・進行度
・原因
を総合的に判断します。
緑内障の治療と薬の例、副作用
緑内障で一度傷ついた視神経を
元に戻すことはできません。
そのため
・早期発見
・適切な治療
によって
病気の進行を遅らせること
が重要です。
治療の主な目的は
・点眼薬などで眼圧を下げ
・視神経への負担を減らす
ことです。
●点眼薬
処方される主な薬は
房水の産生を抑える
・β遮断薬(チモロールなど)
房水の排出を促す
・プロスタグランジン関連薬
(ラタノプロストなど)
などです。
●内服薬
眼圧を下げるために
炭酸脱水酵素阻害薬
(ダイアモックスなど)
などが処方されることもあります。
しかし現在は点眼薬に取って代わられる傾向です。
●手術
・薬物療法で効果が見られない
・失明してしまった
などの場合には
・眼球摘出
・義眼の挿入
といった手術が選択されることもあります。
点眼薬は基本的に
局所的に作用
するため、食事との兼ね合いはほとんど心配いりません。
しかし、内服薬の場合は
・食欲不振
・胃腸の不調
などの副作用が出ることがあるため、食事管理も重要になります。
ヒッポのごはんでの緑内障対策の食事方針
「ヒッポのごはん」は
・愛犬の健康を第一に考えた
・専門家監修の手作りごはん
として緑内障を抱える愛犬にも最適な食事を提供します。
・目の奥の血流改善
・酸化ストレスの軽減
・視神経の保護
をコンセプトに、特定の栄養素を強化したオーダーメイド食を提案します。
強化する栄養素
●目の健康に役立つ栄養素
◇ルテイン
緑内障の原因の一つである
酸化ストレス
から目を守る強力な抗酸化作用に注目
【主な食材】
・小松菜
・ブロッコリー
・カボチャなどの緑黄色野菜
・卵黄
◇アスタキサンチン
こちらも非常に強い抗酸化作用
さらに
目の毛細血管の血行を促進する
働きがあると言われ
視神経に十分な栄養を届ける
手助けが期待されます。
【主な食材】
・トラウトサーモン
・干しアミなど
◇アントシアニン
目の網膜にあるロドプシンという
▶タンパク質の再合成を促し、
▶視覚機能を改善する働きがあります。
【主な食材】
ブルーベリー茎
●神経系の健康に役立つ栄養素
◇ビタミンB群
・視神経の働きを高め
・視力の低下を防ぐ
役割があるとされています。
特にビタミンB12は
神経伝達をスムーズに保つ
働きがあると言われています。
【主な食材】
・豚肉
・レバー
・大豆製品(きな粉など)
・青魚など
◇ビタミンA
「目のビタミン」
とも呼ばれ
・角膜
・粘膜
の健康維持に欠かせません。
【主な食材】
・レバー
・緑黄色野菜など
◇オメガ-3脂肪酸(DHA、EPAなど)
・目の血流を良くする働き
・抗炎症作用
が期待されます。
【主な食材】
・新鮮な鮮魚
(トラウトサーモン、サバ、イワシなど)
●血流改善に役立つ栄養素
・ビタミンE(サチャインチオイル、かぼちゃ)
・タウリン(赤身肉、魚介類)
・プロアントシアニジン(ブルーベリー茎)
・レシチン(卵黄)など
・目の奥の血行を促進し
・視神経への栄養供給を助ける
ような食材を厳選します。
●全体的のバランス
特定の栄養素を大量に摂るのではなく
バランスの取れた食生活
が最も重要です。
また、緑内障リスクを高めるとされる
糖尿病
にならないためにも
・糖質の過剰摂取に注意し
・適度な運動を心がける
ことも大切です。
これらの食事はあくまで
・予防
・進行抑制
の一環であります。
緑内障の治療には
・獣医師の診断
・処方された点眼薬
が不可欠です。
定期的な眼科検診
を欠かさず受けることが、何よりも重要であるとご理解ください。
控えるべきもの
●血流を悪化させる
可能性のある
極端に脂肪分が多い食事
は避けます。
●体内の水分バランスを崩す
可能性のある
過剰な塩分
にも注意します。
●獣医師と相談の上
血液検査の結果に合わせて
・リン
・タンパク質
などの栄養バランスも細かく調整。
腎臓など他の臓器への負担も考慮します。
食事の質と消化吸収の重要性
ヒッポのごはんは
人が食べられる質の高い肉を
▶米麹で熟成させた後
▶低温で丁寧に調理することで
非常に消化吸収性に優れた
食事を提供しています。
これにより
・内臓に負担をかけることなく
必要な栄養素を
・効率的に愛犬の体に届ける
ことができます。
特に食欲が落ちやすい緑内障では
・消化しやすく
・香りが良い
手作りごはんは大きなメリットとなります。
緑内障の治療費の例
治療費は
・病状
・治療法
によって大きく異なります。
一般的な目安として以下のような例が挙げられます。
◇初期の診断
5,000円〜15,000円
・眼圧検査
・眼底検査など
◇点眼薬(継続的に必要)
1本あたり2,000円〜5,000円程度
◇手術費用(片眼)
100,000円〜300,000円
緑内障の愛犬にしてあげられること
●落ち着ける環境づくり
緑内障の痛みで犬は不安になりがち。
静かで落ち着ける場所
を用意してあげましょう。
●アイコンタクトの工夫
見えにくくなっている可能性があるため
・声かけを多くし
・優しく触れてあげる
ことで安心感を与えられます。
●事故防止
・家の中の家具の配置を大きく変えない
・危険な場所には近づけないようにする
など、安全に配慮した環境を整えてあげましょう。
●目のケア
獣医師の指示に従い
点眼を忘れずに行うこと
が最も重要です。
点眼の正しい方法とコツ
犬に目薬をさす際は
・飼い主さんがリラックスし
・愛犬が安心できる環境を整える
ことが成功の鍵です。
基本的な手順
①愛犬を落ち着かせる
触れられることに慣れていない子には
・優しく声をかけたり
・撫でたりして
リラックスさせてあげましょう。
無理に押さえつけると
▶目薬を嫌いになってしまう
原因になります。
②点眼の姿勢
愛犬の後ろに回り
▶優しく抱きかかえて
▶動かないように保定します。
犬は正面からくるものに警戒心を持つため、後ろからの方が安心しやすいです。
③顔を固定する
片方の手で愛犬の顎を軽く持ち
▶顔を少し上向きにさせます。
④まぶたを開く
目薬を持つ手とは反対の指で
▶上まぶたを優しく持ち上げ、目に点眼しやすいようにします。
⑤目薬をさす
目薬の容器が
愛犬の視界に入らないように
後ろから近づけて1滴さします。
容器の先端が
・目
・まつげ
に触れないように注意しましょう。
⑥点眼後
しばらくの間
・愛犬の顔を上向きに保ち
・目薬を目全体に行きわたらせます。
あふれた目薬は清潔な
・ガーゼ
・コットン
で優しく拭き取ってあげましょう。
嫌がる子への特別なコツ
●ご褒美を活用する
点眼後には
・大好きなおやつ
・褒め言葉
で「目薬=良いこと」
というポジティブな経験を積み重ねさせましょう。
●目薬を見せない工夫
目薬を見ただけで怖がる子もいます。
・点眼の直前まで容器を手で隠す
・後ろからそっと近づける
などすると良いでしょう。
●点眼の温度に注意
冷蔵庫から出したばかりの目薬は、冷たさで愛犬がびっくりすることがあります。
手のひらで少し温めてから使用すると、驚きを減らせます。
目薬を使う上での大切な注意点
正しい方法で点眼しても
以下の注意点を守らなければ
・治療の効果が十分に得られい
・目に負担をかける
などの可能性があります。
●処方通りに使う
用法・用量
(点眼回数、1回にさす量など)
は必ず獣医師の指示に従ってください。
たくさんさしても効果は変わりません。
それどころか、かえって
目の周りの皮膚炎
を引き起こすこともあります。
●複数種類の目薬を使う場合
2種類以上の目薬が処方された場合
最低でも5分以上の間隔
をあけて点眼しましょう。
続けてさすと
▶先にさした薬が
▶後からさした薬で流されてしまい
▶効果が薄れてしまいます。
●清潔を保つ
使う前には必ず
・飼い主さんの手を洗い
目薬の容器の先端が
・愛犬の目に触れないよう
に注意しましょう。
開封後は、基本的に1ヶ月を目安に使い切ってください。
●保存方法を確認する
目薬によっては
・冷蔵保存が必要なもの
・光を避ける必要があるもの
があります。
処方された際に獣医師に確認し
▶正しい方法で保管しましょう。
どうしても目薬がさせないときは
あらゆる工夫をしても
愛犬が強く抵抗
する場合。
無理に点眼しようとすると
・犬が飼い主を噛んでしまったり
・目にケガをさせてしまったり
する危険があります。
そのような場合は
▶無理せず獣医師に相談しましょう。
・飲み薬での治療が可能な場合
もありますし
・毎日動物病院で点眼してもらう
という選択肢もあります。
大切なのは
・愛犬
・飼い主さん
の双方にストレスがない方法で
継続的に治療を続ける
ことです。
緑内障は放置すると
失明に至る病気
ですが
・早期発見
・適切なケア
で進行を遅らせることができます。
日頃から愛犬の目の状態をよく観察し
「いつもと違う」
というサインを見逃さないことが、愛犬の視力を守るための第一歩です。

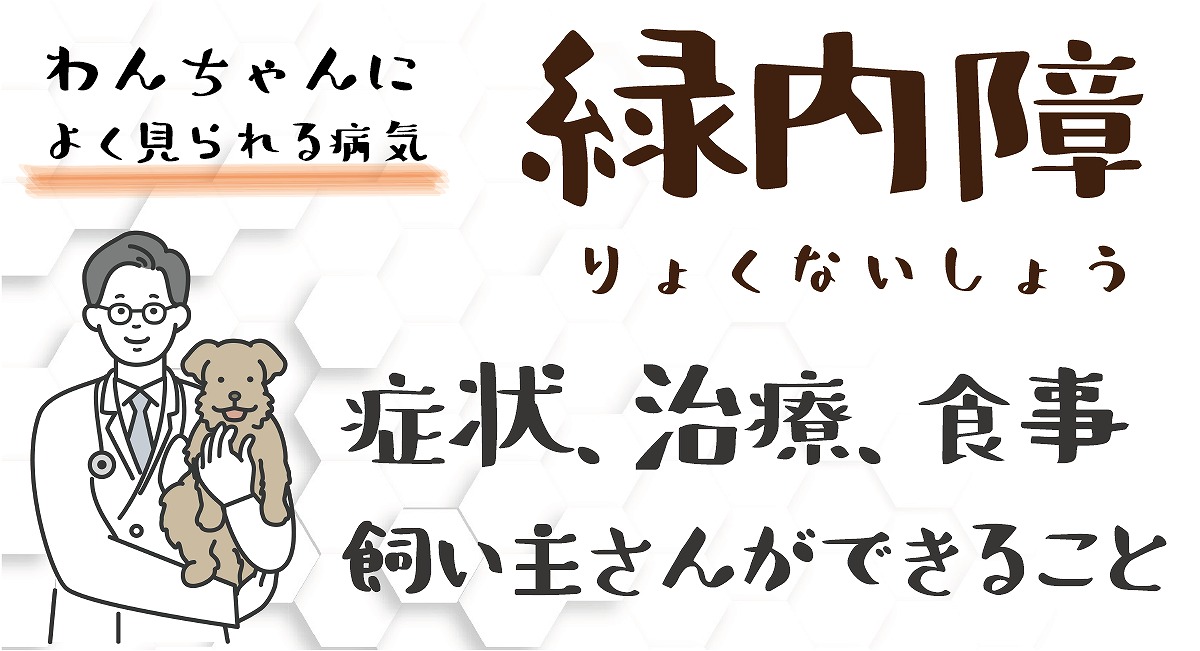

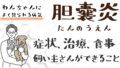
コメント