犬の皮膚炎は
多くの犬が一度は経験する
と言われるほど一般的な病気です。
・痒み
・不快感
を伴うため愛犬のQOL(生活の質)を著しく低下させることがあります。
原因が多岐にわたり、治療が長期にわたることも少なくありませんが、病気を正しく理解し、根気強くケアを続けることが大切です。
犬の皮膚炎とは?どんな病気か?
犬の皮膚炎は、皮膚に炎症が起こっている状態全般を指します。
単なる「皮膚の炎症」という症状であり、その原因は様々です。
皮膚は体の最大の臓器であり
・外部からの刺激
・病原体
から体を守るバリア機能を担っています。
この
・バリア機能が破綻
・免疫システムが過剰に反応
などすることで皮膚炎は起こります。
犬の皮膚は
・ヒトの皮膚に比べて薄く
・皮膚の表面にある角質層の細胞間脂質が少ない
・皮膚のターンオーバー周期が短い
(約22日間、ヒトは約28日間)
新しい皮膚細胞が生まれ、古い細胞が剥がれ落ちるサイクル
といった特徴があります。
これらの特徴から
・外部からの刺激を受けやすく
・一度炎症が起こると進行しやすい
傾向があります。
犬の皮膚炎の主な原因
皮膚炎の主な原因としては、以下のようなものがあります。
●アレルギー性皮膚炎:
◇環境アレルギー(アトピー性皮膚炎)
・花粉
・ハウスダスト
・カビなど
環境中のアレルゲンに対する過剰な免疫反応。
遺伝的な体質が関与することが多いです。
◇食事性アレルギー
食事中の特定の成分(タンパク質源や炭水化物源など)に対する免疫反応。
◇ノミ・マダニによるアレルギー
ノミの唾液やマダニの成分に対するアレルギー反応。
●感染性皮膚炎:
◇細菌性皮膚炎
皮膚常在菌であるブドウ球菌などが過剰に増殖して起こる感染。
◇マラセチア性皮膚炎
皮膚常在菌であるマラセチアという酵母様真菌が過剰に増殖して起こる感染。
◇皮膚糸状菌症(カビ)
真菌(カビ)が皮膚の角質層や被毛に感染して起こる。
●寄生虫性皮膚炎
・ノミ
・マダニ
・ヒゼンダニ
・ニキビダニ
などの外部寄生虫の寄生によるもの。
●脂漏性皮膚炎
皮脂の分泌異常により
・皮膚が乾燥したり(乾性脂漏症)
・ベタついたり(湿性脂漏症)し
それに伴って炎症や感染が起こる。
体質や基礎疾患が関与することが多いです。
●その他:
・接触性皮膚炎
(特定の物質が皮膚に触れて起こる)
・自己免疫疾患
・内分泌疾患
(甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症など)
に伴う皮膚症状など。
犬の皮膚炎の症状
皮膚炎の最も一般的な症状は
「痒み」
です。
痒みの程度は様々で
・軽度な痒みから
・体を掻きむしったり
・舐め続けたり
・噛んだり
家具や床に体をこすりつけたりして自らを傷つけてしまうほどの重度の痒みまであります。
痒み以外には、以下のような症状が見られます。
・皮膚の赤み(紅斑)
・脱毛
・フケ
・かさぶた、落屑
・皮膚のベタつき
(脂っぽくなる)
・皮膚の乾燥、カサつき
・皮膚の色素沈着(黒ずみ)
慢性的な炎症が続くと見られます。
・皮膚の肥厚
(象の皮膚のように厚く硬くなる)
慢性的な炎症が続くと見られます。
・発疹、ブツブツ
・耳の炎症(外耳炎)
皮膚炎に伴って耳の穴にも炎症が起こることがよくあります。
・ 独特のニオイ
細菌やマラセチアが増殖すると、独特の脂っぽい、あるいはカビのようなニオイを発することがあります。
症状は全身に出ることもあれば
・脇の下
・お腹
・内股
・指の間
・顔
・耳
・肛門周囲など
特定の部位に限定されることもあります。
犬の皮膚炎を予防するためには?
皮膚炎の原因は多岐にわたるため、原因によって予防法も異なります。
●アレルギー性皮膚炎(特にアトピー性皮膚炎):
◇アレルゲンの特定と回避
・環境アレルゲン
・食事性アレルゲン
を特定し、可能な範囲で接触を避けることが理想です
しかし、完全に回避するのは困難な場合が多いです。
◇皮膚バリア機能の維持
日頃からの適切なスキンケア(シャンプー、保湿)により、皮膚のバリア機能を健康に保ち、アレルゲンの侵入を防ぎやすくします。
◇環境整備
・ハウスダストマイト対策
(こまめな掃除、寝具の洗濯、空気清浄機の使用)
・花粉対策
(散歩後の体についた花粉を払い落とす、ウェットティッシュで拭くなど)
● 感染性皮膚炎:
◇日頃からの清潔なケア
適切な頻度と方法でのシャンプーやブラッシングにより、皮膚を清潔に保ち、細菌や真菌の過剰な増殖を防ぎます。
◇皮膚バリア機能の維持
健康な皮膚は病原菌の増殖を抑える力を持っています。
◇免疫力の維持
・バランスの取れた食事
・適度な運動
・ストレスの軽減など
により、全身の免疫力を高く保つことも重要です。
●寄生虫性皮膚炎:
◇定期的な外部寄生虫の予防
ノミ・ダニ・マダニなどの予防薬を、獣医師の指示に従って定期的に投与することが最も効果的な予防法です。
●食事性皮膚炎:
◇特定の食材にアレルギーがある場合は、その食材を含まないフードを選びます。
アレルギーが疑われる場合は、獣医師指導のもと、除去食試験を行います。
●全般的な予防:
◇バランスの取れた食事
皮膚の健康に必要な栄養素を十分に摂取できる、高品質な総合栄養食を選びましょう。
◇適度な運動とストレス管理
ストレスは皮膚炎を悪化させる要因となるため、心身の健康を保つことが予防にも繋がります。
◇定期的な健康診断
早期に皮膚の異常を発見し、適切な対処を行うことが重症化を防ぎます。
犬の皮膚の表面には、様々な細菌や真菌などが生息する
「皮膚常在菌叢(マイクロバイオーム)」
が存在します。
このマイクロバイオームのバランスが崩れると、病原菌が増殖しやすくなり、皮膚炎の原因や悪化要因となります。
・日頃からの適切なスキンケア
・皮膚の健康をサポートするプロバイオティクスやプレバイオティクス(経口または外用)の利用
なども、皮膚の健康維持に役立つ可能性が近年注目されています
※ただし、これらはまだ研究段階の知見も多く含まれます
犬の皮膚のpH(一般的に弱アルカリ性)に合わせたシャンプーを選ぶことも大切です。
・強すぎる洗浄剤
・過度な頻度のシャンプー
はマイクロバイオームのバランスを崩す可能性があります。
犬の皮膚炎の治療や処方される薬の例
皮膚炎の治療は
・原因療法と
・対症療法
を組み合わせて行われます。
●原因療法:
◇寄生虫駆除
外部寄生虫の予防薬や駆除薬を投与します。
◇感染症治療
・細菌性皮膚炎には抗生物質
・マラセチア性皮膚炎や皮膚糸状菌症には抗真菌薬(内服薬、外用薬、薬用シャンプー)
を使用します。
◇食事療法
食事性アレルギーが疑われる場合、アレルゲンを含まない療法食を用いた除去食試験を行います。
◇アレルゲン免疫療法(減感作療法)
環境アレルギーの場合、特定されたアレルゲンを少量ずつ体内に投与し、アレルゲンに対する過剰な免疫反応を抑制する治療法です。
効果が出るまで時間がかかりますが、薬の使用量を減らせる可能性があります。
●対症療法(痒み・炎症の緩和)
◇ステロイド※要注意
・強力な抗炎症作用と
・痒み止め作用
を持ち、即効性があります
しかし、長期使用や高用量使用には多くの副作用リスクがあります。
内服薬や外用薬があります。
◇アポキル錠(オクラシチニブ)
痒みの伝達に関わるJAKという酵素の働きを阻害することで痒みを抑えます。
比較的速効性があり、ステロイドに比べて副作用が少ないとされています。
◇サイトポイント(ロキベトマブ)
犬のアトピー性皮膚炎による痒みに関わるインターロイキン-31(IL-31)という物質を標的とする注射薬です。
約1ヶ月間痒みを抑える効果が持続します。
副作用が少なく安全性が高いとされています。
◇免疫抑制剤(シクロスポリンなど)
免疫系の過剰な反応を抑制することで、アレルギー性皮膚炎による炎症や痒みを抑えます。
効果が出るまで時間がかかりますが、長期管理に用いられることがあります。
◇抗ヒスタミン薬
痒みに関わるヒスタミンの働きを抑えます。
効果は限定的ですが、副作用が少なく、他の薬と併用されることがあります。
◇薬用シャンプー
・皮膚の洗浄
・余分な皮脂やフケの除去
・細菌やマラセチアの抑制
・痒みの緩和
・保湿など
皮膚の状態に合わせて様々な種類のシャンプーが用いられます。
◇保湿剤
乾燥している皮膚に潤いを与え、皮膚バリア機能をサポートします。
・ローション
・スプレー
・クリーム
などがあります。
その薬の副作用や食事との兼ね合い
皮膚炎の治療薬は種類が多く、それぞれ異なる副作用や食事との兼ね合いがあります。
ステロイド(内服)
●副作用
・多飲多尿
・多食(食欲が増す)
・パンティング
(ハァハァと息をする)
・体重増加
・筋力低下
・皮膚が薄くなる
・脱毛
・免疫力低下により感染症にかかりやすくなる
・肝臓への負担
・糖尿病の発症リスク増加
・副腎機能抑制など
長期使用や高用量使用で顕著になります。
●食事との兼ね合い
食欲が増すため、食事量の管理が重要です。
タンパク質やビタミンB群の要求量が増えるため、これらの栄養素を強化した食事やサプリメントが推奨されることがあります。
アポキル錠(オクラシチニブ)
●副作用
比較的少ないですが
・嘔吐
・下痢
・食欲不振が見られることがあります。
長期使用による免疫抑制の可能性も懸念されており、定期的な健康チェックが必要です。
●食事との兼ね合い
食事と一緒に与えることで、胃腸への負担を軽減できる場合があります。
サイトポイント(ロキベトマブ)
●副作用
注射部位の一過性の反応(痛み、腫れ)が見られることがありますが、全身性の副作用は非常に少ないとされています。
免疫抑制剤(シクロスポリンなど)
●副作用
消化器症状(嘔吐、下痢、食欲不振)が見られることがあります。
・腎臓への負担
・免疫力低下により感染症にかかりやすくなる
・歯茎の増殖(歯肉が正常よりも大きく腫れて、厚くなる)
などが起こる可能性もあります。
●食事との兼ね合い
食事中の脂肪が多いと吸収率が低下するという報告があります。
そのため、低脂肪食との併用が推奨されることがあります。
※重要な注意点
ここに挙げたのは一般的な例であり、個体差があります。
必ず獣医師の指示に従って薬を与え、気になる症状があればすぐに相談してください。
薬の種類や組み合わせは、病状や個体の状態によって細かく調整されます。
犬の皮膚炎の食事で気を付ける点・療法食の内容
食事療法は、特に
・アレルギー性皮膚炎
・皮膚バリア機能の維持
に重要な役割を果たします。
食事性アレルギーの場合
● 除去食試験
食事性アレルギーが疑われる場合、最も重要なのが除去食試験です。
・今まで食べたことのない「新しいタンパク質源」(例:鹿肉、鴨肉、カンガルー肉、魚肉など)
・「加水分解タンパク質」(タンパク質をアレルギー反応を起こしにくい大きさに分解したもの)
を用いた療法食、あるいは手作り食を、他のものを一切与えずに一定期間(通常8週間程度)与え続けます。
この期間中に皮膚症状が改善すれば、食事性アレルギーの可能性が高いと判断できます。
●療法食
食事性アレルギーに対応した療法食は
・新しいタンパク質源
・加水分解タンパク質
を使用しており、アレルギー反応を起こしにくいように配慮されています。
また
皮膚の健康をサポートする栄養素
・オメガ3脂肪酸
・オメガ6脂肪酸
・亜鉛
・ビタミン類など
が強化されていることが多いです。
・ヒルズ プリスクリプション・ダイエット z/d(食物アレルギー&皮膚ケア)
・ロイヤルカナン 療法食 セレクトプロテイン
・アミノペプチド フォーミュラ
などがよく使用されます。
皮膚バリア機能のサポート
皮膚の健康を維持するために
・バランスの取れた脂肪酸
(オメガ3とオメガ6の適切なバランス)
・皮膚の構成成分となる栄養素
(亜鉛、必須アミノ酸)
・抗酸化物質
(ビタミンE, Cなど)
を十分に摂取できる食事が推奨されます。
●療法食
皮膚の健康をサポートする療法食は、これらの栄養素が強化されています。
・ヒルズ プリスクリプション・ダイエット d/d(食物アレルギー&皮膚ケア)
・ロイヤルカナン スキンケア
などがあります。
犬の皮膚炎で強化すべき栄養素
皮膚の
・健康維持や
・炎症の軽減
に役立つ栄養素を意識して摂取することが重要です。
●オメガ3脂肪酸(EPA, DHA)
魚油などに多く含まれ、強力な抗炎症作用を持ちます。
痒みや炎症を軽減し、アレルギー反応を抑制する効果が期待できます。
●オメガ6脂肪酸(リノール酸)
植物油(ひまわり油、コーン油など)に多く含まれ、皮膚のバリア機能の構成成分となります。
不足すると皮膚の乾燥やバリア機能の低下を招きます。
反面摂りすぎは、炎症を促進します。
●亜鉛
・皮膚細胞の正常な代謝
・細胞分裂
・傷の治癒
に不可欠なミネラルです。
亜鉛が不足すると
・皮膚の再生が遅れたり
・特定の皮膚病(亜鉛欠乏性皮膚炎)
を発症したりすることがあります。
●ビタミン類
◇ビタミンA
皮膚や粘膜の健康維持、細胞の分化に重要です。
◇ビタミンE
強力な抗酸化作用を持ち、皮膚の細胞を保護します。
◇ビタミンB群
皮膚や被毛の健康、エネルギー代謝に関与します。
●抗酸化物質
・ビタミンC, E
・セレン
・ポリフェノールなど
は、体内の酸化ストレスを軽減し、炎症を抑える助けとなります。
犬の皮膚炎で控えるべき栄養素
特定の栄養素そのものを控えるというより
・原因となる可能性
・病状を悪化させる可能性
があるものを避けることが重要です。
●食事性アレルギーのアレルゲン
除去食試験によって特定された、あるいは疑われる特定のタンパク質源や炭水化物源を含む食品は完全に避ける必要があります。
●過剰な脂肪
過剰な脂肪摂取は
・膵臓に負担をかけたり
・消化不良を起こしたり
で全身状態を悪化させる可能性があります。
また、湿性脂漏症の場合は、脂肪の代謝異常が関与していることもあるため、適切な脂肪量の管理が必要です。
●人工添加物
・着色料
・香料
・保存料
などの人工添加物が、一部の犬でアレルギー反応や過敏症を引き起こす可能性が指摘されています。
可能な限り
・無添加
・シンプルな原材料のフード
を選ぶことを検討しましょう。
犬の皮膚炎治療費の例
皮膚炎の治療費は
・原因
・症状の重症度
・必要な検査
・治療内容
・慢性化の有無
によって大きく異なります。
●初診料・再診料
数千円程度
●検査費用
皮膚炎の診断には様々な検査が必要となることが多く、費用が高額になりやすい項目です。
◇皮膚掻爬検査、抜毛検査、セロテープ検査(寄生虫、真菌などの確認):数千円
◇ウッド灯検査(皮膚糸状菌症の確認):数千円
◇細菌培養検査、真菌培養検査:数千円~1万円以上
◇アレルギー検査(血液検査):数万円(原因特定のために有効な場合があります)
◇病理組織検査(皮膚の一部を採取して検査):数万円(腫瘍や自己免疫疾患などが疑われる場合)
●薬代
・内服薬(抗生物質、抗真菌薬、痒み止め、免疫抑制剤など)
・外用薬(軟膏、ローション、スプレーなど)
の種類や量、治療期間によって大きく異なります。
慢性疾患のため、生涯にわたって薬が必要な場合もあり、継続的な費用が発生します。
●薬用シャンプー代
1本数千円程度。
頻繁に使用する場合、負担になることがあります。
●療法食代
一般的なフードに比べて高価になることが多いです。
●入院費
重症化した場合や集中的な治療が必要な場合。
※注意点
皮膚炎は
・原因の特定が難しく
・様々な検査が必要になる
・慢性化して治療が長期にわたる
ことが多いため、全体として治療費が高額になる傾向があります。
特にアトピー性皮膚炎などの慢性疾患は、生涯にわたるケアが必要となり、治療費も継続的に発生します。
ペット保険に加入している場合は、補償内容を確認し、賢く活用しましょう。
その他、この病気になったときに気を付けてあげること、してあげられること
●日々の丁寧なケア
獣医師の指示に基づいた
・適切なシャンプー
・保湿
・薬用ローションや軟膏の使用
など、自宅でのスキンケアが治療効果を高める上で非常に重要です。
シャンプーは
・皮膚の汚れやアレルゲン
・余分な皮脂などを洗い流し
薬用シャンプーであれば原因菌の抑制にも役立ちます。
・洗いすぎや
・シャンプー剤のすすぎ残し
はかえって皮膚への刺激になるため注意が必要です。
シャンプー後は、皮膚をしっかり乾かすことも感染予防のために重要です。
●痒み対策
掻き壊しは症状を悪化させ、新たな感染を引き起こす原因となります。
・エリザベスカラー
・保護服
を着用させて、物理的に掻き壊しを防ぎましょう。
また、爪をこまめに短く切っておくことも大切です。
●環境整備
・アレルゲン対策
(こまめな掃除、空気清浄機の使用、ペットベッドや毛布の洗濯など)
・部屋の温度と湿度の管理
(乾燥しすぎも、高湿でカビやダニが増えるのも良くありません)
も皮膚の健康に影響します。
●観察と記録
・痒みの程度
(掻いている時間や頻度)
・皮膚の状態
(赤み、フケ、かさぶた、脱毛の範囲など)
・食欲、元気、排便
・排尿の様子
などを日頃から観察し、記録しておくと、診察時に獣医師に正確な情報を伝えるのに役立ちます。
・治療の効果判定
・病状の変化
を把握する上で重要です。
●ストレス管理
犬にとってのストレスは
・免疫機能
・ホルモンバランス
を崩し、皮膚炎を悪化させる可能性があります。
・十分な休息
・適度な遊びや散歩
・安心できる環境づくり
など、ストレスを軽減する工夫をしてあげましょう。
●獣医師との密な連携
皮膚炎の治療は
・原因の特定から始まり
・様々な治療法を試したり
・薬の種類や量を調整したり
と、試行錯誤が必要となることがよくあります。
治ったように見えても再発することも多いです。
疑問な点や不安な点があれば、遠慮なく獣医師に質問し、病状の変化に応じて治療計画を一緒に考えていくことが、治療を成功させるための鍵となります。
●マイクロバイオームの意識
表面的な洗浄だけでなく、皮膚常在菌叢のバランスを整えることを意識したスキンケアも、今後の皮膚病治療において重要になってくると考えられています。
例えば、特定の善玉菌を配合した外用剤の使用などが挙げられます。
●サプリメントの活用
・オメガ3脂肪酸
・亜鉛
・特定のビタミン
などの皮膚の健康をサポートするサプリメントは、治療の補助として有効な場合があります。
ただし、闇雲に与えるのではなく
・愛犬の状態
・不足している栄養素
・エビデンスに基づいて
獣医師と相談の上で選択しましょう。
ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバーなど特定の犬種では、亜鉛の要求量が多い可能性も指摘されています。
まとめ
犬の皮膚炎は
・痒みや不快感を伴い
・原因が多様で診断や治療に時間がかかる
ことが多い病気です。
しかし、適切な診断に基づいて原因療法と対症療法を組み合わせ、そして
・日々の丁寧なスキンケア
・環境整備
・食事管理
を行うことで、多くの皮膚炎は管理が可能であり、愛犬が快適に過ごせるようにサポートすることができます。
治療の過程で改善が見られず落ち込むこともあるかもしれませんが、根気強く、かかりつけの獣医師と二人三脚で取り組んでいくことが大切です。
愛犬の痒みや辛さを理解し、寄り添ってケアしてあげることが、何よりの支えになるでしょう。

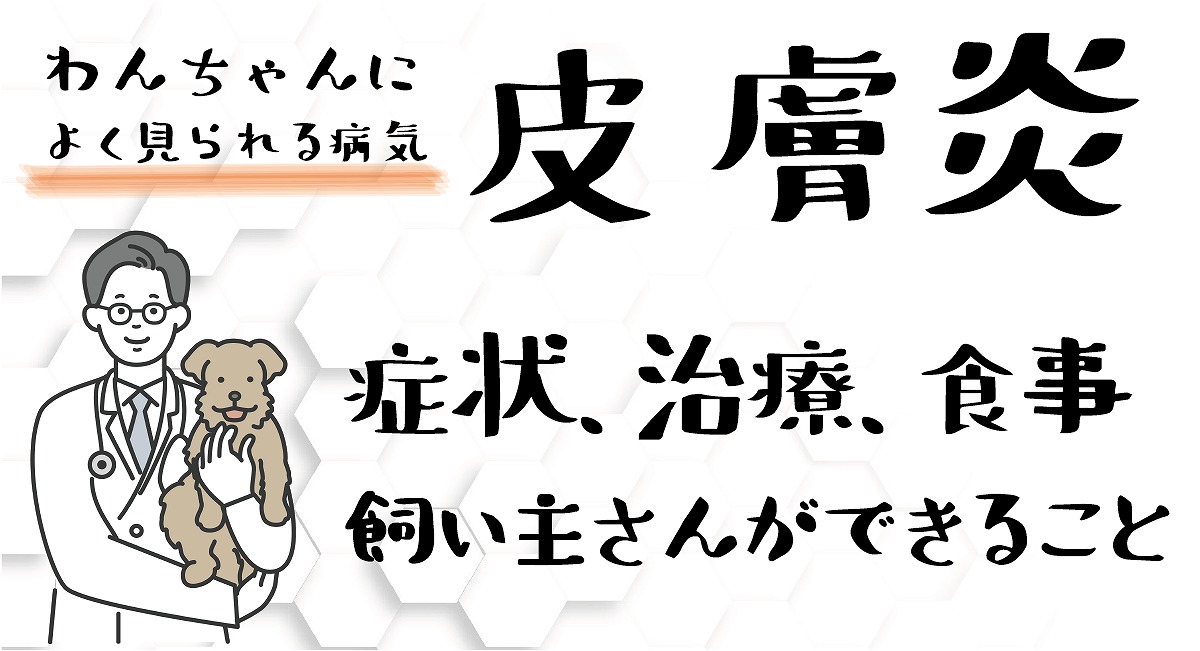

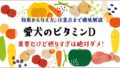
コメント