犬の胆嚢炎は
飼い主さんが気づきにくい
病気の一つです。
しかし、放置すると
命に関わる深刻な事態
を招くことがあります。
この記事では
・胆嚢炎の基礎知識から
他のサイトではあまり触れられない
・気づきのポイント
・獣医療の最新事情
まで深く掘り下げて解説します。
胆汁と胆嚢の働き。胆嚢炎はなぜ気づきにくいのか
胆汁は
肝臓で作られる消化液。
・食事中の脂肪を分解し
・腸での吸収を助ける働き
があります。
また、血液中の老廃物である
・ビリルビン
・コレステロール
の排泄も担うなど、動物の体にとって不可欠なものなのです。
胆嚢は
肝臓で作られた胆汁を
・一時的に貯蔵し
・濃縮する
場所です。
食事が十二指腸に到達すると
▶胆嚢の壁が収縮し
▶胆汁が総胆管という管を通って
▶十二指腸へ排出されます。
この仕組みが正常に働くことで、脂肪の消化吸収がスムーズに行われます。
・何らかの原因で胆汁の流れが悪くなる
・細菌に感染する
などで胆嚢に炎症が起こります。
胆嚢炎が
初期段階で発見されにくい
最大の理由は
はっきりとした症状が現れにくい
からです。
多くの場合
・食欲不振
・元気がない
といった
他の病気でも見られるような
漠然とした症状
しか示しません。
特に犬は
痛みを隠す習性
があるため、飼い主さんは

少し食欲がないだけかな?
と安易に考えてしまいがちです。
犬の胆嚢炎とはどんな病気?
犬の胆嚢炎は、何らかの原因で
胆嚢に炎症
が起こる病気で
急に症状が出る
・急性胆嚢炎と
ゆっくりと進行する
・慢性胆嚢炎
に分けられます。
日本での発症は
10歳前後
の比較的中高齢で多く
・トイプードル
・チワワ
・ミニチュアダックスフント
・ミニチュアシュナウザー
などの
小型犬種
でよく見られるという報告があります。
症状は多岐にわたり
・軽度のものから
・入院が必要な重度なものまで
様々です。
・嘔吐、下痢
・食欲不振、元気消失
・黄疸(目や歯茎、皮膚が黄色くなる)
・腹部の痛みや不快感
・発熱
これらの症状は
他の病気と似ている
ため自己判断せず、すぐに獣医師に相談することが大切です。
検査は
・血液検査
・腹部超音波検査
が中心となります。
血液検査では
・ALT
・ALP
・ビリルビン
・コレステロール値
炎症を示す
・白血球
・CRP
の上昇が認められることが多いです。
超音波検査では
・胆嚢や総胆管、肝臓の状態
・腹水の有無
を確認します。
胆嚢炎の原因と胆嚢疾患の関係性
胆嚢炎の原因は様々で
日常的に多く遭遇する疾患
です。
また胆嚢疾患は
・胆泥症
・胆嚢粘液嚢腫
・胆石症など
互いに影響し合って
発症することも少なくありません。
●細菌感染
急性胆嚢炎は、多くの場合
十二指腸の胆汁の出口
から細菌が感染することで起こります。
・肝炎
・腸炎
・急性膵炎など
他の臓器で起きた炎症が原因で
▶細菌が胆嚢に感染し
▶胆嚢炎を引き起こす
こともあります。
・クッシング病などのホルモン疾患
・ステロイド剤の長期服用
は免疫力を低下させ、細菌感染のリスクを高めます。
●胆汁の鬱滞
・胆嚢粘液嚢腫
・胆石
などの胆嚢内の異常は
▶胆汁の流れを滞らせ
▶細菌が繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。
胆嚢炎によって胆汁が変質して
・結晶化したり
・泥状になったり
すると、それが胆嚢内に蓄積して
・胆泥症
・胆石症
の原因にもなります。
●脂質代謝の異常
慢性胆嚢炎はあまり研究されていません
しかし一説では
脂質代謝の異常
がその原因の一つと言われています。
●胆泥症と胆嚢炎の密接な関係
胆泥症は
胆嚢内に泥状の物質が溜まる
病態です。
これは胆汁の流れが悪くなることで起こり
多くの場合は無症状
ですが、放置すると
▶胆嚢を刺激し
▶炎症を引き起こす
可能性があります。
さらに進行すると
▶胆嚢内にゼリー状の粘液が充満する
胆嚢粘液嚢腫
に移行し
胆嚢が破裂する危険性
が非常に高まります。
胆泥症は
・胆嚢炎の前段階
あるいは
・同時に発症する病態
として、決して軽視してはいけません。
胆嚢炎を予防するためには?
残念ながら、胆嚢炎を完全に予防する方法は確立されていません。
しかし
・発生リスクを低減させる
・早期発見に繋げる
などすることは可能です。
●定期的な健康診断
特に中高齢の犬では
年に一度の健康診断
(血液検査、超音波検査など)
によって
・胆嚢炎の早期発見
・進行度合いのチェック
が可能です。
無症状のうちに発見できれば
▶重症化する前に対応を検討できます
特定の犬種
・シーズー
・コッカースパニエル
・ミニチュアシュナウザー
・シェルティー
・チワワ
・ポメラニアンなど
は胆嚢炎になりやすい傾向があると言われています。
これは
・遺伝的な体質
・特定の疾患にかかりやすいこと
が関連していると考えられています。
これらの犬種の飼い主さんは、より一層注意が必要です。
●適切な食事管理
高脂肪食は
・胆汁の分泌を過剰に刺激
・胆汁の成分バランスを崩す
可能性があります。
そのため
・バランスの取れた食事
・消化の良い食事
を与えることが重要。
後述の食事で気を付ける点を参考にしてください。
●適度な運動とストレス管理
適度な運動
は消化器系の働きを助けます。
ストレス
は体の様々なバランスを崩す要因。
心身の健康を保つこと
が間接的な予防に繋がります。
●適正体重の維持
肥満は様々な病気のリスクを高めます。
適正な体重を維持することは
・胆嚢
・肝臓
への負担を減らす上で重要です。
●基礎疾患の管理
・甲状腺機能低下症
・副腎皮質機能亢進症
(クッシング症候群)
・膵炎など
の基礎疾患があると
▶胆嚢炎のリスクが高まる
ことがあります。
これらの疾患がある場合は、適切に
・治療
・管理
することが重要です。
●十分な水分摂取
水分をしっかり摂ることで
▶胆汁をサラサラの状態に保つ
助けになります。
治療や処方される薬の例
治療は
・胆泥の量や性状
・症状の有無
・合併症の有無
によって異なります。
内科治療(薬物療法)
・症状が軽度の場合
・無症状の胆泥症の場合
定期的な経過観察(超音波検査など)
を行いながら、
・食事療法
・サプリメント
・薬物療法
による内科的管理を行います。
●ウルソデオキシコール酸(UDCA)
胆汁の流れを改善し
▶胆泥をサラサラにする作用
が期待できます。
また
・肝臓や胆管の保護
・免疫調整作用など
も報告されています。
人間の胆石溶解
にも用いられることがありますが
犬の胆泥を「溶かす」
というよりは
・胆汁の組成を変化させて流れやすくする
・胆泥の形成・沈殿を抑制する
イメージです。
ウルソデオキシコール酸は、単に胆汁をサラサラにするだけでなく
・胆嚢や胆管の上皮細胞を保護し
・炎症を抑える効果
も期待されています。
これは胆泥症に伴う
・胆嚢炎
・胆管炎
の管理において重要な側面です。
また胆汁酸のプール
※体内に存在する胆汁酸の総量
大部分が腸肝循環内に存在
を変化させることで
▶腸内細菌叢にも影響を与える
可能性が示唆されています。
【副作用や注意点】
副作用は比較的少ないとされています。
まれに下痢や嘔吐が見られます。
食事との兼ね合いとしては
・一般的に食事と一緒に
あるいは
・食後に与えること
が多いです。
吸収を妨げる可能性のある
制酸剤など
他の薬との飲み合わせには注意が必要です
●肝臓保護剤
●胆汁の流れを助けるサプリメント
直接胆泥をなくす薬ではありません。
・肝臓の機能をサポート
・胆汁の産生や流れを間接的に助ける
目的で使用されることがあります。
◇SAMe (S-アデノシルメチオニン)
・肝臓の代謝を助け
・抗酸化作用があります。
◇シリマリン (マリアアザミエキス)
・肝臓の保護
・再生を助ける効果
が期待されます。
【副作用や注意点】
どちらも副作用は少ないとされますが、体質に合わない場合もあります。
基本的に食事と同時に与えます。
◇消化酵素剤
・消化を助け
・胆嚢への負担を軽減する
目的で処方されることがあります。
【副作用や注意点】
基本的に食事と一緒に与えます。
◇抗生物質
・胆嚢炎
・胆管炎
を併発している場合に
細菌感染を抑える
ために使用されます。
【副作用や注意点】
・下痢
・嘔吐など
消化器症状が見られることがあります。
食欲不振の犬に
無理に与えると吐いてしまう
こともあります。
・少量のご飯に混ぜたり
・投薬補助おやつを使ったり
するなどの工夫が必要です。
◇鎮痛剤・制吐剤
・痛み
・嘔吐
がある場合に
症状を緩和する
ために処方されます。
●重度の合併症(胆嚢破裂、胆管閉塞など)がある場合
緊急性が高く、外科手術(胆嚢摘出術など)が必要になることがあります。
重要な注意点
ここで挙げたのは一般的な例であり
必ず獣医師の指示
に従って薬を与えてください。
・特定の体質
・持病を持つ犬
・他の薬を服用している犬
の場合
・副作用のリスク
・食事との兼ね合い
が異なることがあります。
外科治療
・胆泥が胆嚢全体を塞いでいる
(胆嚢粘液嚢腫の進行など)
・胆嚢破裂の危険性がある
・内科治療に反応しない重度の症状がある
場合などは
胆嚢摘出術(たんのうてきしゅつじゅつ)
という外科手術が選択されることも。
これは
胆嚢そのものを摘出する手術
犬は
・胆嚢がなくても
・胆汁を肝臓から直接十二指腸に流す
ことで生命維持が可能です。
しかし手術にはリスクも伴います。
ヒッポのごはんが重要視する栄養管理の3つの柱
胆嚢炎の管理において、食事療法は非常に重要です。
目標は
・胆嚢への負担を減らし
・胆汁の流れをスムーズにする
ことです。
1.低脂肪
胆嚢炎の食事管理において
脂肪の摂取量を適切に制限
することは最も重要です。
脂肪を消化するためには
▶大量の胆汁が必要となるため
高脂肪食は
▶胆嚢を過剰に刺激し
▶負担をかけてしまいます。
ヒッポのごはんでは
単に脂肪を減らすだけでなく
質と量を厳密にコントロール
しています。
基本的に
・鶏むね
・鹿肉
・白身魚など
脂質の少ないものを使用。
鮮度と料理法にこだわり
・質のいい脂質を
・適量摂取できるよう
バランスを整えます
●脂質代謝に注目
胆嚢炎は
脂質代謝の異常
と深いかかわりがあるため、
食事による脂質管理
が特に重要です。
この代謝異常が膵臓にも影響を及ぼし、
膵炎の併発リスク
があることにも注意が必要です。
そのため、ヒッポのごはんでは
中性脂肪を避けるため
・動物性脂肪を調整し
オメガ3脂肪酸など
・質の良い脂質で構成する
ことを徹底しています。
特に
酸化した脂質
は細胞にダメージを与えるため
・新鮮で
・酸化していない食材
のみを使用します。
2.消化の良いタンパク質
・高品質で
・消化吸収の良い
タンパク質を選ぶことは
・肝臓
・胆嚢
への負担を軽減する上で不可欠。
ヒッポのごはんでは
・鶏肉
・魚
・卵など
消化しやすい食材を厳選
して使用するだけではなく、他の肉も
麹熟成や低温調理
にすることで消化性を高めています。
これにより
・効率よくアミノ酸を吸収させ
・体づくりに必要な栄養素を補給
しつつ
・内臓への負担を最小限に抑えます。
また肉は
BCAA(分岐鎖アミノ酸)
を多めに摂取できるよう調整。
BCAAが不足すると
▶胆汁が濃縮される一因となる
可能性があるためです。
・鶏むね肉
・豚ヒレ
・鹿肉
・馬肉
・ラム肉
・サワラ
などを積極的に活用しています。
●肝臓負担への考慮
タンパク質が多すぎると、代謝の過程で肝臓に負担をかける可能性があります。
そのため、ヒッポのごはんでは
血液検査の肝数値
を見ながら、個体に合わせて
タンパク質の量を調整
しています。
3.適度な食物繊維
特に水溶性食物繊維は
・腸の働きを整える
だけでなく
・胆汁酸と結合して排泄を促すことで
▶コレステロールのコントロールを助ける
可能性があります。
・きのこ
・大麦
などを消化性も考慮しながら加えます
強化すべきと考える栄養素
●抗酸化物質
・ビタミンE、C
・セレン
・タウリンなど
・肝臓
・胆嚢
の炎症を抑え
▶細胞を保護する働き
が期待できます。
特にタウリンは犬の
胆汁酸の主要な構成成分です。
タウリンが不足すると
▶胆汁酸の合成がうまくいかず
▶胆汁の性状が変化する
可能性があります。
特定の犬種(アメコカなど)では
タウリン欠乏が
拡張型心筋症の原因となる
ことも知られていますが
胆泥症との関連
も示唆されています。
適切な量のタウリンを摂取することは、胆汁の健康を保つ上で重要と考えられます。
●ビタミンK
胆汁の流れが悪くなると
脂溶性ビタミンである
ビタミンKの吸収
が悪くなることがあります。
ビタミンKは
血液凝固に必要な栄養素
であるため、欠乏すると
▶出血傾向が見られる
可能性があります。
必要に応じてビタミンKを多く含む食材を検討します。
●卵黄コリン
細胞膜への
不要な脂肪沈着を防ぐ
働きが期待できる
卵黄
も積極的に活用します。
卵黄に含まれる
コリン
が、肝臓の脂質代謝をサポートする上で重要であると考えています。
控えるべきと考える栄養素
●高脂肪
最も注意すべき点です。
▶食材の脂質含有量を細かく計算し
▶過剰摂取にならないよう
徹底的に管理します。
・動物性脂肪だけでなく
・植物性油脂も
過剰摂取は控えるべきです。
●過剰な炭水化物
小麦グルテンなど
・消化に負担をかける炭水化物を避け
・消化吸収の良いものを適量使用
することで
・腸内環境
・脂質代謝
への悪影響を抑えます。
●食品添加物
ヒッポのごはんは
食品添加物を一切使用しません。
手作り食を検討する方へのメッセージ
胆嚢炎に対応した手作り食は
個々の犬の
・体質
・病状
に合わせて
・脂肪量
・栄養バランス
を調整する必要があり、厳密な管理が非常に難しいものです。
特に脂肪は目に見えにくい形で様々な食材に含まれています。
安易な自己流の手作り食は
・栄養不足
・栄養過剰
を引き起こし、病状を悪化させるリスクがあります。
市販食を選ぶ際も、成分表示の
「粗脂肪」
の項目を必ず確認しましょう。
一般的に成犬用フードの粗脂肪は
10~20%程度
ですが、胆泥症に対応した療法食は
10%以下
のものが推奨されることが多いです。
治療費の例
胆嚢炎の治療費は
・病状の進行度
・必要な検査
・治療内容
・入院の有無
・動物病院
によって大きく異なります。
◇初診料・再診料
数千円程度
◇血液検査
数千円~1万円程度
・肝臓の数値
・炎症マーカー
・コレステロール値
などを調べます
◇超音波検査
5千円~1.5万円程度
・胆泥の性状、量
・胆嚢の壁の状態
・胆管の拡張
などを評価します。
定期的な経過観察でも行われます。
◇X線検査
数千円
胆石の有無などを確認
◇薬代
数千円~数万円/月
・症状
・処方される薬の種類
・投与期間
によって大きく異なります。
◇入院費
数万円~十数万円
・症状が重い場合
・手術が必要な場合
◇手術費用(胆嚢摘出術など)
20万円~50万円以上
・合併症の有無
・手術の難易度
によって大きく異なります
飼い主さんがしてあげられること
胆嚢炎は
発見されることが多い
にも関わらず
その原因が特定できない
ケースが多い病気です。
しかし、だからといって飼い主さんが何もできないわけではありません。
・最も重要かつ
・飼い主さんだからこそできることは
「病気の早期発見と進行のモニタリング」
「獣医師の指示に基づいた日々のケア」
「愛犬の小さな変化に気づく観察力」
です。
無症状の胆泥症であっても
「放っておいて大丈夫」
ということではありません。
それが将来的に
・粘液嚢腫に進行しないか
・症状が出てこないか
注意深く見守っていく責任が飼い主さんにはあります。
●日々の観察
・食欲、元気
・嘔吐や下痢の有無
・お腹の張り
・排泄物の色
※黄疸が出ると
・おしっこの色が濃くなる
・便の色が薄くなる
などすることがあります
などを注意深く観察しましょう。
少しでも異常があれば、すぐに獣医師に相談してください。
●定期的な超音波検査
外から見えない
胆嚢の中の状態を知る
唯一の手段です。
検査を継続して行うことで
・胆泥の量や性質
・胆嚢の壁の状態
・周囲の臓器への影響
などを把握し、病気の進行を評価できます。
●ストレスを減らす
ストレスは
自律神経の乱れ
を引き起こし
消化器系の機能にも影響を与える
可能性があります。
・環境の変化
・騒音など
犬にとってストレスとなる要因をできるだけ取り除き、安心できる環境を整えてあげましょう。
●水分摂取を促す
いつでも新鮮な水が飲めるように
・複数の場所に水飲み場を設置
・ウェットフード
・水分を多く含む手作り食
(獣医師・専門家の指示のもと)
を取り入れたりするのも良いでしょう。
●獣医師との密な連携
胆嚢炎は
病状が急激に変化する
こともあるため
・定期的に動物病院を受診し
・獣医師の指示に従う
ことが何よりも重要です。
疑問な点や不安な点があれば遠慮なく質問しましょう。
●優しく触れてあげる
お腹の痛みを抱えていることもあるため
・優しく撫でてあげたり
・マッサージを取り入れたり
するのも
・リラックス効果
・血行促進
に繋がる可能性があります
※ただし、痛がっている場合は無理に行わない
●他の病気との関連を考える
前述のように、胆嚢炎は
・他の内分泌疾患
・代謝性疾患
と関連していることがあります。
胆嚢炎と診断されたら、全身の状態を把握するために他の検査も検討することがあります。
血液検査で注目すべき隠れたサイン
胆嚢炎の早期発見において
血液検査の数値
を詳細に読み解くことは非常に重要です。
胆嚢炎は
無症状で進行することが多い
ため
血液検査の軽微な変化
が唯一の早期サインとなることも珍しくありません。
・獣医師でも見逃しがちな
あるいは
・「様子を見ましょう」と言われがちな
わずかな数値の変化にも
▶飼い主さんが気づくことで
▶より早い段階で超音波検査などの精密検査へとつなげることができます。
注目すべき血液検査の項目と軽微な変化
胆嚢炎の早期発見:血液検査で注目すべき危険な兆候
胆嚢炎は
・胆嚢粘液嚢腫
・胆泥症
に併発することが多く、放置すると
胆嚢の破裂につながる
恐れがあるため、迅速な対応が求められます。
●1.炎症マーカー
炎症の有無を直接的に示す数値は、胆嚢炎を疑う上で最も重要な指標です。
◇白血球数(WBC)
胆嚢炎などを併発すると
▶白血球数が増加する
ことがあります。
軽度な炎症の場合
▶その上昇はわずか
なことも多いため
過去の数値と比較して
少しでも増加傾向
にある場合は注意が必要です
特に
好中球
という種類の白血球が増加傾向にある場合は要注意です。
・元気がない
・お腹を触られるのを嫌がる
などの臨床症状と合わせて判断することが重要です。
◇CRP (C反応性蛋白)
CRPは、体内で炎症が起きると
数時間〜24時間以内に急増する
非常に感度の高い炎症マーカーです。
近年は動物病院でも測定されることが増えましたが
まだ一般的でない
こともあります。
白血球数に大きな変化が見られなくても
CRPがわずかでも上昇
していれば、体内で
炎症が起きている明確なサイン
と捉えるべきです。
この数値の上昇は、胆嚢炎の超早期のサインとなる可能性があります。
●2.胆道系・肝臓関連の数値
胆嚢炎では
▶胆嚢の炎症による腫れが胆管を圧迫し
▶胆汁の流れが悪くなる
ことがあります。
◇ALP(アルカリホスファターゼ)
・肝臓
・骨
に存在する酵素で、特に
胆汁の流れが悪くなる
と上昇しやすい数値です。
正常範囲内であっても
前回の検査時よりも
数値が明らかに上昇している
場合は要注意です。
特に中高齢の小型犬では
加齢による生理的な上昇
と見なされがちです。
他の数値と合わせて慎重に判断する必要があります。
◇GGT(γ-GTP)
ALPと同様に
・胆管
・肝臓
に多く含まれる酵素で
胆汁うっ滞(胆汁の流れが滞ること)
を鋭敏に示します。
犬のGGTは通常、猫や人間よりも
かなり低い数値が正常
とされています。
そのため
わずかでも上昇が見られた場合は
・単なる個体差と判断せず
・胆汁の流れに異常がある可能性
を疑うべきです。。
◇ビリルビン(総ビリルビン)
胆汁が全く流れなくなってしまうと
▶ビリルビンが血液中に逆流し、
▶黄疸が現れます。
しかし、黄疸が出る前の
わずかなビリルビン値の上昇
も重要なサインです。
ビリルビンは
上昇に時間がかかる
ため、わずかな上昇でも
「胆汁の流れが滞り始めている」
と判断すべきです。
●3.併発疾患の可能性を示す数値
・胆嚢
・膵臓
は解剖学的に非常に近く
・胆嚢炎が膵炎を誘発したり
その逆で
・膵炎が胆嚢炎を引き起こしたり
することがあります。
◇アミラーゼ / リパーゼ
これらの数値は
膵臓の炎症
を示す指標です。
胆嚢炎の診断時
これらの数値が正常範囲内であっても
▶前回の検査時よりわずかに上昇している
場合は
膵臓にも炎症が波及し始めている
可能性を疑うべきです。
・胆嚢炎
・膵炎
を同時に治療する必要があるため、見過ごしてはならない数値です。
●4.コレステロール値と脂質代謝の数値
胆嚢炎は
脂質代謝の異常
と深く関わっているため
コレステロール値
も重要なヒントになります。
◇T-cho(総コレステロール)
血中のコレステロール総量を示す数値
高コレステロール血症は
ミニチュア・シュナウザー
などの特定の犬種で多く見られます。
これも
「犬種的なもの」
として見過ごされがちですが
・胆嚢炎
・胆嚢粘液嚢腫
・膵炎
・甲状腺機能低下症
などの基礎疾患が隠れている可能性があります。
数値の上昇が見られた場合は、他の病気と合わせて精査するきっかけと捉えるべきです。
◇TG(中性脂肪)
血液中の中性脂肪の量を示します。
コレステロールと同様、高値は
膵炎などのリスク
を示唆します。
食事療法で
▶低脂肪食を始めたにもかかわらず
▶数値が安定しない
場合は
・胆嚢炎の進行
・他の代謝異常
が原因である可能性を疑い、超音波検査を検討するべきです。
飼い主さんが心がけるべきこと
●「正常範囲内」でも見逃さない
検査結果が正常範囲内であっても
前回の検査時と比べて
数値に上昇傾向が見られる場合
必ず獣医師にその点を確認しましょう。
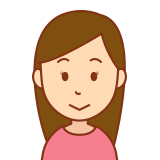
この数値の変化は、何か注意すべきサインではありませんか?
と積極的に質問することが大切です。
●定期的な超音波検査を習慣に
血液検査の数値に
軽微な変化でも見られたら
超音波検査
を組み合わせることを提案しましょう。
超音波検査は
・胆嚢内部の胆泥の有無や性状、量
・胆嚢壁の厚さ
などを直接確認できる唯一の方法です。
特に胆泥症になりやすいとされる犬種
・ミニチュア・シュナウザー
・シェットランド・シープドッグなど
は、定期的な超音波検査をルーティンにすることをお勧めします。
●総合的な判断の重要性
個々の数値だけでなく
・愛犬の年齢
・犬種
・体型(肥満の有無)
・普段の様子(食欲、元気、排泄など)
といった情報も合わせて総合的に判断することが重要です。
胆嚢疾患は、無症状の胆泥症であっても『放っておいて大丈夫』ということではありません。胆泥症が進行して
しかしこれは重篤な
胆嚢粘液嚢腫・胆嚢炎への進行リスク
を考慮すると、決して安全ではない。
・血液検査の数値のわずかな変化を捉え
・適切なタイミングで超音波検査
を行うことが愛犬の健康と命を守るための第一歩となります。
まとめ
犬の胆嚢炎は
はっきりとした症状が現れにくく
初期段階で発見されにくい病気です。
早期発見のためには
定期的な健康診断
が重要であり、診断された場合は
▶獣医師の指示のもと
・適切な食事療法
・薬物療法
・日々の丁寧なケア
を行うことで
・愛犬のQOL(生活の質)を維持し
・病気と上手に付き合っていく
ことが可能です。
不安なことは一人で抱え込まず、かかりつけの獣医師やヒッポのごはんに相談しながら、愛犬にとって最善の方法を見つけていきましょう。

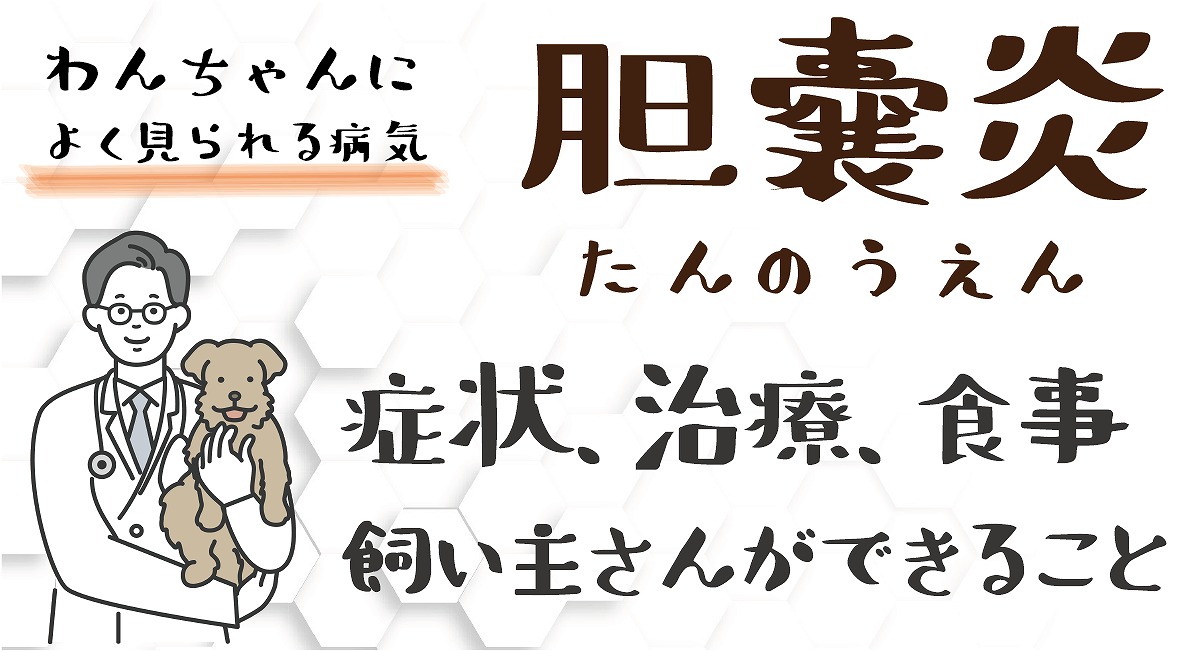
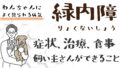
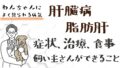
コメント