
うちの子…まさか…
愛犬の異変に気づいた時…
その正体が犬の糖尿病だとしたら…
糖尿病は、一度発症すると
完治しない
恐ろしい病気です。
しかし、本当に怖いのは
命に関わる合併症
が静かに進行すること。
そして、その初期サインが
・水をよく飲むようになった
・ご飯をほしがるようになった
というような、見過ごしてしまいがちな日々の変化の中に隠されていることです。

もっと早く気づいてあげられていたら…
と後悔する前に
・愛犬の小さな変化を見逃さず
・病気から守るために
飼い主さんが知っておくべきこと
は全てこの記事に詰め込みました。
あなたと愛犬の未来を守りましょう。
犬の糖尿病とは?
犬の体内では
インスリンというホルモンが
・食事から得た糖分(ぶどう糖)を
・細胞のエネルギーとして使えるよう働く
という非常に重要な役割を担っています。
なので、インスリンが
・不足したり
・うまく働かなくなったり
など十分に機能しなくなると
▶血液中に糖分が溢れてしまい
▶細胞は常にエネルギー不足
(=血糖値が高いままになってしまう)
に陥ります。
これが糖尿病です。
犬の糖尿病は、大きく2つのタイプに分けられます。
●1型糖尿病
膵臓からの
インスリン分泌がほとんどない状態。
犬の糖尿病のほとんどがこのタイプ。
●2型糖尿病
インスリンは分泌されているものの
その働きが不十分な状態。
犬ではまれです。
飼い主が気づくべき糖尿病のサイン
犬の糖尿病は
気づきにくい病気だと思われがち。
しかし普段の生活で
注意深く観察していれば
いくつかのサインが見られます。
1. 水を飲む量と尿の量の増加
高血糖状態が続くと、体は
▶増えすぎた糖を
▶尿として排出しようとします。
このとき
▶尿と一緒に大量の水分も排出
されるため
▶喉が渇き
▶水をたくさん飲むようになります。
それに伴い、おしっこの量も増えるのが典型的な症状です。
2. 食欲があるのに体重が減る
体内の細胞が
エネルギー不足に陥っているため
▶常に空腹を感じ
▶食欲が増します。
しかし…
せっかく摂取した栄養分が
▶うまく細胞に取り込まれない
ため、代わりに体内に蓄えられた
・脂肪
・筋肉
を分解してエネルギーにしようとします。
その結果
・食事量は増えているのに
・体重はどんどん減っていきます。
また、食べたい欲求が強くなるので
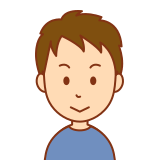
今までおやつに興味がなかったのに、急にしつこく欲しがるようになった
という行動の変化も警戒すべきサインです
3. 検査数値のわずかな変化
●血糖値のわずかな上昇
血糖値は
血液中のブドウ糖の濃度
を示す数値で
・食事や運動
・ストレス
によって変動します。
正常範囲内であっても
過去の健康診断と比べて
少しずつ上昇傾向
にある場合は、注意が必要です。
これは、膵臓が頑張って
▶インスリンを分泌
しているものの、次第に
▶機能が追いつかなくなり始めている
というサインかもしれません。
一度だけの測定では判断が難しいため
数ヶ月に一度の定期的な測定で推移を追うことが大切です。
特に毎回同じように
・食後ではない
・ストレスがない
一定条件の状態での測定がより正確な情報を与えてくれます。
●肝臓の数値(ALT、ALP)の上昇
・ALT
・ALP
は肝臓の状態を示す酵素の数値です。
糖尿病予備軍の犬では、これらの数値がわずかに上昇することがあります。
◇ALTの上昇
肝臓細胞の
・破壊
・炎症
を示します。
・肥満
・高脂肪食
によって引き起こされる
脂肪肝では
▶肝臓に脂肪が蓄積し
▶細胞がダメージを受けるため
▶ALTが上昇することがあります。
この脂肪肝は
インスリン抵抗性を高める
※インスリンが効きにくくなった状態
一因です。
◇ALPの上昇
・副腎皮質ホルモンの過剰分泌
・胆汁の流れが悪くなる
などで上昇します。
糖尿病との関連では、特に
クッシング症候群
を併発している場合にALPが顕著に上昇することがあります。
ALPの上昇は
体がインスリンを効きにくくしている
状態を示唆している場合があります。
これらの数値は
糖尿病そのものではなく
糖尿病を誘発・悪化させる
根本的な原因
を示している可能性があります。
●尿糖のごくわずかな検出
健康な犬の尿には、通常
糖は含まれません。
腎臓が糖分を再吸収するためです。
◇尿糖が検出される条件
血糖値が
腎臓の再吸収能力(腎閾値)
を超えるほど高くなった場合に
▶初めて尿に糖が混ざり始めます。
一般的に
犬の腎閾値は人間より高い
ため、尿糖が検出された時点で
すでに血糖値はかなり高い状態
にあることが多いです。
◇軽度でも要注意
尿検査で
ごくわずかながらも
糖が検出された場合は
すでに血糖値が高い状態
が続いている可能性が高いです。
これは、糖尿病が初期段階から進行し始めているサインと捉えるべきです。
これらの検査数値の変化は
愛犬の体内で
見えない病気が進行している可能性
を示唆する貴重な警告です。
獣医師と協力し、これらの数値を
継続的にモニタリング
することが、糖尿病の
・早期発見
・早期治療
につながります。
4. その他
糖尿病が進行すると、以下のような症状が現れることもあります。
#白内障による目の濁り
#糖尿病性ケトアシドーシスによる独特の甘酸っぱい口臭
#元気がなくなり、ぐったりする
#嘔吐や下痢
これらの症状が複数見られる場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。
糖尿病の原因と予防
犬の糖尿病は
・遺伝
・体質
だけでなく
飼い主さんの日々の生活習慣
が発症に深く関わっています。
適切な予防策を講じることで、愛犬の健康を守ることができます。
1. 肥満と高脂肪食
・高脂肪食
・過剰な食事は
▶犬の体内に脂肪を蓄積させ
▶インスリン抵抗性を引き起こす
大きな原因となります。
これにより
▶血糖値がコントロールできなくなり
▶糖尿病のリスクが高まります。
また高脂肪食は
▶膵臓に負担をかけ
糖尿病の原因となりうる
▶膵炎を誘発することもあります。
●予防策
◇適正体重の維持
・食事量
・運動量
を適切に管理し、肥満を防ぎましょう。
◇食事内容の見直し
脂肪分の多い食事は避け、バランスの取れたフードを選びましょう。
2. 運動不足
運動不足は
・肥満を招く
だけでなく
・インスリン抵抗性を高める
直接的な原因となります。
細胞が
糖分を効率よく利用できなくなる
ため血糖値が上昇しやすくなります。
●予防策
◇適度な運動
・毎日のお散歩
・遊びを通して
適度な運動を心がけましょう。
3. ホルモンバランスの乱れ
未避妊のメス犬は
発情期に分泌される女性ホルモン
エストロゲンが
▶インスリンの働きを弱めるため
オス犬に比べて
糖尿病になるリスクが2〜3倍も高い
とされています。
●予防策
◇避妊手術
繁殖の予定がない場合は
避妊手術
を行うことで
▶ホルモンの影響をなくし
▶糖尿病リスクを下げることができます。
4. 他の病気との合併症
糖尿病は
・クッシング症候群
・膵炎
と関連して発症することがあります。
これらの病気は、インスリンの
・働きを妨げたり
・分泌量を減らしたり
するため、糖尿病を誘発する引き金となります。
●予防策
◇定期的な健康診断
特に高齢の犬は
定期的に健康診断を受け
早期にこれらの病気を
・発見
・治療
することが大切です。
5. 低品質なフードに含まれる「AGEs」の危険性
・安価なドッグフード
・高温で加工されたジャーキー
・スナック類には
AGEs(終末糖化産物)
という物質が多く含まれていることも。
AGEsは、簡単に言うと
「体の焦げ付き」
「サビ」
のようなものです。
体内に余分な糖分があると
▶タンパク質と結びついて
▶AGEsが作られます
それだけではなく
食事からも直接摂取される
ことがあり、特に
・高温で調理された食品
・揚げ物
・焦げ付いた肉
・加熱処理されたジャーキーなど
に多く含まれています。
このAGEsが
▶体内に蓄積されると
・細胞を硬くする
・炎症を引き起こすなど
これによりインスリン抵抗性を高め
・糖尿病の発症
・糖尿病の悪化
を招く大きな要因となります。
さらに
・腎臓
・血管
・目のレンズ
などにもダメージを与え
・腎臓病
・白内障
といった深刻な合併症のリスク
を高めることも分かっています。
つまり
・良質な食材であっても
・不適切な加工がされていると
かえって愛犬の健康を損なう可能性があるのです。
●予防策
◇フードの選び方を見直す
・良質な原材料を使った
・高温調理されていない
フードや、場合によっては手作りごはん
を検討することで、AGEsの摂取を抑えることができます。
5.糖尿病にかかりやすい犬種
特定の犬種は
・インスリンの働きを妨げる体質
・膵臓に異常をきたしやすい
遺伝子を持つ可能性が指摘されています。
遺伝的に発症リスクが高い犬種として
・トイ・プードル
・ミニチュア・ダックスフンド
・ミニチュア・シュナウザー
・ミニチュア・ピンシャー
・ジャックラッセル・テリアなど
が挙げられます。
これらの犬種を飼っている場合は
・日頃から特に注意深く観察し
・定期的な健康チェックを心がける
ことが大切です
犬の糖尿病は
生活習慣を見直す
ことで予防できる部分が多くあります。
普段から愛犬の健康状態をよく観察し
・より良い食生活
・適度な運動
を心がけましょう。
犬の糖尿病が引き起こす「命の危険」
糖尿病は
単なる血糖値の問題
ではありません。
その本当の恐ろしさは
高すぎる血糖値そのもの
が犬の全身を蝕んでいくことにあります。
インスリンには
「血糖値を下げる」
ことと
「細胞にエネルギーを届ける」
という2つの重要な役割があります。
糖尿病ではこの
両方の働きが不十分になる
ため、犬の体は深刻なダメージを受けてしまいます。
放置すると
命に関わる複数の合併症
を引き起こす恐ろしい病気です。
1. 糖尿病性ケトアシドーシス:死に至る合併症
これは糖尿病の末期に発症することがある
最も危険な状態です。
細胞が糖分を
▶エネルギーとして利用できなくなると
体は代わりに脂肪を分解して
▶エネルギーを生み出そうとします。
このとき
ケトン体
という物質が大量に作られ
▶血液が酸性に傾いてしまうのです。
この状態になると、犬は
・強い脱水症状
・嘔吐、下痢
・アセトン臭(独特の甘酸っぱい口臭)を発し
さらに進行すると
▶昏睡状態に陥り
▶命を落とすこともあります。
ケトアシドーシスとケトーシスの違い
●ケトアシドーシス
糖尿病が重度に進行し
インスリンが極端に不足した状態
ケトン体が危険レベルまで増加した病態。
命に関わります。
●ケトーシス
糖質制限時など
生理的な範囲内
でケトン体が増加した状態。
この状態は健康な犬でも起こり得るものであり、特に問題はないとされています。
つまり、ケトン体は
「適度な量であれば有益なエネルギー源」
一方で
「過剰に増えすぎると危険な物質」
という、両極端な顔を持つことを理解しておくことが大切です。
2. 高血糖が招く直接的なダメージと合併症
血液中のブドウ糖が過剰な状態
=高血糖が続くと、ブドウ糖は
本来取り込まれるべきでない
・細胞
・組織
にも入り込み、様々な悪影響。
これが、多くの合併症を引き起こす
根本的な原因となります。
●白内障
ほぼ100%の確率で発症する視覚障害
犬の糖尿病で最も一般的な合併症です。
高血糖状態が続くと
▶目のレンズに糖分が蓄積され
▶白く濁ってしまいます。
発症から
わずか数ヶ月で失明に至る
ケースも少なくありません。
白内障は治療費が高額になることもあり、飼い主にとって大きな負担となります。
●高脂血症
高血糖は
▶脂肪の代謝にも悪影響を及ぼし
血液中の
・コレステロール
・中性脂肪
が増加する
高脂血症を招きます。
これは、後述する膵炎などの病気を引き起こすリスクを高めます。
●血管や神経の障害
・血管
・神経細胞
が高血糖によって傷つき
・腎臓
・肝臓
といった重要な臓器に慢性的な負担をかけ
▶機能不全を引き起こすリスクを高めます
また、高血糖状態では
▶免疫力が低下するため
膀胱炎などの
細菌感染症
にかかりやすくなります。
3. その他、臓器への影響と感染症
膵炎は
・糖尿病の原因にも
・合併症にも
なりうる密接な関係にあります。
・糖尿病が原因で高脂血症になり
▶それが膵炎を引き起こしたり
逆に
・膵炎がインスリン分泌細胞を破壊し
▶糖尿病を悪化させたり
することがあります。
消化器系では
・タンパク漏出性腸炎
・腸リンパ管拡張症
といった病気との関連も指摘されます。
糖尿病によるインスリン抵抗性は
▶腸の機能に影響を与え
・栄養の吸収不良
・タンパク質の漏出
を引き起こす可能性があります。
これらの病気を併発すると
・下痢
・体重減少
がさらに進行し、治療がより複雑になることもあります。
糖尿病の治療と注意すべきポイント
一度発症した糖尿病は
・完治が難しく
・生涯にわたる管理が必要となります。
治療は、主に
・インスリン注射
・食事療法
・輸液療法
を組み合わせるのが一般的です。
1. インスリン治療(注射薬)
犬の糖尿病は
「1型糖尿病」が大多数を占めます。
※膵臓からインスリンがほとんど分泌されない
このため
・インスリンそのものを
・体外から補給する
インスリン注射が治療の基本です。
●インスリンの2つの重要な役割
◇血糖値を下げる(血糖降下作用)
血液中のブドウ糖を
各細胞に取り込ませることで
▶高すぎる血糖値を正常な範囲に戻す
この働きは、高血糖による
細胞への直接的なダメージ
を防ぐ上で不可欠です。
◇細胞にエネルギーを供給する
ブドウ糖というエネルギー源を
・筋肉
・脂肪細胞
に運び、利用可能な形に変えます。
これにより、細胞は
活動するために必要なエネルギー
を得ることができます。
●インスリンの種類
インスリン製剤にはいくつかの種類があり
・犬の個体差
・ライフスタイル
に合わせて適切なものが選ばれます。
◇中間型インスリン
多くの場合、最初に選択されるインスリンです。
1日2回の投与で効果を持続させます。
◇持効型インスリン
作用時間が長く、1日1回の投与で済むケースもあります。
特に小型犬では
・大型犬に比べて体の代謝が速い傾向
・体重が軽いため、投与量がごくわずか
などの理由で
中間型インスリンの効果が短くなりがち
なので、このタイプが選択されることも。
・中間型インスリン
・持効型インスリン
の多くは、もともと
人間用に開発されたものです。
しかし犬と人間では
インスリンの作用時間
が異なります。
一般的に、犬は人間よりも
インスリンの作用時間が短いため
人間用の製剤を使うと
▶薬が効いている時間が短く
▶血糖値が不安定になりやすい
という課題がありました。
そこで開発されたのが
動物用インスリン製剤です。
◇動物用インスリン製剤
作用時間が犬や猫の生理に合わせてあり
血糖値の安定化に優れている
とされています。
これにより、日々の血糖コントロールが
▶より正確に行えるようになり
▶飼い主さんの負担軽減
にもつながっています。
●【インスリンの注意点】
インスリンを投与しすぎると
低血糖
を引き起こす可能性があります。
低血糖になると
・ぐったりしたり
・けいれんを起こしたり
最悪の場合は
・昏睡状態に陥る
こともあります。
もしこれらの症状が見られたら、すぐに
・ブドウ糖
・砂糖水
を口に含ませ、応急処置をしてから動物病院に連絡しましょう。
2. インスリン以外の治療薬
ヒトの糖尿病治療では
飲み薬
が広く使われています
しかし犬の場合、これまでの
経口血糖降下薬
はほとんど効果がないとされていました。
しかし、近年
新しいタイプの飲み薬
が登場し、注目を集めています。
●SGLT2阻害薬(例:センベルゴ®)
この薬は、従来のインスリン治療とは
全く異なるアプローチ
で血糖値を下げる薬です。
◇薬の作用機序
健康な犬の腎臓は
▶血液中のブドウ糖をろ過した後
▶SGLT2というタンパク質を使って
▶ほぼすべてのブドウ糖を体内に再吸収し
▶エネルギー源を失わないようにする
という大切な役割を担っています。
しかし、糖尿病で
高血糖状態が続くと
この再吸収の働きが
さらなる血糖値の上昇
を招いてしまいます。
SGLT2阻害薬は、このSGLT2の
糖の再吸収の働き
を意図的にブロックします。
その結果
再吸収されずに残った過剰なブドウ糖は
▶尿と一緒に体外へ排出され
▶血糖値を下げる
という仕組みです。
この薬は、インスリンの
・分泌量
・働き
に依存しませんが
細胞にブドウ糖を直接運ぶ作用はないため
インスリンがまだ分泌されている犬
※特に2型糖尿病に近い状態の犬
に効果が期待されます。
◇ケトン体が増加するリスク
薬の作用で
▶尿からブドウ糖が排出されると
▶体はエネルギー不足に陥り
代わりに
▶脂肪を分解してエネルギーを産生
しようとするため
▶副作用としてケトン体が増加し
糖尿病性ケトアシドーシス
を引き起こす可能性が高まります。
そのため、使用に際しては厳重なモニタリングが必要不可欠です。
この薬は
猫での使用が承認されたばかり。
犬への適用は獣医師の慎重な判断のもとで行う必要があります。
3. その他の治療
●輸液療法
・脱水症状
・糖尿病性ケトアシドーシス
などの場面では輸液療法で
・体内の水分
・電解質
のバランスを整えます。
●サプリメントによる補助
あくまでも治療の補助として
血糖値のコントロールを助けるサプリメントが使われることもあります。
・サラシア
・バナバ
・クロム
などの成分は
・血糖値の急上昇を抑えたり
・インスリンの働きを高めたり
する効果が期待されています。
ただし、これらのサプリメントは
・安全性
・効果
にばらつきがあるため、必ずかかりつけの獣医師に相談してください。
自己判断での使用は
血糖値が急激に下がりすぎる
などの危険を伴います。
絶対に避けましょう。
ヒッポのごはんでの栄養対策:糖尿病に配慮したごはんづくり
「ヒッポのごはん」では
・単に血糖値を下げるだけでなく
糖尿病にまつわる
・様々なリスクを総合的にケア
するため、以下の3つのコンセプトを大切にしています。
①血糖値の急激な上昇を防ぐ
食事後に
・血糖値が急激に上昇し
・その後急降下する
血糖値スパイク。
この急激な変動は
▶体に大きな負担をかけ
▶血管や臓器にダメージを与えます。
ヒッポのごはんでは
この血糖値スパイクを抑えるため
・低GI値の食品を厳選
さらに
・水溶性食物繊維
・難消化性炭水化物
を適切に配合することで
▶糖の吸収を緩やかにし
▶血糖値の安定をサポートします。
②健康な体重維持をサポート
・低脂肪
・高タンパク
な食材を厳選し、適正体重の維持を目指します。
③合併症のリスクを軽減する
・免疫
・腎臓
・肝臓
・眼
・腸など
糖尿病が影響を与えやすい各臓器の健康維持に配慮します。
これらのコンセプトを実現するため
ヒッポのごはんでは、愛犬の
・個々の症状
・検査結果
に合わせて、以下のようなきめ細やかな栄養対策を実践しています。
1. 糖質の質と量を厳密に管理する
糖尿病ケアの基本は
血糖値を上げやすい
糖質のコントロールです。
●高GI食品の徹底排除
血糖値を急激に上げる
・ブドウ糖や砂糖
・高GI食品(高GLになるような食品)
は基本的に使用しません。
●適切な食物繊維と炭水化物の選択
・満腹感を与えて過食を防ぎ
・血糖値の上昇を緩やかにする
働きを持つ
・食物繊維
・難消化性炭水化物
を適切に配合します。
ただし、野菜の食物繊維は
肝臓に負担をかけることもあるため、全体のバランスを考慮して調整します。
2. たんぱく質の質と量を慎重に調整する
たんぱく質は
・多すぎても
・少なすぎても
リスクがあります。
●たんぱく質量の調整
糖尿病により
血中のアミノ酸が増加している犬に
▶高たんぱく食を与えると
▶腎臓にさらなる負担をかける
可能性があります。
その一方
クッシング症候群を併発している犬は
▶ホルモン異常で
▶体内のたんぱく質が過剰に分解される
▶たんぱく質が不足しがちです。
ヒッポのごはんでは
・個々の症状
・検査結果
に合わせて、たんぱく質を中程度の範囲で調整します。
●高消化性へのこだわり
たんぱく質を効率よく吸収させるため
すべての肉や魚は
・麹熟成
・低温調理
といった工夫で、消化しやすい状態に仕上げています。
●インスリン分泌を助けるアミノ酸
・アルギニン
・BCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)
といった
インスリン分泌を助ける
と言われるアミノ酸を豊富に含む食材
・特定の肉類
・ヤギホエイプロテインなど
を厳選しています。
特にイソロイシンは、血中の糖を
筋肉に取り込むのを助ける
ため血糖値を下げる効果が期待できます
3. 脂質の管理と血中コレステロールのコントロール
糖尿病を抱える犬の多くは
高脂血症を併発し
それが膵炎などの原因になることも。
●低脂肪が基本
脂質は乾物換算で10%以下に抑えることを基本方針としています。
●良質な脂質
サチャインチオイルなど
・酸化しにくい油を選び
・オメガ3とオメガ6脂肪酸のバランスを重視します。
※通常よりもオメガ3脂肪酸の割合を高く調整
●コレステロール対策
特に卵黄に含まれるコリンは、
▶脂質代謝を改善し
▶血中コレステロールを低下させる
効果が期待できます。
それにより
▶細胞膜への不要な脂肪の沈着を防ぎ
▶細胞の活性化を促進します。
4. 腸の健康を優先的に考える
腸は
免疫細胞の約7割が集まる
最大の免疫器官です。
糖尿病下では
▶免疫力が低下し
▶感染症にかかりやすい
ため、腸の健康を維持することは非常に重要です。
●腸内環境の最適化
腸内環境が乱れると
▶せっかく糖質を厳密に管理しても
▶効果が薄れてしまう
可能性があります。
ヒッポのごはんでは
善玉菌のエサとなる
・プレバイオティクス
・発酵発芽玄米甘酒
・水溶性食物繊維など
直接善玉菌を補給する
・プロバイオティクス
・乳酸菌
・酪酸菌など
を適切に配合し、腸内環境を整えます。
また善玉菌は
▶腸内の余分な脂質や糖質をからめとり
▶吸収を抑える働きも期待できます。
5. 重要な栄養素の積極的な補給
糖尿病による体への負担を軽減するため、必要な栄養素を効率よく補給します。
●ミネラルのバランス
高血糖状態が続くと
腎臓が糖を排出しようとする
特殊な利尿作用が働き
▶ミネラルが体外に過剰に排出される
ことがあります。
※特に注意が必要なのは、カリウム、リン、マグネシウム
ヒッポのごはんでは、このミネラルバランスの崩れを考慮し、適切に補給します。
糖尿病による特殊な利尿作用によって過剰に排出される可能性があるミネラルは
◇カリウム
血糖値が高い状態が続くと
腎臓が浸透圧利尿により
糖を尿として排出しようとします。
この過程で
▶カリウムも一緒に体外に排出され
▶血中のカリウム濃度が低下する
可能性があります。
カリウムは
・神経
・筋肉
の機能に不可欠なミネラル。
不足すると
・筋力低下
・心臓の不整脈
などを引き起こす危険があります。
◇リン
糖尿病では
高血糖による腎臓への負担から
▶リンの代謝にも影響が出ることも
リンは
・骨
・歯
の健康に重要ですが、過剰になると
腎臓病を悪化させる要因
にもなるため、バランスの取れた補給が重要です。
◇マグネシウム
マグネシウムもまた、糖尿病による
尿量増加で失われやすい
ミネラルの一つです。
マグネシウムは
インスリンが細胞に作用する
のを助ける役割も担っているため
不足すると
インスリン抵抗性をさらに悪化させる
可能性があります。
ヒッポのごはんでは、これらの
ミネラルが豊富な食材
(例:葉物野菜、魚、特定の肉類)
をバランス良く配合。
特定のミネラルが
・過剰になったり
・不足したり
しないように配慮しています。
ただし、個々の犬の状態に合わせて
獣医師とも相談しながら栄養バランスを調整することが最も重要です。
●ビタミン補給
糖尿病の犬では、高血糖状態が続くことでビタミンB群が不足しやすくなります。
◇ビタミンB群の消費増加
正常な血糖値を保とうとして
▶体が必死に代謝を働かせるため
▶その過程でビタミンB群を大量に消費
◇吸収率の低下
糖尿病は腸の機能にも影響を与え
▶栄養素の吸収が悪くなり
▶ビタミンB群が十分に吸収されなくなる
ことがあります。
◇利尿作用による排出
糖尿病の犬は多尿になることが多いため
▶水溶性のビタミンB群が
▶尿と一緒に体外へ排出されやすくなる
また脂質制限も必要な場合
▶脂溶性ビタミンの吸収率が落ちる
ことがあります。
●抗酸化成分の配合
特に
・ブロッコリー
・ブロッコリースプラウト
に含まれるスルフォラファンは
細胞内にあるNrf2という抗酸化のスイッチをオンにすると言われています。
これにより、体本来の
「サビから守る力」
「毒素を排出する力」
が高まり
・高血糖による細胞のダメージ
・AGEsの蓄積
を減らす効果が期待できます。
●ブルーベリーの茎
特に糖尿病では重要視される食材。
・カテキン
・クロロゲン酸
・アントシアニン
といった複数の有用成分を含みます。
これらは
・血圧やコレステロールの調整
・体脂肪の燃焼
そして糖尿病の合併症である
・白内障のケア
にも役立ちます。
●関節ケアとインスリン
関節ケア成分として知られる
プロテオグリカンEは
インスリンの分泌を促進する
オステオカルシン
※若返りホルモンとも呼ばれる
の生成を助けると言われています。
●DPP-4の抑制
ヤギホエイプロテイン由来の
BCAAを含む生理活性ペプチドが
インスリンを分解する酵素である
DPP-4を抑制し
▶インスリンの働きを長持ちさせる
ことが研究で示唆されています。
6. 併発しやすい病気への特別な配慮
糖尿病は
複数の病気を併発することが多い
そのため
・個々の症状
・検査結果
に応じてレシピを調整します。
クッシング症候群の予防策
犬のクッシング症候群の85~90%は
脳下垂体の腫瘍が原因
と言われています。
特定の犬種では、
抗腫瘍を視野に入れた食材選び
を行うこともあります。
また、副腎皮質ホルモンは体内の
・水分
・電解質
・血糖値
などを調整するため、これが適切に機能しているかどうかも、食事内容を決定する上で重要な情報です。
膵炎の予防策
膵炎は、膵臓が炎症を起こす病気。
尿病の犬では
高脂血症から発症しやすいです。
●低脂肪食
膵臓への負担を減らすため
脂肪分を抑えた食事
を徹底することが最も重要です。
●適切な食事管理
一度に大量の食事を与えず
少量を複数回に分けて与える
ことで、消化器系への負担を軽減できます。
●コレステロールや中性脂肪の管理
定期的な血液検査で、血糖値だけでなく
・血中のコレステロール
・中性脂肪
の数値もチェックし、食事でコントロールします。
●ストレス軽減
ストレスは膵臓に影響を与えることがあるため、愛犬が安心して過ごせる環境を整えましょう。
タンパク漏出性腸炎・腸リンパ管拡張症の予防策
これらの病気は
腸の機能不全により
栄養素が腸から漏れ出す
※特にタンパク質
という病気です。
糖尿病によるインスリン抵抗性が
▶腸の機能に影響を与える
こともあります。
●低脂肪食
腸リンパ管拡張症は
リンパ管に脂肪が詰まってしまうことで悪化するため、
▶脂肪を厳しく制限する
ことが基本です。
●高消化性食
消化しにくい食材は
▶腸に負担をかけるため
・消化の良い食材を選び
・調理法も工夫する
ことが大切です。
●腸内環境の改善
・プレバイオティクス
・プロバイオティクス
を適切に補給し
▶腸内フローラを健康に保つことで
▶腸の機能をサポートします。
糖尿病性ケトアシドーシスの予防策
この重篤な合併症は
▶インスリン不足により体が脂肪を分解
▶ケトン体が過剰に作られる
ことで発症します。
●厳密な血糖値管理
獣医師の指示通りに
・インスリンを投与すること
定期的な血糖値測定で
・血糖値の変動を最小限に抑えること
が最も重要です。
●インスリン投与を怠らない
飼い主さんの判断でインスリン投与を
・中断したり
・量を減らしたり
しないようにしましょう。
●症状の早期発見
・食欲不振
・嘔吐
・ぐったりしている
などの初期症状に気づいたら、すぐに動物病院に連絡します。
口臭が甘酸っぱい臭い(アセトン臭)
になっていないか、日頃から確認することも大切です。
糖尿病の治療費の目安
糖尿病の治療は長期にわたるため、ある程度の費用がかかります。
以下はあくまで目安です。
◇初診・検査費用
1万円〜3万円程度
・血液検査
・尿検査など
◇インスリン代
月5,000円〜1万円程度
◇定期的な検査費用
月1回、数千円〜1万円程度
◇その他
・食事療法食
・合併症の治療費など
ペット保険に加入している場合は、補償内容を確認しておきましょう。
その他、飼い主ができること・注意すべきこと
●毎日の血糖値チェック
可能であれば、獣医師の指導のもと
自宅で血糖値を測定しましょう。
・インスリン投与量
・食事内容の調整
に役立ちます。
家庭で犬の血糖値を調べる主な方法は2つあります。
1. 血糖測定器(グルコメーター)による測定
これは人間用のものと同様に
・小型の測定器を使って
・少量の血液で
血糖値を測る方法です。
◇費用
#初期費用(測定器本体)
約3,000円〜1万円
#ランニングコスト(試験紙・針)
1回あたり数十円〜100円程度
◇メリット
・リアルタイムで血糖値が分かり
・費用が比較的安いです。
◇デメリット
毎回採血が必要なため
犬にストレスを与える可能性
2. 持続血糖測定器(CGM)の利用
これは、犬の体に
・専用センサーを装着し
・24時間血糖値を自動で測定する
方法です。
◇費用
#初期費用(装着・診察代)
約5,000円〜1万5,000円
#ランニングコスト
①センサー代
センサー1個(約14日間分)で約5,000円〜1万円
②センサー交換費用
約3,000円〜1万円
センサーは通常、2週間ごとに交換が必要となるため、継続して利用する場合は
その都度この費用がかかります
◇メリット
採血の必要がなく
犬にストレスがかかりません。
24時間分の血糖値の変動がグラフで分かり、夜間の低血糖も発見できます。
◇デメリット
・導入費用
・ランニングコスト
がやや高めです。
どちらの方法を選ぶかは
・愛犬の性格
・飼い主さんの負担
を考慮したうえで、獣医師との相談で決めるのが最も大切です。
●ストレスを減らす
ストレスは
血糖値を上昇させる要因の一つです。
・安心できる環境を整え
・穏やかな生活を送らせてあげましょう。
●複数の病気の可能性を考える
糖尿病は、クッシング症候群などの
他の病気と合併して発症
することがあります。
複数の病気が同時に発症
している可能性も念頭に置き、獣医師と密に連携を取りましょう。
糖尿病は治らない病気ですが
・適切な治療
・日々の管理
で愛犬との生活の質を高く保つことができます。
最も大切なのは
・飼い主さんが病気への理解を深め
・根気強く向き合っていくことです。

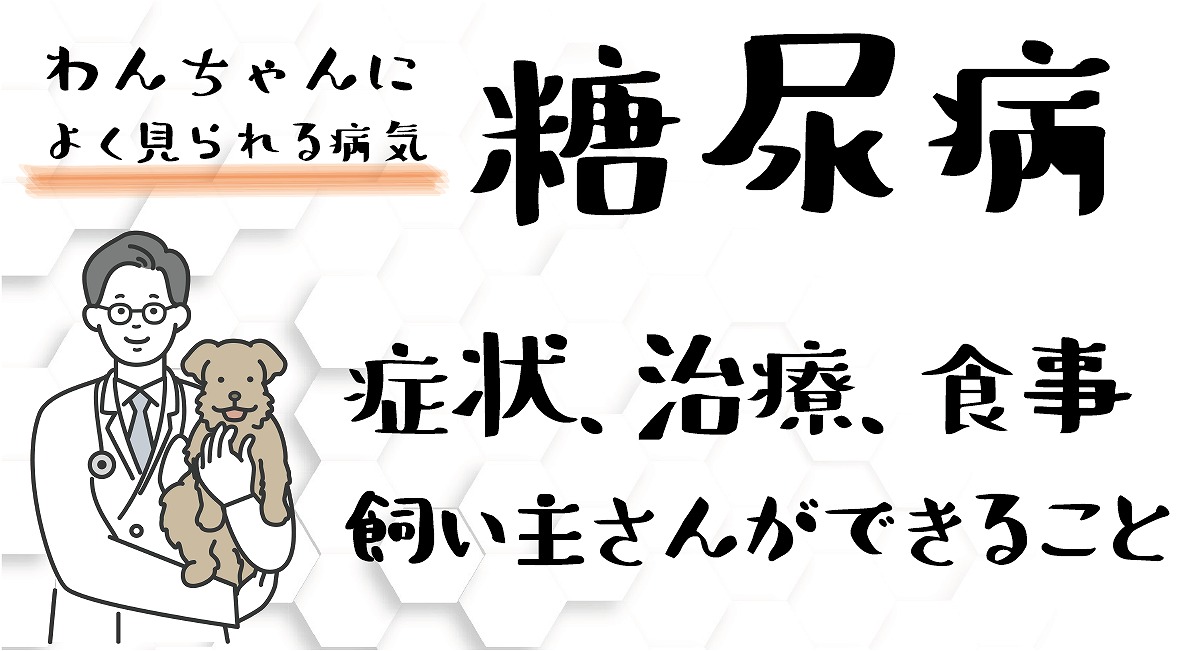
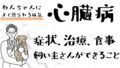

コメント