愛犬の「吠え」は
時に飼い主さんにとって
頭を悩ませる問題。
しかし、犬が吠えるのには
必ず理由があります。
その理由を理解し
▶適切な対策を講じることで
▶吠えの問題を解決へと導くことができます。
何よりも、愛犬が
「なぜ吠えているのか?」
を理解することが、問題解決への第一歩です。
なぜ吠える?まずは愛犬の行動を観察してみましょう

宅配便が来るたびに吠えまくり!配達員さんにも迷惑かけてしもてる…

来客のたびにケージに…それでも吠え止まへん…かわいそうやし、ストレスになってへんか心配。

仕事で家を空けてる時に、ご近所から『犬がずっと鳴いている』と苦情が来てしもた

見守りカメラ見たら、家を出た途端に吠え始めて、何時間も鳴き続けてる。仕事中も心配で気が気やないわ

自転車やバイクが通るたびに吠えて追いかけんねん。危なくてヒヤヒヤするわ

電線に止まっている鳥にまで吠えんねん。もう散歩がストレスやわ

私がキッチンに立つと吠え続ける。おやつをあげんと止まらへん

遊んでほしい時にクンクンクンクン鳴くねん。無視でけへんわ。
愛犬の吠えの理由を知るために
以下のチェックシートを参考に
愛犬の行動を注意深く観察
してみましょう。
●愛犬の吠え
【原因特定チェックシート】
以下の項目に当てはまるものがないか?
愛犬が吠えた時の状況を思い出してチェックしてみましょう。
◇吠える「時」と「状況」
吠えた時、どんな状況でしたか?
□おやつ
□散歩
□遊び
□構ってほしい時
▶要求吠え
何かを得るために吠えています。
吠えることで要求が通る
と学習している可能性があります。
□インターホン
□来客
□郵便配達員
□窓の外の人や犬
▶警戒吠え・縄張り吠え
・見知らぬ人や物
または
・自分のテリトリーに近づくもの
に対して
・警戒したり
・追い払おうとしたり
しています。
・不安
・恐怖
を感じている場合もあります。
□留守番中
□飼い主が見えない時
□姿が見えなくなった時
▶不安吠え・分離不安
飼い主がいないことへの
・不安
・寂しさ
から吠えています。
重度になると
分離不安症
の可能性があります。
□遊んでいる時
□飼い主が帰宅した時
□嬉しい時
▶興奮吠え・遊びの誘い吠え
・喜び
・興奮
の感情が抑えきれずに吠えています。
遊びに誘っている場合もあります。
□特定の場所を触られる
□特定の動作をする時
▶痛み・不調による吠え
体に
・痛み
・不調
がある可能性があります。
・関節炎
・怪我など
身体的な問題が隠れているかもしれません。
□退屈そうにしている時
□刺激が少ない時
▶退屈・欲求不満による吠え
・運動不足
・遊び不足
・精神的な刺激の欠如
などから、欲求不満を感じて吠えていることがあります。
□雷
□花火
□工事の音など
大きな音や聞き慣れない音
▶恐怖・不安による吠え
・大きな音
・慣れない音
に対して
▶恐怖を感じ
▶不安を訴える
ために吠えています。
◇吠え方と付随する「行動」
どんな吠え方?
あるいは
どんな行動をしていましたか?
□甲高く連続して吠える
□前足を上げて催促する
▶要求吠え
明確な要求がある場合に多い吠え方です。
□低く唸るように吠える
□毛を逆立てる
□体を硬直させる
▶警戒吠え・縄張り吠え
・威嚇
・防御
の姿勢を示しています。
・相手への強い警戒心
・自分を守ろうとする意識
の表れです。
□鳴き続ける
□破壊行動を伴う
□ソワソワする
▶不安吠え・分離不安
・精神的なストレス
・パニック状態
を示していることがあります。
□尻尾を振って飛びつく
□駆け寄ってきて吠える
▶興奮吠え・遊びの誘い吠え
・喜び
・興奮
を全身で表現しています。
□特定の場所を舐める
□震える
□食欲がない
▶痛み・不調による吠え
身体的な不調を示唆しています。
しつけで解決できないため
▶獣医の診察が必要です。
□遠くを見つめて低い声で「ワン」と鳴く
▶警告・合図の吠え
何か異常を発見し
▶飼い主に知らせようとしている
場合があります。
これらの情報を注意深く観察することで
愛犬がどのような
・感情
・要求
を持って吠えているのか、ヒントが見えてきます。
場合によっては動画を撮って
・後から見返す
・家族で情報を共有しする
のも有効です。
この記事では
▶犬が吠える主なタイプ別に
・具体的な対策
・しつけの方法
をすぐに実践できる内容に特化して詳しくご紹介します。
そのため前段階の
・基本的なしつけ
・犬の行動学に関する知識
は以下のリンク先をご覧ください。
1.「要求吠え」への対策としつけ
・おやつが欲しい
・散歩に行きたい
・構ってほしいなど
何かを要求するために吠えるのが
「要求吠え」
です。
対策の基本
徹底した無視と吠えても要求が満たされないことを学習させる
●吠えても一切応じない
吠えている間は
・目を合わせない
・話しかけない
・おやつをあげない
・遊ばない など
一切の反応を示さない。
これが最も重要です。
飼い主が少しでも反応してしまうと
犬は
吠えれば何らかの反応が得られる
と学習してしまい
吠えが強化
されます。
●「諦める」まで待つ
吠えが収まらず
▶愛犬がしつこく吠え続けても
要求が満たされない
ことを理解するまで無視を貫きます。
最初は
吠えがエスカレート
することもあります。
これは
「もっと強く要求すれば通るかも」
と試している状態です。
ここで応じてしまうと逆効果になります。
●吠え止んだ瞬間を逃さない
吠えるのをやめて
▶静かになった瞬間に
▶「よし!」と声をかけ
▶ご褒美を与えましょう。
最初は
一瞬でも静かになったら
▶すぐに褒めます。
この
静かになったら良いことがある
という経験を繰り返すことで
吠える必要がない
ということを学習します。
●吠える前に要求を察知し
先回りする
例えば
散歩の時間が近づくと吠え始める場合
吠え始める前に
▶「散歩に行こう」と声をかけ
▶静かに準備を始めるようにします。
ただし、これはあくまで吠えるきっかけを与えないための
予防策
であり、要求吠えの根治には
「無視」
が必須です。
要求する機会を減らす工夫
●食事の時間を決める
おやつの催促がひどい場合は
▶おやつの時間を決め
▶それ以外の時間は与えない
ようにします。
●遊びの時間を設ける
・毎日決まった時間に
・しっかりと遊んであげる
ことで
遊び足りない
という要求を減らすことができます。
●ご褒美を「稼がせる」
ただ与えるのではなく
「オスワリ」
「フセ」
などの簡単な指示に従えたら
▶ご褒美を与えるなど
愛犬が自ら行動して
「ご褒美を稼ぐ」
機会を作りましょう。
これにより、吠えるのではなく
指示に従うこと
で良いことが起こる、と学習します。
2.「警戒吠え・縄張り吠え」への対策としつけ
・見知らぬ人や犬
・物音
などに対し
警戒心から吠える
のが
「警戒吠え」
「縄張り吠え」
です。
対策の基本
安全だと認識させ、無駄に吠える必要がないことを教える
吠える対象からの距離と刺激をコントロールする
まず最も大切なのは
・愛犬が吠え始める前に
あるいは
・吠え始めてしまったらすぐに
吠える原因となっている対象から愛犬を遠ざけ、物理的に刺激を減らすことです。
●吠える対象から距離を取る
例えば散歩中に
・他の犬
・人
が見えたら
・吠え始める前にUターンする
・道の反対側に渡る
などして、距離を取りましょう。
興奮して吠え続ける場合は
・一時的に物陰に隠れる
もしくは
・その場から離れる
などして
愛犬が落ち着ける場所
へ移動させましょう。
インターホンに吠える場合は
・音量を下げる
・一時的に電源を切る
なども有効です。
●窓からの刺激を遮断する
窓から外が見えることで吠える場合
・遮光カーテンを引く
・目隠しになるものを置く
・すりガラスシートを貼る
などして
視覚的な刺激
を物理的に遮断しましょう。
網戸越しでも吠える場合は、窓を閉めることも検討してください。
吠えを未然に防ぎ、行動を切り替えさせる「指示」を使う
吠えそうになったら
▶愛犬の意識を飼い主に向けさせ
▶別の行動に切り替えさせる
練習をします。
●犬の意識を飼い主に向ける
吠える兆候
・耳が動く
・対象を見つめる
・唸り始めるなど
が見えたら
・すぐに愛犬の名前を呼ぶ
・軽く音を立てる
などして
愛犬の注意
を飼い主さんに向けさせましょう。
興奮している最中に
・名前を呼ぶ
・アイコンタクトを取る
などすると
・かえって吠えを助長する
・「吠える=飼い主が反応」と学習する
などの可能性があるので注意が必要です
●落ち着かせる指示を出す
愛犬が飼い主さんに意識を向け
・吠えるのを少しでもやめる
・一瞬でも静かになる
などの瞬間を逃さず
「ハウス」
「オスワリ」
「フセ」
など
愛犬が確実にできる指示
を出します。
指示に従えたら
▶すぐに「よし!」と褒め
▶ご褒美を与えましょう。
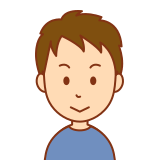
吠えても良いことはないけど、静かに指示に従ったら良いことがあるねんで
と教えてあげることが重要です。
「吠える必要がない」ことを学習させる
警戒吠えの原因となる状況で
▶愛犬が安心して静かにいられるように
練習を重ねましょう。
●来客時
来客がある際は、愛犬を
・クレート
・別の部屋
に移動させるなどして
物理的に吠えにくい状況
を作ります。
そこで静かにしていられたら
▶ご褒美を与え
▶褒めてあげましょう。
慣れてきたら
お客様に愛犬におやつをあげてもらう
など
・来客と
・「良いこと」
を結びつける練習も有効です。
ただし、この練習は愛犬が興奮しすぎないよう、慎重に進めましょう。
●散歩中
・他の犬
・人
に吠えずに通り過ぎられたら
▶大いに褒めて
▶ご褒美を与えましょう。
・その場で立ち止まって褒める
もしくは
・少し歩いてからご褒美をあげる
など愛犬にとって
最も効果的なタイミング
を見つけましょう。
「おすわり」
「待て」
などの指示で一度落ち着かせ
それができたらご褒美として
・おやつ
・おもちゃ
を使って刺激から意識をそらすなどの練習も有効です。
●音に対する慣れを作る
・インターホン
・特定の音
に吠える場合
その音自体に対する
ポジティブな関連付け
を行います。
例えば家族に
▶インターホンを鳴らしてもらう
▶鳴った瞬間に「おやつ!」と声をかけ
▶ご褒美を与えます。
最初は小さな音量から始め、徐々に音量を上げて練習しましょう。
3. 「不安吠え・分離不安による吠え」への対策としつけ
・飼い主の留守中に吠え続ける
・特定の状況下で不安から吠える
のが不安吠えです。
特に
分離不安
では、留守番中に深刻な問題となることがあります。
対策の基本
安全基地を作り、留守番に慣れさせる練習を段階的に行う
安全な場所の提供
=クレートトレーニング
犬にとって安心できる場所
・クレート
・ケージなど
を用意し、そこが
・安全で
・落ち着ける
場所であることを学習させます。
普段からクレートの中で
・食事をさせる
・おやつを与える
などして
ポジティブな印象
を与えましょう。
クレート内に
・タオル
・毛布
・飼い主の匂いのついた服
などを入れてあげると、より安心感が増します
段階的な留守番練習
最初から
長時間の留守番
に慣れさせるのではなく
ごく短時間から
少しずつステップアップしていきます。
●「一人」に慣れさせる練習
まずは
①飼い主が愛犬を一人にして
②数分間部屋を出て
③すぐに戻る
ことから始めます。
愛犬が吠えずにいられたら
▶すぐに戻って褒めてあげましょう。
慣れてきたら
部屋を出る時間を少しずつ
例えば
5分→10分→30分…
と延ばしていきます。
●「出発の合図」をなくす
・鍵を閉める音
・コートを着る
・カバンを持つなど
出発の合図
を日常の中で何度も繰り返します。
・これらの合図と
・「飼い主がいなくなる」
ことを関連付けさせないようにします。
例えば
・コートを着てすぐに脱ぐ
・鍵を鳴らしてすぐにしまう
など。
これにより、愛犬が飼い主の行動から
もうすぐ一人になる
という不安を感じにくくします。
●落ち着いた状態で出発・帰宅
出発時も帰宅時も
・犬が興奮している時には構わず
・落ち着いてから対応する
ようにしましょう。
出発時は
▶愛犬に背を向けて静かに出ていきます
帰宅時は
▶興奮して飛びついてもすぐに反応せず
愛犬が静かに落ち着いてから
・声をかけたり
・撫でてあげたり
します。
退屈させない工夫
●長時間楽しめるおもちゃ
留守番中に退屈しないよう
・コングにおやつを詰める
・知育玩具を与えるなど
長時間一人で楽しめるおもちゃを与えるのも有効です。
これらは
▶愛犬の集中力を高め
▶不安から意識をそらす
効果も期待できます。
●適度な運動
出かける前に
・十分な散歩
・運動
をさせて
体を疲れさせておくこと
も落ち着いて留守番できる助けになります。
4.「興奮吠え・遊びの誘い吠え」への対策としつけ
・嬉しい時
・遊びに誘う時
に興奮して吠えるのが
「興奮吠え」
「遊びの誘い吠え」
です。
対策の基本
興奮をコントロールし、落ち着かせることを教える
愛犬を「興奮させすぎない」工夫をする
・遊び
・飼い主の帰宅時など
愛犬が興奮しやすい状況
で飼い主が過度に刺激を与えないように工夫しましょう。
●遊びのペースと種類を調整する
・激しい追いかけっこ
・引っ張りっこ
ばかりではなく
・ボール探し
・ノーズワーク(嗅覚を使った遊び)
など
落ち着いて集中できる遊び
も積極的に取り入れましょう。
遊びの最中に愛犬が興奮してきたら
・一度おもちゃを隠す
・遊びを中断する
などして
▶クールダウンさせ
休憩を挟みましょう。
●声のトーンと動きを意識する
愛犬が興奮しやすい場面では
・高い声で大げさに褒めない
・激しく動き回ったりしない
などを意識しましょう。
・落ち着いた低い声で優しく話す
・自身の動きもゆっくりめにする
ことで、愛犬の興奮を抑えることができます。
●帰宅時の対応
帰宅した際に、愛犬が
・興奮して飛びついてくる
・吠える
などしても
すぐに構わない
ようにしましょう。
・目を合わせず
・声もかけずに
まずは自分の荷物を置くなど
飼い主自身が落ち着いた行動
をとります。
愛犬が
・落ち着いて座ったり
・静かに待っていられたり
するまで待ち
できたそのタイミングで
・優しく声をかけたり
・撫でてあげたり
しましょう。
最初は数秒でも構いません。
落ち着いたら良いことがある
ということを学習させることが重要です。
「落ち着かせる指示」を教え、行動を切り替えさせる
興奮している時に
落ち着いた行動を促すための指示
を教え、実践させます。
●指示によるクールダウン
興奮している時に
「フセ」
「マテ」など
愛犬が確実にできる指示を出して
▶行動を切り替えさせる練習をします。
指示に従えたら
▶すぐに褒めて
▶ご褒美を与えましょう。
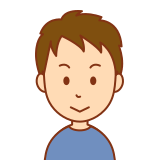
興奮するより、指示に従って落ち着いている方が良いことがあるよ~
と学習させます。
●吠え始めたら一旦中断
遊びの最中などに吠え始めたら
・遊びを中断する
・その場から離れる
などして
吠えると良いことがない
ことを学習させます。
愛犬が静かになったら
▶遊びを再開する
などして、良い行動を強化しましょう。
「落ち着いてから褒める」を徹底する
愛犬が興奮して
・飛びついてきたり
・吠えたり
する時ではなく
・落ち着いて座る
・静かに待っていられる
時にこそ
・褒めたり
・構ってあげたり
するように徹底しましょう。
●ポジティブな行動を強化
例えば
散歩に行く前に興奮して吠える場合
リードを持つ前に
▶「オスワリ」をさせ
▶それができたらリードを持つ
といったように
▶落ち着いた行動の後に
▶良いことが起きる
ように仕向けます
5.「痛み・不調による吠え」への対策
・特定の動作で吠える
・いつもと違う状況で吠える
などの場合は
・体の痛み
・不調
が原因である可能性があります。
対策の基本
獣医に相談する
すぐに獣医に相談
・いつもと違う吠え方や
・特定の場所を触ると嫌がる
・食欲がない
など
体調の変化
が見られる場合は
▶すぐに動物病院を受診してください。
・病気
・ケガ
が原因で吠えている場合は
しつけだけでは解決できません。
しつけの際の共通の注意点
●一貫性を持つ
家族全員で
・同じ方法でしつけを行い
・一貫した態度で接する
ことが重要です。
●忍耐強く、根気強く
しつけは一朝一夕にはいきません。
・犬の性格
・これまでの経験
によって改善には時間がかかることがあります。
焦らず、根気強く取り組みましょう。
●褒めて伸ばす
・犬が吠えずにいられた時
・落ち着いて行動できた時
は大いに褒めてご褒美を与えましょう。
ポジティブな経験を積み重ねることが、しつけの成功に繋がります。
●罰を与えない
吠えたことに対して
・怒鳴る
・体罰を与える
ことは絶対にやめましょう。
犬は
なぜ怒られているのか理解できず
▶かえって飼い主さんへの不信感を募らせる原因になります。
●専門家の助けを借りる

自力では解決が難しい
と感じた場合は
・ドッグトレーナー
・獣医行動学専門医など
専門家のサポートを積極的に利用しましょう。
愛犬の吠えは
犬からの大切なメッセージ
です。
そのメッセージを理解し、適切な方法でコミュニケーションを取ることで
・愛犬との絆を深め
・より快適な共生関係
を築くことができるでしょう。
吠えの改善には
時間がかかることもあります。
諦めずに続けること
が大切です。




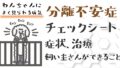
コメント