犬のレントゲン検査は、X線を利用して
▶体の内部を画像化し
▶様々な病気の診断に役立てる
重要な検査です。
・骨
・臓器
はX線の透過率が異なるため
▶白黒のコントラストで映し出され
▶肉眼では見えない体の内部の異常を発見することができます。
どんなときにレントゲン検査が行われるの?
獣医師がレントゲン検査を提案するきっかけは、主に以下のような状況です。
1. 愛犬の身体に異常が見られる時
●咳や呼吸困難
・呼吸器
・心臓
に問題がある可能性がある場合に
・肺や気管
・心臓の大きさ
を確認するために行われます。
●歩き方がおかしい、足を痛がる
・骨折
・脱臼
・関節炎
・椎間板ヘルニアなど
骨や関節に異常がないか
を調べるために行われます。
●嘔吐、食欲不振、排便・排尿の異常
・腸閉塞
・異物の誤飲
・内臓の腫大
・尿路結石など
消化器や泌尿器の異常を疑う場合
に腹部のレントゲンを撮影します。
●お腹が膨らんでいる
・腹水
・臓器の腫大
・腫瘍の有無など
を確認するために行われます。
●体のしこりや腫れ
骨の腫瘍など
体の内部にできたしこりの状態
を確認するために行われます。
2. 誤飲・誤食の疑いがある時
犬が
何かを誤って飲み込んでしまった
可能性がある場合。
X線に写る異物(金属、石など)が
・胃や腸のどこにあるのか
・閉塞を起こしていないか
を確認するために緊急で検査が行われることがあります。
3. 健康診断の一環として
特に
・シニア期に入った犬
・特定の犬種(大型犬など)では
病気の早期発見のために健康診断で
定期的なレントゲン検査
が提案されることがあります。
・心臓病
・股関節形成不全など
外見からはわかりにくい病気を早期に発見する目的で行われます。
4. 繁殖の目的で
妊娠している犬の場合
▶出産前にレントゲンを撮影して
・胎児の数や大きさ
・位置
を確認し、難産の可能性を判断するために行われます。
獣医師がレントゲン検査を提案する理由は?
獣医師は
・問診
・触診
・聴診
といった身体検査の結果から
より詳しい情報を得るために
レントゲン検査を提案します。
●病気の絞り込み
咳の原因が
・心臓なのか?
・呼吸器なのか?
を区別するなど
症状から疑われる複数の病気の中から
原因を絞り込むことができます。
●病変の特定
・異物の場所
・骨折の程度など
病変の位置や状態を正確に把握
することで
▶その後の治療方針を立てる上で不可欠な情報が得られます。
●治療計画の立案
・手術の必要性やその方法
・投薬治療の効果判定など
治療の計画を立てるために役立ちます。
このように、レントゲン検査は
▶犬の体の内部の状態を画像で確認し
・正確な診断
・適切な治療方針の決定
に欠かせない検査です。
愛犬の様子がおかしいと感じたら、早めに動物病院を受診し、獣医師に相談することが大切です。
レントゲン検査でわかる主な病気や状態
レントゲン検査でわかる
・主な病気
・状態は
撮影する部位
によって以下のように分けられます。
1. 骨や関節の異常
●骨折、脱臼、ひび割れ
・骨の断裂や変形
・関節のずれ
などを明確に確認できます。
●関節炎、股関節形成不全
関節の状態を評価し
・炎症
・形成異常の有無
を診断します。
●骨腫瘍
骨にできる腫瘍の
・有無
・状態
を確認します。
●椎間板ヘルニア
脊椎(背骨)の異常を確認し、神経疾患の原因を絞り込むことができます。
●成長期の骨の発育状況
成長期の犬の骨の発達が正常かを確認します。
2. 胸部・呼吸器系の異常
●心臓病(心肥大など)
心臓の
・大きさ
・形
を調べ、心臓病の診断に役立ちます。
特に、咳や呼吸困難の原因が
・心臓にあるのか?
・呼吸器にあるのか?
を区別する上で重要です。
●肺炎、肺気胸
・正常な肺は空気が多いため
▶黒く映りますが
・肺炎を起こすと
▶白っぽく見えます。
●気管虚脱
呼吸器系の異常を確認します。
●胸水、胸部の腫瘤
胸腔に
・水が溜まっていないか?
・腫瘍がないか?
を確認します。
3. 腹部・消化器系の異常
●異物の誤飲・誤食
・胃や腸の中に異物がないか?
・ある場合はその場所を特定できます。
特に
・金属
・石など
X線に映るものを食べてしまった場合に非常に有用です。
●腸閉塞、胃拡張
腸や胃が
・詰まっていないか?
・膨張していないか?
などを確認します。
●腹水
お腹の中に水が溜まっていないか?
を確認します。
●臓器の腫大
肝臓や脾臓、腎臓などの臓器が
・腫れていないか?
・異常な形をしていないか?
を確認します。
●尿路結石、胆石
・膀胱
・胆のうに
結石がないか?
を確認できます。
4. その他
●腫瘍
骨や臓器の腫瘍の
・有無
・形
・大きさ
などを確認します。
●妊娠の確認
妊娠している場合
・胎児の数
・発育状態
を把握することができます。
●口腔内の異常
・歯周病の進行具合
・抜歯の必要性
などを、歯の根元まで含めて確認します。
レントゲン検査の限界と他の検査との組み合わせ
レントゲン検査は
体の構造的な異常を捉える
のに優れています。
しかし病気の確定診断には
他の検査と組み合わせること
が一般的です。
●超音波(エコー)検査
・臓器の内部構造
・血流などを
リアルタイムで詳しく見る
のに適しています。
●血液検査、尿検査
・臓器の機能
・炎症の有無
などを数値で確認します。
●CT/MRI検査
より精密な立体画像を撮影し
・腫瘍
・神経疾患
などを詳しく調べることができます。
これらの検査を組み合わせて行うことで、より正確な診断が可能になります。
愛犬に気になる症状がある場合は
▶かかりつけの獣医師に相談し
▶適切な検査を受けることが大切です。
レントゲン検査の安全性と最新技術
レントゲン検査で用いられる
放射線量は
診断に必要な最小限の量に抑えられおり、通常の使用では
犬の体に悪影響を及ぼすことは極めて稀。
獣医療における放射線検査は
・診断による利益が
・リスクを大きく上回る
と判断される場合に行われます。
デジタルレントゲン(CR・DR)の普及
近年、多くの動物病院では
フィルムではなく
デジタル画像で撮影する
デジタルレントゲンシステム
が導入されています。
これには以下のメリットがあります。
●少ない被曝量
デジタル化により、
・従来よりも少ない放射線量で
・鮮明な画像を得る
ことが可能になりました。
●迅速な画像表示
撮影後
すぐにモニターで画像を確認
できるため、検査時間が短縮されます。
●画像処理
・明るさ
・コントラスト
を調整することで、診断の精度が向上。
●画像の共有
データを簡単に
・保存
・共有
できるため、専門医への相談がスムーズ。
愛犬のレントゲン検査について
不安な点があれば
▶かかりつけの獣医師に遠慮なく相談し
▶納得した上で検査を受ける
ことが大切です。
レントゲン検査をもっと知りましょう
1. 検査前の準備と注意点
●麻酔・鎮静の必要性
多くの犬は
短時間のレントゲン検査であれば
麻酔なし
で実施できます。
しかし正確な画像を撮るために
・動いてしまう犬
・痛みを伴う部位の検査
・精密な検査(股関節の評価など)
などでは
・鎮静剤
・麻酔
が必要になる場合があります。
これにより
・犬へのストレスを減らし
・安全かつ正確な検査
が可能になります。
獣医師と相談し、愛犬の状態に合わせて最適な方法を決めましょう。
●絶食の指示
腹部の検査の場合
・食べ物
・ガス
が画像診断の妨げになることがあります。
そのため
検査前には絶食
の指示が出ることがあります。
・絶食時間
・飲水の制限など
獣医師の指示に必ず従ってください。
2. レントゲン画像の見方
レントゲン画像は
専門知識
がなければ正確な判断は難しいですが
基本的な見方を知っておく
ことで、獣医師の説明をより深く理解できます。
●白く映るもの
X線を透過しにくい物質
は白く映ります。
・骨
・金属(誤飲したおもちゃなど)
・尿路結石
・腫瘍
などが該当します。
●黒く映るもの
X線を透過しやすい物質
は黒く映ります。
・肺や胃腸などの空気やガス
・脂肪
などが該当します。
●灰色に映るもの
・筋肉
・臓器
・液体などは
X線の透過率が中間であるため
様々な濃淡の灰色で映ります。
3. 費用について
●費用の目安
レントゲン検査の費用は
・撮影枚数
・撮影部位(胸部、腹部など)
・鎮静剤の使用の有無
・動物病院
によって異なります。
一般的には1回の撮影で数千円から1万円程度が目安となります。
●保険の適用
ペット保険に加入している場合。
レントゲン検査の費用も補償対象となることが多く、事前に保険会社に確認しておくと安心です。
4. レントゲン検査で「わからない」こと
レントゲン検査は万能ではありません。
以下のようなケースでは、他の検査が必要になります。
●軟部組織の内部構造
肝臓や腎臓などの
臓器の内部にできた
・小さな腫瘍
・嚢胞(のうほう)などは
レントゲンだけでは見つけにくい
場合があります。
この場合は
超音波(エコー)検査
が非常に有効です。
●早期の病変
・骨折のごく初期のひび割れ
・炎症の初期段階など
ごくわずかな変化は画像に現れないことがあります。
●血管や血流
・血管の異常
・血流の状態は
レントゲンでは判断できません。
これらは超音波検査で確認することが一般的です。
5. 検査後のフォローアップ
●画像の説明
検査後、獣医師は
撮影したレントゲン画像を見せながら
愛犬の状態について説明してくれます。
わからないことがあれば遠慮なく質問しましょう。
●治療計画
レントゲン検査の結果に基づいて
今後の治療方針
・内科的治療
・外科手術など
が立てられます。
獣医師の提案に納得し、飼い主さん自身が治療に積極的に関わることが重要です。
まとめ
愛犬のレントゲン検査は
・病気の早期発見
・正確な診断
に不可欠なツールです。
不安に思うことがあれば
▶かかりつけの獣医師に相談し
▶納得した上で検査を受ける
ことが大切です。
デジタルレントゲンの普及により
・より少ない負担で
・迅速かつ精度の高い検査
が可能になっています。
愛犬の健康を守るために
レントゲン検査がなぜ必要か?
を理解し、獣医師と協力して最適な治療を選んでいきましょう。


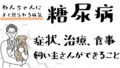
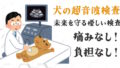
コメント