犬のケンネルコフは
単なる「犬の風邪」
と侮れない
・多様なウイルス
・細菌の混合感染
によって引き起こされる呼吸器疾患です。
特に
・子犬や高齢犬
・免疫力の低い犬
では重症化するリスクも伴います。
このガイドでは
・ケンネルコフの基本情報
・ヒッポのごはんを活用した食事管理
・治療や予防に関する最新情報
まで、愛犬の健康を守るための具体的なアドバイスをご紹介します。
ケンネルコフとはどんな病気か?
ケンネルコフは、正式には
犬伝染性気管気管支炎
と呼ばれ
・ウイルスと
・パラインフルエンザウイルス
・アデノウイルス
・ヘルペスウイルスなど
・細菌が
・ボルデテラ
・ブロンキセプティカなど
単独または複合的に感染
することで発症します。
犬が多く集まる場所、例えば
・ペットホテル
・ドッグラン
・動物病院の待合室
などで感染が広がりやすいことから
ケンネル(犬舎)
という名前がついています。
ケンネルコフは
単一の病原体
によって発症することもあります。
しかし多くの場合は
複数の病原体が関与する
多因子性
の疾患である点が重要です。
特に注意すべきは
・単一の病原体による感染
で症状が出たとしても
・他の病原体が二次感染を起こす
ことで症状が悪化しやすい点です。
多くの場合
まずウイルス感染によって
▶気道粘膜がダメージを受け
▶そこに細菌(ボルデテラなど)が二次感染
▶症状が悪化
この「複合的な感染」が
・診断
・治療
を複雑にする要因の一つです。
また、病原体によっては
感染しても発症しない
不顕性感染
の犬も存在し
自覚症状がないまま感染源となる
可能性もあります。
これは見た目には元気な犬でも
▶知らず知らずのうちに
▶ウイルスを拡散している
可能性があることを意味します。
ケンネルコフの主な症状
ケンネルコフの主な症状は、特徴的な咳に見られます。
●激しい咳
「カッカッ」
「カハッカハッ」という
・何かを吐き出すような
あるいは
・喉に何かが引っかかったような
乾いた咳
が特徴です。
時に
えずくような動作
を伴うこともあります。
●鼻水・くしゃみ
初期は
・透明な鼻水
が出ることが多いですが
二次感染があると
・粘り気のある鼻水
・膿性の鼻水
に変わることもあります。
●元気・食欲の低下
軽症であれば見られないことも
▶重症化すると
・元気がなくなり
・食欲も低下する
ことがあります。
●発熱
軽度な発熱が見られることもあります。
●結膜炎
・目やに
・目の充血
が見られることもあります。
飼い主さんがケンネルコフを疑うきっかけとなることが多いのが
その独特な咳の音です。
「ケンネルコフ特有の咳」
と表現されるほど特徴的で
・散歩中
・水を飲んだ時
・興奮した時
に発作的な咳が出たり
・喉を軽く触るだけ
で咳が出やすくなる傾向があります。
ケンネルコフを予防するためには?
ケンネルコフの予防には、以下の点が重要です。
●ワクチン接種
・パラインフルエンザウイルス
・アデノウイルス
・ボルデテラ・ブロンキセプティカ
に対する
混合ワクチン
が有効です。
特に
・ドッグラン
・ペットホテル
・しつけ教室など
犬が多く集まる場所
に連れて行く予定がある場合は
▶接種を強く検討しましょう。
鼻腔内投与型のワクチンもあります。
確かにワクチン接種はケンネルコフの予防に非常に有効です。
しかし
すべての病原体
に対応しているわけではありません。
※ヘルペスウイルスは混合ワクチンに含まれない場合が多い
また、ワクチンを接種していても
・体調が優れない
・多くの病原体に同時に曝露された
場合には発症することもあります。
これは、人間のワクチンと同様
「発症を完全に防ぐ」
というよりも
「症状の重症化を防ぐ」
という側面が強いことを理解しておく必要があります。
●感染源との接触を避ける
・感染が疑われる犬
・咳をしている犬
との接触は避けましょう。
・ドッグラン
・ペットホテル
を利用する際は
・施設の衛生管理
・体調不良の犬の利用制限の有無
を確認することも大切です。
●免疫力の維持
・栄養バランスの取れた食事
・適度な運動
・十分な休息
は愛犬の免疫力を高め
▶病気にかかりにくくします。
●ストレス軽減
ストレスは
免疫力を低下させます。
そのため愛犬が
安心してリラックスできる
環境を整えてあげましょう。
ケンネルコフの治療や処方される薬の例
ケンネルコフの治療は
・原因となっている病原体
・症状の重さ
に応じて異なります。
●対症療法
・咳を抑える鎮咳剤
・リン酸コデイン
・デキストロメトルファンなど
・炎症を抑える消炎剤
が処方されることがあります。
●抗菌薬
・細菌感染が疑われる場合
・二次的な細菌感染を予防する
という目的で
抗生物質
・ドキシサイクリン
・アモキシシリン
・クラリスロマイシンなど
が処方されます。
●去痰剤
痰を出しやすくする目的で処方されることがあります。
●ネブライザー治療
呼吸器に直接薬を届けるために
ネブライザー=吸入器
による治療が行われることもあります。
特に
・症状が重い場合
・高齢犬
などでは効果的です。
獣医師によっては
単なる対症療法だけでなく
・免疫力を高めるサプリメント
・乳酸菌
・ベータグルカンなど
・ハーブ療法
を併用することを提案することも。
また、軽症の場合には
・加湿器の使用
・安静にさせる
ことで、自然治癒を待つこともあります。
獣医さんと相談し、愛犬に合った治療法を選択することが大切です。
その薬の副作用や食事との兼ね合い
処方される薬には、それぞれ
副作用のリスク
があります。
●鎮咳剤
・眠気
・便秘
・嘔吐
などが見られることがあります。
●抗生物質
・嘔吐
・下痢
などの消化器症状が最も一般的です。
◇ドキシサイクリン
食道に貼りつき
潰瘍
を起こす可能性があるため
・必ず多めの水と一緒に飲ませる
・食後に与える
必要があります。
また
・乳製品
・カルシウムを多く含む食品
と一緒に与えると吸収が阻害されることがあります。
◇アモキシシリン
比較的副作用が少ないです。
稀にアレルギー反応を起こすことがあります。
特に抗生物質を使用する際には
腸内細菌のバランス
が崩れることがあります。
そのため、獣医師の指示に従って
プロバイオティクス
(乳酸菌などの善玉菌)
を併用することで、下痢などの
消化器症状を軽減
できる場合があります。
薬によっては
食事の有無で吸収率が変わる
ものもあるため、獣医師から指示された通りに与えることが非常に重要です。
自己判断で
・投薬を中止する
・量を変更する
などは絶対に避けましょう。
ヒッポのごはんの工夫:ケンネルコフからの回復をサポート
ケンネルコフにかかった愛犬の食事は
・体力回復
・免疫力維持
の鍵となります。
ヒッポのごはんでは、この時期の犬に最適なごはんをご提案しています。
ヒッポのごはんの工夫:回復期の愛犬をサポート
愛犬がケンネルコフにかかった際
・食欲が落ちたり
・消化器が敏感になったり
することがあります。
ヒッポでは、これらの状況に対応できるよう、以下の点を重視してごはん作りをしています。
●消化の良い食事
食欲が低下している愛犬のために
・消化吸収に優れた食材を厳選
・さらに消化に考慮した調理
をしています。
例えば
・鶏むね肉
低脂肪で良質なタンパク源として使用
▶麹で熟成させてさらに消化性アップ
・玄米
そのままではなく
▶甘酒にして消化性と栄養価のアップ
などしたものをバランス良く配合。
また、必要に応じて
水分を多く含んだスープ仕立て
にするなど
・食感
・形状
も調整できます。
●積極的な水分補給
脱水は体力消耗を招くため
・スープ
・水分
を多く含むよう
料理の仕方を調整
することで、自然な形で水分補給ができるように工夫しています。
ごはん自体に適切な水分量を含ませ
▶飲み水をあまり飲まない愛犬でも
▶食事を通して効率的に水分を摂取できます。
●高栄養価で体力回復をサポート
ケンネルコフに特化した療法食というものはありません。
ヒッポのごはんは、病気からの回復に必要な高栄養価を重視しています。
愛犬の
・現在の体調
・年齢
・基礎疾患など
を考慮し、個別のレシピを作成。
元気を取り戻すためのエネルギー源をしっかりと補給できるよう、栄養バランスを最適化します。
●消化器への負担を最小限に
ケンネルコフで体が弱っている時期には
消化器に負担をかけない
よう注意が必要です。
そのため、ヒッポのごはんでは
・高脂肪食
・アレルギーの原因となりやすい食材
は避けることを基本としています。
これにより、回復期にある愛犬の
▶消化器系への負担を最小限に抑え
▶スムーズな回復を促します。
●腸内環境を整え免疫力の回復
消化器に負担をかけないと同時に
・プロバイオティクス
・プレバイオティクス
を摂取できるように設計。
免疫の7割を担うと言われる
腸の健康を整えます。
ヒッポのごはんで強化する栄養素
ヒッポのごはんでは、
・愛犬がケンネルコフと闘い
・回復するための体作り
をサポートするため、特定の栄養素を意識的に取り入れています。
●良質なタンパク質
・免疫細胞の生成
・組織の修復
に不可欠な
良質なタンパク質
・低脂肪の鶏肉
・消化しやすい白身魚など
を豊富に使用しています。
これは
・体力の回復を助け
・免疫機能の維持に貢献します。
●抗酸化作用のあるビタミン
・ビタミンC
・ビタミンE
・ポリフェノール
といった
抗酸化作用
を持つビタミンは
・体の酸化ストレスを軽減し
・免疫機能のサポートに役立ちます。
ヒッポのごはんでは、これらを豊富に含む
・野菜
・ブルーベリー茎など
自然な形でこれらの栄養素を供給します。
●免疫を支える栄養素
亜鉛
は免疫機能に深く関わる重要なミネラル。
手作りごはんでは不足しがちですが、
ヒッポのごはんでは
亜鉛を含む食材をバランス良く配合
愛犬の免疫システム
を内側から支えます。
その他免疫細胞を活性化させると言われる
βグルカン(きのこ・大麦など)
にも注目しています。
●抗炎症作用を持つオメガ3脂肪酸
炎症を抑える働きがある
オメガ3脂肪酸
・新鮮な魚からDHA・EPA
・サチャインチオイルなど
も積極的に取り入れています。
これは
▶ケンネルコフによる気道の炎症を軽減し
▶愛犬の不快感を和らげる一助となります。
「強化すべき栄養素」
はケンネルコフを直接的に治療するわけではないです。
しかし、病気と闘うための基盤となる
強い体
を作るために不可欠な要素です。
ヒッポのごはんは、日頃からバランスの取れた栄養を提供することで
・愛犬が病気になりにくい体質を維持し
もし病気になったとしても
・その回復を早められる
ようオーダーメイドでサポートします。
ケンネルコフの治療費の例
ケンネルコフの治療費は
・症状の重さ
・通院回数
・処方される薬の種類
・検査の内容
によって大きく異なります。
◇初診料・再診料
数千円程度
◇診察料
数千円程度
◇検査費
・レントゲン検査
5千円~1万円程度
(肺炎の有無を確認する場合)
・血液検査
5千円~1万円程度
(全身状態の確認や他の病気の鑑別)
・ウイルス・細菌検査
数千円~1万円程度
(病原体の特定)
◇薬代
数千円~1万円程度
(処方日数や薬の種類による)
軽症で済めば
数千円から1万円程度
で済むこともありますが
重症化して
・入院が必要になる
・複数回の通院や検査が必要になる
などすると
数万円から10万円
を超えることもあります。
ワクチンで予防できる病気
については、多くのペット保険で
補償対象外
となるのが一般的です。
しかしケンネルコフは
ワクチンで完全に防ぐのが難しい
病気であるため、多くのペット保険で
補償対象となる
傾向があります
加入している保険の内容を事前に確認しておくことをお勧めします。
愛犬がケンネルコフになったときに飼い主がしてあげられること
愛犬がケンネルコフにかかってしまった時、飼い主さんができることはたくさんあります。
●安静にさせる
激しい運動は咳を悪化させる
可能性があるため
▶愛犬がゆっくり休める環境を整え
▶安静にさせましょう。
●湿度を保つ
空気が乾燥していると喉が刺激されやすいため、加湿器を使用するなどして
室内の湿度を50~60%程度
に保つようにしましょう。
・咳がひどい時
・特に呼吸が苦しそうな時
一時的な応急処置として
蒸しタオル
を置いてあげるのは良い方法です。
温かく湿った空気が
・喉
・気道
を潤し、咳の刺激を和らげる効果が期待できます。
ただし、蒸しタオルはすぐに冷めてしまうため、あくまで一時的なものです。
持続的に湿度を保つには
・加湿器を使う
・濡らしたタオルを部屋に干す
などの方法がより効果的です
●清潔な環境
・愛犬が過ごす場所を清潔に保ち
・定期的に空気の入れ替え
を行いましょう。
ハウスやベッドの清掃も忘れずに。
●首輪ではなくハーネスの使用
首輪は
▶喉を圧迫し
▶咳を誘発する
可能性があるため
散歩の際はハーネスを使用しましょう。
咳がひどい時期は
無理に散歩に出ず
排泄は庭などですませるのも良いでしょう。
●定期的な健康チェック
症状が改善しても、完全に回復するまでは注意深く観察しましょう。
少しでも異変を感じたら、すぐに獣医師に連絡してください。
●他の犬との接触を避ける
ケンネルコフは感染力が強いです。
他の犬に感染を広げないため
完全に回復するまでは他の犬との接触は避けましょう。
ケンネルコフは、犬にとっても非常に不快な病気です。
咳が続くことで
・体力を消耗し
・食欲も落ちやすくなります。
飼い主さんができることは
・薬をきちんと飲ませる
だけでなく
・精神的なサポート
も非常に重要です。
・安心できる環境で
・愛情をもって接してあげる
ことで愛犬の回復を早めることができます。
また、ケンネルコフは
一度治っても再発する
可能性があります。
そのため、日頃からの
・健康管理
・免疫力の維持
が何よりも大切です。
愛犬の健康状態を常に注意深く観察し、異変があれば早期に獣医師に相談する習慣をつけましょう。



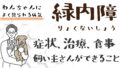
コメント