愛する家族である犬との別れは
避けられない現実
です。
しかし、その別れまでの時間を
・後悔なく
そして何よりも
・愛犬にとって穏やかに過ごせるよう
飼い主ができることはたくさんあります。
その中心となるのが
・ターミナルケア
・緩和ケア
です。
「ケア」という言葉に、辛いイメージを持つかもしれません。
しかし、これは決して
「諦め」
なんかではありません。
むしろ、愛犬への
・深い愛情
・責任感
の表れであり、最期の瞬間まで
・最高のQOL(生活の質)を追求する
ための、最も尊い選択肢なのです。
1.ターミナルケアと緩和ケア:その本質と違いを理解する
まずは
それぞれのケアが何を意味するのか?
その
・本質
・違い
を明確に理解しましょう。
1-1.ターミナルケア(終末期医療):命の終わりを支える
ターミナルケアとは
根治が困難
と診断された病気の
最終段階
にある愛犬に対し
・残された時間を穏やかに
・苦痛なく過ごせるよう
総合的に支えるケア
を指します。
●目的
・命を救うこと
を目的とする治療から
・愛犬の心身の快適さを最優先
するケアへと移行します。
残された時間を
・最大限に豊かにし
・尊厳を保つこと
に重点が置かれます。
●主な内容
・疼痛管理(痛みの緩和)
・呼吸困難の軽減
・吐き気や食欲不振の管理
・身体の清潔保持
・褥瘡(じょくそう)予防
寝たきりなどにより
体重で圧迫されている場所の血流が
・悪くなる
・滞る
ことで、皮膚の一部が
・赤い色味をおびる
・ただれる
・傷ができる
などすることです。
一般的に「床ずれ」ともいわれています。
・栄養管理(必要であれば補液など)
・排泄補助など
愛犬の
「苦しい」
「不快」
を取り除くためのあらゆる
・医療的アプローチ
・看護的アプローチ
が含まれます。
1-2.緩和ケア:痛みを和らげ、生活の質を高める
緩和ケアは
病気の進行段階にかかわらず
・愛犬が抱える痛み
・その他の不快な症状
を和らげ
生活の質(QOL)を最大限に高める
ことを目的としたケアです。
●目的
病気の
・種類
・進行度
に関わらず
・愛犬
・その家族
の苦痛を軽減し
▶より良い生活を送れるようサポート
することです。
・根治を目指す治療と並行して行われる
こともあれば
・ターミナルケアの一環として行われる
こともあります。
●主な内容
・疼痛管理
・内服薬
・注射
・神経ブロックなど
・症状緩和のための処方食やサプリ
・リハビリテーション
・鍼灸
・アロマセラピー
・温熱療法など
幅広い選択肢があります。
1-3.ターミナルケアと緩和ケアの関係性
この二つのケアは密接に関連しています。
緩和ケアは病気の
・診断時
から
・終末期
まで
病気の進行段階全体
を通して行われる可能性のある
症状緩和のためのアプローチ全般
を指します。
ターミナルケアは緩和ケアの概念を
終末期に特化させたもの
と考えると分かりやすいでしょう。
つまり、終末期においては
緩和ケア=ターミナルケアの重要な柱
となります。
2.ターミナルケアが必要になる代表的な病気
愛犬が
ターミナルケアの段階
に入るのは、一般的に
▶根治が難しい病気が進行し
・日常生活を送ることが困難になった
・身体的な苦痛が大きくなった
時です。
ここでは、ターミナルケアが必要となる代表的な病気をいくつかご紹介します。
2-1. がん(悪性腫瘍)
犬の死因として最も多いのががん。
診断された時点で
・進行が進んでいる場合
・治療が難しいタイプのがんの場合
ターミナルケアが中心となります。
●症状の例
・腫瘍の痛み
・食欲不振
・体重減少
・倦怠感
・呼吸困難(肺転移がある場合)
・嘔吐
・下痢など
●ターミナルケアでの対応
・痛みの緩和(モルヒネなどの鎮痛剤)
・吐き気止め
・栄養補給(輸液や流動食)
・腫瘍からの出血管理など
症状に応じた
苦痛の軽減
が重点的に行われます。
2-2. 慢性腎臓病(末期腎不全)
腎臓の機能が徐々に低下し
▶体内の老廃物が排出できなくなる病気。
一度壊れた腎臓は元に戻らず
▶病状が進行すると
▶末期腎不全となり
ターミナルケアが必要になります。
●症状の例
・著しい食欲不振
・嘔吐
・脱水
・口内炎
・貧血
・けいれん
・全身の倦怠感など
●ターミナルケアでの対応
輸液による
・脱水の改善
・老廃物の排出補助
その他
・吐き気止め
・食欲増進剤の投与
・貧血への対応
・腎臓病食の継続
・口腔ケア
などが行われます。
2-3. 心臓病(慢性弁膜症、心筋症などによる末期心不全)
特に小型犬に多い
・僧帽弁閉鎖不全症
などの慢性弁膜症や
大型犬に多い
・拡張型心筋症
などが進行し
▶心臓の機能が著しく低下して
▶内科治療ではコントロールが難しくなった状態です。
●症状の例
・慢性的な咳
・呼吸困難(特に夜間や安静時)
・肺水腫
・腹水
・失神
・運動不耐性(少しの運動で疲れる)
・チアノーゼ(舌が青紫色になる)など
●ターミナルケアでの対応
・利尿剤による肺水腫や腹水の軽減
・血管拡張剤
・酸素吸入による呼吸困難の緩和
・鎮静剤による不安の軽減
・体位変換による呼吸の補助
などが中心となります。
2-4. 認知機能不全症候群(老犬痴呆)の進行
いわゆる「犬の認知症」が進行し
▶通常の生活が困難になる
ケースです。
直接命に関わる病気ではないものの
▶QOLが著しく低下し
▶飼い主の介護負担も大きくなる
そのため
ターミナルケアの視点
が必要になります。
●症状の例
・昼夜逆転
・徘徊
・目的のない吠え
・狭い場所に入り込む
・排泄の失敗
・食欲の異常
・飼い主を認識できない
・呼びかけに反応しないなど
●ターミナルケアでの対応
・快適な睡眠を促すための薬
(睡眠導入剤など)
・症状緩和のための
・サプリメント
・食事療法
・昼夜のリズムを整える工夫
・褥瘡予防
・排泄補助
・転倒防止のための環境整備
・精神的な安定を促すための
・声かけ
・触れ合い
などが重要になります。
2-5. 重度の神経疾患・運動器疾患(自力歩行が困難になった場合)
・脊髄疾患(椎間板ヘルニアなど)
・脳疾患
・重度の関節炎
などにより、自力での
・移動
・起立
が困難になり介護が必要となる状態。
直接の死因とならなくとも
QOLの維持が困難
になることがあります。
●症状の例
・麻痺
・強い痛み
・自力での排泄困難
・起立不能
・褥瘡
・食欲低下など
●ターミナルケアでの対応
・疼痛管理
・褥瘡予防と治療
・排泄補助(圧迫排尿など)
・清拭や体位変換などの全身管理
・リハビリテーション
・現状維持
・苦痛軽減目的
・食欲維持のためのサポート
・栄養管理
などが行われます。
これらの病気は
進行が予測できるため
飼い主さんは
予期悲嘆
その死を事前に体験するような感情や反応
を経験しながらも
・愛犬の状況を獣医師と共有し
・最も適切なターミナルケアの選択
をすることができます。
どの病気であっても
・愛犬が感じる苦痛を最小限にし
・残された時間を穏やかに過ごせるよう
支えることが、ターミナルケアの最も大切な目的です。
3.なぜターミナルケア・緩和ケアが重要なのか?:飼い主の「後悔」を減らすために
愛犬の最期を迎えるにあたり
多くの飼い主さんが

もっと何かできたんかも…

苦しませてしまったかも…
という
・後悔
・罪悪感
を抱きがちです。
・ターミナルケア
・緩和ケア
はこの
「後悔」を最大限に減らす
ための重要な選択肢となります。
3-1.愛犬の「声」を聞き、苦痛を取り除く
犬は痛みを訴えることができません。
しかし
・ターミナルケア
・緩和ケア
を通じて
・獣医師
・動物看護師
は愛犬の些細な変化を読み取り
▶痛みのサインを見逃さず
▶適切な処置を施す
ことで、彼らの
苦痛を最小限に抑える
ことができます。
●最新の疼痛管理
痛み止めも日々進化しています。
単に「効く薬」というだけでなく
愛犬の
・体質
・病状
に合わせた
多角的なアプローチ
・非ステロイド性消炎鎮痛剤
・オピオイド系鎮痛剤
・神経障害性疼痛薬
・医療用大麻のCBD成分サプリなど
が検討されることもあります。
獣医さんと密に連携し、最適な方法を探しましょう。
●家庭でのサインの見極め
・食欲不振
・元気がない
・呼吸が速い
・震え
・唸り声
・特定の場所を触られるのを嫌がる
・姿勢の変化
などは痛みのサインかもしれません。
これらのサインを見逃さず、獣医さんに伝えることが重要です。
3-2.飼い主と愛犬の「絆」を深める時間
適切なターミナルケアにより
・治療による負担が減り
・苦痛が和らぐ
ことで、愛犬は
飼い主さんとの残された時間
をより穏やかに過ごすことができます。
これは、お互いにとって
かけがえのない時間
となります。
●質の高いコミュニケーション
痛みが少ない愛犬は
・撫でられる喜びを感じる
・飼い主さんの声に反応
などする余裕が生まれます。
今まで以上に
深いレベルでのコミュニケーション
が可能になるでしょう。
●「いつもの場所」での安心
自宅でのターミナルケア
を選ぶことで、愛犬は
・慣れ親しんだ環境で
・愛する家族に囲まれて
最期を迎えることができます。
これは愛犬にとって
最高の安心感
となります。
3-3.飼い主の心の準備とグリーフケア
愛犬の体調管理だけでなく
飼い主自身の心の準備
もターミナルケアの重要な側面です。
●予期悲嘆のケア
愛犬の病状が悪化していく中で
飼い主は
「予期悲嘆」
を経験します。
ターミナルケアを通じて
・獣医師
・動物看護師
は飼い主の
・不安
・悲しみ
に寄り添い
▶心の準備を促すグリーフケアを提供
することもあります。
愛犬を失った悲しみを抱える人が
▶その悲しみを乗り越え
▶立ち直り
▶前向きに生きていく
ための支援
●後悔の軽減
治療の限界を受け入れ
▶愛犬の苦痛軽減に全力を尽くす
ことで
「やれることはやった」
という気持ちが生まれます。
これはお別れ後の
・後悔
・罪悪感
を軽減することに繋がります。
4.ターミナルケアの具体的な内容:愛犬の苦痛を和らげるために
ターミナルケアでは
愛犬が感じる不快な症状
を可能な限り取り除き
▶安楽に過ごせるよう
多岐にわたるケアが行われます。
4-1.疼痛管理(痛みへのアプローチ)
愛犬が痛みを感じている場合、その痛みを和らげることが最優先されます。
●鎮痛剤の投与
◇非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)
軽度から中程度の痛み
に用いられます。
・炎症を抑え
・痛みを和らげる
効果があります。
◇オピオイド系鎮痛剤
・モルヒネ
・フェンタニルなど
人間にも使われる強力な鎮痛剤です。
特に
・がん性疼痛
・重度の痛み
に効果を発揮します。
・経口薬
・注射
・貼付剤など
様々な形態があり
▶愛犬の状況に合わせて選択されます。
・眠気
・便秘
などの副作用が出ることもあるため、獣医師が慎重に量を調整します。
◇神経障害性疼痛薬
神経の損傷による特有の痛みに効果的な薬です。
●補助療法
薬剤だけでなく、以下のような方法も痛みの緩和に役立つことがあります。
◇温熱療法
・温かいタオル
・湯たんぽ
などで体を温めることで
▶筋肉の緊張をほぐし
▶血行を促進して痛みを和らげます。
◇鍼灸(しんきゅう)
専門の獣医師による
・鍼治療
・灸治療
などの東洋医学の治療法が
・痛みの緩和
・QOL向上
に効果を示すことがあります。
◇マッサージ
飼い主さんによる優しいマッサージは
・血行促進
に加え、愛犬とのスキンシップを通じて
・安心感
を与えます。
4-2.呼吸器症状の管理
・呼吸が苦しい
・咳がひどい
といった症状がある場合
呼吸を楽にするためのケア
が行われます。
●酸素吸入
呼吸困難が顕著な場合
・酸素室
・酸素マスク
を用いて酸素を供給し
▶呼吸を楽にします。
自宅で酸素濃縮器をレンタルして使用することも可能です。
●利尿剤・気管支拡張剤
・肺水腫
・気管支の収縮
による呼吸困難に対して、症状を和らげる薬が投与されます。
●体位変換
・呼吸が楽になる体勢を見つけてあげる
・定期的に体位を変えてあげる
ことで、呼吸の負担を軽減します。
4-3.消化器症状の管理
・食欲不振
・吐き気
・下痢
・便秘など
も愛犬のQOLを著しく低下させます。
●制吐剤・食欲増進剤
・吐き気を抑える
・食欲を刺激する
などの薬が用いられます。
●消化しやすい食事
・少量で高栄養の流動食
・消化器に優しい療法食
などを試します。
●補液(点滴)
・食事
・水分
が十分に摂れない場合
・脱水
・栄養不足
を防ぐために
・皮下点滴
・静脈点滴
が行われます。
自宅で飼い主さんが行える場合もあります。
●整腸剤・便秘薬
便の状態を整え
▶排泄の苦痛を和らげます。
4-4.身体の清潔保持と褥瘡予防
寝たきりになった愛犬は
▶自分で体を清潔に保つことが難しくなります。
●清拭(せいしき)
温かいタオルで体を拭いてあげることで
▶皮膚を清潔に保ち
▶リフレッシュさせます。
●排泄補助
・おむつを使用する
・定期的に排泄を促す
などすることで
▶清潔を保ち
▶皮膚炎を防ぎます。
●褥瘡(床ずれ)予防
寝たきりの場合
骨の突出した部分
に床ずれができやすくなります。
・柔らかい寝具の使用
・体位変換(2~4時間おきが目安)
・ドーナツクッションの活用
などで予防します。
特に褥瘡ができやすい部位は
・肩甲骨の先端:肩の骨の尖った部分
・肘:前足の関節部分
・手根部:前足首にあたる部分
・腰骨の側面:腰の横にある骨の出張り
・大腿骨の付け根:後ろ足の股関節
・かかと(足根部):後ろ足の関節部分
・ほほ:頭部の側面にある骨の突出部
これらの部位は
▶寝ているときに体重が集中し
▶床に強く当たるため
▶皮膚の血行が悪くなり
▶褥瘡が発生しやすくなります。
特に
・中型犬以上の犬
・痩せて筋肉や脂肪が薄くなった犬
は骨がより突出するため注意が必要。
これらの部位を定期的に確認し
・赤み
・皮膚のただれ
がないかチェックすることが、予防の第一歩となります。
4-5.精神的なケアと環境整備
医療的なケアだけでなく
愛犬の精神的な安定
も非常に重要です。
●安心できる環境
騒がしい場所を避け
▶静かで落ち着ける場所を提供します。
●飼い主との触れ合い
・優しく撫でる
・話しかける
・傍にいるなど
愛情を伝えるスキンシップ
は愛犬に大きな安心感を与えます。
●無理のない散歩・日光浴
体調が許す範囲で
・外の空気に触れさせる
・日光浴をさせたる
などすることで、気分転換になることもあります。
5.自宅でのターミナルケア:愛犬が「家」で過ごす最期
近年
自宅でのターミナルケア
を選択する飼い主さんが増えています。
これは
・愛犬にとっての精神的な安定
・飼い主の見送りたいという願い
を叶える選択肢です。
5-1.在宅ケアのメリットと課題
●メリット
◇慣れた環境での安心感
愛犬にとって
最もリラックスできる場所
で過ごせる。
◇飼い主の精神的な安定
最期の瞬間まで傍にいられるため
・安心感があり
・愛犬との絆を深められる
◇ストレス軽減
・病院への移動
・見慣れない場所での処置
によるストレスがない。
◇他の愛犬との時間
多頭飼育の場合、残された犬たちも共に過ごすことができる。
●課題
◇飼い主の負担
・ 医療処置
・投薬
・補液
・排泄補助など
・介護
・体位変換
・清拭など
の負担が大きい。
◇精神的負担
・愛犬の衰弱を間近で見る辛さ
・いつ訪れるか分からない最期への不安
◇緊急時の対応
症状が急変した場合の対応。
◇医療設備・体制の限界
自宅では行えない
・処置
・検査
がある。
5-2.在宅ターミナルケアを支える最新サービス
このような課題をサポートするため
多様な在宅ケアサービス
が拡大しています。
●往診専門動物病院
自宅まで獣医師が訪問し
・診察
・処置
・投薬
・点滴
などを行います。
・夜間
・休日
の対応をしているところもあります。
●動物看護師による訪問ケア
獣医師の指示のもと
▶動物看護師が自宅で
・点滴
・清拭
・体位変換
・食事補助
などのケアを行います。
飼い主さんの介護負担を軽減し
▶精神的なサポートも行います。
●在宅ホスピスサービス
専門のチームが
・医療
・看護
・精神面
で飼い主と愛犬をトータルでサポートするサービスです。
看取りから葬儀まで
一貫して支援するところもあります。
●オンラインでの相談・サポート
遠隔地からでも
・獣医師
・カウンセラー
に相談できる
オンラインサービス
も増えています。
・症状の変化へのアドバイス
・精神的な支え
となります。
5-3.飼い主さんの声:「自宅で見送ってよかった」
●Aさんの声(15歳柴犬とのお別れ)
●Bさんの声(腎臓病の12歳Mダックス)
6.後悔しないための選択肢:今、できること
愛犬の最期に後悔を残さないために、飼い主さんが今できることはたくさんあります。
6-1.獣医師との綿密なコミュニケーション
●病状の共有
愛犬の
・病状
・予後
について
正確な情報を獣医師から得ましょう。
理解できない点は
▶納得がいくまで質問し、疑問を解消することが重要です。
●治療方針の話し合い
・根治を目指す治療の継続
・緩和ケアへの移行
・自宅でのケアなど
様々な選択肢について
・メリット
・デメリット
を含めて十分に話し合いましょう。
●看取りの時期や方法の相談
具体的に
・どのようなサインが出たら危ないのか
・最期の瞬間にどう対応すべきか
など
▶事前に獣医師と相談しておくことで
▶いざという時に冷静に対応できます。
6-2.家族間での話し合いと意思統一
●希望の共有
・家族それぞれの愛犬への思い
・最期に向けてどのようなケアを望むか
を率直に話し合いましょう。
意見が異なる場合は
▶互いを尊重し
愛犬にとって何が最善か
を一緒に考えましょう。
●役割分担の検討
在宅ケアを選択する場合
誰がどのケアを担当するのか?
具体的な役割分担を決めておくことで
▶負担が偏るのを防ぎます。
6-3.安楽死という選択肢と向き合う
愛犬の命を救うための治療が難しく
緩和ケアでも
苦痛を取り除くことが極めて困難
になった時…
獣医師から
安楽死
という選択肢が提示されるかも…
この決断は、飼い主さんにとって
・最も重く
・辛い
選択の一つであり
・大きな罪悪感
・葛藤
を伴うものです。
しかし、安楽死は
愛する愛犬の
計り知れない苦痛
を終わらせるための
「最後の優しさ」
「最後の愛情表現」
であると考えることもできます。
決して
・愛を放棄したわけでも
・裏切ったわけでも
ありません。
●十分な情報と話し合い
安楽死を検討する際は
・愛犬の病状
・残された時間の予測
・苦痛のレベル
について
▶獣医師から徹底的に説明を受け
▶納得がいくまで話し合ってください。
・他に可能な選択肢がないか?
・本当に最期の手段なのか?
を共に考えましょう。
●家族全員での合意
可能な限り
▶家族全員で話し合い
▶それぞれの気持ちを共有し
▶最終的な合意に至る
ことが大切です。
この困難な決断を一人で抱え込まないでください。
●罪悪感は自然な感情
安楽死を選択した後
深く愛しているからこそ
飼い主さんは
「本当にこれでよかったのか?」
という
・強い罪悪感
・後悔
を抱くことがあります。
しかし、それは決して
異常なことではありません。
愛犬の苦痛を軽減するために
悩み抜いた末の決断
であったことを忘れず、自分を責めすぎないでください。
●獣医師や専門家のサポート
・安楽死の決断
・実行
そして
・その後の心のケア
まで、獣医師は飼い主さんに
・寄り添い
・サポート
します。
また他にも
ペットロス専門のカウンセラーなども
・深い悲しみ
・罪悪感
と向き合う上で大きな助けとなるでしょう。
あなたは一人でこの重荷を背負う必要はありません。
安楽死は、愛犬の
「生きたい」という本能
に反する、飼い主にとって
究極の苦渋の選択
です。
しかし、その決断の裏には
愛犬の苦しみ
をこれ以上見たくないという
深く、計り知れない愛情
があったことを、どうか忘れないでください。
6-4.「もしもの時」の準備
●葬儀・供養の検討
愛犬が旅立った後
どのように見送りたいか?
・火葬
・土葬
・合同供養
・手元供養など
を事前に調べておき
▶家族で方針を決めておきましょう。
信頼できる
・ペット葬儀社
・霊園
を調べておくことも大切です。
●心の準備
愛犬との別れは
計り知れない悲しみ
を伴います。
・グリーフケア
・ペットロスサポートグループ
の存在を知り、必要に応じて利用することを検討しておきましょう。
6-5.愛犬に「ありがとう」「大好きだよ」を伝え続ける
最期の瞬間まで
愛犬への愛情
を惜しみなく表現しましょう。
・たくさん撫でてあげ
・話しかけ
共に過ごす時間を大切にしてください。
●「ありがとう」を伝える
愛犬があなたの人生にもたらしてくれた
・喜び
・癒し
に感謝の気持ちを伝えましょう。
●「大好きだよ」を伝える
彼らがどれほど愛されているかを
・言葉
・態度
で示し続けてください。
●触れることの力
・体を優しく撫でる
・抱きしめる
などすることは
▶言葉以上に深い愛情を伝え
▶愛犬に安心感を与えます。
7.ターミナルケア・緩和ケアを支える社会的な動きと未来
愛犬の終末期医療やケアは
社会全体
でより良くしていくべき課題として認識されつつあります。
●愛玩動物看護師国家資格化
2023年に「愛玩動物看護師」が
国家資格
となったことは、動物医療における
・ターミナルケア
・グリーフケア
の質向上に大きく貢献すると期待されています。
専門知識を持った看護師が
・医療行為
だけでなく
・飼い主への精神的なサポート
も担うことができます。
●ホスピスケアの概念の浸透
人間の医療と同様に
・ペットのホスピスケア
・緩和ケア
の重要性がより広く認知され
・専門施設
・サービス
が増加しています。
●研究と技術の進歩
獣医療における
・疼痛管理
・症状緩和
の技術は日々進歩しています。
・新しい治療法
・ケア方法
が開発され
愛犬の苦痛
をより軽減できるようになるでしょう。
愛犬の
・ターミナルケア
・緩和ケア
は決して簡単な道のりではありません。
しかしそれは愛する家族の最期を
最大限に
・穏やかで
・尊厳あるもの
にするための、飼い主としてできる最後の愛情表現です。
このガイドが、あなたが
・愛犬との残された時間を大切に
そしてなにより
・後悔なく過ごす
ための一助となることを心から願います。
もし何か疑問や不安があれば、いつでも
・獣医師
・専門家
・ヒッポんごはん
にご相談ください。
あなたは一人ではありません。


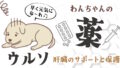

コメント