犬は古くから人間と共生してきた動物。
彼らの行動の多くは
・何万年も前に持っていた
野生の本能
・私たち人間との共同生活の中で
学習し適応してきた結果
が複雑に絡み合って現れるもの。
愛犬の何気ない仕草の中に
太古の昔から受け継がれてきた
本能の片鱗
を見つけるのは、飼い主さんにとって
・大きな喜びであり
・彼らへの理解を深める
かけがえのない機会になるでしょう。
ここでは、あなたの愛犬が見せるさまざまな行動の裏にある
・面白くて奥深い習性と本能
そして飼い主さんが
・特に気をつけてあげたいサイン
について、詳しくご紹介します。
1.なぜ両手で「ちょうだい!」?:学習と本能の融合が生み出す愛らしい行動

ぼくの得意技は「ちょうだい!」手を合わせて、いただきますのポーズから一生懸命手を振れば、パパさんもママさんもイチコロ!
立ち上がって、必死で手を振って
「ちょうだい!ちょうだい!」
とおねだりする姿…
本当に愛らしいですよね。
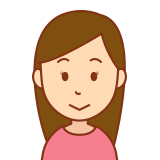
こんなん教えてないのに…うちの子もしかして天才?!
実はこの行動こそ
・野生の本能
と人間との共同生活の中で
・学習し適応してきた結果
が複雑に絡み合って現れるものだと考えられます。
●「もっと欲しい」欲求の本能
食べ物や何かを欲しがる気持ちは
生き物として当然の生存本能
この強い欲求が、さまざまな行動を誘発します。
虎之介の場合はこちらが80%だと思います
●「注目を引きたい」社会性本能
群れで暮らす犬は
・リーダー
・仲間
からの注目を常に意識しています。
特に子犬は
母犬の気を引くために
さまざまな仕草をします。
彼らは人間社会でも、家族からの関心を引こうとします。
虎之介は撫でてもらいたいときは、ヘソ天で「ちょうだい」してました
●学習と強化
人間と一緒に暮らす中で犬は

この行動をしたら、ご飯やおやつがもらえる!

こんな仕草を見せたら飼い主さんが喜んでくれる!
と学習します。
立ち上がって前足を振る行動が
▶たまたま飼い主さんの気を引き
▶結果としてご飯に繋がった
という経験を繰り返すうちに
▶その行動が強化され
▶定着
していったのかもしれませんね。
つまり
「もっと欲しい」
「注目してほしい」
という
本能的な欲求
が根底にあり、それを人間社会で
効果的に達成するための手段
として、その犬独自の
「おねだりポーズ」
を編み出し、学習していった
と考えられます。
虎之介ちゃんは、まさに
・環境に適応し
・人間とのコミュニケーションを工夫する
天才
と言っても過言ではないしょう!
2.犬の基本の習性:群れで生きる社会性と驚異の感覚
犬は元々、オオカミのように
群れで生活する
社会性の高い動物。
この群棲本能は、現代の犬にも色濃く残っています。
●家族を群れと認識する
・飼い主さん
・その家族
を自分の群れの一員として認識します。
そしてその中で
▶自分自身の役割を理解し
▶安心して暮らそうとします。
家族との絆が深まるほど、犬は
・強い安心感
・幸福
を感じるでしょう。
●リーダーを求める
群れには秩序があり
▶リーダーが存在します。
犬は本能的に
▶群れの中にリーダーを求め
▶その指示に従うことで
・群れの安定
・自身の安全
を確保しようとします。
飼い主さんが
・穏やかで一貫した態度で
・リーダーシップを発揮
することで、犬は混乱することなく、安心感を得て落ち着くことができます。
●コミュニケーションの達人
犬は鳴き声だけでなく
・ボディランゲージ
・しっぽの動き
・耳の向き
・体の姿勢など
・表情
・アイコンタクト
など非常に多様な方法で
・感情
・意図
を伝えます。
例えば
〇しっぽを振る
・速さ
・高さ
で喜びの度合いを
〇耳の向きで
・警戒
・集中
を示します。
さらに、人間の
・言葉のイントネーション
・表情
・声のトーン
から感情を読み取る能力も非常に優れています。
犬の驚異的な嗅覚:匂いが語る彼らの世界
彼らの世界認識において最も重要なのが
驚異的な嗅覚
犬の嗅覚は人間の
数千万倍から1億倍
とも言われるほど優れており
▶匂いから膨大な情報を得ています。
●匂いを嗅ぐ
散歩中に
・地面
・電柱
の匂いを熱心に嗅ぐのは、彼らにとってSNSのようなもの。
他の犬の
・存在
・性別
・体調
・発情状況
さらには
・気分
まで把握しようとしています。
●匂いによるコミュニケーション
犬にとって
匂い
は私たちの
・目
・耳
と同じくらい、いや
・それ以上に
重要な情報源です。
彼らは
▶驚異的な嗅覚を駆使して
▶言葉を交わさずとも多くの情報を交換し合っています。
◇お尻の匂いを嗅ぐ
=肛門腺からの情報
犬がお互いのお尻の匂いを嗅ぐのは
「自己紹介」
のようなもの。
お尻の周りにある
肛門腺
からは
その犬固有の非常に複雑な匂い
が分泌されています。
この匂いには
・性別
・年齢
・健康状態
・感情
・興奮しているか
・怖がっているかなど
といった、その犬の
「名刺」とも言える情報
がぎゅっと詰まっているのです。
初対面の犬同士が挨拶としてお尻の匂いを嗅ぎ合うのは
・お互いの素性を探り
・友好的な関係を築けるかを探る
ための、ごく自然な行為なのです。
◇顔の匂いを嗅ぐ
初対面の犬同士が
▶鼻と鼻を近づけ
▶互いの顔の周りを嗅ぎ合う
ことがあります。
これは、特に
・目の周り
・口の周り
には、アポクリン腺から出る
フェロモン
が多く分泌されており
▶相手のパーソナルな情報を
▶より詳細に読み取ることができる
からです
◇尿や便の匂い
他の犬の
・尿
・便
の匂いを嗅ぐことで、その犬が
いつ、どんな状態であったか
・発情期かどうか
・健康状態など
といった
最新の「動向」
を得ています。
そして
▶その上に自分の匂いをつけて
・自己主張
・縄張り
をアピールをします。
犬たちの社会では
匂いは単なる
「香り」
ではなく、まるで情報が詰まった
「手紙」
のようなもの。
彼らはそれを嗅ぎ取ることで
▶複雑な社会を理解し
▶お互いの関係を築いているのです。
●マーキング
・尿をかける
・体をこすりつける
などは自分の匂いをつける行動です。
これは
・自分の縄張りの主張
・他の犬に自身の存在をアピール
などするためです。
オス・メス問わず見られますが、特にメスは発情期に多く見られます。
●食べ物探し
優れた嗅覚は
食べ物を探し出す能力
に長けています。
そのため
拾い食い
などにも繋がることがあります。
お散歩中は特に注意してあげましょう。
臭いもの好き?飼い主さんの靴下を嗅ぐのは愛情の証!
あなたの愛犬が
飼い主さんの脱いだ
・服
・靴下
に特に反応して
「フンガフンガ」
と熱心に匂いを嗅ぐ姿は、まさに
・嗅覚の優位性
・社会性
が融合した行動です。
決して
「臭いものが好き」
なわけではなく、そこに込められた
情報
に夢中になっているのです。
●個体識別のための情報収集
犬は匂いを通して
人間が
・視覚
・聴覚
で得る以上の情報を得ています。
家族一人ひとりの
・体臭
・フェロモン
・汗の匂い
というものは、その人の
・個性
・体調
・感情
までも伝える貴重な情報源です。
普段ママさんにべったりでも
パパさんの服や靴下ばかりを嗅ぐのは
「臭いから」
ではなく
「パパさんの最新情報」
を熱心に収集しているのです。
●安心感と愛着の確認
飼い主さんの匂いは、愛犬にとって
・自分の群れの一員
・大切な家族
の匂いです。
その匂いを深く嗅ぐことで
▶飼い主さんの存在を再確認し
・安心感
・安堵感
を得ていると考えられます。
特に、飼い主さんが不在の時に
▶残された服の匂いを嗅ぐことは
▶まるで飼い主さんがそばにいるかのような心地よさを与えることもあるでしょう。
●縄張りの匂い
家族の匂いは、愛犬にとって
・自分たちの縄張り
を示す匂いでもあります。
飼い主さんの匂いを嗅ぎ
▶それに自分の匂いを重ねることで
▶家族との一体感を強めている
とも解釈できます。
このように、愛犬が飼い主さんの
・服
・靴下
を熱心に嗅ぐ行動は
・彼らなりの深い愛情表現
であり
・家族への信頼と絆の証。
彼らが匂いから得ている
・複雑な情報
・感情の世界
そっと見守ってあげてくださいね。
3.これも本能?!愛犬の意外な行動の理由
私たちの愛犬が日常で見せるユニークな行動の裏には、野生時代の名残が隠されています。
寝る前の「くるくる」:安心できる場所探しとマーキングの儀式
ベッドに入る前に
▶何回かくるくる回ってから
▶寝転がる
こんな行動、見たことありますか?
これは、野生時代に
寝床を作る
際に行っていた行動の名残と言われます。
●安全の確認
野生では
・寝床の周囲に危険がないか
・小石や枝などの邪魔なものがないか
を確認していました。
このくるくるは、寝る前の最終チェックのようなものです。
●快適な寝床作り
足で草を踏み倒し
▶自分の体にフィットするように
寝床を整える行動の名残です。
●自分の匂い付け
自分の匂いをつけ
▶ここは自分のテリトリーである
ことを示していた可能性もあります。
愛犬がくるくるしているのを見たら
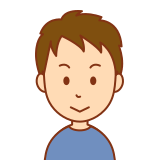
今日もがんばって安全で最高の寝床を作ってるんやね!
と微笑ましく見守ってあげてくださいね。
排泄前のくるくる:母なる大地とのつながり
愛犬がウンチをする前に、
▶その場でくるくる何回か回ってから
体勢を整える姿もよく見られます。
これもまた、興味深い本能的な行動です。
●なぜするの?
◇一つは
排泄中に無防備になるため
▶周囲に危険がないかを確認する
ための行動と言われています。
◇もう一つは
犬が排泄する際に
地球の磁場
に沿って体を合わせる習性があるという研究結果があります。
最も落ち着く方角を探していると考えられています。
※東西を向くのを好まず、南北を向くと落ち着くらしいです・・
●現代の愛犬は?
安全が確保された室内でも、この本能的な動きが残っているのは
DNAに深く刻まれた習性
だからこそ。
安心して排泄できる場所かどうか?
彼らなりに
最終チェック
を行っているのです。
愛犬が排泄後に見せる「しゃっしゃっ」の秘密
愛犬が
・おしっこ
・うんち
をした後、後ろ足で地面をかく
=室内であれば床や絨毯
「しゃっしゃっ」
土をかけるわけでもないのにこの行動をするのは
彼らなりの大切なメッセージ
が込められているからです。
●匂いのマーキングと自己主張
犬は足の裏にも
アポクリン腺
があり
その犬固有のフェロモン
を含む分泌物を出しています。
排泄後に地面をかくことで
▶この足裏の匂いを地面に強く擦り付け
・自分の存在
・縄張り
を強力にアピールしているのです。
排泄物の匂いに加え
▶足裏のパーソナルな匂いを拡散
させることで
「ここで用を足したのはボクだよ!」
というメッセージを、周囲に伝えていると考えられます。
●排泄物の隠蔽(野生時代の習性)
もう一つの理由は、野生において
泄物を隠す
という本能的な行動の名残です。
・獲物に気づかれないように匂いを消す
・群れの生活空間を清潔に保つ
などのため
排泄物を覆い隠す習性
が身についたとされています。
室内でも見られるこの行動は
▶土がない場所でも
▶彼らの根深い本能的な動作として残っているためです。
食事後の「顔拭き」:獲物の匂いを消し、身を隠す本能
ご飯を食べた後
・床や絨毯に顔をこすりつける
・口の周りを拭く
などの姿を見たことがありますか?
これは
単に口元をきれいにするだけではない
食べ物の匂いを消すための行動
だったと考えられています。
●捕食者からの身隠し
野生では、食事の匂いは
他の捕食者に
自分の居場所を知らせてしまう
危険がありました。
▶匂いを消すことで
・自分自身
・隠している獲物
を守っていたのです。
●縄張りの主張
食べ物の匂いを
▶体の他の部分に擦り付けることで
・自分の匂いを広げ
・縄張りを主張していた
という説もあります。
「お口拭き」
の行動には、全く別の本能の側面があるとも考えられています。
●独り占めの欲求
野生の世界では
▶良い獲物を見つけたら
・他の群れの仲間
・競争相手
に横取りされないよう
▶その存在を隠したい
という本能があります。
しかし、同時に
その獲物を手に入れたという
優位性をアピールしたい
気持ちもあるかもしれません。
●自分のものにする
獲物の匂いを
▶自分の体に擦り付けることで
「これは私の獲物だ」
と周囲に示す、一種の
「匂いのマーキング」
としての役割も果たしていた可能性も指摘されています。
愛犬がご飯の後に顔を拭くのは
単にきれいにしているのではなく
「こんな美味しいものを食べた!」
という
▶喜びを全身で表現し
▶同時にその匂いを独り占めしたい
という
食に対する根源的な本能
が隠されているのかもしれません。
愛犬のこうした行動を
美味しさの余韻を全身で味わっている
と理解してあげましょう。
愛犬の食への情熱に共感してあげることで、より愛おしく感じられるでしょう。
穴掘り:隠す・保管する・ストレス解消の多目的行動
犬が穴を掘る行動は、野生時代の名残が色濃く出ています。
●隠す・保管する
・食べ物を貯蔵する
・大切なもの(おもちゃなど)を隠す
などするために穴を掘っていました。
これは
未来の食料を確保する
ための本能です。
●寝床を作る
・暑さ
・寒さ
から身を守るために、地面を掘って快適な巣穴を作ることがありました。
土の中は外気温の影響を受けにくいため、天然のエアコンや暖房の役割を果たしていたのです。
●ストレス解消
室内で
・クッション
・カーペット
を掘るような行動は
▶単なる遊びだけでなく
・運動不足
・ストレス
のサインであることもあります。
・エネルギーを持て余している
・不安を感じている
ことがあるのかもしれません。
吠える:多様な意味を持つコミュニケーション手段
犬にとって吠えることは
人間にとっての
会話
と同じくらい重要なコミュニケーション。
様々な意味合いを持ちます。
●要求吠え
飼い主さんに何かしてほしい!
例えば
・散歩に行きたい
・ご飯がほしい
・遊んでほしい
・かまってほしい
といった要求を伝えるために吠えます。
●警戒吠え
見慣れない
・もの
・音
・人
・犬
に警戒したり
危険を感じたりしたときに吠えます。
「そこに何がある?」
「誰か来たぞ!」
と知らせているのです。
●興奮吠え
・遊び
・嬉しい
など気持ちが高ぶったときに
・喜び
・興奮
を表現するために吠えます。
●防衛本能
・自分の縄張り
・大切なもの(家族や物)
を守ろうとして吠えることもあります。
犬種によって
・吠えやすい
・吠えにくい
といった傾向はあります・
しかし犬は
基本的に吠える動物
であることを理解し
その吠え声の背景にある意図
を読み取ろうとすることが、しつけにおいても重要です。
鳴き声(音声)によるコミュニケーション:様々な感情の表現
犬は様々な鳴き声を発し、それぞれに異なる意味が込められています。
●吠える(ワンワン)
◇高い声で短く
・興奮
・喜び
・遊びの誘い
◇低く連続して
・警戒
・威嚇
・縄張りの主張
◇甲高い声で連続して(キャンキャン)
・恐怖
・痛み
・不安
●唸る(ウー)
・警告
・威嚇
これ以上近づくと
攻撃する可能性がある
という強いサインです。
●クンクン鳴く(クーン)
・甘え
・要求
・寂しさ
・不安
「かまってほしい」
「おやつがほしい」
「どこかに行かないで」
といった気持ちを伝えます。
これらの多様なコミュニケーション手段を
▶総合的に読み解くことで
▶犬たちは互いの気持ちを理解し
▶社会的な関係を築いています。
私たち人間も、彼らの
・ボディランゲージ
・鳴き声
に耳を傾け
▶その意味を理解しようと努めることで
▶愛犬との絆をより一層深めることができるでしょう。
遠吠え:孤独と呼びかけの魂の叫び
遠吠えは単なる吠えとは異なり
彼らの
・非常に根源的な本能
・感情
が表れたものです。
●孤独と不安の訴え
オオカミだった頃
群れから離れてしまった仲間は
▶遠吠えをして
▶自分の居場所を知らせ
▶群れとの再会を求めていました。
現代の犬も、飼い主さんという
「群れの仲間」
がいなくなると
▶分離不安を感じ
・孤独
・不安
を遠吠えで訴えることがあります。
時に
・子供が駄々をこねるような
あるいは
・「泣いている」
ように聞こえるのは、まさにその
・心の痛み
・助けを求める気持ち
が切ない声となって現れているのでしょう。
●仲間への呼びかけ
遠吠えは
▶遠く離れた仲間にも聞こえるように
・自分の存在を知らせ
・呼びかけるためのもの
です。
飼い主さんが不在の時に遠吠えをするのは
「ここにいるよ!」
「どこにいるの?」
と離れてしまった飼い主さんを探し
▶呼び戻そうとしている
のかもしれません。
●共鳴と反応
遠吠えは
・他の犬の遠吠え
・サイレンの音
・特定の音楽
などにも誘発されることがあります。
これは、本能的に
「仲間の声」
に反応し、自身も群れの一員として
「応える」
ことで、群れの絆を再確認しようとする行動です。
このように、遠吠えは犬にとって非常に深い意味を持つコミュニケーション。
特に愛犬が
・孤独
・不安
を感じている時に発するサインとして、理解してあげることが大切です。
追跡・捕獲本能:遊びの中に見る狩りの名残
▶獲物を追いかけ
▶捕獲する
という狩猟本能は、現代の犬にも強く残っています。
●動くものを追いかける
・鳥
・猫
・自転車
・ボールなど
動くものを見ると
▶追いかけたくなる
のは、獲物を追う本能的な衝動です。
●持来(もちきたり)本能
撃ち落とした獲物を持ち帰る
というレトリバー種などに特に見られる習性は、この本能によるものです。
・スリッパをくわえて持ってくる
・投げたボールを持ってくる
のも、この愛らしい本能の現れかもしれません。
「獲物を首振りで仕留める」ような動き:遊びの中の狩猟本能
・おもちゃをくわえて
▶頭をブルブルと激しく振る姿
・タオルなどを振り回して
▶「ウー!」と唸っている姿
は一見、ただの遊びに見えます。
しかし、これも
狩猟本能
が遊びとして昇華された行動です。
●なぜするの?
野生で獲物を捕らえる際
犬の祖先は
▶仕留めた獲物を素早く弱らせるため
▶首を激しく振ってとどめを刺す
これは
・獲物の息の根を止め
・反撃を防ぐ
ための効率的な方法だったのです。
●現代の愛犬は?
・おもちゃ
・タオル
を獲物に見立て、本能的な「仕留める」動きを再現しています
この行動は、彼らにとって
・ストレス解消
・運動
になっています。
また獲物(仮)を捕らえることで
・達成感
を得ています。
遊びを通して、彼らの中の
野生が満たされている
と考えると、さらに愛おしく感じられますね。
その他の愛らしい習性:体のサインと感情の表現
●甘噛み
子犬は
・コミュニケーションの一環
・歯の生え変わりで
甘噛みすることがあります。
しかし成犬になっても続く場合は
・遊び
・ストレス
あるいは
・要求
を表していることもあり
▶問題行動になることもあります。
●パンティング
=口を開けて「ハァハァ」と息をする
犬は全身を被毛で覆われているため、人間のように汗をかくことができません。
なので通常パンティングは
▶唾液を蒸発させ
▶体温を下げる
ために行われます。
しかし
・緊張
・不安
・痛み
などでも見られることがあるので注意が必要です。
●首をかしげる
飼い主さんの言葉を
・聞き取ろうとしたり
・理解しようとしたり
するサインです。
特に聞いたことのない
・音
・言葉
に反応して見せることが多いです。
●仰向けでお腹を見せる
これは、飼い主さんに対する
・絶対的な信頼
・服従
そして
究極のリラックス
のサインです。
「あなたに身を任せています」
というメッセージであり、同時に
「撫でてほしい」
という甘えの表現でもあります。
4.犬が送る「心の声」:カーミングシグナルを読み解く
犬は言葉を話せません。
その代わりに
ボディランゲージ
を使って私たちの心に語りかけます。
特に
・ストレス
・不安
・葛藤
を感じたときに
・自分を落ち着かせたり
相手に
「私は敵意がありません」
「落ち着いてください」
と伝えたりする特定の行動を
カーミングシグナル
と呼びます。
これは、犬が
・群れの中で争いを避け
・共存するために
古くから培ってきた
・服従
・降伏の姿勢
の表れでもあります。
かつては
群れのリーダーに見せていた
ようなこれらの行動。
現代では
飼い主という「リーダー」
に対して見せることで、関係の安定を保とうとするのです。
カーミングシグナルは、
〇犬同士のコミュニケーションにおいて非常に重要な役割を果たし
〇飼い主さんが理解することで
▶愛犬の「心の声」をより深く察してあげることができます。
代表的なカーミングシグナルとその理由
●あくびをする

犬があくびをするのは
・眠い時
だけでなく
・ストレス
・不安
・緊張
を感じている時にも見られます。
たとえば
・動物病院の待合室で急にあくびをする
・叱られている時にあくびをする
のは
自分自身を落ち着かせよう
としているサインです。
野生では、緊張状態にある仲間に対して
「私はリラックスしています」
と伝えることで
▶場の緊張を和らげる役割も果たします。
●痒くないのに体をかく

体が痒くないのに
突然体をかく
動作を見せることがあります。
これは
▶不安や戸惑いを感じた時に
▶その気持ちを紛らわせる
ための行動です。
また相手に
「困ったな」
「どうしたらいいかわからない」
というメッセージを送っていることもあります。
●鼻・口の周りをなめる

・鼻先
・口の周り
を素早くペロペロとなめる行動は
・緊張
・不安
・葛藤
を感じている時によく見られます。
これは口周りの動きを活発にすることで
▶自律神経のバランスを整え
▶心を落ち着かせようとする
生理的反応
とも考えられます。
また相手に対して
「私は攻撃するつもりはありません」
「落ち着いてください」
と伝える、犬同士の平和的なサインでもあります。
●目をそらす・顔を背ける

・相手と目を合わせないようにする
・顔や体をそむける
などすることは
・相手に対する敵意がないこと
あるいは
・プレッシャー
・恐怖を感じていること
を示すサインです。
「あなたに敵意はありません」
「攻撃しないでください」
というメッセージを送っていると考えられます。
直接的なアイコンタクトは、
犬同士では威嚇
と受け取られることがあるため
▶これを避けることで争いを回避しようとします。
●フリーズ(動きが止まる)
突然動きが止まり
▶まるで固まったようになる
ことがあります。
これは
極度の緊張や恐怖
を感じている時に見られ
▶これ以上状況が悪化しないように
・自分を小さく見せる
・注意を引かないようにする
本能的な行動です。
状況を観察し、次にどう動くべきかを判断している場合もあります。
●地面の匂いを嗅ぐふりをする

散歩中、他の犬と出会った時などに
▶急に地面の匂いを熱心に嗅ぎ始める
ことがあります。
これは
・緊張を和らげる
・相手との直接的な対立を避ける
ための行動です。
「私はあなたに興味がありません」
「今は穏やかでいたいです」
というメッセージを送っていると考えられます。
●体をブルブルと振る

体が濡れていないのに、
▶全身をブルブルと振る
のは
・ストレス
・緊張
を「振り払う」ための行動です。
例えば
・叱られた後
・苦手な場所から解放された時
などに見られます。
・余分なエネルギーを放出
・感情をリセット
などする役割があります。
●ゆっくりとした動き
・普段よりも動きがゆっくりになる
・わざとゆっくり歩く
などすることがあります。
これは
・相手に敵意がないことを示す
・落ち着きを促す
ためのサインです。
速い動きは
・興奮
・攻撃性
を連想させるため
▶ゆっくり動くことで
「私は危険ではありません」
と伝えています。
●尻尾を低くする・股の間に挟む

・尻尾が普段より低い位置にある
あるいは
・股の間に挟んでいる
場合は
・不安
・恐怖
・服従の気持ち
を表しています。
これは
▶自分を小さく見せ
▶相手からの攻撃を避けようとする本能的な行動です。
●しきりに水を飲む
・不安
・ストレス
を感じると、喉が渇くことがあります。
特に緊張している場面で
▶必要以上に水を飲みたがるのは
▶カーミングシグナルである
可能性があります。
●遠吠え(カーミングシグナルとして)

前述したように
遠吠えは群れの呼びかけ
ですが
・不安
・ストレス
が高まり、その感情が極限に達した際に
自分を落ち着かせよう
と本能的に発してしまう場合もあります。
これらの
・カーミングシグナルを理解
することは
・愛犬の「心の声」を聴く
上で欠かせません。
なぜなら
犬にとってカーミングシグナルは
・自分を落ち着かせ
あるいは
・相手に平和的な意図を伝える
ための大切なコミュニケーション手段だからです。
もし
・愛犬が強いストレスを感じ続ける
・せっかく送っているカーミングシグナルが無視され続ける
などすると、彼らはコミュニケーションを諦めてしまうことがあります。
それは、私たち人間が
言葉を話せなくなる
のと同じくら犬にとって辛く
▶時には問題行動に繋がる
可能性さえあります。
飼い主さんが
▶愛犬の気持ちを正確に読み取り
・不安を取り除いてあげる
・無理強いしない選択をする
ことは
犬との間に深い信頼関係
を築く上で不可欠です。
カーミングシグナルは決して特別な行動ではなく、愛犬が日常生活のあらゆるシーンで私たちに送ってくれているサインです。
ぜひ、これらのシグナルを学び、愛犬の行動を注意深く観察してみてください。
彼らが送る
▶小さなサインに気づき
▶応えてあげること。
それが
・愛犬との絆をより一層深め
・共に幸せに暮らす
ための大切な一歩となるでしょう。
5.飼い主さんが特に気を付けてあげたい本能:痛みを隠す習性
愛犬との生活の中で、特に飼い主さんが心に留めておいてほしい本能があります。
それは
・怪我
・慢性的な痛み
を隠そうとする習性です。
野生の動物にとって、体の不調は
▶弱点を見せることになり
・捕食者に狙われたり
・群れから外されたり
する危険に繋がります。
そのため、犬は
本能的に痛みを隠そう
とします。
つまり彼らは、苦痛を我慢して
「元気なフリ」
をしてしまうことがあるのです。
痛みや不調のサインを見逃さないで!
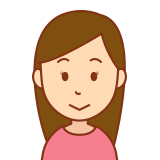
うちの子、元気そうに見えるけど、もしかして…?
という視点を持つことが非常に大切です。
普段の様子との
わずかな変化
に気づいてあげることが病気の
・早期発見
・早期治療
そして
・愛犬の苦痛を和らげること
に繋がります。
●行動の変化
・いつもより遊びたがらなくなった
・散歩に行きたがらない
・落ち着きがなくなった
・やたらと甘えてくるようになった
・特定の場所を触られるのを嫌がる
など。
●食事の変化
・食欲がない
・食べ方がおかしい(食べにくそう)
・水を飲む量が変わった
・増えた
・減った
など。
●排泄の変化
・回数、量、色、形状の変化
・排泄を我慢する
・粗相が増えた
など。
●体の変化
・特定の部位を気にしている
・舐める
・噛む
・姿勢がおかしい
・背中を丸める
・足を引きずる
・歩き方がぎこちない
・震えがある
・呼吸が速い
など。
●表情の変化
・目つきがぼんやりしている
・口角が下がっている
・不安げなカーミングシグナル
・あくび
・体をかく
・鼻をなめるなど
が頻繁に見られる
など。
「いつもとちょっと違うな」
「なんだか変だな」
と少しでも感じたら、迷わず動物病院に相談することをおすすめします。
愛犬は言葉で「痛い」とは言えません。
彼らが安心して快適に暮らせるよう
私たち飼い主が
彼らの小さなサイン
を見逃さないようにすることが
究極の愛情表現
と言えるでしょう。
5.飼い主との関係性と「しつけ」:習性を理解して絆を深める
・犬
・飼い主
の関係は、何よりも
信頼関係
が重要です。
この信頼は
▶犬の習性を理解し
▶それに基づいて適切に接する
ことで深まります。
●信頼関係の構築
飼い主さんが
・穏やかで一貫した態度で接し
・犬の習性を理解し
▶その気持ちに寄り添うこと
が大切です。
犬は
予測可能な環境
で安心感を覚えます。
●適切なコミュニケーション
犬のボディランゲージを理解し
▶彼らが発するサインを読み取ること。
そして、飼い主からも
・明確なサイン
・はっきりとした言葉
でコミュニケーションを取ることで、犬は安心して行動することができます。
●リーダーシップ
飼い主が
・穏やかで
・安定した
リーダーとして適切な指示を出すことで
▶犬は群れの秩序を理解し
▶安心して生活できます。
これは
・力で支配するのではなく
・信頼と尊重に基づいた関係性
を築くことを意味します。
犬のしつけは、これらの習性を理解した上で行うことで
・より効果的に
・そして犬に負担なく
進めることができます。
●褒めるしつけの重要性
悪い行動を叱るのではなく
▶良い行動を褒めて教える
ことが非常に重要です。
犬は褒められることで喜び、その行動を繰り返すようになります。
これは、犬が学習する上で最も効果的な方法の一つです。
●社会化の徹底
子犬の
社会化期(生後4週齢~12週齢)
は、犬の
生涯の性格形成
に非常に重要な時期です。
この時期に、さまざまな
・人
・犬
・環境
・音
・匂い
に慣れさせることで
▶社会性を身につけさせ
・将来の不安
・問題行動
を減らすことができます。
●一貫性のある対応
家族全員で
・しつけのルール
・指示の出し方
を統一し
一貫した態度で接する
ことが
▶犬の混乱を防ぎ
▶しつけの成功
に繋がります。
あいまいな
・指示
・ルール
は、犬を不安にさせてしまいます。
犬の習性は
・多様であり
・個体差もあります
しかし、基本的な理解を持つことで
▶愛犬との絆をより一層深め
▶共に幸せな日々を送る
ことができるでしょう。
あなたの愛犬が今日も見せてくれる
可愛らしい仕草
の裏には
・長い歴史
・賢い知恵
が隠されているのかもしれませんね。




コメント