犬の尿検査は
・腎臓
・泌尿器系
の病気だけでなく
・糖尿病
・肝臓病など
全身性の疾患
に関する貴重な情報を与えてくれる
・非侵襲的で
・重要
な検査です。
尿は体内の老廃物を排泄する
「お便り」
のようなもの。
その
・色
・成分
を調べることで、愛犬の健康状態を多角的に把握することができます。
・身体を傷つける
・体内に器具を挿入する
などせずに、行われる医療行為や測定など
身体への負担が非常に少ない!
ここでは犬の尿検査の主要項目の
・その意味
・基準値の目安
・異常が見られた場合に考えられること
・薬やサプリメントの影響
そして
・一歩進んだ豆知識
などを項目ごとに詳しく解説します。
●基準値はあくまで目安です。
・動物病院
・検査方法
・採尿方法
によって異なります。
必ず検査を受けた動物病院で示された基準値と照らし合わせてください
●検査結果の解釈は総合的に
一つの項目だけで判断せず
・他の検査項目(特に血液検査)
・臨床症状
・犬種
・年齢
・採尿方法
・尿の新鮮度
などを考慮し
獣医師が総合的に診断します。
●ここの情報は一般的なもの
・自己判断せず
必ず獣医師の説明を受けてください
●尿検査は新鮮な尿で
時間が経つと
・成分が変化したり
・細菌が増殖したり
することがあります。
・採尿方法
・提出までの時間
についても獣医師の指示に従ってください。
本ページは詳細をお伝えするため
長いです
「簡単に尿のチェックをしたい!」
そんなときは
以下のページをご参考ください
1. 物理的検査(性状検査)
尿の
・見た目
・量
などを評価します。
1.1. 外観(色調、混濁度=にごり)
●意味
尿の
・色
・透明度
を肉眼で観察します。
●正常な状態
◇色調
淡黄色〜黄色透明
・飲水量
・尿の濃縮度
により濃淡は変動します
◇混濁度
透明(新鮮尿の場合)
●異常な所見と主な原因
◇無色透明
・多尿
・腎不全
・糖尿病
・クッシング症候群
・尿崩症など
・飲水過多
◇濃い黄色〜琥珀色
・濃縮尿
・脱水
・飲水不足
・黄疸
・ビリルビン尿
◇赤色〜ピンク色
・血尿
・尿路結石
・膀胱炎
・腫瘍
・外傷
・腎疾患など
・ヘモグロビン尿
・溶血性疾患
・ミオグロビン尿
・筋肉の広範な損傷
◇褐色〜黒色
・重度の血尿
・メトヘモグロビン尿
・メラノーマ(まれ)
◇乳白色・白濁
・膿尿
・細菌感染
・リン酸塩や炭酸塩結晶
・アルカリ尿時
・脂肪尿
・リンパの流れが悪くなる
・特定の病気(フィラリア症、糖尿病など)
が原因で起こることがあります
・乳び尿
(リンパ液が尿路に混入した際に発生)
◇緑色・青色
・緑膿菌感染(まれ)
・特定の薬剤(メチレンブルーなど)
●薬やサプリメントの影響
◇一部のビタミン剤
(特にビタミンB群)で尿が蛍光黄色になることがあります。
◇特定の薬剤
・スルファサラジンでオレンジ色
・メトロニダゾールで暗赤褐色など
で尿色が変化することがあります。
●その他情報
◇タンパク尿
・尿が泡立ちやすく
▶泡がなかなか消えない場合は
タンパク尿の可能性があります。
尿中に正常値よりも多くのタンパク質が排泄される状態
・腎臓
・泌尿器
の機能に何らかの問題があることを示唆
◇新鮮尿でも結晶が多いと濁って見えることがあります。
◇時間の経過とともに
・細菌が増殖したり
・結晶が析出したり
して混濁することがあります。
1.2. 尿量 (参考情報)
●意味
1日に排泄される尿の量。
・自宅での観察
・入院管理下
で測定します。
●基準値の目安
約 20〜40 mL/体重kg/日
(飲水量や環境により大きく変動)
●異常な所見と主な原因
◇多尿 (基準より明らかに多い)
・糖尿病
・慢性腎不全の初期〜中期
・クッシング症候群
・尿崩症
・肝不全
・高カルシウム血症
・低カリウム血症
・特定の薬剤の投与
・利尿剤
・ステロイドなど
・精神性多飲
◇乏尿 (基準より明らかに少ない)
・脱水
・急性腎障害
・慢性腎不全の末期
・尿路閉塞
・ショック
◇無尿 (尿が全く出ない)
・完全な尿路閉塞
・重篤な急性腎障害
緊急事態です
●その他情報
◇多飲多尿
・飲水量
・尿量
のバランスは非常に重要です。
「多飲多尿」
は様々な病気のサインとなり得ます。
◇正確な尿量測定
には入院管理が必要です。
しかし自宅でもペットシーツの
・濡れ具合
・交換頻度
などで変化に気づくことができます。
1.3. 尿臭 (参考情報)
●意味
尿の臭い。
主観的な評価です。
が病気のヒントになることも。
●正常な状態
特有の芳香臭(犬種や食事内容によって多少異なります)。
●異常な所見と主な原因
◇アンモニア臭が強い
・細菌性膀胱炎
(細菌が尿素を分解するため)
・尿の放置
◇甘酸っぱい臭い (アセトン臭、ケトン臭)
甘酸っぱく、リンゴや果物が腐ったような独特な臭い
・糖尿病性ケトアシドーシス
・長期の絶食や飢餓
◇腐敗臭・悪臭
・重度の細菌感染
・組織の壊死
●その他情報
◇食事内容
特にタンパク質の多い食事によっても尿臭は変化します。
◇尿臭の変化
だけで病気を診断することはできませんが、他の所見と合わせて考慮されます。
2. 化学的検査(尿試験紙検査)
尿試験紙を用いて
尿中の様々な化学物質の
・有無
・濃度
をある程度数値的に評価します。
2.1. 尿比重 (USG)
●意味
尿の濃さ
=尿中に溶けている物質の濃度
を示します。
腎臓の尿濃縮・希釈能力
を反映する重要な指標です。
●測定方法
試験紙よりも
屈折計(=尿比重計)
で測定するのが最も正確。
試験紙の比重項目
は犬では不正確なことが多いです。
●基準値の目安
1.015〜1.045 (飲水状況や個体により変動)
◇適切に濃縮された尿
一般的に1.030以上
◇等張尿
1.008〜1.012
腎臓での
・濃縮
・希釈
が行われていない状態
●高値で考えられること (尿が濃い)
・脱水
・飲水不足
・急性腎障害(乏尿期)
・心不全(腎血流量低下)など
◇脱水時には
体は水分を保持しようとするため、腎臓は尿を濃縮します。
●低値で考えられること (尿が薄い)
・飲水過多
・慢性腎不全(尿濃縮能低下)
・糖尿病
・クッシング症候群
・尿崩症
・肝不全
・ステロイド剤や利尿剤の投与
◇慢性腎不全では
▶腎臓の尿細管機能が低下し
▶尿を十分に濃縮できなくなるため
▶薄い尿が多量に出る
「多飲多尿」
が見られます。
USGが持続的に
等張尿(1.008~1.012)
を示す場合は
腎機能の約2/3が失われている
可能性があります。
●薬やサプリメントの影響
◇利尿剤の投与で低下します。
◇見かけ上尿比重が高くなる
・ブドウ糖
・タンパク質
が尿中に多量に存在する場合
●その他情報
◇尿比重は
単独で評価せず、必ず
・飲水状況
・体の水分バランス
・血液検査(特にBUN、CRE)
と合わせて評価します。
◇腎臓の濃縮力低下が強く疑われる
脱水しているにもかかわらず
▶尿比重が低い場合(例:1.020以下)
◇早朝尿(一晩絶水後の尿)は
最も濃縮された尿であり
腎臓の濃縮力
を評価するのに適しています。
2.2. 尿pH
●意味
尿の
・酸性度
・アルカリ性度
を示します。
・体の酸塩基平衡(体の調節機能)の状態
・特定の結晶の形成しやすさ
と関連します。
●基準値の目安
5.5〜7.5
犬は肉食傾向のため、やや酸性〜中性が多い
●酸性尿 (pH < 7.0) では
・高タンパク食
・飢餓
・代謝性アシドーシス
・糖尿病性ケトアシドーシス
・腎不全など
・呼吸性アルカローシス
肺から二酸化炭素が過剰に排出され、血液のpHが上昇した状態
・特定の薬剤(塩化アンモニウムなど)
◇結晶が析出しやすい環境です
・シュウ酸カルシウム結晶
・シスチン結晶
・尿酸塩結晶など
●アルカリ尿 (pH > 7.0) では
・植物性の多い食事
・尿路感染症
・ウレアーゼ産生菌による
・代謝性アルカローシス
・持続的な嘔吐による体内の酸喪失など
・呼吸性アシドーシス
・尿の放置
・細菌増殖
・二酸化炭素の逸脱
・特定の薬剤
・重曹
・クエン酸カリウムなど
◇結晶などが析出しやすい環境
・ストラバイト結晶
(=リン酸アンモニウムマグネシウム結晶)
・リン酸カルシウム結晶
・炭酸カルシウム結晶など
●薬やサプリメントの影響
◇ビタミンCの大量摂取で尿が酸性化することがあります。
◇尿pHを調整する目的の
薬剤
・塩化アンモニウム
・クエン酸カリウムなど
他サプリメント
・クランベリーなど
があります。
●その他情報
◇食後
一時的に尿pHがアルカリ性に傾く
「アルカリ潮」
が見られることがあります。
◇尿路感染症を伴うストラバイト結石症では、持続的なアルカリ尿が見られることが多いです。
◇結晶について
尿pHは
結晶の種類を推定する
上で重要な手がかりとなります
しかし結晶の種類は
必ず顕微鏡で
確認する必要があります。
2.3. 尿タンパク質 (Protein)
●意味
尿中に排泄される
タンパク質の
・有無
・量
通常、健康な犬の尿にはごく微量しか含まれません。
●基準値の目安
試験紙法では
・「陰性(-)」
・または「痕跡(±)」
●陽性(+以上)で考えられること
◇腎前性タンパク尿
・発熱
・激しい運動
・ストレス
・痙攣
・ヘモグロビン尿
・ミオグロビン尿など
(一過性で生理的な場合もある)
◇腎性タンパク尿
・糸球体疾患
・糸球体腎炎
・アミロイドーシスなど
アミロイドと呼ばれるナイロンに似た線維状の異常蛋白質が全身の様々な臓器に沈着し、機能障害をおこす病気の総称
・尿細管間質性腎炎
・腎盂腎炎
★持続的なタンパク尿
=慢性腎臓病(CKD)の重要なマーカー
◇ 腎後性タンパク尿
・尿路の炎症
・膀胱炎
・尿道炎
・出血
・結石
・腫瘍
・生殖器からの混入
・精液
・膣分泌物など
◇試験紙法では
主にアルブミンを検出します。
・アルカリ尿
・消毒薬の混入
で偽陽性を示すことがあります。
また
▶非常に濃縮された尿では
▶正常でも微量のタンパクが検出されることがあります。
●薬やサプリメントの影響
一部の薬剤
・ペニシリン
・サルファ剤など
で偽陽性となることがあります。
●その他情報
◇持続的なタンパク尿がある場合
その重症度を評価するために
UPC(尿タンパク/クレアチニン比)
という追加検査が行われます。
UPCは
▶尿の濃縮度に影響されにくく
▶より正確にタンパク尿の程度を評価できます。
慢性腎臓病の
・診断
・ステージ分類
・予後判定
に非常に重要です。
◇タンパク尿の原因の特定
・尿沈渣検査
・血液検査
・画像検査
場合によっては
・腎生検
などが必要になります。
◇自然排尿で採尿した場合
膣や包皮からの分泌物が混入し、偽陽性となることがあります。
2.4. 尿ブドウ糖 (グルコース, Glucose)
●意味
尿中のブドウ糖の有無。
通常、血液中のブドウ糖は
▶腎臓の糸球体でろ過された後
▶尿細管でほぼ完全に再吸収される
そのため、尿中にはほとんど検出されません。
●基準値の目安
試験紙法では「陰性(-)」
●陽性(+以上)で考えられること
◇高血糖性糖尿
血糖値が
腎臓の再吸収能力の限界値
(犬では約180〜220 mg/dL)
を超えた場合。
糖尿病が最も代表的です。
その他
・クッシング症候群
・急性膵炎
・ストレス(特に猫)
・ブドウ糖含有輸液の投与後など
◇腎性糖尿
血糖値は正常範囲内でも
腎臓の尿細管
でのブドウ糖再吸収機能が低下している状態。
・ファンコニ症候群
腎臓が本来再吸収すべき物質
(ブドウ糖、アミノ酸、尿酸、リン酸、重炭酸水素塩など)
を尿中に排泄してしまう疾患
・遺伝的素因(犬種は特にバセンジー)
・後天的な原因(薬剤、重金属中毒など)
で起こります
・急性腎障害
・一部の遺伝性疾患など。
★糖尿病を強く疑う所見です。
持続的な尿糖陽性が見られたら、必ず血糖値を確認します。
●薬やサプリメントの影響
◇偽陽性または偽陰性
・ビタミンCの大量摂取
・一部の抗生物質
(セファロスポリン系など)
による偽陽性または偽陰性
◇副腎皮質ステロイド剤の投与
▶血糖値を上昇させ
▶尿糖の原因となることがあります。
●その他情報
◇尿糖試験紙は
酸化酵素反応を利用しているため
・還元物質(ビタミンCなど)
・酸化剤(漂白剤など)
の混入で影響を受けることがあります。
2.5. 尿ケトン体 (Ketone bodies)
●意味
脂肪がエネルギーとして利用される際に
肝臓で作られる代謝産物
・アセトン
・アセト酢酸
・β-ヒドロキシ酪酸
●基準値の目安
試験紙法では「陰性(-)」
●陽性(+以上)で考えられること
◇糖尿病性ケトアシドーシス (DKA)
インスリン作用の著しい不足により
▶体がエネルギー源としてブドウ糖を利用できず
▶代わりに脂肪を過剰に分解することで産生されます。
生命を脅かす緊急状態です。
◇その他
・長期の絶食
・飢餓
・重度の嘔吐や下痢
・高脂肪・低炭水化物食
・妊娠
・授乳期など。
◇尿糖とケトン体が同時に陽性の場合
糖尿病性ケトアシドーシスを強く疑います。
特有の甘酸っぱいアセトン臭
がすることがあります。
●薬やサプリメントの影響
特定の薬剤
・カプトプリル
・メスナなど
で偽陽性となることがあります。
●その他情報
◇尿試験紙は主に
・アセト酢酸
・アセトン
を検出し
β-ヒドロキシ酪酸に対する感度は
・低いか
・検出しません。
しかし
糖尿病性ケトアシドーシスでは
β-ヒドロキシ酪酸を最も多く産生。
そのため
試験紙が陰性でも
ケトーシス(血中ケトン体高値)が存在することがあります。
血中ケトン体の測定がより正確です。
2.6. 尿ビリルビン (Bilirubin)
●意味
古くなった赤血球のヘモグロビンが分解されてできる黄色い色素。
通常は
▶肝臓で処理され
▶胆汁中に排泄されます
が一部は尿中にも排泄されます。
●基準値の目安
健康なオスで微量(±〜+程度)検出されることがあります。
メスでは通常陰性です。
猫では常に陰性が正常です。
●陽性で考えられること
・メスで+以上
・オスで++以上など
◇肝疾患
・肝炎
・肝硬変
・肝臓腫瘍などによる肝細胞障害や胆汁うっ滞
◇胆道閉鎖・閉塞
◇溶血性疾患
赤血球の破壊亢進によるビリルビン産生過剰
★犬の腎臓は
ビリルビンをある程度
・代謝
・排泄
する能力があります。
そのため
▶血中ビリルビン値が上昇する前に
▶尿中ビリルビンが陽性になる
ことがあります。
=黄疸の早期発見
に役立つことがあります。
●薬やサプリメントの影響
一部の薬剤
・フェノチアジン系薬剤
・アスコルビン酸など
で偽陽性または偽陰性となることがあります。
●その他情報
◇尿試験紙で検出されるのは主に抱合型(直接)ビリルビンです。
◇尿を長時間光に当てると
▶ビリルビンが分解され
▶偽陰性になることがあります。
◇犬のオスでは
特に濃縮尿の場合、生理的に
微量のビリルビンが検出される
ことがあります。
そのため、その意義は他の所見と合わせて慎重に判断します。
2.7. 尿ウロビリノーゲン (Urobilinogen)
●意味
腸内細菌によって
▶ビリルビンから作られ
▶一部が再吸収されて尿中に排泄される物質。
●基準値の目安
「正常」または微量陽性
●高値で考えられること
・溶血性疾患
・ビリルビン産生亢進
・肝実質障害(初期や軽度の場合)
●低値または陰性で考えられること
◇完全胆道閉塞
ビリルビンが腸管に排泄されない
▶ウロビリノーゲンが作られない
◇広域スペクトラム抗生物質の長期投与
=多くの細菌に対して効果のある抗生物質
腸内細菌叢の変化による
尿ウロビリノーゲンの臨床的意義は限定的とされています。
不安定な物質であり、尿が
・酸性であったり
・光に長時間さらされたり
すると分解されて偽陰性になりやすいため、解釈には注意が必要です。
単独で診断的価値を持つことは少ないです。
●薬やサプリメントの影響
尿中に着色物質が存在すると、偽陽性を示すことがあります。
2.8. 尿潜血 (Occult blood / Hemoglobin)
●意味
尿中に血液成分
・赤血球
・ヘモグロビン
・ミオグロビン
が含まれているかどうかを調べます。
●基準値の目安
試験紙法では「陰性(-)」
●陽性(+以上)で考えられること
◇血尿
尿路
・腎臓
・尿管
・膀胱
・尿道
の出血。
原因として
・結石
・感染症
・膀胱炎
・腎盂腎炎
・腫瘍
・外傷
・凝固異常
・特発性腎出血など
尿沈渣で赤血球が確認されます。
◇ヘモグロビン尿
血管内で
▶赤血球が大量に破壊(溶血)され
▶ヘモグロビンが尿中に出た状態。
原因として
・免疫介在性溶血性貧血(IMHA)
・タマネギ中毒
・遺伝性溶血性貧血
・重度の感染症など
尿沈渣では赤血球は
・少ない
or
・見られません。
血漿も赤色を呈します。
◇ミオグロビン尿
筋肉細胞が
▶広範に損傷し
▶筋肉中のミオグロビンが尿中に出た状態。
原因として
・重度の外傷
・熱中症
・激しい運動
・毒物(一部の蛇毒など)。
尿沈渣では赤血球は
・少ない
or
・見られません。
血漿は正常色です。
★試験紙法では上記3つを区別できません。
・尿沈渣検査
・血液検査
・臨床症状
と合わせて鑑別します。
●薬やサプリメントの影響
◇ビタミンC
大量摂取で偽陰性となることがあります。
◇酸化作用のある物質
消毒薬などの混入で偽陽性となることがあります。
●その他情報
◇他陽性になる場合
・カテーテル採尿
・膀胱穿刺
では、処置に伴い微量の出血が起こり、潜血が陽性になることがあります。
また
・メス犬の発情期
には、外陰部からの血液混入で陽性となることがあります。
◇尿潜血が陽性で
▶尿沈渣に赤血球が見られない場合
・ヘモグロビン尿
・ミオグロビン尿
を疑います。
2.9. 尿白血球 (Leukocytes)
●意味
尿中の白血球の存在を示し、主に
・炎症
・感染
を示唆します。
●基準値の目安
試験紙法では「陰性(-)」
●陽性(+以上)で考えられること
・尿路感染症
・膀胱炎
・腎盂腎炎
・尿道炎
・尿路結石や腫瘍による炎症
・生殖器系の炎症からの混入
・前立腺炎
・子宮蓄膿症
・膣炎など
尿試験紙における白血球の項目は
▶偽陽性や偽陰性が多く
▶信頼性が低いとされています。
特に猫ではほとんど反応しません。
必ず尿沈渣検査での白血球数を確認する必要があります。
●薬やサプリメントの影響
尿中に着色物質が存在すると、判定に影響することがあります。
●その他情報
尿沈渣で白血球が多数確認されれば
・炎症
・感染
が強く疑われます。
その場合
▶細菌の有無も確認し
▶必要であれば尿の
・細菌培養検査
・感受性試験
を行います。
2.10. 尿亜硝酸塩 (Nitrite)
●意味
尿中の特定の細菌
硝酸塩を亜硝酸塩に還元する細菌
=主にグラム陰性桿菌
の存在を示唆します。
●基準値の目安
試験紙法では「陰性(-)」
●陽性(+以上)で考えられること
・細菌性尿路感染症
(特に大腸菌などのグラム陰性桿菌)
この試験紙の感度は低く
偽陰性が多い
そのため
▶陰性であっても
▶細菌感染を否定できません。
理由として
・犬の尿は膀胱に溜まる時間が短い
・全ての細菌が硝酸塩を還元するわけではない
ことなどが挙げられます。
・尿沈渣での細菌確認
・培養検査
がより重要です。
●薬やサプリメントの影響
ビタミンCの大量摂取で偽陰性となることがあります。
3. 尿沈渣検査(顕微鏡検査)
尿を遠心分離し
▶沈殿した固形成分=尿沈渣を
▶顕微鏡で観察します。
尿路系の
・細胞
・結晶
・細菌
などを直接確認できる非常に重要な検査です。
3.1. 赤血球 (RBC)
●意味
尿中の赤血球の数。
●基準値の目安
0〜5個/HPF(強拡大視野)
●多数出現で考えられること (血尿)
◇尿路
・腎臓
・尿管
・膀胱
・尿道
のいずれか、または複数の
・炎症
・感染
・結石
・腫瘍
・外傷
・凝固異常
◇腎臓からの出血
・糸球体腎炎
・腎梗塞など
◇生殖器系からの混入
・発情
・前立腺疾患
・子宮疾患など
★赤血球の形態も重要です。
◇均一な形態であれば
=下部尿路(膀胱や尿道)からの出血
◇大小不同or変形した赤血球
特に有棘赤血球など
=腎臓(糸球体)由来の出血を示唆
※ただし、犬では判断が難しいことも多い
赤血球の表面に不規則なトゲ状の突起が多数ある状態
●その他情報
◇採尿方法によって出現数が変動
・膀胱穿刺では
=通常ほとんど見られません
・カテーテル採尿
・自然排尿(特に中間尿でない場合)
では
=尿道や外陰部からの混入で少数見られることがあります。
◇尿比重が低い尿中(薄い)では
▶赤血球が膨張して溶け
▶「ゴースト細胞」として観察されることがあります。
細胞が死んでしまって内部構造が消失し、輪郭だけが残った状態の細胞
3.2. 白血球 (WBC)
●意味
尿中の白血球の数。
●基準値の目安
0〜5個/HPF
●多数出現で考えられること (膿尿)
◇尿路の炎症
特に細菌感染
・膀胱炎
・腎盂腎炎
・尿道炎
◇尿路結石や腫瘍に伴う炎症
◇生殖器系からの混入
・前立腺炎
・子宮蓄膿症
・膣炎など
白血球の種類(主に好中球)も確認します。
細菌と一緒に
多数の白血球
が見られる場合は
細菌性尿路感染症
が強く疑われます。
●その他情報
◇尿試験紙の
白血球項目よりも
はるかに信頼性が高い
評価です。
◇汚染された容器や古い尿では
▶細菌が増殖し
▶白血球が破壊されている
が、炎症は存在した
可能性もあります。
3.3. 上皮細胞
尿路の様々な部位から剥がれ落ちた細胞。
・種類
・数
によって
・炎症の部位
・炎症の程度
を推測する手がかりになります。
●扁平上皮細胞
◇由来
・尿道遠位部
・膣
・包皮
◇臨床的意義
通常、特に自然排尿では
少数見られるのは正常。
多数出現する場合は
・外部からの汚染
まれに
・扁平上皮癌
の可能性も考慮。
●移行上皮細胞
◇由来
・腎盂
・尿管
・膀胱
・尿道近位部
◇臨床的意義
少数見られるのは正常。
カテーテル採尿ではやや多いことも。
多数出現する場合は
・炎症
・結石
・腫瘍(移行上皮癌など)
・異型細胞など
●尿細管上皮細胞
◇由来
腎臓の尿細管
◇臨床的意義
通常はほとんど見られません。
多数出現する場合は
腎尿細管の障害
・急性腎障害
・腎盂腎炎
・中毒など
を示唆します。
●その他情報
◇移行上皮癌が
疑われる場合
細胞診の専門家による評価が推奨されます。
◇炎症が強いと
上皮細胞も変性して
▶形態が変化することがあります。
3.4. 円柱 (Casts)
腎臓の尿細管内で
・タンパク質
・細胞
などが固まって形成される
細長い円筒状の構造物。
種類によって
・腎臓のどの部分に?
・どんな問題があるか?
を示唆します。
●硝子円柱
◇成分
主にタンパク質(ムコタンパク)
◇臨床的意義
健康な犬でも
少数見られることがあります。
・激しい運動後
・発熱
・脱水
・軽度の腎疾患
などでも増加。
多数出現する場合は
・持続的なタンパク尿
・腎疾患
の可能性
●顆粒円柱
◇成分
・変性した細胞
・タンパク質の顆粒
を含む。
◇臨床的意義
腎尿細管の
・細胞変性
・壊死
を示唆。
・慢性腎臓病
・急性腎障害
・糸球体腎炎
などで見られます。
硝子円柱よりも
病的な意義が高い
とされます。
●蠟様円柱
◇成分
変性が進行した顆粒円柱。
◇臨床的意義
・慢性で重篤な腎疾患
・尿流の停滞
を示唆。
予後不良のサイン
となることがあります。
●細胞円柱
◇赤血球円柱
腎臓内での出血
・糸球体腎炎
・腎梗塞など
を示唆。
◇白血球円柱
腎臓内での炎症
特に腎盂腎炎を示唆
◇上皮細胞円柱
(尿細管上皮細胞円柱)
腎尿細管の重篤な障害
・急性尿細管壊死など
を示唆。
●脂肪円柱
◇成分
脂肪滴を含む。
細胞内に存在する中性脂質が、リン脂質の一重膜に囲まれた構造体のこと
◇臨床的意義
・糖尿病
・ネフローゼ症候群など
脂質代謝異常
を伴う腎疾患で見られることがあります。
腎臓の糸球体の異常によって
▶尿から大量のタンパク質が漏れ出し
▶血液中のタンパク質が減ってしまう病態
全身のむくみ(浮腫)が起こるのが特徴
●その他情報
◇新鮮な酸性尿での観察が重要
円柱は尿pHが
アルカリ性になると溶けやすい
ため、必ず新鮮な尿を観察します
◇円柱の種類と数
腎疾患の
・診断
・重症度評価
に非常に役立ちます。
3.5. 結晶 (Crystals)
尿中に溶けている物質が
▶飽和状態になり
▶析出したもの。
・種類
・数
・尿pH
などから
・結石症のリスク
・結石症の種類
を推定する手がかりになります。
●ストラバイト
(リン酸アンモニウムマグネシウム)
◇形状
・無色の直方体(棺の蓋状)
・羽毛状
・シダの葉状など。
◇出現しやすい尿pH
アルカリ性 (pH > 7.0)
◇臨床的意義
尿路感染症、特に
ウレアーゼ産生菌
に伴って形成されやすい。
犬で最も一般的な結石の一つ。
・食事療法
・感染コントロール
が重要。
●シュウ酸カルシウム
◇形状
・二水和物
・無色の正八面体(封筒状、X印)
・一水和物
・ダンベル状
・卵円形
・柱状
※より重篤な
・高カルシウム尿症
・エチレングリコール(不凍液)中毒
を示唆することがある
◇出現しやすい尿pH
酸性〜中性 (pH < 7.0)
◇臨床的意義
・高カルシウム血症
・高シュウ酸尿症
・特定の食事
で形成されやすい。
ストラバイトに次いで多い結石
遺伝的素因もあるので
・ミニチュア・シュナウザー
・ヨークシャー・テリアなど
はさらに要注意
●尿酸アンモニウム
◇形状
・黄褐色の球状でとげとげした形状
(ソーンアップル状)
・束状
◇出現しやすい尿pH
中性〜アルカリ性
◇臨床的意義
・肝機能障害
=特に門脈体循環シャント
・遺伝的素因(尿酸代謝異常のため)
・ダルメシアン
・ブルドッグ
などで見られやすい。
●シスチン
◇形状
無色の扁平な六角板状
◇出現しやすい尿pH
酸性
◇臨床的意義
遺伝性のシスチン尿症で見られる。
アミノ酸の再吸収障害によるもの。
特定の犬種
・ダックスフンド
・ニューファンドランド
・ブルドッグなど
に好発。
●ビリルビン結晶
◇形状
・黄色〜赤褐色の針状
・顆粒状。
◇出現しやすい尿pH
酸性
◇臨床的意義
・肝疾患
・胆汁うっ滞
・溶血性疾患など
ビリルビン尿が見られる状態。
●コレステロール結晶
◇形状
無色の大きな扁平な板状で、角が欠けている
◇出現しやすい尿pH
酸性
◇臨床的意義
ネフローゼ症候群など
・重度のタンパク尿
・脂質代謝異常
で見られることがまれにある。
●薬剤結晶
特定の薬剤(サルファ剤など)が
▶尿中に高濃度で排泄されると
▶結晶化することがある。
●その他情報
◇健康な犬でも、特に
・濃縮尿
・冷却された尿
では少量の結晶が見られることがあります。
その場合
・臨床症状
・他の検査所見
と合わせて意義を判断します。
◇結晶の種類によって
結石の予防法
・食事療法
・pHコントロールなど
が異なります。
◇尿を冷蔵保存すると
結晶が析出しやすくなります。
そのため、新鮮尿での検査が理想。
もし冷蔵した場合は、検査前に常温に戻してから観察します。
3.6. 細菌 (Bacteria)
●意味
尿中の細菌の有無。
●基準値の目安
・膀胱穿刺尿では
=通常無菌
・カテーテル採尿
・自然排尿では
=外部からの汚染で少数見られることがある。
●多数出現で考えられること
・尿路感染症
・膀胱炎
・腎盂腎炎など
白血球と共に多数見られることが多い。
◇確定診断のために
・細菌の形態
・球菌
・桿菌
・染色性
・グラム陽性
・グラム陰性
も参考になります。
・確定診断
・適切な抗生物質の選択
のためには、尿の
・細菌培養検査
・感受性試験
が推奨されます。
●その他情報
◇無症候性細菌尿
無症状でも
細菌尿が見られることがあります。
特に基礎疾患
・糖尿病
・クッシング症候群など
を持つ犬では注意が必要です。
治療の要否は獣医師が判断します。
◇尿のpHや特定の結晶の存在
細菌の種類を推測する手がかりになることも
【例】
アルカリ尿+ストラバイト結晶
→ウレアーゼ産生菌感染の可能性
3.7. 酵母・真菌 (Yeast / Fungi)
◇意味
尿中の
・酵母
・真菌
の有無。
◇臨床的意義
通常は見られません。
・免疫力の低下した犬
・抗生物質の長期投与後
・糖尿病
・カテーテル留置
などで
真菌性尿路感染症(カンジダなど)
を起こすことがあります。
・皮膚
・生殖器
からの汚染の可能性も考慮します。
3.8. 精子 (Spermatozoa)
◇意味
尿中の精子の有無。
◇臨床的意義
オスの未去勢犬では、特に
・自然排尿
・カテーテル採尿
の場合に見られることがあります。
通常、病的な意義はありません。
・精液の逆流
・前立腺疾患
の可能性も考慮。
3.9. 脂肪滴 (Fat droplets)
◇意味
尿中の脂肪の球
◇臨床的意義
健康な犬でも
少数見られることがあります。
・カテーテル潤滑剤の混入
・肥満
・糖尿病
・甲状腺機能低下症
・ネフローゼ症候群
などで増加することがあります。
4. その他特記事項
採尿方法の選択とその影響
●自然排尿
最も非侵襲的。
中間尿(出始めと終わりを除いた尿)
を採取するのが望ましい。
ただし、外部からの
・細菌
・細胞
の汚染が最も多い。
●カテーテル採尿
膀胱から直接採尿。
自然排尿より汚染は少ないが
・処置に伴う微量の出血
・細胞混入
・細菌感染
のリスクがある。
●膀胱穿刺
腹壁から針を刺して膀胱から直接採尿。
細菌培養検査に最も適した方法
=汚染が最も少ない。
・鎮静
・超音波ガイド下
で行われることが多い。
微量の出血を伴うことがある。
下超音波装置(エコー)を用いて
▶その画像をリアルタイムで確認しながら
▶針の挿入や処置を行うこと
獣医師は
・検査の目的
・犬の状態
に応じて最適な採尿方法を選択します。
尿の保存と提出
◇尿は採取後
▶できるだけ速やかに
(理想は30分〜1時間以内)
▶検査するのが望ましいです。
◇すぐに検査できない場合
密閉容器に入れて冷蔵保存(2〜4℃)し
▶24時間以内に検査します。
ただし、冷蔵すると
・結晶が析出しやすくなったり
・pHが変化したり
することがあります。
提出時には
「冷蔵していたこと」
を伝えましょう。
◇凍結保存は
細胞成分が破壊されるため、一般的には行いません。
UPC (尿タンパク/クレアチニン比) の重要性
持続的なタンパク尿は
腎臓病の
・早期発見
・進行度評価
・治療効果判定
に非常に重要です。
UPCは
▶尿の濃さの影響を受けずに
▶タンパク尿の程度を客観的に評価
できるため、近年その重要性がますます高まっています。
尿検査と血液検査の組み合わせ
尿検査の結果は
血液検査の結果
と合わせて解釈することで、より多くの情報を得ることができます。
【例えば】
・尿比重が低いにもかかわらず
・BUNやCREが高い場合
▶腎機能低下を強く示唆
他にも
・尿糖陽性で
・血糖値も高い場合
▶糖尿病を強く疑います。
定期的な尿検査の推奨
症状がなくても
特に
・中高齢の犬
・慢性疾患を持つ犬
では、定期的な尿検査が病気の早期発見に繋がることがあります。
この情報が
▶愛犬の尿検査結果を理解し
▶健康管理に役立てるための一助となれば幸いです。
繰り返しになりますが
・検査結果の解釈
・診断
・治療方針
については、必ず獣医師にご相談ください。

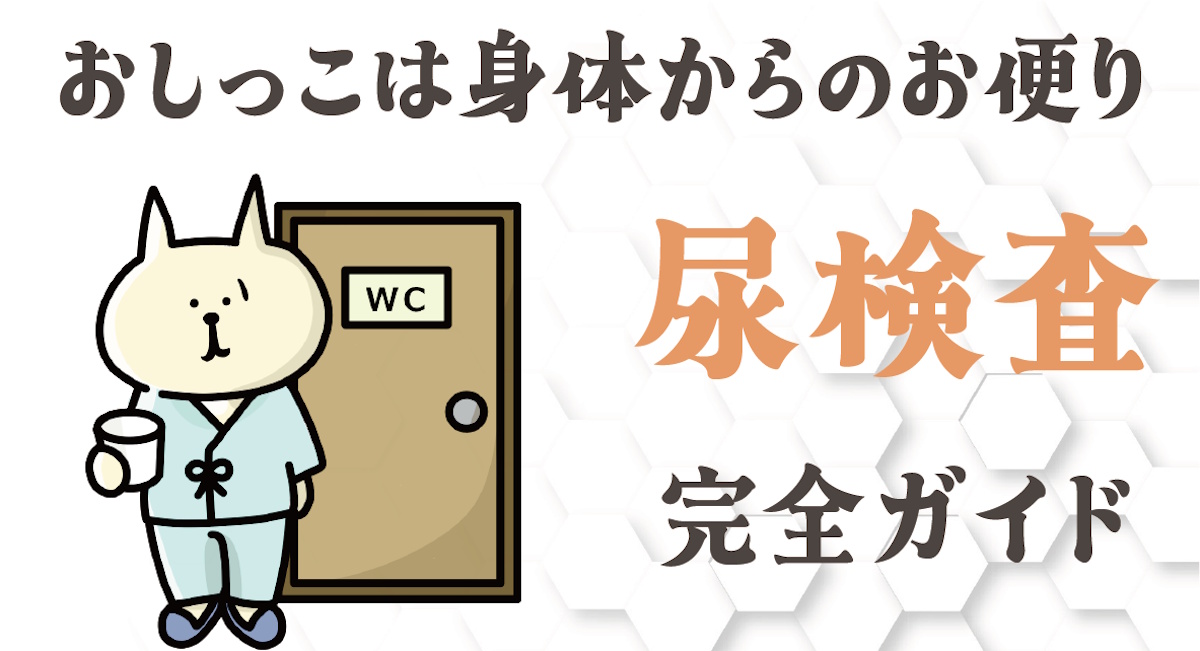
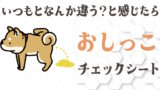
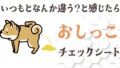

コメント