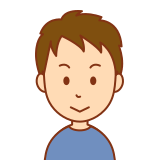
うちの子、なんか水めっちゃ飲むし、おしっこも増えたみたいやわ
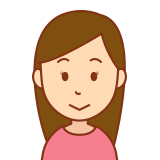
うちの子は最近、お腹がぽっこり出てきた気がする
愛犬にこのような変化が見られたら!
それは
クッシング症候群
のサインかもしれません。
クッシング症候群は
副腎から分泌される
コルチゾール
というホルモンが過剰になることで引き起こされる病気です。
すぐさま命に関わる病気ではありません
しかし放置すると
・糖尿病
・高血圧
・膵炎など
重篤な合併症を引き起こす可能性があり
愛犬の生活の質(QOL)
を著しく低下させてしまいます。
そのため
・早期発見
・適切な治療
そして
・生涯にわたる丁寧なケア
が非常に重要です。
この記事では
犬のクッシング症候群について
・原因や症状
・診断・治療法
・食事管理
・治療にかかる費用
・飼い主さんが家庭でできること
など
・深掘り情報
・役立つ豆知識
を交えながら、徹底的に解説します。
・愛犬の健やかな毎日
・快適なシニアライフ
を守るために、ぜひ最後までお読みください。
1. 犬のクッシング症候群とは? — ホルモンの異常が引き起こす病気
犬のクッシング症候群は
正式には
副腎皮質機能亢進症
(ふくじんひしつきのうこうしんしょう)
と呼ばれます。
体内のコルチゾールが
▶慢性的に過剰になることで発症。
コルチゾール=
・副腎皮質から分泌される
・ステロイドホルモンの一種。
以下のような生命維持に欠かせない重要な働きをしています。
しかし、このコルチゾールが
何らかの原因で
▶過剰に分泌され続ける
▶体の様々なシステムに悪影響
▶特徴的な症状を引き起こす
という症状なのです。
主な原因は3つのタイプ
クッシング症候群の原因は
大きく分けて3つ。
それぞれ治療法が異なります。
1.下垂体性クッシング症候群
●原因
脳の下垂体にできた腫瘍(ほぼ良性)が
▶副腎を刺激するホルモンを過剰に分泌
(=ACTH:副腎皮質刺激ホルモン)
▶過剰なACTHによって副腎が刺激
▶コルチゾールを過剰分泌し発症
●特徴
犬のクッシング症候群の
80〜85%
を占める最も一般的なタイプです。
小型犬に多く見られる傾向
2.副腎腫瘍性クッシング症候群
●原因
副腎自体に腫瘍(良性または悪性)ができ
▶その腫瘍がコルチゾールを自律的に過剰に分泌することで発症。
●特徴
約15〜20%を占めます。
大型犬に比較的多い。
腫瘍が悪性の場合=副腎癌
は予後が悪いこともあります。
3.医原性クッシング症候群
●原因
・アレルギー
・自己免疫疾患など
の治療のために
▶ステロイド薬を長期間・大量に投与
▶体がコルチゾールが過剰な状態と認識
▶同様の症状を引き起こすものです。
●特徴
このタイプは
原因となるステロイド薬を
獣医師の指示のもと
で徐々に
・減量
・中止
することで改善が見込めます。
★自己判断での中止は
非常に危険
です。
薬によって
▶コルチゾール分泌機能が抑制されている
▶急に中止すると命に関わる「アジソン病(副腎皮質機能低下症)」のような状態に陥る可能性。
必ず獣医師の指示に従いましょう。
かかりやすい犬種や年齢
●好発犬種
・プードル
・ダックスフンド
・ビーグル
・ボストン・テリア
・ボクサー
などが知られています。
●年齢
多くは6歳以上のシニア犬で発症。
ですがどの年齢でも発症する可能性はあります。
2. どんな症状が現れるの? — 見逃さないで!愛犬からのサイン

これ実はクッシング症候群の症状やったんやな・・・いつものことと思って全然気にしてなかったわ・・・
クッシング症候群の症状は
非常にゆっくりと進行
します。
なので初期には
「年のせいかな?」
と見過ごされがちです。
しかし以下の
□複数のサインに当てはまる場合
▶早期発見のために
▶早めに動物病院を受診しましょう。
□多飲多尿
最もよく見られる症状です。
・水を飲む量
・おしっこの量
が異常に増え、夜間の排尿回数が増えることもあります。
◆なぜ?
コルチゾールが
▶腎臓での水の再吸収を妨げ
▶抗利尿ホルモンの働きを抑制
するためです。
□多食
食欲が異常に旺盛になります。
◆なぜ?
・コルチゾールが食欲中枢を刺激する
・また血糖値を上昇させ
▶インスリン抵抗性を引き起こす
▶細胞が糖を十分に利用できなくなる
▶脳がエネルギー不足と判断する
ためと考えられています。
□腹部膨満(お腹がぽっこり膨らむ)
・お腹がポコッと出ている
・たるんでいる
と表現されることが多いです。
◆なぜ?
・脂肪の再分布(胴体に集中)
・筋肉の萎縮
・肝臓の腫大(ステロイド肝)
などが複合的に関与するためです。
□脱毛・皮膚症状
◇脱毛
特に
体幹部分に左右対称に脱毛
が見られ
・毛艶が悪くなったり
・薄くなったり
します。
◇皮膚の菲薄化(ひはくか)
皮膚が薄くなり
・血管が透けて見える
・打ち身や擦り傷ができやすくなる
などします。
◇色素沈着
黒ずんだ斑点が見られることがあります。
◇皮膚の石灰沈着症(皮膚石灰沈着症)
皮膚に
・白いブツブツとした
・硬いしこり
ができることがあります。
これはコルチゾールがカルシウム代謝に影響を与えるためです。
◇皮膚感染症(膿皮症)を繰り返すこともあります。
◆なぜ?
コルチゾールが
▶毛周期を休止させ
▶皮膚のコラーゲン生成を抑制するため
□筋力低下・筋肉の萎縮
足腰が弱くなり
・立ち上がりが困難になる
・散歩を嫌がる
・段差を上れなくなる
などします。
□パンティング(荒い呼吸)
暑くもないのに、ハァハァと浅く速い呼吸をすることがあります。
◆なぜ?
コルチゾールの影響で
・体温調節機能に異常が生じる
・呼吸筋が弱まったりする
ためと考えられています。
□元気消失・活動性の低下
全体的に活力が低下し
・以前より活発さがなくなる
・寝てばかりいるようになる
・散歩や遊びに興味を示さなくなる
などもあります。
□その他
◇生殖能力の低下
・メスでは発情周期の乱れ
・オスでは精巣の萎縮
が見られることがあります。
◇合併症
・糖尿病
(コルチゾールが血糖値を上げるため)
・膵炎
・高血圧
・血栓症
のリスク増加など
様々な合併症を引き起こす可能性。
初期症状の見逃しがちポイント
クッシング症候群の初期症状は
・加齢による変化
・他の一般的な病気
と区別がつきにくいことがあります。
●多飲多尿は
「年のせいでおしっこが近くなった?」
●お腹の膨らみは
「太ったのかな?」
と見過ごされがちです。
また
●パンティングも
「暑がっているのかな?」
と解釈されやすい症状。
愛犬の
「いつもと違う」
・小さな変化に気づき
・メモしておき
獣医さんに相談する際に役立てることが
・早期発見
・早期治療
につながる重要なポイントです。
3. 予防はできるの? — 早期発見がカギ
残念ながら
・下垂体性
・副腎腫瘍性
といった自然発生型のクッシング症候群を確実に予防する方法は、現在のところ確立されていません。
多くの場合
・遺伝的要因
・加齢
によるものです。
しかし
医原性クッシング症候群
は、獣医師の指示のもとで
ステロイド薬を適切に使用
することによって予防が可能です。
どのタイプのクッシング症候群においても、定期的な健康診断による
・早期発見
・早期治療
が最も重要です。
●特にシニア期に入ったら
半年に一度程度は健康診断を。
・血液検査
・尿検査
で異常が見つかることがあります。
●行動の観察
日頃から愛犬の
・飲水量・排尿量
・食欲
・体重
・被毛や皮膚の状態
・行動の変化
を注意深く観察しましょう。
少しでも気になる点があれば、すぐに獣医さんに相談することが大切です。
●直接的な予防にはなりませんが
・バランスの取れた食事
・適度な運動
を毎日続けることで
・健康的な体を維持し
・合併症のリスクを減らす
ことにつながります。
4. 診断と治療薬 — 生涯にわたるコントロールを目指す
クッシング症候群の診断は
・症状の確認
・血液検査
・尿検査
・超音波検査など
複数の検査を組み合わせて行われます。
特に
・ACTH刺激試験
・低用量デキサメタゾン抑制試験
といった特殊な血液検査が診断確定に不可欠です。
治療は
・原因
・症状の重症度
によって異なります。
主に内科療法が中心となります。
目的は
・コルチゾール値を正常範囲に管理
・症状を緩和し
・合併症を予防すること
です。
完治を目指すというよりは
病気と上手に付き合っていく
ことが目標となります。
代表的な治療薬・治療法
1.トリロスタン(商品名:アドレスタン、ベトリールなど)
現在、最も一般的に使用されている薬。
●作用
副腎でのコルチゾール合成に必要な酵素の働きを直接阻害
▶コルチゾール分泌を抑制します。
●副作用
・食欲不振
・嘔吐
・下痢
・元気消失など
が比較的多く見られます。
まれに、コルチゾールが過剰に抑制されることで
アジソン病(副腎皮質機能低下症)
を引き起こす可能性があります。
これは命に関わるため、注意深いモニタリングが必要です。
●食事との兼ね合い
一般的に
食事と一緒にまたは食後すぐに
投与することが推奨されます。
これにより、薬の吸収が良くなるとされています。
必ず獣医師の指示に従ってください。
●その他
トリロスタンは
効果の持続時間が比較的短いため
▶1日1回または2回の投与が必要です。
・投与量
・回数
は定期的な血液検査(ACTH刺激試験など)の結果を見ながら慎重に調整されます。
2.ミトタン(商品名:オペプリム、リスドレン®など)
●作用
副腎皮質細胞を破壊する
▶コルチゾール分泌を抑制する薬。
かつては主流でしたが
・副作用が強く
・調整が難しい
ため、現在ではトリロスタンが第一選択となることが多いです。
●副作用
・食欲不振
・嘔吐
・下痢
・神経症状など
トリロスタンよりも重篤な副作用が出やすい傾向があります。
アジソン病のリスクも高いです。
●食事との兼ね合い
ミトタンも吸収を安定させるために
食事と一緒に投与すること
が推奨されます。
特に高脂肪食との併用で吸収が促進されるという報告もありますが、個体差が大きいため、獣医さんの指示に従うことが重要。
その他の治療法
●外科療法
副腎腫瘍性クッシング症候群の場合
手術による腫瘍の摘出
が最も有効な治療法です。
・腫瘍が良性で
・転移がなく
・手術が可能な場合
は根治を目指せる可能性がありますが、リスクの高い手術です。
●放射線療法
下垂体腫瘍が大きく
神経症状
・ふらつき
・旋回
・意識障害など
を引き起こしている場合に検討も。
専門的な施設での実施となり、費用も高額です。
治療の注意点
●治療開始後は
・定期的な血液検査(ACTH刺激試験など)
・診察
が不可欠です。
薬の
・効果
・副作用
をチェックし、投与量を慎重に調整します。
●薬の投与は
必ず獣医師の指示通りに行い
・自己判断で中断したり
・量を変更したり
しないでください。
治療薬選択の裏側とジェネリック薬
トリロスタンの
・投与量設定
・維持量の調整
は非常にデリケートです。
コルチゾールが少なすぎると
▶アジソン病を引き起こす
可能性があるため
▶定期的なACTH刺激試験を行い
▶慎重に用量を調整します。
獣医師は
・犬の個体差
・症状の重さ
・基礎疾患など
を総合的に判断して、最適な治療薬と投与量を決定しています。
近年
トリロスタンのジェネリック薬
も流通し始めています。
・費用を抑えたい場合
に選択肢となり得ます。
が!
ジェネリック薬は
・先発薬と全く同じというわけではなく
・吸収性や効果にわずかな違いがある
可能性もゼロではありません。
変更を検討する際は
・必ず獣医師さんと十分に話し合い
・愛犬の状態を慎重にモニタリングする
必要があります。
5. 食事で気を付ける点・療法食 — 体の中からサポート

うちの子クッシング症候群になってもうたんやけど…どんなごはんがええの?
クッシング症候群の犬にとって
食事管理は
・治療をサポートし
・QOL(生活の質)を維持するため
非常に重要な役割を果たします。
特定の「治療食」として明確に確立された療法食は少ないです。
それでも
・症状の管理
・合併症の予防
のために、食事内容に配慮することは非常に重要です。
食事管理の基本方針
●高タンパク質
コルチゾールの影響で
筋肉のタンパク質が分解されやすい状態
のため
・筋肉量の維持
・筋肉量の改善
を目指して、良質なタンパク質を十分に補給することが重要です。
●低脂肪
コルチゾールが原因で
高脂血症になりやすい傾向
があるため、脂肪の摂取は控えめに。
また、膵炎のリスクも考慮されます。
●低炭水化物(特に単純炭水化物)
コルチゾールが
血糖値を上昇させる
ため
▶血糖値の急激な上昇を避ける必要
▶消化しやすい良質な炭水化物を適量に抑えることが推奨されます。
●適切な食物繊維
・便秘の予防
・食欲亢進への対応
・血糖値の急上昇を抑える
ために、適度な食物繊維を含む食事が良いとされています。
●ナトリウム(塩分)の制限
・多飲多尿の症状を悪化させないため
・また高血圧のリスクを考慮して
ナトリウム含有量の少ない食事。
●水分補給の徹底
多飲多尿のため
▶脱水になりやすい
▶常に新鮮な水を十分に用意
▶いつでも飲めるように
療法食の活用
多くのメーカーから
クッシング症候群の合併症
・糖尿病
・高脂血症など
に対応した療法食が販売されています。
これらの療法食は、上記の基本方針に基づいて栄養バランスが調整されていることが多いです。
療法食は、一般的なフードとは栄養組成が大きく異なります。
必ず獣医師の
・診断
・推奨
に基づいて
・選択
・給与
してください。
・ 糖尿病を併発している場合
=糖尿病用の療法食
・腎臓病を併発している場合
=腎臓病用の療法食
が推奨されるなど、合併症に応じて選択肢が変わります。
強化すべき栄養素
●良質なタンパク質
筋肉の材料となります。
・鶏むね肉(皮なし)
・魚
・卵
・赤身肉
・豆腐
などが良い供給源です。
特に
BCAA(分岐鎖アミノ酸)は
▶筋肉の分解を抑え
▶合成を助けます。
●抗酸化物質
・ビタミンC
・ビタミンE
・β-カロテン
・セレンなど
コルチゾールの過剰分泌は
▶体内で酸化ストレスを増加
させる可能性があります。
これらの栄養素を適度に摂取することは、細胞の保護に役立つと考えられます。
緑黄色野菜や果物に含まれます。
●オメガ-3脂肪酸(EPA・DHA)
抗炎症作用があり
・皮膚炎
・関節の健康維持
に役立つ可能性があります。
青魚のオイルなどが良い供給源。
が、脂肪分なので与えすぎ注意。
魚からの摂取が望ましく
たんぱく源として新鮮な魚
を選択するのもおすすめです。
●ビタミンD・カルシウム
皮膚の石灰沈着症が見られる場合でも
▶骨粗しょう症のリスクがある
そのため適切な量の
・ビタミンD
・カルシウム
は重要。
ただし、過剰摂取は避けるべきです。
●ビタミンB群
・代謝機能の維持
・ストレスに対する体の抵抗力を高める
ために重要です。
控えるべき栄養素
●過剰な脂肪(特に飽和脂肪酸)
・高脂血症
・膵炎
・肥満
のリスクを高めます。
・脂身の多い肉
・高脂肪のおやつ
は避けましょう。
●高ナトリウム(塩分)
多飲多尿を悪化させ
▶高血圧のリスクを高めます。
・塩分の多い加工食品
・人間用の食事
は絶対に与えないでください。
●過剰な炭水化物(特に単純糖質)
血糖値を急激に上昇させ
▶糖尿病のリスクを高めます。
・白米
・パン
・おやつ
は控えめに。
●過剰なリン
腎臓に負担をかける可能性があります。
6. 治療費はどれくらいかかる? — 知っておきたい費用の目安
クッシング症候群の治療は
多くの場合
生涯にわたることが多い
ため、治療費も継続的にかかります。
あくまで一般的な目安としての参考です。
●診断費用
◇初期診断:
・血液検査
・尿検査
・超音波検査
・ACTH刺激試験
・低用量デキサメタゾン抑制試験など
数万円〜10万円程度
◇MRI検査:
・下垂体腫瘍の評価
・専門施設で実施
5万円〜15万円程度
★診断確定までに、合計で数万円〜十数万円かかることも珍しくありません。
●治療費用(内科療法の場合)
◇薬代(トリロスタン)
・犬の体重
・薬の用量
によりますが
月額1万円〜3万円程度
が目安です。
大型犬ほど高額になります。
◇定期的な検査費用
治療開始後も
・薬の効果
・副作用
を確認するために
・ACTH刺激試験
・血液検査
を定期的に行います。
2ヶ月〜3ヶ月に1回程度実施
1回あたり1.5万円〜3万円程度
かかります。
★年間で数十万円かかることも十分に考えられます。
●治療費用(外科手術の場合)
◇副腎腫瘍摘出術
数十万円〜100万円以上
かかることもあります。
・手術の難易度
・入院日数
・術後の管理
などによって変動
◇別途
・術前検査
・麻酔費用
・入院費用
・術後ケア費用
などが加算されます。
★総額で数十万円〜100万円以上かかることもあります。
7. 愛犬がクッシング症候群になったら:飼い主ができること・注意点
病気と診断されると不安になるかと思います。
しかし
・適切なケア
・愛情
があれば、クッシング症候群の愛犬も
・穏やかで
・幸せな
生活を送ることができます。
愛犬との豊かな生活のため
飼い主さんができることを知り、実践していきましょう。
獣医師との密な連携:病気と向き合うパートナー
・診断内容
・治療方針
・予後
について
納得いくまで
説明を受けましょう。
・疑問
・不安な点
はどんな些細なことでも遠慮なく相談し、指示をしっかり守ることが何よりも大切です。
そのため信頼できるかかりつけ医の選択は非常に重要になります。
定期的な診察を欠かさず、愛犬の状態を報告しましょう。
精神的なケア:ストレスは病状悪化の要因に
コルチゾールは
ストレスを受けると分泌が促進されるため
ストレスホルモン
とも呼ばれます。
ストレスは病状を悪化させる可能性。
そのため愛犬が
・安心して過ごせる静かな環境を整え
・優しく声をかけ
・スキンシップを大切にしましょう。
過度な興奮は避け、リラックスできる時間を作ってあげてください。
生活環境の整備:快適で安全な毎日を
●滑り止め
筋力低下に備え
床には
・カーペット
・マット
を敷き、滑りにくくしましょう。
●温度・湿度管理
体温調節が苦手になることがあるため
・室温
・湿度
を快適に保ちましょう。
●トイレ環境
多飲多尿になるため
・トイレシートを多めに置く
・散歩の回数を増やす
などの配慮が必要です。
必要であれば、おむつを使用することも検討しましょう。
日常の細やかなモニタリング:変化を見逃さない「見守りスキル」
症状の変化
□飲水量
□尿量
□食欲
□元気
□体重
□被毛や皮膚の状態
などを
・毎日チェック
・記録しておく
と診察時に正確な情報を伝えることができ、治療の調整に役立ちます。
●副作用のチェック
薬の副作用と思われる症状
・嘔吐
・下痢
・食欲不振
・元気消失など
見られたら、すぐに動物病院に連絡を
●早期発見のための「見守りスキル」
クッシング症候群は、典型的な症状が揃うまで時間がかかることがあります。
しかし、家族が日頃から愛犬の様子を「注意深く」見守ることで
・些細な変化に気づき
・早期発見につながる
可能性が高まります。
例えば
「最近、やけにお水を飲む量が増えたな」
「なんかお腹がポコッと出てる気がする」
「散歩で疲れやすくなったかな?」
など、漠然とした違和感でも良いのです。
それらをメモしておき、獣医さんに相談する際に役立てましょう。
・早期発見
・早期治療
は愛犬のQOLを大きく左右します。
合併症への注意:もう一つの重要な側面
・糖尿病
=さらに飲水量が増える、体重が減る
・高血圧
=元気消失、神経症状
・血栓症
=突然の呼吸困難、足の麻痺
・感染症
=皮膚炎、膀胱炎など
など、クッシング症候群は様々な合併症を引き起こす可能性があります。
これらの兆候にも気を配り、異変があれば速やかに獣医師に相談しましょう。
適切な運動と身体ケア:無理なく活動性を維持
筋肉の萎縮を防ぐためにも
▶無理のない範囲での
▶適度な運動は大切です。
愛犬の状態に合わせて
短い散歩を複数回行う
などの工夫をしましょう。
急な坂道や階段は避けるのが賢明。
●皮膚のケア
皮膚が弱くなっています。
掻きむしりによる二次感染を防ぐため
・爪をこまめに切る
・必要であればエリザベスカラーを使用
などすることも検討しましょう。
●口腔ケア
免疫力の低下により
▶歯周病などの口腔内のトラブル
も起こりやすくなります。
・定期的な歯磨き
・獣医さんによるデンタルチェック
も重要です。
最後に
犬のクッシング症候群は
生涯にわたる管理
が必要な病気です。
ですが
・飼い主さんの深い愛情と適切なケア
・獣医師との密な連携
によって
・症状をコントロールし
・愛犬のQOLを高く保つ
ことが可能です。
・病気を正しく理解し
・愛犬の変化に注意を払いながら
一日一日を大切に過ごしていきましょう。
この記事が、犬のクッシング症候群について深く理解し、愛犬のために最善を尽くす一助となれば幸いです。
愛犬のクッシング症候群 クイズ!あなたの知識を試そう
この記事で学んだ内容をクイズで確認!
全問正解目指して頑張ってくださいね!
Q1. 犬のクッシング症候群の最も一般的な症状として見られる組み合わせは次のどれでしょう?
Q2. 犬のクッシング症候群の最も多い原因として挙げられるものは次のどれでしょう?
Q3. クッシング症候群の治療で最もよく使われる薬「トリロスタン」の主な働きは次のどれでしょう?
Q4. トリロスタンを使用する際に、特に注意が必要な副作用で、命に関わる可能性もあるものは次のどれでしょう?

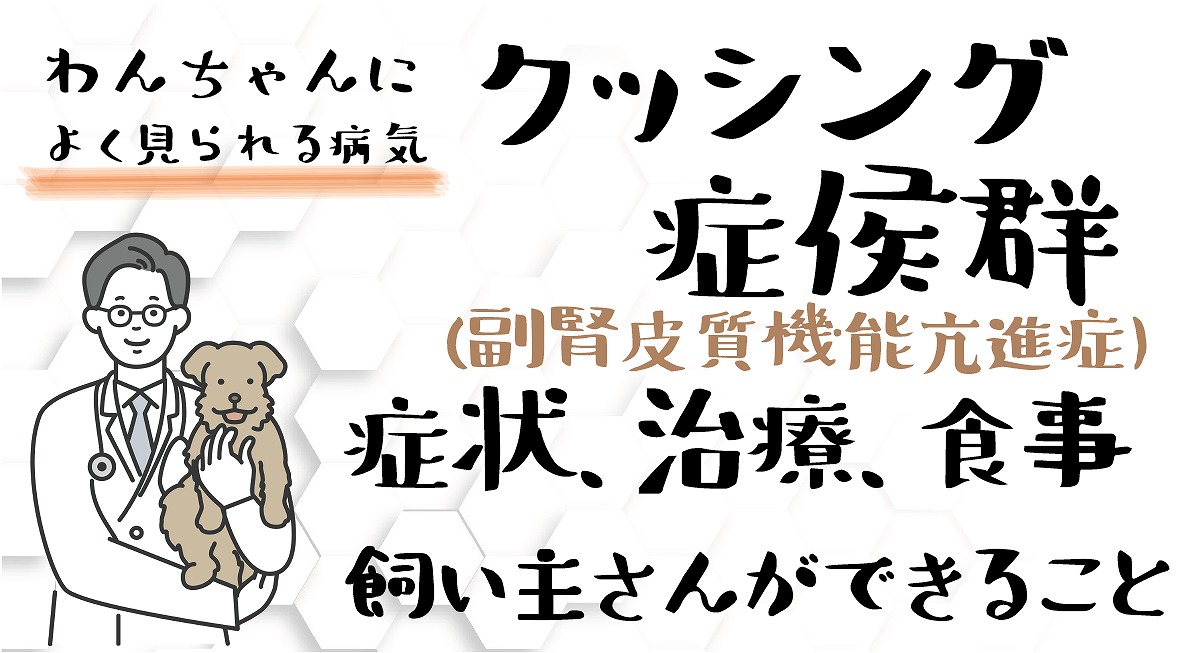


コメント