はじめに
なぜ家庭でドッグトレーナー級の知識が必要なのか?
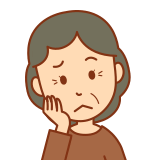
うちの子、トレーナーさんに任せれば完璧になるのに…
そう思っていませんか?
もちろんプロのトレーナーの技術は素晴らしいものです。
しかし、愛犬との本当の絆
は、日々の生活の中で
飼い主さん自身が築き上げていくもの。
家庭でドッグトレーナー並みの知識と技術を身につけることは、単にしつけや訓練ができるようになるだけでなく
・愛犬の気持ちを深く理解し
・より豊かなコミュニケーションを築く
ための第一歩なのです。
このガイドでは
プロのトレーナーが実践する
・考え方
・アプローチ
を家庭で実践できるよう、具体的な方法と知識を交えながら解説します。
あなたの愛犬が
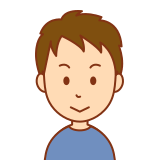
うちの子、天才かも!?
と思えるような、素晴らしいパートナーシップを築きましょう。
愛犬の「心」を理解する:犬の学習理論とボディランゲージ
ドッグトレーニングの第一歩は、犬がどのように学習し、どのようにコミュニケーションをとるかを理解することです。
犬の学習理論:なぜ「ご褒美」が重要なのか?
私たちはよく
「ご褒美で釣る」
と言います。
実はこれは犬の学習理論に基づいた非常に効果的なアプローチなのです。
●古典的条件付け(パブロフの犬)
・特定の刺激と
・反応
を結びつける学習方法です。
・「リード」と
・「散歩」
のように
・ある刺激(リード)が
・別の刺激(散歩)
を予期させることで、犬は興奮するようになります。
これをしつけに応用することで
例えば
・「マテ」の合図と
・「静かに待つ」
という行動を結びつけることができます。
●オペラント条件付け(スキナー)
・自発的な行動と
・その結果(ご褒美や罰)
を結びつけて学習する方法です。
◇正の強化
望ましい行動(例:おすわり)をしたとき
▶犬にとって嬉しいこと
((おやつ、褒める、撫でる)
を与える
ことで、その行動が増えるように促します。
これが家庭でのしつけの基本中の基本。
※ご褒美は「価値」を意識しましょう。
おやつだけでなく
・大好きなオモチャ
・撫でられること
・お散歩
など、その犬にとって何が最も価値があるかを観察し、使い分けましょう。
また、ご褒美を与えるタイミングは
「行動の直後」
が鉄則です。
0.5秒以内が理想とされます。
◇負の強化
嫌なことを取り除くことで、望ましい行動が増えるように促します。
例えば、散歩中引っ張りっこになる時
▶犬がリードを引っ張らないで歩く
▶飼い主もリードを引っ張るのを止める
といった、不快な刺激の除去
しかし不適切な負の強化は
・犬にストレスを与え
・行動問題を悪化させる可能性
があります。
そのため家庭犬のしつけでは非推奨。
◇正の罰
望ましくない行動(例:飛びつき)をした
▶犬にとって嫌なこと
(例:大きな音を出す)
を与える
ことで、その行動を減らします。
これも家庭犬のしつけでは極力避けるべき方法です。
関係性を悪化させる可能性が大!
◇負の罰
望ましくない行動(例:噛む)をした
▶犬にとって嬉しいことを取り除く
(例:遊びを中断する)
ことで、その行動を減らします。
これは有効な場合があります。
ですが
・犬がなぜその行動をするのか?
根本的な原因を探ることがより重要です
犬のボディランゲージ:言葉なき会話を読み解く
犬は言葉を話せませんが、全身を使ってコミュニケーションをとっています。
彼らのボディランゲージを理解することは
・愛犬の感情や意図を正確に読み取り
・信頼関係を築く
上で不可欠です。
特に犬は
・相手に安心感を与えたい
・ストレスや不安を感じている
・自分や相手の興奮を鎮めたい
・争いを避けたい
・不快なことを鎮めたい
・威嚇から逃げたい
そんなときには様々な
カーミングシグナル
・calming=落ち着かせる
・signal=信号
という
相手に自分の気持ちを伝える行動をとります。
ここでは、犬のボディランゲージの
・主な種類
・その意味について解説します。
1. 尻尾(しっぽ)
尻尾の動きは、犬の感情を理解する上で最も分かりやすいサインの一つです。
◇高い位置で速く振る
またはブンブンと大きく振る
喜び、興奮、自信、親しみ
を示します。
◇高い位置でゆっくり振る
・好奇心
あるいは相手の出方次第では
・攻撃的な意図
がある場合もあります。
◇水平に伸ばして振る
興味、好奇心、やや緊張している
状態です。
◇低い位置でゆっくり振る
力を抜いている
リラックス、安心
している状態です。
◇下がっている
または股の間に挟んでいる
不安、恐怖、怯え、服従、警戒心
を表します。
◇下がった尻尾の先だけを小刻みに振る
やや不安、心配、状況確認中
といった気持ちを表します。
◇右に振る
ポジティブな感情(嬉しい、友好的など)
◇左に振る
ネガティブな感情(警戒、嫌悪感など)
★尻尾の振り方だけでなく
・高さ
・硬さ
・振り幅
なども総合的に判断することが重要です。
尻尾が激しく振られていても、高さが低い場合は緊張していることもあります。
2. 耳
耳の動きは、犬の
・集中度
・感情の強さ
を示します。
◇ピンと立てて前に向ける
集中、緊張、警戒心、自信
を表します。
攻撃的な気持ちのサインでもあります。
◇リラックスして通常の位置
リラックスしている状態です。
◇横に向いている
不安や警戒
を示します。
◇後ろに倒れている
(頭に貼り付くように)
恐怖、不安、服従、弱気、又は嫌悪感
を示します。
3. 目
・目の動き
・表情
も、犬の感情を伝える重要な手がかり。
◇じっと見つめる
信頼、愛情、親しみを
示します。
しかし、場合によっては
敵意や威嚇
のサインにもなります。
※見知らぬ犬を見つめるのは控えましょう。
◇目をそらす、上目遣い
不安、敵意を避けたい、服従
の意思を示します。
◇大きく見開いている
白目が見える
興奮、恐れ、警戒、ストレスを感じている
可能性があります。
いわゆる「鯨の目」
不安やストレス、不快感
を示しているサインです。
相手に敵意がないことを示している
とも考えられます
◇目を細める、まばたきする
リラックス
あるいはストレスを感じている
サインでもあります。
◇瞳孔が広がっている
興奮、恐れ。
◇瞳孔が縮んでいる
リラックス。
★飼い主が犬の目を凝視し続けることは、犬にとってプレッシャーになることも。
アイコンタクトは重要ですが
・短時間で
・ポジティブなもの
にしましょう。
4. 口
・口の動き
・表情
も、犬の心理状態を読み解くヒント。
◇軽く開いている、歯が見えない
リラックスしている
状態です。
◇舌を出す(ハァハァしている)
楽しい、リラックスしている
あるいは暑い時に体温調節
をしている状態です。
◇口角が上がっている
(笑顔のように見える)
リラックス、友好
◇口を硬く閉じている
緊張、警戒、不安、集中。
◇歯を剥き出す
牙を見せる
うなる
威嚇、興奮、恐怖。
◇鼻をなめる
舌なめずりをする
口をくちゃくちゃさせる
落ち着かない、緊張、不安、ストレス
あるいは何かを訴えているサイン
リラックスしているときにも見られることがあります。
◇あくびをする
眠いだけでなく
ストレス、不安
相手を落ち着かせたい
「カーミングシグナル」
の可能性があります。
5. 姿勢・体全体
体全体の姿勢は、犬の
・感情
・意図
を総合的に表します。
◇リラックスした姿勢
(力が抜けている)
友好的、リラックスしている
状態です。
◇伏せる、お腹を見せる(仰向け)
最大限の服従
敵意がないこと、安心感
を示します。
◇前足を下げてお尻を高く上げる
(プレイバウ)
遊びに誘っている
サインです。
尻尾も振っていることが多いです。
ただし、この姿勢のままじっと動かない場合は、相手に落ち着いてほしいという「カーミングシグナル」の場合もあります。
◇体を固める
緊張している
背中を丸める
動揺、不安、恐怖
攻撃的になる前のサインです。
◇毛が逆立つ(特に背中)
恐怖、興奮、攻撃性、威嚇
を示します。
◇腰が引けている
後ずさりする
体を避ける
恐怖、不安
◇体をかがめる、姿勢を低くする
服従、恐怖
または遊びに誘っている
場合もあります。
◇立ち上がる、体を膨らませる
自信、主張、威嚇。
その他カーミングシグナル
犬は
・自分や相手の興奮を鎮めたり
・争いを避けたりする
ために様々な「カーミングシグナル」と呼ばれる行動をとります。
◇あくびをする
ストレス、不安、相手を落ち着かせたい
◇鼻をなめる、舌なめずりをする
ストレス、不安、緊張
◇顔をそむける、視線を外す
相手との緊張を和らげたい、敵意がないことを示したい。
◇地面の匂いを嗅ぐ、地面をひっかく
ストレス、不安、その場から逃れたい
◇体をかく、ブルブル震える
ストレス、緊張、不安
◇ゆっくり動く、座る
争いを避けたい、自分や相手を落ち着かせたい
◇弧を描いて近づく
(真っ直ぐ近づかない)
友好的な意図、相手に警戒心を与えないようにしている。
★愛犬の体全体を観察する習慣をつけましょう。
特に、いつもと違う
・姿勢
・動き
をしている場合
・体調不良
・ストレス
のサインかもしれません。
犬のボディランゲージは、一つだけでなく複数のサインを組み合わせて読み取ることが重要です。
例えば
・尻尾を振っていても
▶同時に耳が後ろに倒れている
▶目が大きく見開かれてる
場合は、必ずしも「嬉しい」という感情だけではない可能性があります。
日頃から愛犬の様子をよく観察し、それぞれのサインが示す意味を理解することで
・より深く愛犬の気持ちを理解し
・より良い関係を築く
ことができるでしょう
家庭で実践!基本のしつけと応用テクニック
ここからは
・具体的なしつけの方法と
・プロも使う応用テクニック
を紹介します。
吠え・噛みつき・トイレの解決策
これらの問題行動は、多くの場合
・犬のニーズが満たされていない
・または誤った学習をしている
ことが原因です。
吠え:なぜ吠えるのか?その原因と対策
●なぜ吠えるのか?
◇要求吠え
・ご飯
・散歩
・遊び
など、何かを要求している。
◇警戒吠え
見慣れない
・人
・音
に警戒している。
◇分離不安吠え
飼い主と離れることへの不安。
◇興奮吠え
・遊び
・散歩前
などに興奮して吠える。
◇退屈吠え
・刺激不足
・運動不足
★吠える行為は、犬にとって「表現」。
ただ止めさせるのではなく
なぜ吠えているのか?
その根本原因を探ることが重要です。
●対策
◇要求吠え
要求には応じない。
吠えが止まってから、望ましい行動(例:座る)をしたら要求を満たす。
◇警戒吠え
外の音や人に慣らす(社会化)。
吠え始めたら、ご褒美で注意をそらす。
「ハウス」などで安全な場所に誘導する。
・カーテンを閉める
・テレビをつける
など、外部刺激を遮断することも一時的な対策になります。
◇分離不安吠え
留守番練習を短時間から始める。
留守番中に犬が安心して過ごせる環境を整える
・安心できるベッド
・長時間遊べるおもちゃ
◇興奮吠え
・「マテ」や
・「フセ」で
興奮する前に落ち着かせる練習。
遊び始める前にクールダウンさせる。
◇退屈吠え
・適切な運動量
・知的な刺激
(知育玩具、ノーズワークなど)
を提供する。
噛みつき:甘噛みと本気噛みの見極めと対処法
●なぜ噛むのか?
◇子犬の甘噛み
遊びの一環、歯の生え変わりによるむず痒さ。
◇要求噛み
・構ってほしい
・遊んでほしい。
◇恐怖、不安による噛みつき
・追い詰められた
・身の危険を感じた
◇痛みによる噛みつき
体のどこかに痛みがある。
◇縄張り、独占欲による噛みつき
オモチャやご飯を奪われそうになった。
★噛みつきは犬にとって最終手段です。
それまでに様々なボディランゲージでサインを出していることが多いので、それらを見逃さないことが重要です。
●対策
◇甘噛み
負の罰
噛まれたらすぐに遊びを中断し、無視。
噛んでもいいオモチャを与える。
★人の手を噛んでくる場合
指に匂いが残っているなど、手を口に入れたくなるような環境になっていないかを見直しましょう。
◇要求噛み
噛みつきが止まってから要求に応じる。
噛まない行動にご褒美を与える。
◇恐怖、不安による噛みつき
・その原因となるものを取り除く
・無理強いしない
・安心できる環境を作る。
◇痛みによる噛みつき
動物病院で診察を受ける。
◇縄張り、独占欲による噛みつき
・物
・場所
への執着をなくすトレーニング
(交換練習など)
トイレのしつけ:失敗しないための実践的アプローチ
●なぜ失敗するのか?
◇トイレの場所が覚えられない
適切な場所に誘導できていない。
◇間に合わない
トイレのタイミングを逃している。
◇ストレス、不安
環境の変化や不安から粗相をする。
◇病気
膀胱炎など。
●対策
◇サークル内でのトイレトレーニング
狭い空間で排泄場所を限定し、成功体験を積ませる。
◇成功報酬
トイレでできたらすぐに大袈裟に褒めてご褒美を与える。
◇タイミングの見極め
・食後
・寝起き
・遊びの後
など、トイレに行きたくなるタイミングで誘導する。
◇においの消臭
失敗した場所は徹底的に消臭する。
犬はにおいで場所を覚えるため。
★トイレシートの場所を頻繁に変えない
また
シートの上で遊ばせない
ことも重要です。
★犬の集中力は短い
成功報酬は
・短く
・シンプル
そして
・継続的
に与えましょう。
叱るより教える!ポジティブな訓練の鉄則
「叱る」
ことは
・犬との信頼関係を壊し
・不安や恐怖心を植え付ける
可能性があります。
望ましい行動を
「教える」
ことが、家庭犬トレーニングの基本です。
「待て」「ふせ」「おすわり」の応用
★これらのコマンドは、単なる芸ではなく
・興奮を鎮める
・危険から身を守る
・公共の場でマナーを守る
ための基本的なツールです。
●教え方(共通)
◇ルアーリング(誘導)
ご褒美で誘導して望ましい姿勢に導く。
◇言葉とジェスチャー
姿勢ができた瞬間にコマンドを言う
例:「オスワリ!」
と同時にご褒美。
◇成功報酬
大袈裟に褒めてご褒美。
◇繰り返し
様々な
・場所
・状況
で練習し、徐々に時間を伸ばす。
★「マテ」は
ご褒美を目の前に置いても我慢できるレベルまで練習すると、衝動制御能力が向上します。
★最初は
ご褒美を常に持っている状態から始め
・徐々に隠したり
・与えるタイミングをランダムに
することで、犬のモチベーションを維持できます。
アイコンタクト:全ての基本となる「集中」の練習
飼い主の目を見て指示を待つ習慣は、全てのトレーニングの土台となります。
●教え方
◇ご褒美を
鼻先に持っていき、ゆっくりと目の位置に持っていく。
◇犬が目を合わせた瞬間
「GOOD!」と褒めてご褒美。
◇アイコンタクトの時間が伸びたら
徐々に「見て」などの合図を追加。
★犬が自発的に
アイコンタクトをとるように仕向けることが重要です。
散歩中、名前を呼んでアイコンタクトが取れたら褒める、なども良い練習になります。
クリッカートレーニング:犬が「考える」ことを促す
・クリック音と
・ご褒美
を結びつけ、望ましい行動の瞬間にクリック音を鳴らすことで、
「今、これが正解だった!」
と愛犬に明確に伝えるトレーニング方法。
●メリット
・タイミングが正確
・犬が主体的に考えるようになる
・集中力が向上する。
●教え方
◇ローディング
クリック音を鳴らしたら
▶すぐにご褒美を与える
を繰り返す(数回)。
愛犬は
・クリック音が
・ご褒美と結びついている
ことを学習する。
◇シェイピング
望ましい行動に近づくたびにクリック
▶ご褒美を与える。
例えば、「フセ」を教えるなら
▶お尻を下げた瞬間にクリック
▶床に伏せた瞬間にクリック
など。
★クリッカーがない場合
「Yes!」などの短いポジティブな言葉で代用できます。
ただし、常に同じトーンで言うことが重要です。
問題行動予防:社会化と環境エンリッチメント
問題行動の多くは
・適切な社会化ができていないこと
・犬の満たされない欲求
が原因です。
社会化の重要性
●様々な
・人
・犬
・環境(音、匂い、場所)
に慣れさせることで、新しい経験に対して柔軟に対応できる犬になります。
●実施時期
生後3週齢から16週齢が最も重要ですが、成犬になってからでも遅すぎることはありません。
●社会化の例
◇様々な年齢、性別の人間と触れ合わせる
(優しく撫でてもらう、おやつをもらうなど)
◇他の犬と安全な場所で交流させる
(ドッグランやしつけ教室など)
◇色々な場所に連れて行き
(公園、駅、車の中など)
様々な音や匂いに慣れさせる。
◇掃除機やドライヤーなどの生活音に慣れさせる。
●強制的な社会化
かえって逆効果です。
・犬のペースを尊重し
・ポジティブな経験を積み重ねさせる
ことが重要です。
嫌がったらすぐに中断し、別の方法を試しましょう。
環境エンリッチメント:退屈させない工夫
●犬の身体的・精神的な欲求を満たす
ことで、問題行動の発生を防ぎます。
例えば
◇知育玩具
おやつを詰めるタイプのおもちゃ。
犬が頭脳を使って取り出すことを促す。
◇ノーズワーク(嗅覚トレーニング)
隠されたおやつを探させるなど
・犬の嗅覚を使い
・集中力を高める
宝探しのような遊び
◇ガムや硬いおやつ
噛む欲求を満たす。
◇定期的な運動
適切な散歩時間と運動量。
◇新しい場所への散歩
毎回同じコースではなく、たまには違う道を歩くことで、新しい刺激を与える。
★犬の退屈は
・破壊行動
・過剰な吠え
に繋がることがあります。
知育玩具は、留守番中のストレス軽減にも非常に有効です。
愛犬ともっと仲良くなる!意思疎通と絆を深める秘訣
ドッグトレーナーが意識しているのは、単に芸を教えることだけではありません。
・犬との「対話」を重視し
・深い絆を築く
ことを目指します。
ルーティンの重要性:犬の安心感を育む
犬は予測可能な環境で安心します。
一貫したルーティンは
・犬のストレスを軽減し
・安心感
を与えます。
◇規則正しい生活
・起床時間
・食事の時間
・散歩の時間
・就寝時間
などをできるだけ一定にする。
◇トイレのタイミング
も一定にする。
◇遊びの時間
もできる限り同じタイミングで。
★完璧なルーティン
は難しいかもしれません
大まかな時間帯を決めるだけでも愛犬の精神的な安定に繋がります。
褒める言葉のレパートリーと声のトーン
「良い子!」
だけでなく、様々な
・言葉
・トーン
で褒めることで、犬は飽きずにモチベーションを維持できます。
●言葉の例
「グッド!」
「すごいね!」
「えらい!」
「パーフェクト!」
●声のトーン
・喜びや興奮を伝える高い声と
・落ち着いて褒める低い声
を使い分ける。
★犬は言葉の意味だけでなく
・声のトーン
・抑揚
・表情
をよく見ています。
心から褒める気持ちを込めることが大切です。
犬のサインを読み解く「観察力」を磨く
プロのトレーナーは、犬の小さな変化を見逃しません。
日頃から愛犬を注意深く観察する習慣をつけましょう。
●日々の健康チェック
□食欲
□飲水量
□排泄の状態
□目の輝き
□被毛の状態
などを毎日確認する。
●行動の変化
いつもと違う行動
□食欲不振
□元気がない
□特定のものに怯える
などがないか注意する。
●ボディランゲージの観察
□ストレスサイン
□不安サイン
を見逃さない。
★普段から愛犬の
「普通」の状態を知っておくことで、異変にすぐに気づけるようになります。
飼い主の気持ちと犬の学習の関係
私たちの感情は、犬に敏感に伝わります。
飼い主がイライラしていると
・犬も不安になったり
・指示が入らなくなったり
します。
●冷静さを保つ
トレーニング中は特に、落ち着いてポジティブな気持ちで接する。
●一貫した態度
家族全員で
・同じルール
・同じコマンド
を使う。
●忍耐力
すぐに結果が出なくても焦らない。
犬のペースに合わせて進める。
★飼い主が楽しみましょう!
犬もトレーニングを楽しいものだと認識します。
家庭でできる!犬の「芸」「技」入門
ドッグトレーナーのように、愛犬に色々な芸を教えることは
・犬との絆を深め
・知的好奇心を満たす
素晴らしい方法です。
覚えさせたい「技」と「芸」の教え方
●基本中の基本
愛犬に「技」を教えるときは
・言葉の合図と
・愛犬の動作
を関連付けるように練習することが大切。
◇短時間で教える
集中力が切れる前に練習を終えます。
◇一貫性
家族全員で
・同じ言葉や
・シグナル
を使用します。
◇焦らず
・焦らず
・根気強く
犬のペースに合わせて練習を進めます。
◇褒める
成功したら、しっかりと褒めましょう。
◇休憩
集中力が切れたら、休憩を挟みます
具体的な技と訓練法
●おすわり
①ご褒美を犬の鼻先に持って行く
▶それを頭上に向けて動かすことで、犬が自然と座る姿勢になるように誘導。
②おしりが床についたときに
「おすわり!」と声かけし、褒めてご褒美。
●お手
①愛犬をお座りさせます
②「お手」と声かけ
▶飼い主の手のひらに愛犬の前足を乗せる
▶すぐご褒美
③ご褒美の後すぐに前足を下ろしてあげる
※①~③を繰り返し教える
※「おて」ができたら逆の前足で「おかわり」も教えましょう。
●ふせ
①ご褒美を犬の鼻先に持っていき
▶ゆっくりと地面に向かって下げる
②愛犬が自然と伏せの姿勢になったら、
「ふせ!」と声かけし、褒めてご褒美。
※最初は、ご褒美で誘導しながら愛犬が伏せの姿勢を取るまで繰り返し練習します。
●ゴロン(横になる)
①「ふせ」をさせる。
②ご褒美を犬の肩から耳の方向に弧を描くように動かし、体が横になるように誘導する。
③体が横になった瞬間に「ゴロン!」と声かけし、ご褒美。
●まて
①「おすわり」をさせる
②愛犬に「待て」のコマンドを出し、
同時に手で合図(手を差し出すなど)。
最初は短い時間(1~2秒)待たせます。
③動かずにおすわりができている間に、ご褒美をあげ褒めちぎります。
※待ちきれずに動いてしまったときは
・おやつはあげず
・もう一度①から挑戦
④少しずつ待つ時間を延ばしましょう。
最初は1秒から、徐々に3秒、5秒と増やしていきます。
その後は少しずつ距離を離していきましょう。
◇解除の合図も同時に
ご褒美をあげるとき「よし」などのコマンドで待つ状態を解除し、犬が自由に動けるようにします。
●おまわり(スピン)
①ご褒美を愛犬の鼻先に持っていき、体を一周させるように誘導する。
②愛犬が一周したら「おまわり!」と声かけし、ご褒美。
③慣れてきたら、ジェスチャーを小さくしていく。
●ハイタッチ(ハイファイブ)
※「お手」を先に覚えさせておく方がうまくいく可能性が高いです
①「おすわり」をさせる。
②ご褒美を握った手を愛犬の鼻先に持っていき、少し上に上げる。
③愛犬が前足を上げた瞬間に「ハイタッチ!」と声かけし、ご褒美。
※最初は肉球に触れなくても良いので、前足を上げたことを褒める。
※愛犬が飼い主の手に触れるようになったら、ご褒美を握った手を徐々に高くしていきましょう。
●バイバイ
①ハイタッチした状態から
▶少しずつ、手が当たらない位置まで距離を取る
②犬がハイタッチしようと前足を数回動かしたら「バイバイ!」と声かけし、ご褒美。
これらの芸は、犬のボディコントロール能力を高める練習にもなります。失敗しても怒らず、成功した時に大袈裟に褒めることが大切です。
★犬の学習能力は非常に高いです。
芸を教えることで
・犬の自信も高まり
・より指示を聞くようになります。
もっと深く知りたい!愛犬との生活を豊かにする豆知識
●犬の嗅覚は人間の100万倍!?
散歩中に色々な場所を匂わせる=
・犬にとって重要な情報収集
・ストレス軽減
にもなります。
室内でもノーズワークなど、嗅覚を使った遊びも取り入れましょう。
●犬の睡眠時間はどのくらい?
成犬で12~14時間
子犬や老犬はもっと長いです。
安心して眠れる場所を提供し、睡眠を妨げないようにしましょう。
●犬のストレスサイン
・頻繁なあくび
・舌なめずり
・震え
・しっぽの振り方
・耳の位置
など、細かい変化を見逃さないようにしましょう。
●犬の年齢と学習能力
犬は何歳になっても学習できます。
老犬になっても、脳を刺激するような新しいことを教えることは、認知症予防にもなります。
●飼い主の声かけ一つで犬は変わる
ポジティブな声かけは
・犬の自信を育み
・行動を促します。
常に明るい声で話しかけましょう。
●運動不足は万病の元
適度な運動は、心身の健康を保つために不可欠です。
散歩だけでなく、室内での遊びも取り入れましょう。
●愛犬の「好き」を知る
・おやつ
・オモチャ
・遊び
・撫でられること
愛犬が何に一番モチベーションが上がるのかを知り、それを最大限に活用しましょう。
●獣医との連携
・問題行動がなかなか改善
・体調不良が疑われる
場合は、迷わず獣医に相談しましょう。
おわりに:あなたはもう立派な「家庭ドッグトレーナー」
このガイドを読み終えたあなたは、もう立派な「家庭ドッグトレーナー」です。
プロの
・知識
・技術
を家庭で実践することで
愛犬との絆は
・より深く
・より強固なもの
になるでしょう。
大切なのは、「こうあるべき」と完璧を求めることではありません。
・愛犬の個性を受け入れ
・それぞれのペースで
・楽しみながら
トレーニングを続けることです。
愛犬との毎日が、かけがえのない喜びと感動に満ちたものになりますように。
そして、あなたの愛犬が
「うちの子、天才かも?」
と、あなたにとって最高のパートナーとなることを願っています。





コメント