犬の尿路結石症の中でも
特に厄介な存在
として知られる
シュウ酸カルシウム結石。
一度できてしまうと
・完全に溶かすことが難しく
・再発しやすい
という特徴があります。
大切な愛犬がこの病気と診断された時、飼い主さんは大きな不安を抱えることでしょう。
この記事では、飼い主さんの不安を少しでも和らげるため、犬のシュウ酸カルシウム結石について徹底的に解説します。
シュウ酸カルシウム結石とはどんな病気?
シュウ酸カルシウム結石は
尿中の
・シュウ酸
・カルシウム
が結合▶結晶化して結石を形成する病気です。
・腎臓
・尿管
・膀胱
・尿道など
尿路のあらゆる場所に発生する可能性があります。
シュウ酸カルシウム結石の発生メカニズムと特徴
●溶解困難性
ストルバイト結石とは異なり、シュウ酸カルシウム結石は
・食事療法
・薬
でも完全に溶かすことが非常に困難。
そのため、外科手術による摘出が主な治療法となるケースが多くなります。
●再発率の高さ
手術で取り除いても
根本的な
・体質
・食生活
が変わらなければ再発しやすい
のが特徴です。
生涯にわたるケアが必要となることも少なくありません。
●できやすい場所
最も多く見られるのは膀胱内
ですが
・腎臓
・尿管
にできた場合は
水腎症
などを引き起こし、より重篤な状態になることもあります。
初期には症状が出にくいことも多いため、注意が必要です。
▶尿路のどこかで尿の流れが妨げられ
▶腎臓に尿が溜まって膨らんだ状態
多くの場合、腎機能障害が伴い、
・食欲不振
・元気がない
・嘔吐
などの症状が見られます
●シュウ酸の供給源
シュウ酸には
◇外因性シュウ酸
=食事から摂取されるもの
◇内因性シュウ酸
=体内で
・アミノ酸
・ビタミンC
などから作られるものがあります
●形成環境
一般的に
・尿が酸性に傾いている状態
(pHが低い)
かつ
・尿中のシュウ酸とカルシウム濃度が高い
場合に形成されやすくなります。
●できやすい犬種・年齢・性別
◇一般的に犬種は
・ミニチュア・シュナウザー
・ヨークシャー・テリア
・シー・ズー
・ビション・フリーゼ
・ミニチュア・プードル
・マルチーズなど
小型犬種に好発すると言われています。
遺伝的な素因も関与の可能性。
これらの犬種では特に注意が必要です。
◇年齢
中高齢(7歳以上)での発生が多い傾向。
若齢でも発症するケースは見られます。
◇性別
オスの方が尿道が細く長いため
▶結石が詰まりやすく
▶症状が重篤化しやすい
傾向があります。
メスでも膀胱結石は多く見られます。
●代謝異常との関連性
犬の中には
遺伝的にシュウ酸の代謝異常
を持つ場合があります。
これがシュウ酸カルシウム結石のリスクを高める一因と考えられています。
また
高カルシウム血症は
▶尿中へのカルシウム排泄量を増やし
▶シュウ酸カルシウム結石のリスク高める
なので高カルシウム血症を引き起こす病気
・上皮小体機能亢進症
・一部の腫瘍など
も原因となり得ます。
シュウ酸カルシウム結石ってどんな症状が出るの?
シュウ酸カルシウム結石の症状は
・結石の大きさ
・数
・存在する場所
によって様々です。
●頻尿
何度もトイレに行くが、少ししか尿が出ない。
●血尿
尿に血が混じる
(ピンク色、赤色、茶褐色など)
肉眼では分からなくても、検査で潜血が検出されることもあります。
●排尿困難・排尿痛
尿を出すのに
・時間がかかる
・痛そうに鳴く
・いきむ
●尿が出ない(尿閉)
尿道に結石が詰まると尿が全く出なくなり、これは命に関わる緊急状態です。
・元気消失
・食欲不振
・嘔吐
・腹部膨満
などの症状が現れます。
●落ち着きがない、腹部を気にする
痛みや不快感から
・そわそわしたり
・お腹を舐めたり
することがあります。
●無症状
小さな結石の場合などでは、膀胱内にあっても症状を示さないこともあります。
健康診断などで偶然発見されるケースも少なくありません。
シュウ酸カルシウム結石予防するためには?
シュウ酸カルシウム結石の完全な予防は難しい面もあります。
が、リスクを低減するための対策はいくつかあります。
●飲水量の確保
尿を薄く、たくさん出す!
◇新鮮な水をいつでも飲めるように
複数の場所に水飲み場を設置する。
◇食事からの水分摂取も工夫
・ドライフードをふやかす
・ウェットフードを取り入れる
・肉や野菜のゆで汁を少量加える
など。
◇水の種類について
ミネラルウォーターの中にはかなりミネラル含有量が高いものもあるため、水道水やペット用の水を与えるのが無難です。
ただし
水道水の硬度が非常に高い地域
(関東地方や沖縄県、他岩手県、三重県、香川県、徳島県、大分県、熊本県なども、硬度が高い傾向)
では、獣医師に相談の上、飲用水を考慮することも。
過度なミネラル制限は他の問題を引き起こす可能性もあるため、バランスが重要です。
●食事管理:バランスの取れた適切な食事
◇最重要ポイント
食事中の
・シュウ酸
・カルシウム
のバランスを適切に保つことが、シュウ酸の腸管からの吸収を抑えるために重要です。
◇カルシウムは適切に摂取
カルシウムを極端に制限すると
▶腸管でのシュウ酸吸収率が上がり
▶逆効果
になることがあります。
獣医師の指導のもと、適切な量のカルシウムを摂取させることが大切です。
詳しくは▶
◇シュウ酸が多い食材を避ける
ほうれん草、ビーツ、ナッツ類など
◇尿pHの目標
シュウ酸カルシウム結石は酸性尿で形成されやすいと言われています。
なので食事療法では
▶尿pHが過度に酸性に傾かないよう
▶中性~弱アルカリ性を目指す
(一般的にpH6.5~7.5程度)
ことが推奨されます。
※療法食については注意点があります
(後述)
◇タンパク質やナトリウム
過剰摂取が尿中カルシウム排泄を増やす可能性があるため注意する。
◇ビタミンCの過剰摂取
=体内でシュウ酸に変換されるため、サプリメントなどで大量に与えるのは避けるべきです。
●定期的な検査
早期発見・早期対応
◇定期的な尿検査
・尿比重
・pH
・尿沈渣など
で尿の状態をチェックする。
◇レントゲン検査や超音波検査
結石の有無や大きさを確認する。
◇シュウ酸カルシウム結晶は
正常な尿中でも少数見られることも。
継続的に多数認められる場合
は結石形成のリスクが高いと考えます。
●適度な運動とストレス管理
◇適度な運動
・肥満を防ぎ
・飲水量を増やす効果
も期待できます。
◇ストレス
▶免疫力を低下させ
▶様々な病気のリスクを高める可能性
愛犬がリラックスできる環境を整えましょう。
シュウ酸カルシウム結石の治療や処方される薬の例
シュウ酸カルシウム結石の治療は
・結石の大きさ
・場所
・数
・症状の有無
・基礎疾患の有無など
を総合的に判断して決定されます。
食事療法
シュウ酸カルシウム結石の管理において、食事療法は
・治療の根幹
であり
・再発予防の鍵
となります。
●療法食の目的と内容
◇シュウ酸制限・カルシウムの調整
結石の原料となる成分の摂取量を適切にコントロールします。
ただし
▶カルシウムを極端に制限
▶逆にシュウ酸の吸収率が上がる
▶結石ができやすくなる
という報告もあります。
バランスが重要です。
◇尿量の増加
尿を希釈=結石成分の濃度を下げるため
・ナトリウム含有量を調整
・水分摂取を促す成分が配合
されていることがあります。
◇クエン酸の添加
尿中クエン酸濃度を上げ、シュウ酸カルシウムの結晶化を抑制します。
◇タンパク質の適切な量
過剰なタンパク質は尿中カルシウム排泄を増加させる可能性。
質と量を適切に調整します。
◇尿pHコントロール
犬の尿pHは食事内容だけでなく
・飲水量
・体内の代謝状態
・運動量
・ストレス
・特定の薬の影響など
非常に多くの要因によって常に変動しています。
そのため、食事だけで尿pHを常に一定の理想的な値に厳密に固定することは困難。
なので極端なアルカリ化など
無理なコントロール
は別の種類の結石リスクなど他の問題
を引き起こす可能性もあるため
推奨されません。
食事療法は
これらの変動要因を考慮した上で
結石が形成されにくい尿環境
を作るための一つの重要な手段として位置づけられます。
療法食は、必ず獣医師の診断と指導のもとで使用してください。
自己判断で選んだり、長期間与え続けたりすることは、かえって健康を損なう可能性があります。
薬物療法
●クエン酸カリウム
尿のpHをアルカリ化
▶尿中のクエン酸濃度を上げる
▶シュウ酸カルシウムの結晶化を抑制
する効果が期待されます。
◇副作用
・高カリウム血症
(特に腎機能が低下している場合)
・胃腸障害(嘔吐、下痢)
などが起こる可能性があります。
◇食事との兼ね合い
カリウムを多く含む
・サプリメント
・一部の食品との併用には注意が必要
療法食自体にカリウム含有量が調整されている場合もあります。
●サイアザイド系利尿薬
(ヒドロクロロチアジドなど)
尿中へのカルシウム排泄を減少させる目的で使用されることがあります。
ただし、副作用や他の薬剤との相互作用に注意が必要です。
◇副作用
・低カリウム血症
・高カルシウム血症
・高血糖
・脱水、食欲不振
などが報告されています。
定期的な血液検査によるモニタリングが重要です。
◇食事との兼ね合い
カリウム保持性の利尿薬ではないため
・低カリウム血症に注意し
・必要に応じてカリウムを補給
することもあります。
食事中のナトリウム制限と併用することで効果が高まる場合があります。
●その他
・尿路感染を併発している場合
▶抗生物質
・痛みがある場合
▶鎮痛剤
などが対症療法として用いられます。
・薬の選択
・投与量
・期間
は、個々の犬の状態や他の病気の有無によって大きく異なります。
必ず獣医師の指示に従い、自己判断での投薬や中断は絶対に行わないでください。
副作用が疑われる場合は、速やかに獣医師に相談しましょう。
外科療法:結石の物理的な除去
●膀胱切開術
膀胱内の結石を外科的に摘出する手術です。
●尿道切開術・尿道造瘻術
・尿道に詰まった結石を摘出したり
・結石が詰まりにくいように新たな尿の出口を作る
手術です。
●レーザー砕石術、体外衝撃波砕石術(ESWL)
人間の医療では一般的です。
が、犬では実施できる施設が限られ、適応も限定的です。
シュウ酸カルシウム結石に対する「ヒッポのごはん」の栄養対策
シュウ酸カルシウム結石の食事療法は
・治療の根幹であり
・再発予防の鍵です。
ヒッポのごはんでは
①非常に難易度の高い栄養バランスの調整を
②科学的根拠に基づいて行い
③結石が形成されにくい安定した尿環境の維持を目指します。
コンセプト:尿の希釈・原料成分の適正化・安定した尿環境の維持
ヒッポのごはんでは
・結石リスクを最小限に抑え
・尿路の健康をサポートするため
以下の3つの柱で食事を提供します。
1.徹底した水分補給と尿の希釈
結石成分の濃度を下げるための最優先事項。
2.シュウ酸とカルシウムの絶妙なバランス調整
腸内でシュウ酸を結合させ、尿中への排泄を減らすための鍵。
3.結石リスクを高める栄養素の厳格な制限と個体別調整
・タンパク質
・ナトリウム
・特定のビタミン
を適切に管理し、併発疾患を考慮します。
具体的な対策:食事の内容と栄養素のコントロール
1.最重要:水分補給と結晶化抑制
●水分
何よりも重要です。
常に新鮮な水を与えていただきながら
レシピの水分量を工夫し、
尿量を増やして尿を希釈
することを目指します。
定期的な尿検査で
尿比重を1.020以下に保つ
ことを目標とします。
●ビタミンB6
体内でのシュウ酸の産生を抑制する働きがあると言われています。
ただし、過剰摂取は避けるべきです。
●オメガ3脂肪酸
炎症を抑制する効果に期待。
尿路の健康維持に役立つ可能性があります。
2.シュウ酸とカルシウムのバランス管理
●シュウ酸
特に含有量の多い食品
・ほうれん草
・ビーツ
・ルバーブ
・ナッツ類
(特にアーモンド、カシューナッツ)
・大豆製品
ただし、野菜は茹でこぼすことで、シュウ酸含有量を減らすことができます。
例1:ほうれん草の場合
ゆでこぼすことで
30~87%のシュウ酸を減らせます。
・茹でる水の量
・茹で時間
・茹でた後の水切り方法
・品種
・収穫時期
などによってシュウ酸の溶出量は変動。
一般的に
多量の水で長時間茹でる
ほど減少率は高くなります。
生の状態:約600mg~1200mg
ゆでこぼした後:約100mg~400mg
減少率:約50%~85%

ゆでこぼした後でも、結構な量のシュウ酸が残ります。すでにシュウ酸カルシウム結石がある場合、無理して使う食材ではないですね。
例2:さつま芋の場合
さつま芋は
・ほうれん草ほどシュウ酸は多くはない
・他のイモ類と比較すると含有量が高め
ゆでこぼすことで
15~30%のシュウ酸を減らせます。
サツマイモのシュウ酸低減効果は、ほうれん草ほど劇的ではありません。
これは
・シュウ酸の形態(水溶性/不溶性)
・細胞構造の違い
が関係しています。
蒸したり焼いたりする調理法では、シュウ酸は閉じ込められたままになるため、ほとんど減少しません
生の状態:約50mg~120mg
ゆでこぼした後:約35mg~90mg
減少率:約15%~30%

こちらは「おやつにさつま芋」などの過剰にさえならなければ、大丈夫!
●カルシウム
極端な制限は避けるべきです。
が、過剰摂取も逆効果になることも。
療法食では適切に調整されています。
カルシウムが多いおやつ
・チーズ
・煮干し
・骨など
を与える際は注意が必要です。
★「カルシウム不足」がなぜ問題なのか?
食事から摂取されたシュウ酸は
▶腸管内でカルシウムと結合
▶不溶性のシュウ酸カルシウムになる
▶便として排泄
このため
▶食事中のカルシウム量が適切
▶シュウ酸の吸収が抑えられる
▶尿中へのシュウ酸排泄量が減少する
▶結石のリスクが低下する可能性
と考えられています。
逆に
▶食事中のカルシウムが不足
▶シュウ酸がカルシウムと結合できない
▶腸管から吸収されやすくなる
▶結果として尿中のシュウ酸濃度が上昇
▶結石のリスクが高まる可能性
3. 結石リスクを高める栄養素の制限
●タンパク質
過剰な動物性タンパク質は
▶尿中へのカルシウム排泄を増加
▶尿を酸性化させる傾向
があるため、適切な量と質のタンパク質を摂取することが重要です。
●ナトリウム
過剰摂取は飲水量を増やす一方で、尿中へのカルシウム排泄も増加させる可能性があります。
人間用の加工食品などを与えるのは避けましょう。
●ビタミンC
体内でシュウ酸に代謝されます。
サプリメントなどによる積極的な大量摂取は避けるべきです。
通常の食事に含まれる量であれば問題ありません。
ヒトの研究では
ビタミンC(またはその代謝産物)
が尿中で
・シュウ酸と
・カルシウム
の結合を妨げ
結石の結晶化を抑制する可能性
が示唆されています。
しかし、これは犬の結石予防食にそのまま当てはめるべきではありません。
犬は体内でビタミンCを合成できるため
▶サプリメントなどで過剰に摂取すると
▶それが体内でシュウ酸に代謝され
▶尿中のシュウ酸濃度を上げてしまう
というように、
かえって結石のリスクを高める
可能性があるからです。
●ビタミンD
カルシウムの吸収を促進する
▶過剰摂取は高カルシウム血症のリスク
▶結果的にシュウ酸カルシウム結石のリスクを高める可能性
どのみち過剰摂取は禁忌です。
ヒッポのごはんの強み:オーダーメイドの調整力
併発疾患を考慮した柔軟なレシピ調整
ヒッポのごはんでは、愛犬の状態によってレシピを細かく変更します。
例えば、高脂血症を併発している場合
・タンパク質やシュウ酸の制限に加え
・徹底した低脂肪食の原則も同時に満たす
よう、食材や調理法を調整します。
これにより
・結石予防
・高脂血症の管理
を両立させます。
尿pHコントロールと食事回数の管理
●尿pHコントロールの考え方
尿pHは多くの要因で変動するため、
中性~弱アルカリ性の範囲(pH6.5~7.5程度)に留めることを目標とします。
極端なアルカリ化
など無理なコントロールは
▶別の種類の結石リスクを高める
ため推奨しません。
尿㏗にとらわれるのではなく
身体全体の原因
・水分不足
・内分泌代謝異常
・肝・腎疾患
・栄養バランスの悪い食事
・たんぱく質の過剰摂取
・原因成分の過剰摂取
を視野に入れることが重要。
●食事の与え方
一度に多量の食事を与えることは
・消化器への負担
・急激な尿pH変動
につながる可能性があるため
1日2〜3回に分けて少量ずつ与える
ことを推奨します。
●身体を温める
直接的に体を冷やさない生活の他
・ラム
・チキン
・サーモンなど
身体を温めると言われる食材を盛り込みます。
専門家による厳密なレシピ作成と微調整
シュウ酸カルシウム結石の手作り食は
栄養バランスを完璧に調整
するのが非常に難しく
▶専門的な知識が必要です。
安易な自己流の手作り食は病状を悪化させる危険性があります。
・愛犬に寄り添った
・安全で効果的なごはんづくり
を実現できるのがヒッポのごはんの最大の強みです。
●フィードバックと調整
ヒッポのごはんでは
・専門家のもとで厳密なレシピを作成
・尿検査の結果を見ながら微調整
を行います。
手作り食を開始・変更した際
最初の数週間は
尿検査を頻繁に行い
(尿比重、尿pH、結晶の有無など)
レシピが愛犬の体質に合っているか
迅速なフィードバックと調整
を行うことが不可欠です。
シュウ酸カルシウム結石の治療費の例
犬のシュウ酸カルシウム結石の治療費は
・症状の重症度
・検査内容
・治療法(内科か外科か)
・入院の有無
・通院頻度
・動物病院の規模や地域
によって大きく変動します。
●初期検査・診断
◇尿検査:
2,000円~5,000円程度
◇レントゲン検査:撮影枚数による
5,000円~15,000円程度
◇超音波検査:
5,000円~15,000円程度
●内科療法(月額)
◇療法食:犬のサイズ、フードの種類による
5,000円~15,000円程度
◇処方薬:クエン酸カリウムなど
3,000円~10,000円程度
◇定期的な検査費用:
上記検査費用が定期的にかかる
●外科療法(膀胱切開術の場合):
◇手術費用
術前検査、麻酔、手術、入院費含む
15万円~40万円程度。
・結石の場所や数
・犬の状態
・合併症の有無
などで大きく変動します。
尿道閉塞など緊急性が高い場合はさらに高額になることもあります。
これらはあくまで一般的な目安であり、実際の費用とは異なる場合があります。
治療を開始する前に、必ず動物病院から詳細な見積もりをもらい、内容をよく確認しましょう。
ペット保険に加入している場合は、補償範囲や請求方法を確認しておくことも大切です。
その他シュウ酸カルシウム結石になったときにしてあげられること
シュウ酸カルシウム結石は、一度診断されると生涯にわたる付き合いになることが多い病気です。
飼い主さんの
・きめ細やかなケア
・愛情
が、愛犬のQOL(生活の質)を大きく左右します。
●定期的な通院と検査の継続
:再発との闘い
◇獣医師の指示通りに定期的な尿検査や画像検査を受け、再発の兆候を早期に捉えることが最も重要です。
◇症状が落ち着いていても、自己判断で療法食や投薬を中断しないこと。
●飲水量と排尿状態の細やかな観察
:日々のチェックが鍵
◇毎日どれくらい水を飲んでいるか
加えて尿の
・回数
・量
・色
・排尿時の様子など
を記録しておくと、変化に気づきやすくなります。
◇排尿時に
・痛がる
・時間がかかる
・尿が出にくい
などのサインを見逃さないように!
●ストレスの少ない生活環境の提供
◇穏やかで安心できる環境は、免疫機能の維持にもつながります。
◇トイレ環境を清潔に保ち、我慢させないようにしましょう。
●飼い主さんの精神的なサポート
◇長期的なケアが必要となるため、飼い主さん自身が正しい知識を持ち、前向きに取り組むことが大切です。
◇不安なことや疑問点は遠慮なく獣医師に相談し、信頼関係を築きましょう。
◇ 同じ病気を持つ犬の飼い主さん同士のコミュニティなどで情報を交換することも、精神的な支えになることがあります。
ただし、治療法は個々の状態によるため、必ず獣医師の指示を優先してください。
●他の病気との関連性への配慮
◇ 副腎皮質機能亢進症など
内分泌疾患は
▶高カルシウム尿症を引き起こし
▶シュウ酸カルシウム結石リスクを高める
ことが知られています。
基礎疾患がある場合は、その治療も並行して行うことが重要です。
◇腎臓への配慮
高齢になると腎機能が低下しやすいため、腎臓への配慮も必要になってきます。
●おやつやサプリメントは慎重に
◇良かれと思って与えたものが、結石のリスクを高める可能性があります。
新しいおやつやサプリメントを与える前には、必ず獣医師に相談しましょう。
まとめ:獣医師との連携こそが最良の道
犬のシュウ酸カルシウム結石は
・完治が難しく
・再発しやすい
厄介な病気です。
しかし
・適切な食事管理
・飲水量の確保
・定期的な検査
・何よりも獣医師との緊密な連携
によって
・結石の成長をコントロール
・再発のリスクを最小限に抑え
・愛犬の快適な生活を守る
ことは十分に可能です。
飼い主さんだけで抱え込まず、信頼できる獣医師をパートナーとして、二人三脚で治療とケアに取り組んでいきましょう。
毎日のごはんのことであれば、ヒッポのごはんでも無料でご相談を受け付けています。
この記事が、愛犬と飼い主さんの不安を少しでも和らげ、前向きな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

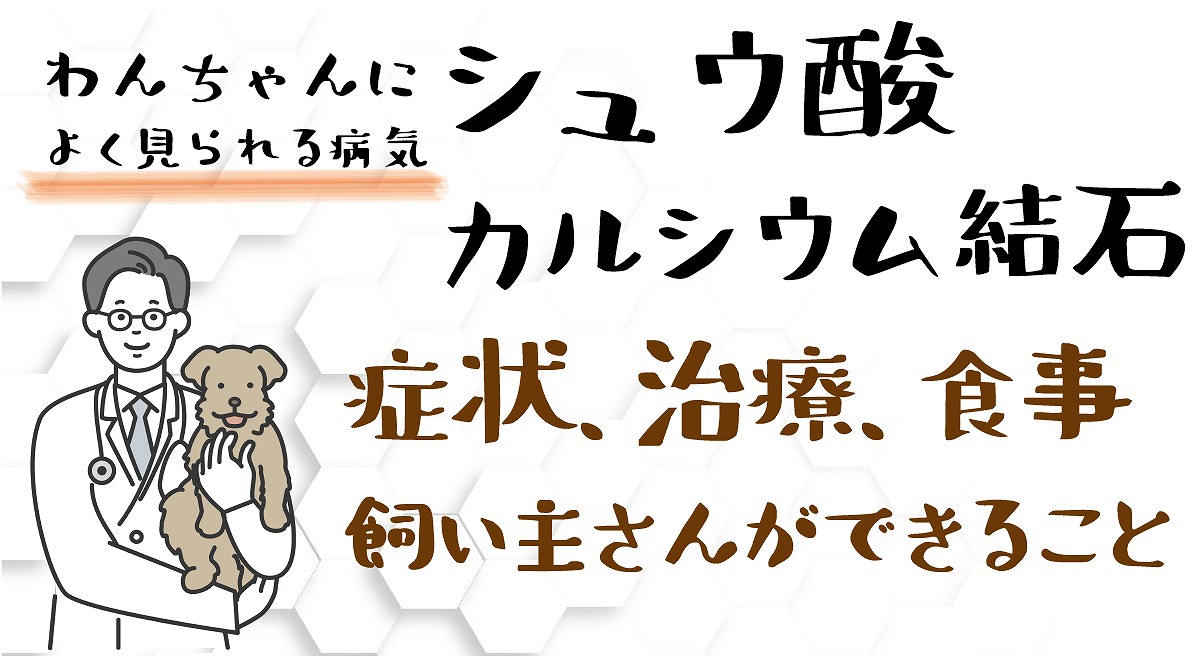

コメント